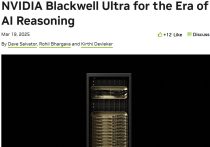米国の輸出規制で中国ファーウェイが高性能AIサーバーを開発、エヌビディアを脅かす存在に
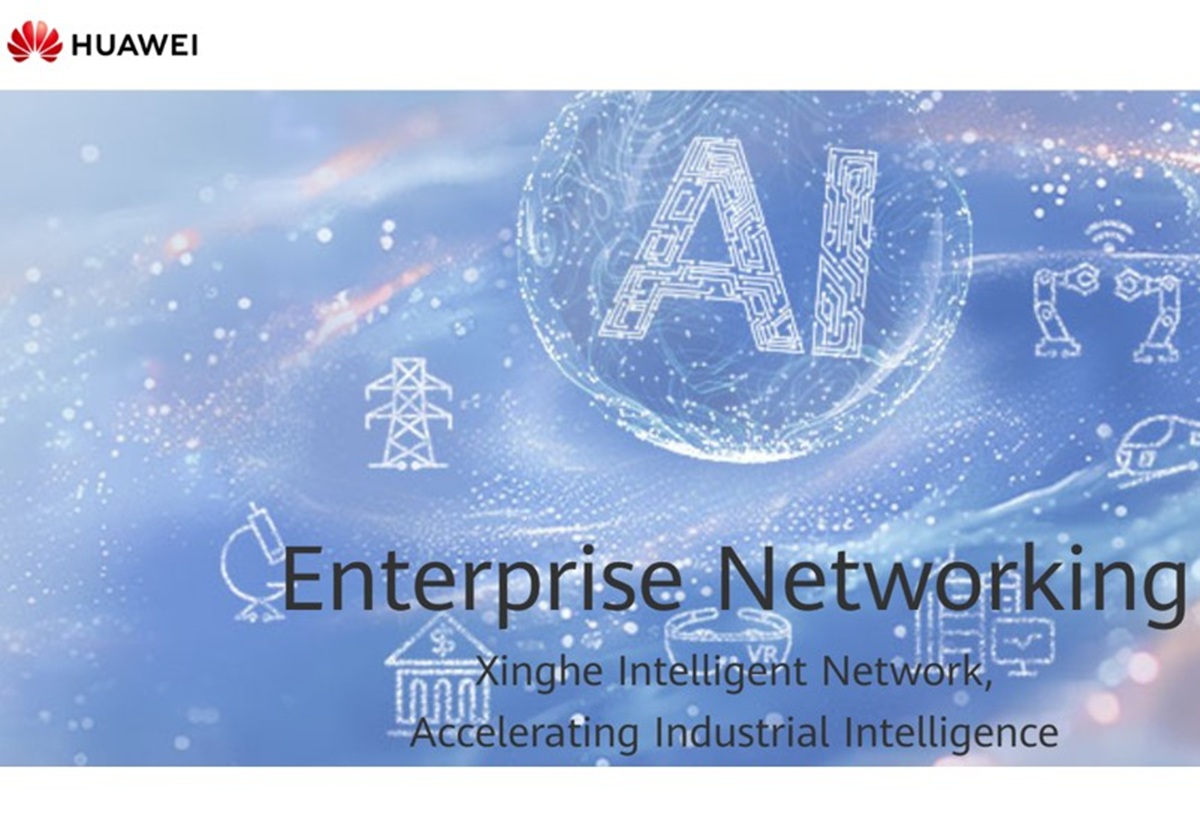
●この記事のポイント
・中国のファーウェイが、米エヌビディアのAIサーバーに匹敵する性能を持つ製品を開発か
・中国市場におけるエヌビディアのシェアが95%から50%に低下
・SMIC1~2年後くらいには最先端の3nmの半導体を出荷できるようになる可能性は高い
米国の輸出規制により高性能の半導体を輸入できない中国。その中国の華為技術(ファーウェイ)が、米エヌビディアのAIサーバーに匹敵する性能を持つ製品を開発したとみられている。ファーウェイは自社で開発する半導体「アセンド」の性能を急速に高めており、採用する中国企業が増えていることによって、中国市場におけるエヌビディアのシェアはバイデン政権発足時の95%から50%に低下した。同社のジェンスン・フアンCEOが21日に台北で開催されたテクノロジーイベント「COMPUTEX」で明かした。さらにファーウェイが提供するAI開発プラットフォームを利用する企業も急速に増えており、「DeepSeek-R1(ディープシークR1)」に匹敵する性能のAIモデルも開発したと発表。5月には中国の小米(シャオミ)も最先端となる回路線幅3ナノメートル(nm)の半導体を開発したと発表。中国が影響力を持つ国で中国製の高性能半導体やAIモデル、AI開発基盤の利用が広まれば、エヌビディアの一強状態を揺るがしかねない。なぜファーウェイは急速に半導体の技術力を高めているのか、そして、同社の躍進が世界の半導体市場にどのような変化をおよぼす可能性があるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
ソフトウェア面でも強い総合力がエヌビディアの特徴
まず、現在のファーウェイの半導体の技術力は、どう評価できるのか。国際技術ジャーナリストの津田建二氏はいう。
「日本よりははるかに上です。ファーウェイは米国のバイデン政権のときに実質的な輸出禁止企業リストであるエンティティー・リストに掲載され、同社は米国企業から高性能の半導体を輸入できなくなりました。そこで子会社のハイシリコンが7nmの半導体を設計して、中国の受託製造会社・SMICが製造できるようになりました。トランジスタや配線を三次元化したり、チップ上の単位面積あたりのトランジスタ数を増やして集積度を上げたりといった方法をマスターして、7nmの半導体の製造を実現できたんですね。
エヌビディアもそれほど微細化しているわけではなく、最新の『Blackwell』も4nmです。ちなみに、スマートフォン向け半導体は端末内に組む込むため非常に小さいサイズにする必要があるので、アップルは最新のiPhoneに3nmの半導体を搭載しており、2026年をめどに2nmを搭載するとみられています。
ただ、エヌビディアは半導体のハードに加えて、『CUDA』というAI開発プラットフォームを持っており、このプラットフォームの利用が世界的に広まったことがエヌビディアの成長につながりました。このようにソフトウェア面でも強いのが特徴です。開発ツールなどソフトウェアの優良資産を膨大に持っており、例えばメディカル関係のAI開発をしたいという会社があったとして、エヌビディアは創薬開発用ソフトや遺伝子解析用ソフト、手術や診断用のソフトも提供することができる。顧客の『こういうものをAIで開発したい』というニーズに対して、あらゆる技術を提示することができるという総合力が同社の強みです」
ファーウェイが急速に半導体の技術力を高めている理由は何か。
「アメリカによる制裁措置が最大の理由です。米国から最先端の半導体を輸入できないということになれば、自社で開発するしかなくなります。シャオミも3nmの半導体を開発したと発表しており、SMICはまだ3nmの開発能力はないとみられていますが、1~2年後くらいには出荷できるようになる可能性は高いです」(津田氏)
エヌビディアは中国市場を重要視
エヌビディアのフアンCEOは中国の半導体市場は数年後に500億ドル(約7兆円)になると語っているが、中国勢の躍進が世界の半導体市場に大きな影響をおよぼす可能性はあるのか。
「ファーウェイの半導体は現時点では通信用がメインなので、直接的に競合するのはエヌビディアというよりはクアルコムです。なので中国市場ではクアルコムがシェアを大きく奪われてしまうかもしれません。エヌビディアの国別の売上でみると中国は15%ほどですが、中国の半導体市場は非常に大きいです。同社はこれまで米国政府による輸出規制のなかでも『H10』『H20』といった低い性能の半導体を輸出してなんとか中国市場でシェアを維持してきましたが、5月には『H20』の輸出も禁止され、同社はより低い性能の半導体を輸出しようという動きをみせています。4月にはファンCEOが中国を訪問して北京市で政府高官と会談しており、中国市場を重要視していることは確かです」
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=津田建二/国際技術ジャーナリスト)