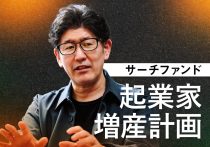“日本式”の枠を超えた選択肢を。エンデバー・ジャパンが示す起業家支援とは

●この記事のポイント
・世界最大級の起業家支援コミュニティ「エンデバー」の日本法人の代表理事とオペレーションマネージャーにインタビュー。なぜ日本企業にはユニコーンが少ないのか、また海外進出する企業が少ないのか、それには日本のスタートアップ独自の事情があるという。
・そのなかでエンデバーが支援するスタートアップはグローバルを見据えるケースが多い。エンデバーはVCとの姿勢の違いに、起業家の「人間性」をかなり重視している点を挙げる。
日本では、起業家の数こそ多いものの、ユニコーン企業の数では世界に大きく後れを取っている、グローバル進出が少ないという印象があります。先人が少ない状況に、次のアクションに迷いが出る起業家も少なくありません。
そうした状況に一石を投じる存在が、1997年に設立された非営利団体「エンデバー」。現在、2900人を超える起業家と3000人以上のメンターをつなぐ、世界最大級の起業家支援コミュニティです。世界最大の起業家支援コミュニティとして地域経済にインパクトを与えうるハイインパクトアントレプレナーを選考し支援することで、46以上の市場に活動地域を拡大し、起業家支援とエコシステムの構築とサポートを行っています。
今回は、エンデバーの日本活動拠点、一般社団法人エンデバー・ジャパンの代表理事 大塚 莉菜氏と、オペレーションマネージャー 小田嶋 アレックス太輔氏に、日本のスタートアップが抱える課題やグローバルに活躍する起業家を生み出すためのカギをお聞きしました。
目次
- 日本人起業家はグローバルを見ていない!?
- 起業家には周囲への影響力が不可欠
- 日本が持つ、グローバルスタンダードとのギャップ
- 各国に学ぶ、日本に必要な起業家支援とは
- 「自分だけじゃない」と思える起業家支援
日本人起業家はグローバルを見ていない!?

——日本では企業数に対してユニコーン企業が登場しづらいといわれていますが、海外のスタートアップ事情などを知るおふたりから見ると、その原因はどこにあると感じますか?
大塚:「ユニコーン企業」という言葉の定義に当てはまる企業が少ない、ということが原因のひとつにあると考えています。
ユニコーン企業とは、企業評価額が10億ドル以上、さらに未上場の企業を指します。日本は創業数年で上場してしまうケースが多いため、ユニコーン企業の定義に当てはまらない場合が多いのです。
小田嶋:経済規模がほとんど同じドイツでは、現在ユニコーン企業が30社以上あります。日本とは違い、上場が容易ではないからです。
また、海外の企業はアメリカでの資金調達を行い、企業の時価総額を上げているケースが多いですね。ドイツやフランスなどで時価総額が数十億ドル規模の企業は、大体そのパターンに当てはまるのではと考えています。
——日本の特殊な事情も原因にあるのですね。それでは、スタートアップにおける日本独自の課題などはありますか?
小田嶋:コロナ禍終了の前後からやや風向きは変化したものの、日本のスタートアップはあまりグローバルに出たがらない、という傾向があると感じています。日本の起業家の多くが、グローバルで事業を広げることを当たり前の動きとしていないのです。
これは、日本の市場が大きく、よくも悪くもここで完結してしまうことが起因しています。もちろん、市場が大きいということは、日本市場での起業自体も非常にチャレンジングなことではあるのですが。
大塚:ほかの国は、国内の市場だけでは完結できないため、ビジネスをスタートする時点からグローバルを見据えて計画しているケースも多いですね。そうしないと、スケールするビジネスにならないのです。
日本の企業は「まず日本で成功してからグローバルへ」という考え方なので、そもそものマインドセットに違いがあります。
小田嶋:日本のスタートアップ支援やVCも、基本は国内用にできあがっているので、「まず日本で成功してから」の方式でグローバルを見据えると、ゼロベースでグローバル仕様の事業展開をつくり上げなければなりません。
こういった事情もあり、日本において最初からグローバルを見据えてビジネスをスタートする方は、やや考え方などが特殊な方が多いですね。
——エンデバーが支援する起業家には、そういった最初からグローバルを見据えている方が多いと思うのですが、その動き方や人物像にはどのような特徴があるのでしょうか?
大塚:エンデバーはグロース(成長)ステージにある企業のスケールアップを中心に支援しているのですが、その段階だと、創業者は日本人でありつつも本社をアメリカやシンガポールなどの海外に置いているケースは多いですね。最初からグローバル展開を見据えている場合、日本に本社を置いているとスケールアップが難しいと考えているためでしょう。
あとは、グローバルでの資金調達を受けられる状況を最初から設計していて、日本のVCだけで株式構成がされていないというケースも多いです。
小田嶋:人物の特徴でいうと、出自も関係しているかもしれません。子どもの頃に海外に住んでいた、なんらかのタイミングで海外で生活していたという方は多いです。
日本の外に世界があるという感覚にリアリティがある上に、言葉の壁がないのでグローバル展開をある程度「当たり前のこと」と捉えやすく、ハードルが低いのでしょう。
大塚:先日、ある日本人のファウンダーの方が、「アメリカで創業する起業家と戦おうとしたら、日本人は日本からインドあたりまでの規模感でビジネスを考えていないといけない」とおっしゃっていました。
というのも、アメリカは国内だけでも、東海岸から西海岸まで飛行機で5〜6時間かかります。そもそも「国内」というものの規模感が違うのですよね。
起業家には周囲への影響力が不可欠

——それでは、エンデバーが支援対象となる起業家を選定する際、どういった部分を見ていますか? 日本、海外問わずVCの観点と大きく違う部分があれば教えてください。
小田嶋:VCとの決定的な違いは、起業家の「人間性」をかなり重視していることです。テイカーではなくギバーであるか、自身の成長が周囲にこう影響を与えられるか、などを見ています。
大塚:また、起業家としての資質とビジネスモデル、そのビジネス自体のインフレクションポイント(転換点)などを見て評価しているので、日本の市場で早々にIPOするかどうか、などの部分もあまり評価の基準にはなりません。
小田嶋:たしかに、それも大きな違いです。グローバル基準のため、日本のように「上場がゴール」という感覚はあまりないですね。
——エンデバーは「事業がスケールする」ということをどう定義しているのでしょうか? 人間性と事業のスケールアップをどうリンクさせているのかが気になります。
小田嶋:エンデバー起業家に選出された時点で、さらに売り上げ規模が10倍に増えるほどのポテンシャルがあるか? という、事業そのもののスケールアップももちろん重要ですが、エンデバーでは、その起業家、企業が存在することで「マルチプライヤーエフェクト」があるかどうかも「スケールするかどうか」という考え方に含まれています。
つまり、起業家や企業が成長してネットワークを広げていくことで、周囲に新たな起業家や事業が増えていくかどうか、ということです。
エンデバーでは、エンデバー起業家が創業した企業の数や従業員数、そのエンデバー起業家の出資額などを数値化しています。
大塚:最初にエンデバーが創設されたラテンアメリカでは、そのネットワーク構築の効果が顕著です。現在、ブラジルでユニコーン企業の創業者となっている方々の80%ほどが、エンデバーで支援しているスタートアップです。
このように、傑出した個人は世界に並外れた影響を与えてくれます。彼らは社会をよりよくするだけでなく、周囲の起業家エコシステムの成長にも寄与します。並外れた個人の影響は一つの社会を超えて広がる、ということですね。
起業家自身(個人)の人間性を重視しているのはそのためです。
日本が持つ、グローバルスタンダードとのギャップ

——日本において、エンデバーのネットワーク構築の障壁になりそうなことはありますか?
小田嶋:やはり、エンデバーはグローバル基準でエンデバー起業家を選出し、ネットワークを形成しているので、そこに対してギャップが大きい点が障壁になると考えています。
具体的には、「失敗を許容しない文化」があることですね。日本は、金額的な意味ではなく、信頼性などの心理的部分で失敗からのリカバリーが非常に難しいと感じます。
たとえば、トランプ大統領はこれまで4回も破産申請を行っています。日本ではあまりこういった形で起業を繰り返す方は多くないですよね。
大塚:この文化が、影響力を持つ存在になり得る企業が登場することの妨げになってしまう可能性はあると感じます。
エンデバーでは昨年、ユニコーン創業者がどういった経歴をたどってきたのかという調査を行ったのですが、BIG5(※1)やBIG3(※2)での勤務経験のほか、「ユニコーン企業の前に少なくとも1つのほかの企業を立ち上げ経営」した経験がある方、いわゆる連続起業家が多いという結果が出ています。
日本では、連続起業家といえばIPOを行って、また企業を創業して、というイメージが強いですが、海外では、必ずしも先に創業した事業がうまくいっているケースだけではありません。
小田嶋:日本ではIPOを評価する風潮はありますが、事業の失敗に対してポジティブに興味を持って会話することが少ないですよね。失敗を言いたがらないし、聞いてはいけない空気がある。これは大きく変えなければいけない部分だと思っています。
これはネットワークの構築だけでなく、企業そのものにとっても大きな機会損失です。
実際に、非常に面白いアイデアを持っていたはずの企業が、失敗のレッテルを恐れるあまり、いつの間にか下請けのシステム会社に甘んじてしまう、というもったいないケースを非常に多く目にします。
※1: GAFAM(Google、Apple、Meta(旧Facebook)、Amazon、Microsoft)
※2: マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)、ベイン・アンド・カンパニー
各国に学ぶ、日本に必要な起業家支援とは

——今お話いただいたような日本の実情と、似た傾向を持ちつつも克服した、という国があれば教えてください。
小田嶋:まったく同じではないですが、フランスが似ていますね。10年ほど前までは今の日本とあまり変わらない状況だったと思います。
フランスは、日本とは比べものにならないほどの学歴社会な上、当時は非常に失業率が高かったのです。30歳以下に限定すると失業率が20%を超え、給与水準が高い学士や博士ほど無職になってしまう状態でした。これを打開しようと2013年からフランス政府はスタートアップの支援プロジェクト「フレンチテック」を推進しはじめました。
自分たちで起業しないと仕事がない、という切迫した状況からスタートしたプロジェクトですが、この10年でフランスは起業数も格段に増え、スタートアップ事情が急激に変化していますね。
スタートアップが盛んになるきっかけは、国によってさまざまです。
北欧などは、ガラケー時代の終焉によって市場にあふれてしまった優秀な人材がスタートアップに流れたことが起因しています。エストニアはSkype社の創業チームにエストニア人がいたことで、スタートアップの潮流が高まるという流れがありました。その方がきっかけで次の世代を育てていく、起業家による起業家のためのコミュニティが形成されています。現在のエストニアの起業家たちは、そのコミュニティで育っているのです。
——日本が参考にするとしたら、どの国のスタイルがよいのでしょうか?
大塚:エンデバーはまだオフィスを置いていないのですが、韓国でしょうか。商談にはスーツを着用していくなど、ビジネスの文化も近いものがありますね。
小田嶋:そうですね。国が支援のために支出できる予算額にしても、大学などの教育レベルにしても、英語習得の度合いにしても、非常に似ていると感じます。つまり、韓国にできることは日本にも可能なのです。
ただ、違いがあるとすれば支援をする行政側に、イノベーション支援などの観点を持って横串で動ける人たちがいることですね。全体を把握してハンドリングできる人材がいるわけです。
今の状況で真にどういった人材が必要なのか? という部分において、圧倒的に参考になる国だと思います。
「自分だけじゃない」と思える起業家支援

——日本のスタートアップ事情、起業家が抱えるこうした課題に対して、エンデバー・ジャパンはどのようにアプローチしていくのでしょうか?
小田嶋:最初は、日本の持つ課題に対して方法や思考を変化させるアプローチを考えていたのですが、そもそも日本でスタンダードとされる方法も、グローバル展開を見据える方法も、どちらも選択肢としてある状態でもよいのではないか、という結論になっています。
選択肢がある中で、我々の思想に共感してチャレンジしたい、と考えている方に対して必要なネットワークにアクセスできる手段を提供することが、我々がやるべきことだと考えています。
大塚:そのために、本来のエンデバーの動きとは少し変えている部分があります。
グロースステージにある起業家の事業のスケールアップを支援する、というのが我々のメインの活動なのですが、昨年、東京都との協定事業でアーリーステージ向けのプログラムを立ち上げました。早い段階から、エンデバーの持つグローバルネットワークにアクセスし、今のグローバルスタンダードやトレンドを把握できるようにするためです。グローバル投資家との接点の提供なども行っています。
小田嶋:グローバルのユニコーン企業創業者と話す機会はなかなかないですよね。なかなか出会うことがない国の起業家の話を聞けるだけでなく、日本人同士ではなかなか話題に上がらない、失敗の経緯や克服の秘話なども聞くことができます。
大塚:同じ志を持ったファウンダーが集まっているので、「自分以外にも同じマインドセットの日本人がいるのか」と感じていただくことが多いです。
我々は非営利団体なので、競合という概念がありません。VCなどとはまた違った独自の視点でサポートすることが可能です。同じ目線で動く、視座が高いメンバーのネットワークを提供できる、ということはエンデバーの大きなメリットですね。
*
日本の起業家にとっても、フィールドとしてグローバルを選ぶ道は、もはや遠い話ではなくなっています。しかし、グローバル展開を見据えたとき、日本にいながら世界とつながり、必要な情報やトレンドを捉えるのは難しい場合もあります。
日本の起業家が選択する道に対して、最適なソリューションを提供し、自由に事業の展望を描ける場をつくる。そして、起業家が互いに影響し合い、起業家のエコシステムが形成する。
エンデバー・ジャパンは、この日本を土壌にそんな未来を切り拓こうとしています。