中国人、ベトナム人、インドネシア人にも通用している、部下に火をつけるほめ方の極意
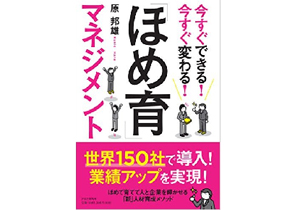 ※画像:『今すぐできる! 今すぐ変わる! 「ほめ育」マネジメント』著:原邦雄/PHP研究所
※画像:『今すぐできる! 今すぐ変わる! 「ほめ育」マネジメント』著:原邦雄/PHP研究所どんなに働きかけても部下から自主的な提案があがってこない、自分も部下もがんばっているのに業績が伸びない、そして、がんばりが成果に結びつかないために「消耗」してしまったスタッフはどんどん辞めていく……。
そんな状況を少しでも好転させようと、「とりあえず部下をほめてみる」も、思ったような成果を得られず八方塞がり。そんな世の上司にこそ、目をとめてほしい言葉がある。
「今すぐ、スタッフをほめるのを止めてください。あなたの“ほめ方”では、スタッフのやる気も、業績も上がりません」
こう語るのは、『今すぐできる! 今すぐ変わる! 「ほめ育」マネジメント』(PHP研究所/刊)の著者である原邦雄さんだ。
原さんは、38,000人以上の現場スタッフへのヒアリングにもとづき、業績アップに直結する部下の“ほめ方”を新たな人材育成メソッドとしてまとめあげた人物。
彼が提唱する“ほめ方”とはどのようなものなのだろうか。
■「ネクタイの色をほめる」はダメなほめ方
部下のモチベーションだけでなく業績もアップさせるためのほめ方とはどのようなものなのか。その話に入る前に、まずは上司がついやってしまいがちな“ダメなほめ方”がどのようなものなのかについて触れておきたい。
本書のなかで一例として挙げられているのが、「○○くん、そのネクタイ、センスいいね!」というほめ方。一見すると、ほめられた部下は気分を良くし、仕事にも前向きに取り組んでくれそうだと思うかもしれない。だが原さんは、このほめ方に対して、「甘い組織や慣れ合いの組織を生んでしまう」と警鐘を鳴らす。
というのも、このほめ方には「なぜ、ほめるのか」という上司側の目的が欠けているからだ。そして、このような上司は往々にして「きちんと叱る」こともできない。ほめる目的と叱る目的はコインの表裏の関係にあることを考えれば当然だろう。
その結果、部下は自分がどのような行動をとれば上司からほめられ、叱られるのかが分からなくなり、組織としての力は低下してしまう。つまり、ほめ方を間違えると、組織は良くなるどころか崩壊への道を進んでしまうのだ。
■効果的な“ほめ”を実現するための3ステップ
上の話を踏まえ、正しくほめるにはどうすればよいのだろうか。本書では以下の三つのステップを踏むことを推奨している。
1.ほめる基準を作る
2.ほめる風土を作る
3.長所をぶっこ抜く
ほめる基準とは、部下がどういう行動をとったときにほめるのかというもの。この基準を用意することで、上司は「何をほめればよいのか」がクリアになり、部下は「何をすればほめられるのか」が分かるというわけだ。





