 「Thinkstock」より
「Thinkstock」より現在、直近10年間の年純利益平均が、1000億円を超える上場企業は、日本に30社ある。このいわば「1000億円クラブ」に、総合商社は3年連続で5社(三菱商事、三井物産、伊藤忠、住友商事、丸紅)を送り込んでいる。いまや日本でもっとも高収益の業界ともいえる総合商社も、バブルが崩壊した1990年代後半は、業界が消滅しても不思議ではないほど経営が悪化していた。
まず、総合商社5社について、1986年から5年ごとに1社当たりの年平均連結純利益(税後利益)をみてみよう。
1986年~1990年:281億円
1991年~1995年:217億円
1996年~2000年:▲3億円
2001年~2005年:496億円
2006年~2010年:2223億円
2011年~2015年:2673億円
※会計基準の変更(米国基準・IFRS)があっても同じ「当期利益」をピックアップした。
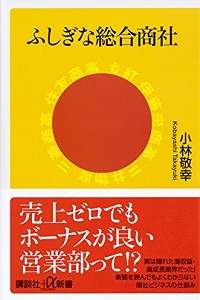 『ふしぎな総合商社』(小林敬幸/講談社+α新書)
『ふしぎな総合商社』(小林敬幸/講談社+α新書)この表をみると、バブル崩壊前は数百億円の収益力だったが、バブル崩壊の後始末に追われた90年代後半は、赤字になった。それが、2000年代に収益を急成長させ、17年の現在では、バブル発生前の10倍の数千億円の利益水準に達している。拙著『ふしぎな総合商社』(講談社+α新書)で、「総合商社はポストバブルの勝ち組」と呼ぶ所以である。
この2000年代の商社の急成長が実現したのは、「稼ぎ方」そのものを大きく変えていったからである。従来の売買仲介型ビジネスから事業投資型ビジネスに全商品分野で変えていった。
とりわけ興味深いのは、このビジネスモデルの変更が明確な戦略やビジョンの提示なしに、しかも相互に示し合わせてもいないのに、業界5社がそろって全商品分野において行われたことである。まるで、メダカの群れの方向転換のようである。
とはいえ、その変革を支えたものがいくつか見てとれる。まず、変革のエンジンであり原動力になったのは、現場末端の社員一人ひとりの強烈な危機意識だった。
一方で、変革の方向性については、成功に導く「芽」や「ヒント」になるものを、商社は苦しいときにも常に保存してきたことである。
多様性を維持してきた商社
商社は90年代の苦しいときも、2000年代の業態を変革して急成長したときも、従来の多様性を維持し続けた。売買仲介型ビジネスから事業投資型ビジネスに大きく業態を変えたけれども、売買仲介型ビジネスも、いまだ無視できない規模で行っている。むしろ、従来の商品の多様性に加え、収益方法の多様性にまで軸を広げていったといえる。
そこでは、かっこいい成長戦略のビジョンを提示して、それに向かってビジネスを集中させ、会社を純化し、多様性を失うようなことをしていない。資源依存度の高い商社も、ずっと非資源分野の重要性を訴える苦しい説明を株主にし続けている。過度の純化や集中をせず多様性を確保した「戦略なき戦略」が、商社の置かれた環境では正しい選択であったと思われる。
対照的に都市銀行では、その時代時代に不動産融資、住宅ローン、消費者ローンなど、戦略的と称するターゲットを定めた。そうして社内の目標を設定すると、コストも効率もモラルも度外視で、あらゆる手段を組織的に構築して、多くの社員がそこに殺到した。これは、戦略的アプローチにみえなくもないが、田畑を食い荒らして自らも大量死するイナゴの襲撃のようにもみえる。最近のメガバンクのフィンテックへの殺到具合にも同様の動きを感じるのは、私だけだろうか。このような過度の競争志向のアプローチは、少なくとも持続可能な経営にはみえない。
また、商社とは別の「ポストバブルの勝ち組」である中小の優良製造業をみても、多様性の確保が生き残りに重要だと気付かされる。国内工場を閉鎖して海外生産に完全移行したもののうまくいかず潰れてしまった多くの製造業とは対照的に、優良製造業では国内のマザー工場を残しながら、そのサポートを軸に海外生産を立ち上げて、現在安定的な高収益を出している。
一般的にいって、長期の存続可能性と、短期の効率性は矛盾する。長期存続には多様性が必要だが、多様性を維持するのは無駄が多く、短期的効率性にはマイナスだからだ。ビジネスの言葉でいうと、多角化と短期の収益極大化は矛盾する。
コングロマリットディスカウントに抗った商社
企業価値の分析では、「コングロマリットディスカウント」とよくいわれる。ある会社が多角化した事業を持っているとき、それぞれの分野の事業価値の合計に比べて、その会社の株式市場での株価でみた企業価値が下回っていることをいう。性質の異なる事業を一緒に経営して、ガバナンスを効かせるのが難しいからだ。総合商社は、その典型例として挙げられる。
だから、総合商社の株主やアナリストは、事業を分割して株価を上げろと激しく迫ることがある。これに対して、総合商社の経営者も社員も、頑なに抵抗している。実際、2000年代の商社の急成長と変革を可能にしたのは、この商社の多様性であったと思われる。
組織でも生物でも、環境の変化に直面して存続が危うくなったときに、それまで自分が無駄を含みつつ抱えていた多様性を頼りに、生き残りの道を模索する。商社はバブル崩壊後の危機の時に、それまで細々と試行錯誤していた事業投資型ビジネスの小さな成功をみて、そこに大きく舵を切った。その事業投資型ビジネスで成功して急成長した。
コングロマリットディスカウントを避けよというのは、そもそも、短期保有のファンド系株主の一方的な主張に私にはみえる。ファンド自らは、多角的な分野にポートフォリオを組んで投資して安定性と存続性を確保している。だからこそ、そのポートフォリオを構成する各パーツである投資先会社は、存続可能性などいらないから、短期の収益極大化を目指してほしい。投資先が多角化していないことによって、環境変化に対応できず潰れそうになれば、その株を売って別の会社の株に入れ替えれば、ファンドとしては安泰だ。
ところが、投資先会社のほうでは、声の大きな株主の言うままに多様性を失うと、ちょっとした環境変化でたちまち存続できなくなる。これでは、従業員や少ない会社の株を長期に持っている一般個人株主、取引先など、その会社の存続可能性に大きな利害をもつステークホルダーにとっても、たまったものではない。
多角化を続けながら、コングロマリットディスカウントを避けるには、多角化した事業のシナジーを見せよと、株主から要求されることがある。これも目に見える数字や成功したプロジェクトで見せるのは難しい。しかし、現場では、はっきりと感じる効果があるものだ。
『ふしぎな総合商社』でも説明した、エビ博士の例をみてみよう。アジアの高度技術者人材を日本に紹介するビジネスを検討するときに、エビビジネスのスぺシャリストにサポートを頼むと、エビの養殖場の運営、M&A、工場の運営までやった経験から、人材ビジネスにも実に的確なサポートをしてもらえたという話である。
また、私が観覧車のプロジェクトを、従来の売買仲介型ビジネスから事業型ビジネスに変えて始めたときに、会ったこともないガス事業の部長さんが、「これからの商社はこういうビジネスだ」と言っておられた。商社の事業投資型ビジネスの源流は、60年代から始まった天然ガスのプロジェクトに由来すると私は考えていたので、恐縮至極であった。商社は、このようにまったく違う商品分野で成功した儲け方をお互いよくみながら、新しい事業投資型ビジネスを導入していったのは間違いない。
つまり、2000年代の商社は、存続を志向して多様性を維持したことによって、コングロマリットの間接的なメリットが生じ、その結果として急成長ができたともいえるだろう。
人も入れ替えずに多様性を確保した
会社の稼ぎ方を大きく変えるときには、一般的には社員を大きく入れ替える。しかし、総合商社の業態変革では、売買仲介型ビジネスをしていた社員が、にわかに事業投資型ビジネスを勉強して、試行錯誤してその手法を身につけていった。会社全体の経営をし、案件の評価と管理をする幹部も、戸惑いながら考え方を変えていった。その過程では、現場の担当と管理側でかみあわない議論が行われた。
たとえば、「お台場の観覧車」を従来の売買仲介型ではなく、事業型のビジネスにしようとしたとき、会社の幹部から「観覧車を回すのがウチの仕事か」と問われた。問われたほうは、自分の担当の仕事をバカにされたようで面食らった。しかし今思えば、売買ではなく事業として観覧車を回そうとしている現場の意図を正しく理解した上で、戸惑いながらそこまで当社がやれるのかという質問であった。
また、買収投資案件で企業価値を算定するときに、従来の売買仲介での取引先の債権限度額の算定から、考え方を切り替えられない人もいた。投資ではなく融資の視点で、貸した金を返済する資産があるかどうか、純資産を中心に債権の担保価値から企業価値をみてしまう。具体的には、対象会社がベンチャー企業であっても、その会社の純資産の小ささや、過去に高金利で借り入れて返済した財務履歴に過度に注意が向かってしまう。
投資における企業価値の算定では、業種・業界によって将来に稼ぐキャッシュフローから算定した価値が、企業価値のほとんどを占めることがある。つまり、債権の担保の視点では、過去の稼ぎの蓄積が気になるが、投資の視点では将来の稼ぎの成長に関心が集中する。この違いを自覚的に理解していないと、筋違いの指摘になってしまう。
あるいは、投資総額と投資件数が年度計画よりも少ないとして、「投資規律が弱い」との批判がなされたこともある。私が思うに、お金を稼ぐ売上や利益は、計画を上回り多ければ多いほどよいが、お金を使う投資は、同じ利益を産み出すなら少なければ少ないほうがいい。経費と同じで計画を下回って同じ成果が出せるなら、それに越したことはない。年度の計画を達成するためにリスクの高い投資を無理にしようとするのは、むしろ投資規律の欠如だ。これも、売買仲介型の管理の発想が抜けきれず、投資計画を売上計画の視点でみてしまっているために生じた過ちだろう。
このような指摘をする本人も、自分が売買仲介型ビジネスの視点にとらわれていると自覚していない。指摘された投資案件担当者のほうも、思いもよらなかった指摘を受けて、意味がわからず戸惑うばかりである。まったく別の考え方を理解してもらうのは不可能だと感じてしまう。こうして、すれ違う議論もままあった。
今思えばビジネスの仕方を大きく変えたので、本人が気づかないうちに昔の「売買仲介型」の考え方が出てきてしまうのは、仕方のないことだった。このような、すれ違いを乗り越えてきたからこそ、人材を入れ替えずに変革を実行できたといえる。
今、日本企業の成長のために、なにかというと「ヴィジョンだ」「戦略だ」「選択と集中だ」という“上から目線の評論家的議論”がなされることが多い。しかし、実際のビジネスの現場において、生き残るには必死で多様性を確保し、上下の意向よりも横の成功事例を現場的目線でよくみて試行錯誤していくしかない。
総合商社が生き残った姿をみると、そう思わざるを得ない。
(文=小林敬幸/『ふしぎな総合商社』著者)


















