 「Gettyimages」より
「Gettyimages」より前回の記事で、アマチュアスポーツ界における組織上層部によるパワハラ問題や、独裁的な経営がされている組織などにおける不祥事など一連の騒動は、氷山の一角にすぎず、日本社会全体に“組織の金属疲労”が起きているのではないかと指摘しました。そして、そうした日本の組織で起きている事象は欧米のトップスクールで教えられているネットワーク分析の理論(以下、ネットワーク理論)とプラットフォーム戦略®を学ぶことでより深く理解できると指摘しました。
ここまでS・グラノヴェッターの「弱い紐帯の強さ(“The strength of weak ties”)」、シカゴ大学ビジネススクール教授のロナルド・S・バートの「構造的空隙の理論」「ネットワーク密度」「構造同値」等についてご紹介してきました。
今回ご紹介するネットワーク理論は、「ランダムネットワーク」と「スケールフリーネットワーク」です。『世界のトップスクールだけで教えられている 最強の人脈術』(KADOKAWA)からその内容をご紹介します。
ランダムネットワークとは、分布のピークが真ん中付近にあり、左右対称に長い裾を引くような正規分布のネットワークのことを指します。
人間の身長などが例として挙げられます。大人のうち大多数の人の身長は150~180センチメートルくらいの範囲にあり、身長が10センチメートルあるいは3メートルというような人はまずいません。そして、このランダムネットワークの分布のかたちは、山のかたちになります。
スケールフリーネットワークの特徴
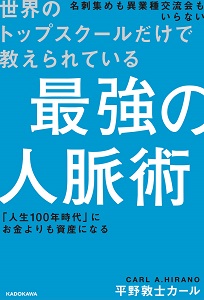 『世界のトップスクールだけで教えられている 最強の人脈術』(平野敦士カール/KADOKAWA)
『世界のトップスクールだけで教えられている 最強の人脈術』(平野敦士カール/KADOKAWA)これに対してスケールフリーネットワークとは、一部のノードが多数のつながりを持つ一方で、ほとんどのノードは少数のノードとしかつながっていないような構造のことを意味します。つまり、スケール(尺度・分布)からフリー(自由)という意味です。
ネットワーク理論においては「点」とこれらを結ぶ「線」からできる図形のことを、「グラフ」と呼びますが、このとき「点」のことを頂点(ノード)、ノードとノードとを結ぶ線のことを辺(エッジ)と呼びます。
スケールフリーネットワークの例としてよく挙げられるのは、World Wide Web(ワールド・ワイド・ウェブ=WWW)です。WWWとは、インターネット上で提供されるハイパーテキストシステムのことで、ウェブページをノードとし、ノード同士はハイパーリンクでリンクされるネットワークです。そこではごく少数のサイトが多数のリンク数を集めるのに対し、大多数のサイトは小さなリンク数にすぎないことがわかっています。
航空網、電力網、あるいは学術論文の引用など、世の中の多くのネットワークの構造は、スケールフリーネットワークであることがわかっています。航空網でいえば、多数の国に路線がつながっているようなハブ空港が少数存在する一方、大多数の空港は少数の路線しかないことなどが例となります。
性的関係においても、多くの人が生涯に数人としか性交渉を持たない一方で、ごく一部の人は100人を超える相手と関係していることがわかっています。このため性感染症などが広まってしまうのは、こうした一部の多くの人と性交渉をもつ人の存在が原因だといわれています。
このスケールフリーネットワークの特徴は、偶発的な障害に対しては非常に強いことです。高速道路網のようなランダムネットワークでは災害などによってノードがいくつか破壊されると、陸地であっても孤島のように寸断されてしまいます。しかしスケールフリーネットワークでは、いくつかの経路が残り続けるのです。インターネットの原型といわれる「アーパネット」というシステムが、もともとは軍用に開発されたもので外部からの攻撃に強い分散ネットワークである、ということからも、その性質の本質がわかることでしょう。
「優先的選択」
それでは、なぜスケールフリーネットワークが起きるのでしょうか。
ノートルダム大学教授のアルバート=ラズロ・バラバシと彼の教え子のレカ・アルバートは、スケールフリー性が実現されるネットワークであるバラバシ・アルバート(BA)モデルを提案しました。
たとえば、10人から構成される人脈ネットワークがあるとします。このネットワークに新しい人(ノード)を加えると、そのネットワークは成長しますが、もしどの人と結びつけるかを等しい確率、すなわち10分の1の確率で決めていったとすると、スケールフリーにはなりません。
しかし、世の中には事実としてスケールフリーのネットワークが多数ある。そこで、いったいどうやったらこうしたネットワークができるのか、ということをBAモデルでは考えました。先の例でいえば、10人のうち、すでにより多くの人物とつながりをもっている人に、新しいノードが優先的につながるという仮定を考えたわけです。
これを「優先的選択」といいます。そこで次数(対象の個数)が高くなった人は、その後、新たに加入する人からさらに新しいリンクを獲得しやすくなります。たとえばフェイスブック、ツイッター、インスタグラムなどですでに多くの人とつながっている人や、フォロワーが多い人は、そこからさらに新しいつながりを得てフォロワーが増えていく可能性が高い、ということが感覚的に理解できるのではないでしょうか。
SNSにおいてもいったんフォローを自分からお願いし、その後、フォローをやめるのを繰り返すことによって、フォロワー数を多く見せる一方、自分がフォローしている数を小さく見せるという涙ぐましい努力をしている人もいますが、これもこの「優先的選択」を無意識に理解しているからです。
これはフォロワー数からフォロー数を引いた数字が大きいほうが、自分が人気者であるかのように装うことができる、という考えから発する行動です。そうすることによって、その人はさらに新しいフォロワーを獲得できるかもしれませんが、まさにこれが「優先的選択」という考え方です。優先的選択とそれに伴う成長によって、ごく少数の中心的な人が、紐帯の大多数を保持するネットワークをつくり出すことができます。
そして、こうした中心的な人になりやすいのは、早い時期からたくさんの人物とつながっている人、ということになりがちです。これは経営学においてよくいわれる「ファーストムーバーアドバンテージ(First Mover Advantage)」、つまり「最初に参入した者がその後も優位に立つ」という先行者優位につながる考え方ともいえます。
SNS上での偽装
このようにスケールフリーネットワークを構築することができれば影響力を持つことができるわけですが、注意が必要です。
たとえばグーグルの検索結果の順位次第で企業の収益が左右されてしまう、あるいはフェイスブックやツイッターなどSNS上における多数派の意見に、多くの人が影響されてしまうという事態が起こってしまうのです。
人は自信がないことについては他人の意見を参考にしますが、本来は少数派であるにもかかわらず、多くの人の意見であるかのようにSNS上で偽装が行なわれてしまうと、その少数意見こそが正しいのではないかと誤認してしまう傾向があるのです。
人脈ネットワークも自然に任せておくと、どうしても自分と似たような考え方の人ばかりとつながる傾向になり、スケールフリーネットワークになってしまいます。とくにフェイスブックなどのSNSでは、自分と近い考え方をする人に「いいね!」などを押すことによって、そうした人との交流頻度がさらに高くなるアルゴリズムのため、多様な意見に耳を貸さなくなっていくことで、いつの間にか自分と同じ意見が世の中の大多数の意見だと勘違いしてしまう危険が生じてしまうのです。逆にいえば、独裁的な組織では異なる意見の人との交流を遮断しようとするのにも、理論的な根拠があるといえるかもしれません。
したがって個人が人脈ネットワークを構築するうえでは、意図的にスケールフリーネットワークにならないよう、自らと異なるさまざまな考え方をする人たちと交流することを心がける必要があります。すでに指摘したように、多様性こそが新たなイノベーションを生み出すわけですから。
(文=平野敦士カール/株式会社ネットストラテジー代表取締役社長)





















