被害者意識が強い“メンヘラ社員”の精神構造とは?口癖は「誰も自分をわかってくれない」

昨今、よく耳にする「メンヘラ」という言葉。心の健康状態を表す「メンタルヘルス」に由来する略語で、特にネット上では心に病を抱える人を指すケースが多い。職場や人間関係でトラブルを繰り返すメンヘラな人々をあらゆる角度から分析しているのが、早稲田大学名誉教授で社会学者の加藤諦三氏の著書『メンヘラの精神構造』(PHP研究所)だ。
“メンヘラ社員”が生まれる2つの原因
同書の「はじめに」では、心理的に問題を抱えたまま社会人になる“メンヘラ”が生まれる原因について詳しく綴られている。
原因のひとつめは、人が成長していく過程で経験する「心理的課題」から逃げ続けることだという。心理的課題を解決せずに年齢を重ねると人生が行き詰まり、被害者意識が強まっていき、人間関係でトラブルを引き起こすメンヘラになってしまう。
ふたつめは、幼い頃から与えられた破壊的メッセージを解決できるかどうか。ここで言う破壊的メッセージとは「お前は生きる価値がない」など、個人の存在を否定するような言葉を指す。通常、人は破壊的メッセージと命がけで戦いながら、自分の長所や自分だけの素晴らしさに気づくことができるという。
「この戦いから逃げて被害者意識に逃げ込むと、最高の自分、素晴らしい自分に気がつくことなく、人生が行き詰まる。この破壊的メッセージは、一つめの『それぞれの時期の人生の課題解決』についても最大の障害となる。要するに、それぞれの時期の人生の課題の解決ができないことが多い」(同書より)
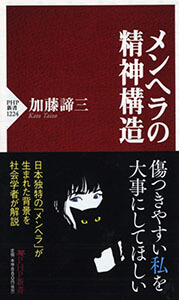
心理的課題と向き合わないまま社会人になると、どれだけ出世しようとも“人間関係のトラブル”を引き起こす。そうした人々を、同書では「メンヘラ社員」と定義している。
メンヘラ社員たちについて、加藤氏は「騒ぎ嘆くだけで、困難に具体的に対処しない」と解説している。彼らは被害者意識が強く「ひどい目に遭った!」と騒ぎながら他者を攻撃し、本心では「私をもっと大切にしてくれ、私をもっと褒めてくれ」とアピールしているという。
また、会社の役職や年齢と精神の健康は関係ない、と加藤氏は強調する。
「メンヘラか心理的健康かは、部長のポストか部下のポストかは関係ない。問題はその人のパーソナリティーである。心理的に健康な新入社員もいれば、心の病んだ課長もいる。心の病と会社のポストは関係ない」(同書より)
私たちは、つい「会社で役職に就いているなら、人格者なのだろう」と考えてしまいがちだ。しかし、メンヘラの心理を知るためには、まず先入観を捨てる必要がありそうだ。
“メンヘラ社員”とナルシシズムの関係性
同書では、現代のメンヘラを読み解く重要なキーワードとして「ナルシシズム」を挙げている。ナルシシズムは「自己陶酔」や「うぬぼれ」と訳される。そのため「自分の容姿が好きな人」というイメージが強いが、加藤氏はナルシシズムとメンヘラの関係についても同書で説いている。
「ナルシシストには、大きく分けて二つのタイプがあるといわれている。(中略) 露出症的で壮大な自我像を持ったナルシシストと、過敏に反応し、傷つきやすいナルシシストといる。日本人はどちらかというと後者のタイプが多い。そしてこの過敏で傷つきやすいナルシシストはもちろん内向的で防衛的である」(同書より)
タイトルにもなっている「メンヘラの精神構造」の本質もまた、後者の“過敏で傷つきやすいナルシシスト”を指すという。そして、彼らは総じて「被害者意識」が強いのも大きな特徴だ。
メンヘラ社員たちは、ナルシシズムが傷つけられたときの対処法として「被害者の立場」を取る。自分が被害者になることで、周囲への敵意を否定しながら“怒り”を表現するのが、彼らの処世術だという。たとえば、職場で「私ばかりがひどい目に遭う」と主張している人は、特定の敵をつくらずに不満を漏らしている“メンヘラ社員”の可能性が高いという。
「誰も自分をわかってくれない」が口癖に
著者の加藤氏は、ラジオ番組『テレフォン人生相談』(ニッポン放送)のレギュラーパーソナリティとして、人々の悩みに長年耳を傾けてきた。中には、メンヘラな人々からも相談が届くという。
「私は50年以上、悩んでいる人から手紙をもらい続けました。そして、つくづく『これは悩むだろうなあ』と感じます。また、ラジオに電話をくれる相談者も、とにかく要求が多いんです。周囲の人はその非現実的な要求に耐えられず、逃げ出してしまうのです。赤ん坊なら母親にむちゃくちゃな要求をしてもおかしくないですが、メンヘラな人は大人になっても周囲の人に同じ態度を取ってしまい、自分のむちゃくちゃな要求が通らないと傷つき、怒り、悩みます。不幸になるメンヘラの要求は、見境がないのです」(加藤氏)
メンヘラたちは、要求の多さに加えて、強い不満や不公平感を抱いているケースが多い。その結果、会社や周囲から孤立して「誰も私(俺)の気持ちをわかってくれない」という言葉を発するのも特徴だという。
「不公平感を抱いて周囲に敵意を抱けば、人間関係はうまくいきません。しかし、ナルシシストは傷つきやすく、自分の怒りや不満は正当なものと認識しています。同時に、物事が自分の期待に反して進んだときに『なぜそうなったか』が考えられず、すべて自分以外が悪い、という“被害者意識”に苛まれるのです」(同)
メンヘラたちは周りに責任を転嫁して、問題から目をそらし続ける。周囲にも迷惑をかけるが、メンヘラ本人もつらく苦しい日々を送っているのかもしれない。
加藤氏は『メンヘラの精神構造』を執筆した理由について、こう語る。
「きっかけは、コミュニケーション能力が衰えている人々が増えた、と感じたことです。具体的には、いろいろな人との関わり方がわからずにキレてしまう人です。近年、職場ではパワーハラスメントや過労死の問題が注目され、家庭ではドメスティック・バイオレンスやモラルハラスメント、幼児虐待が増えています。社会的にはギャンブル依存症やアルコール依存症など、依存症問題が増えているのは誰が見ても明らかです。このまま問題が山積すると、社会が社会として成立するための共通感覚が失われていきます」(同)
さまざまな問題が浮上する現代社会の根底に、メンヘラの存在があるという。そして加藤氏は、心の病が増えている日本では「今後もメンヘラ社員が増えていく可能性が高い」と指摘する。
「勝ち組と負け組では社会的階層がまったく違うはずなのに、今の日本人はいずれも他者に対する感情を失ってお互いに張り合っている状況です。これこそが、日本人の心が崩壊した原因だと考えています」(同)
『メンヘラの精神構造』は、さまざまな観点で“メンヘラ”について考察している。厳しい言葉も多く書かれているが、最後の章では「メンヘラ本人ができる四つの改善策」を提示し“救いの道”を示している。人間関係や自分を追い込む“被害者意識”に悩んでいるなら、同書がその原因を探るヒントになるかもしれない。
(文=谷口京子)











