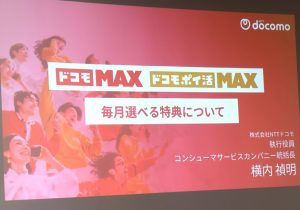指揮に不可欠な「叩き」とは?しゃくい、跳ね上げ…指揮者以外は知らない特殊用語

「叩きの練習をしっかりやって」
「しゃくいができてない」
「引っ掛けを教える」
このような言葉を聞いても、皆さんは何の話かよくわからないと思いますが、僕が通っていた音楽大学の指揮の教師の言葉です。日本人指揮者なら、やる・やらないは別として、知らない人はいないはずです。ほかにも、「平均運動」「跳ね上げ」のように、まるで体操の競技のような名前があったり、どういう動きか名前からは想像もつかない「先入」は、音楽大学時代に、難関中の難関として立ちはだかりました。
これらは、日本の指揮教育の第一人者で、小澤征爾氏、秋山和慶氏、飯守泰次郎氏、尾高忠明氏らを育て、世界の第一線に送り込んだ名教師、斎藤秀雄氏がつくった言葉です。斎藤氏は、昨年のショパン国際ピアノコンクールで第2位を受賞し、今も話題の渦中にいる反田恭平氏を輩出した桐朋学園音楽科の創設メンバーの一人でもあります。実は、僕も斎藤氏の孫弟子にあたります。
斎藤氏は、本人も指揮者として活躍なさったのですが、それ以前に優秀なチェロ奏者でした。ドイツ留学を果たしたのちに帰国し、NHK交響楽団の前身である新交響楽団の首席チェロ奏者を務めました。斎藤氏から直接習ったチェロ奏者は少なくなりましたが、多くの孫弟子、ひ孫弟子が、現在でも大活躍しています。ちなみに、当時の新交響楽団のコンサートマスターは、女優・黒柳徹子さんのお父様の黒柳守綱さんです。
そんな斎藤氏が音楽の本場ドイツから帰国してまず取り組んだのは、チェロだけでなく、指揮の教育でした。ドイツで多くの大指揮者をつぶさに見ながら、「どうしたら、あのように指揮者がオーケストラを自由にコントロールできるのだろうか?」と研究したのです。そこで、「指揮のテクニックというものが、運動に関する事柄である」(著書『指揮法教程』より)と理解し編み出したのが、前出の「たたき、しゃくい、ひっかけ」などの運動の名前を付けたテクニックでした。
実は指揮だけでなく、音楽を演奏することは肉体運動です。意外に思われたかもしれませんが、たとえばヴァイオリンを演奏するのも、左手の指を信じられないくらい速く動かしながら、右手に持った弓で音を出すために大きく腕を動かしますし、オーケストラの中で一番大きな楽器のコントラバスのように、身長よりも大きな楽器を演奏するのは、それこそ全身運動です。管楽器は息を吹きこむので体全体を使いますし、打楽器も腕を酷使します。
そんななか、情熱的に体全体を使って指揮をする指揮者は、ものすごい運動量です。本人は大好きな音楽を夢中でやっているだけですし、僕も長い間、指揮者をしているので慣れましたが、20代のデビューをした頃は、コンサートの翌朝、今まで経験したことがないような全身の筋肉痛で、ベッドから起き上がることができませんでした。
指揮者に不可欠な「叩き」の技術
ところで、もう35年くらい前のことですが、指揮者になりたいという野望を抱えた僕は、桐朋学園大学に入学して意気揚々と初めての指揮のレッスンに向かいました。ほかの大学の指揮科は存じませんが、今も桐朋学園では、ピアノやヴァイオリン、声楽のようにマンツーマンで教師が生徒を仕込んでいくのとは違い、指揮科だけは集団レッスンです。
集団といっても、みんなで一緒に指揮をするわけではなく、一人が指揮をしているのをほかの生徒が見ながら意見を出したりするのです。時にはレッスンが先に進んでいる下級生から辛辣な指摘をされて悔しい思いをしつつ、もちろん教師にもしぼられるわけです。しかし最初は、同じ1年目の生徒と並ばされて、まずは「叩き」を仕込まれたのが、僕の指揮の初レッスンでした。
「ベートーヴェンを指揮できるかも。いや、もしかしてチャイコフスキーか」などと夢見ている指揮の生徒に与えられた課題は、まずピアノの下に手を置き、瞬間的に上方に力を加えてすぐに脱力して腕を落とす。そうやって、指揮に使う前腕部の筋肉を鍛え上げるのですが、僕が習った時代には、これを毎週、毎週、それこそひと月くらい繰り返していました。
先輩からは、「腕の上に10円玉を置いて、筋肉に力を入れて上に飛ばせ」「500円玉でも飛ばせるよ」などと、本当か嘘かわからないような話を聞かされながら、暇があればピアノの下に手をかざしていました。もちろん、一般授業でも講義を聴きながら、机を使っていそいそと練習に励みました。
今はそこまではやらないかもしれませんが、そうやって出来上がった筋肉を使って、空気中を鋭く叩く動作をする。一般的に皆さんがよく見る指揮の動作ですが、これを斎藤先生は「叩き」と名付けたのです。
腕をしゃくうような運動だから「しゃくい」、引っかけるような動作の「引っ掛け」、速度変化なく腕を動かす「平均運動」、腕を跳ね上げるから「跳ね上げ」、音が出る直前に指揮棒を下ろしてから、ちょうどのタイミングで次の動きを始めるので「先入」。ベートーヴェン交響曲第5番『運命』を指揮するのに苦労している学生に、指揮教師はこれらの言葉を使って的確に指導していきます。
世界的指揮者の小澤征爾氏も、オーケストラをコントロールしづらい時には、ホテルの鏡を使って「叩き」をチェックしていたそうです。欧米の著名指揮者であっても、僕はその指揮姿を見ながら、「あれは叩き、あれは引っ掛け」と、すべて当てはめることができます。もちろん、当の外国人指揮者が知らない言葉ではありますが、とても実用性のある用語なのです。
しかし、それらを知っているだけで素晴らしい音楽ができるわけではありません。あくまでも、自分が考えている音楽をオーケストラに伝えるためのひとつの手段であることは、斎藤秀雄氏の著書『指揮法教程』(音楽之友社)でも触れられているとおりで、指揮者に音楽の能力がないことには話になりません。しょっちゅう怒り出して、自分がかけている眼鏡を床に叩きつけ、踏みつけて壊してしまうほど、とにかく怖かったことで有名な斎藤先生は本書で、指揮と音楽について細かく、厳しく書かれていますが、ユニークなのは最後に、なんと指揮者の服装について触れていることです。
「指揮者は常に演奏者と聴衆の注目を受けるのであるから、服装については、十分な注意が必要である。(中略)些細なことであるからといって、ネクタイが曲がっていたり、ボタンがとれていたりする儘、指揮をし演奏者の信頼を損ねるような事があれば、それは単に服装の問題に止まらず、指揮に依る統率力にひいては演奏全体にその影響が及ぶことになると言っても決して過言ではない」
服装に無頓着な僕には正直、痛いところを指摘されていますが、一般企業のリーダーも同じではないかと、仕事柄、大企業の社長や取締役にお会いするたびに痛感するのです。
(文=篠崎靖男/指揮者)