非難轟々の【元少年Aの手記『絶歌』】で軽視される「言論の自由」と出版の意義
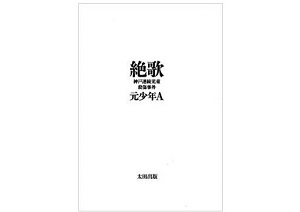 被害者遺族の反発もあり、その出版が批判されている『絶歌』。販売を自粛する書店もあるが、出版流通大手のトーハンが発表した週間ベストセラーでは総合1位を記録した(16日時点)。
被害者遺族の反発もあり、その出版が批判されている『絶歌』。販売を自粛する書店もあるが、出版流通大手のトーハンが発表した週間ベストセラーでは総合1位を記録した(16日時点)。神戸の児童連続殺傷事件の加害者である「元少年A」(32)=事件当時14歳=が出した手記『絶歌』(太田出版)に、轟々たる非難が起きている。本に対する評価は人それぞれだし、「こんなものは読みたくない」という人がいても当たり前。私が気になるのは、「遺族の許可なく出版すべきでない」「印税収入はすべて被害者に渡すための法律を作れ」などと出版に対する規制を求める動きや、行政が本の販売や購入の自粛を求めたり、貸し出し制限をする図書館も出るなど、表現の自由にもかかわる動きが出ていることだ。
置き去りにされた「表現の自由」
被害者の1人である土師淳君(当時11)の父親、守さんは、手記の出版に強く反発し、報道を通じて憤りのコメントを発表。出版社にも回収を求める書面を送った。土師さんは、出版によって「重篤な二次被害」を受けているとし、加害者による手記などの出版は「被害者の承諾を得るべきである」と主張している。
以前、Aの両親が手記『「少年A」この子を生んで』(文藝春秋社)を出版した時も、土師さんは事前に了解を得なかったことなどを強く批判している。今年4月、月刊誌「文藝春秋」5月号に、医療少年院送致にした神戸家裁の決定全文が掲載された時にも、土師さんは抗議の声を上げた。むごい事件だったこともあり、自身がコントロールできない形で愛息の殺害にかかわる情報が発せられることに、強い警戒心を抱いているのだろう。
そういう被害者の心情を考えれば、遺族が報道機関から出版を知らされて驚くことがないよう、少し前には本の概要などを伝えておいたほうがよかった。Aがやらないなら、出版社がやるべきだったろう。それは、遺族への配慮であると同時に、出版社が著者の立場を守るためにも必要だったと思う。
ただ、事前に伝えたとしても、土師さんは出版に納得しなかっただろう。その心情や自身の見解を、土師さんが述べるのは自由だ。だが、「加害者の出版には被害者の承諾を得るべき」との見解を、「表現の自由」に敏感であるべきメディアの多くが、きちんとした解説や論評もないまま報じたことには疑問を感じる。
もちろん、「表現の自由」とて、絶対ではない。名誉毀損やプライバシーの侵害に当たるとして出版が差し止められたり、法律で禁じられたわいせつ図画に当たるなどとされた場合には刑罰まで科せられる。その判断を下すのは裁判所、最終的には最高裁だ。
罪を犯した者といえども人間であり、その人から「表現の自由」という基本的人権を取り上げるか否かという最高裁裁判官のような重い役割を、遺族に担わせることが果たして適切なのだろうか。こういう理性的な問いを、メディアはもっと発するべきだろう。
一口に「被害者」「遺族」といっても、考え方や感じ方は一様ではない。メディアでは、土師さんの発言が盛んに伝えられているが、やはりAによって殺害された山下彩花ちゃん(当時10)の母親、京子さんもコメントを出している。京子さんは、突然の出版に戸惑いながら、「なんのために手記を出版したのかという彼の本当の動機が知りたいです」と述べていて、土師さんとは違った思いがあるように受け取れる。
同じ被害者でも異なる受け止め方
これまでも、加害者が手記を書いた事件はいくつもある。連続ピストル射殺事件の永山則夫は、手記『無知の涙』(合同出版、のち河出文庫)を発表して注目され、以後、死刑が執行されるまで獄中作家として執筆を続けた。文学賞も受けている。遺族が出版を批判したという報道に接したことはないが、永山は日本文藝家協会への入会を拒否された。そのことに抗議して、柄谷行人、中上健次、筒井康隆、井口時男らが同会を脱会している。
オウム真理教の地下鉄サリン事件では、最初に事件への関与を告白し、裁判では自首が認められて無期懲役となった林郁夫が、手記『オウムと私』(文藝春秋社)を執筆している。
林がまいたサリンによって夫を殺害された高橋シズヱさんは、その出版を報道で知った。林本人からはもちろん、弁護人や出版社などから、事前に連絡はなく、事後に手紙や献本もなかった。
「裁判を傍聴した人はわずかだし、後になってから事件を知りたい人もいるだろうから、こういう記録を残すことは必要だと思ったので、別に腹も立たなかった」と高橋さん。
高橋さんは裁判を傍聴し、林の供述や証言を聞いており、何が書かれているかは察しがついたので、すぐに読みたいとは思わなかった。
「でも、後から読みたくなるかもしれないと思って、本屋さんで一冊買いました」
高橋さんは、後世に事件の記録を残すためには、被害者サイドの記録も必要だと考え、その後、自身の手記を出版している。
秋葉原無差別殺傷事件を起こした加藤智大死刑囚も、手記『解』(批評社)を出した。被害者や遺族からは、その内容に「子どもの言い訳」などと批判の声が上がっているが、出版そのものをとりやめろという動きにはなっていないようだ。
このように、犯罪の被害者でも受け止め方はいろいろだ。土師さんの見解は、土師さん個人の見解であって、被害者を代表する見解というわけではないだろう。それに、死者13人、重軽傷者が6300人もいる地下鉄サリン事件のようなケースでは、被害者一人ひとりの承諾を得ることなど不可能な話だ。「加害者は被害者の了解がなければ出版してはいけない」などと、一般化して議論できる話ではない。もっと冷静な受け止めが必要だ。
『絶歌』出版は無意味ではない
『絶歌』については、明石市が書店や市民に「配慮」を求め、泉房穂市長が「遺族の同意なく出版されること自体許されない行為で、加担してほしくない。私個人の思いとしては売らないでほしいし、買わないでほしい」と発言。いくら被害者感情に対する配慮といっても、自治体の長が出版物の販売や購入の自粛を要請する趣旨の発言をするのは尋常ではない。
図書館にも閲覧制限の動きが出ている。明石市図書館では本を購入せず、兵庫県立図書館では貸し出し制限として、「研究目的」に限り館内限定で閲覧を認め、複写は一切認めない、という。
いずれも被害者感情に配慮するあまり、人々の知る権利が過小に扱われてはいないだろうか。図書館関係者は、日本図書館協会が採択した「図書館の自由に関する宣言」を読み直してもらいたい。
また、印税収入の扱いをめぐって、多くのメディアに「サムの息子法」なる米国の法律が紹介されている。犯罪の加害者が犯罪行為に関わる手記の出版などで得た収入を、被害者の申立によって取り上げることができるようにする法律と説明されている。こうした法律の制定を求める声が高まっているという報道もあり、ネットでのアンケートでも同様の結果が出ているようだ。
しかし、少なくとも今回のケースでは、現行制度で対応ができるはずだ。土師さんが約1億円の損害賠償を求めた民事裁判は、A側が争わなかったため請求通りの金額で判決が確定している。「週刊文春」(文藝春秋社/6月25日号)によると、Aと両親は、他の被害者2人の分も含めて総額約2億円の賠償責任を負った。両親の手記の印税やAの父親の退職金に加え、毎月A自身が1万円、両親が6万円ほどの支払いを続けているが、現在でも1億数千万円の負債が残っているという。
この場合、土師さんは、Aの印税支払い請求権を差し押さえるなどの法的措置をとることができる。前述したオウム事件の林郁夫の本については、遺族ではない被害者が印税を差し押さえる手続きをしたと聞く。表現の自由や財産権のうえで問題になりそうな新たな法を作って規制しなくても、すでに法的手段は用意されている。メディアは、そこをきちんと伝える必要があるのではないか。
また『絶歌』の編集者は、ネットメディアの取材に対して、「著者本人は、被害者への賠償金の支払いにも充てると話しています。これまで著者自身としては微々たる額しか、支払えていなかったということですので」(弁護士ドットコムより)と述べており、わざわざ土師さんが法的措置をとる必要もないかもしれない。
先の「週刊文春」によれば、Aは執筆している間の生活費を出版社から借りているらしい。また、これだけの騒ぎになれば、しばらくアルバイトをすることも難しいだろう。それを考えると、全額召し上げろというのは酷に過ぎるような気がする。生活すらままらない状況に追い込めば、社会に対する恨みや疎外感を募らせるだけはないか。罪を犯し、裁判所が定めた矯正措置を終えた者を社会が受け入れなければ、受け入れてくれる所は刑務所しかなくなる。
冒頭に書いたように、ひとたび出版された本に対する評価は自由である。この本に対するどんな酷評もあってよい。ただ、本の出版の意味がまったくないかのような論評は、言い過ぎのような気がしている。
彼の更生のために、少年院を仮退院してからも、多くの人が彼に関わったことを、私はこの本で初めて知った。里親となって彼を受け入れた夫婦もいる。そうした人たちとの関わりの中で、彼が少しずつ「命」を実感していった経緯が見て取れて、犯罪者の更生という点でいろいろ考えさせられるところがあった。
Aが起こした事件が与えた影響は大きい。「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いが若い人から発せられたり、殺人を犯した者が「誰でもいいから人を殺してみたかった」と供述する事件がいくつも起きている。Aは一部の人たちに「神」扱いされ、名古屋で女性を惨殺した女子大生なども、「Aを尊敬している」と伝えられている。
そのAも、この本を読む限り、罪の大きさにおののく「ただの人間」だ。「なぜ人を殺してはいけないのか」の問いに、彼なりの答えも出している。この本が、彼への歪んだ「尊敬」や「憧れ」が色あせるきっかけになればと願う。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)











