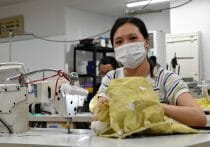“外国人の人権は全て守られるべき”なのか?…法社会学者が問うウィシュマさん事件の真相
名古屋出入国在留管理局にて収容中のスリランカ人女性(当時33歳)、ウィシュマ・サンダマリさんが2021年3月に死亡した。ウィシュマさんの死は、おりしも政府が第204回通常国会に提出した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」(入管法改正案)審議のさなかに報じられ、人々の注目を集めることとなった。
政府の提出した入管法改正案は「退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとするため、在留特別許可の申請手続の創設、収容に代わる監理措置の創設、難民認定手続中の送還停止に関する規定の見直し、本邦からの退去を命ずる命令制度の創設等の措置を講ずるほか、難民に準じて保護すべき者に関する規定の整備その他所要の措置を講ずる必要がある」ことを改正の理由に掲げるものであった。
しかし、ウィシュマさんの死をめぐって繰り広げられた与野党協議の決裂や入国管理行政に対する世論の反発もあって、この第204回通常国会での採決は見送られ、さらにそこから1年たち、岸田政権発足後初の通常国会となる第208回通常国会でも再提出はされない見通しとなっている。
一方で2021年8月には、ウィシュマさんの死亡前の様子を映した施設内の監視カメラ映像の一部が遺族に開示され、政府は死亡の経緯に関する最終報告を公表している。しかし野党側は、「報告書は不十分」として映像の開示を要求し続け、2021年12月の衆院法務委員会の与野党筆頭間協議でようやく合意。遺族に追加の映像が公開され、衆参両院の法務委員会の議員らにも一部映像が開示されたものの、全容解明はいまだ道半ばだ。
ウィシュマさんの死は痛ましいものであり、故人の冥福を祈るとともに、二度と同じような事案が起きないよう、真相の究明と問題の把握、改善策の実行といった対応が求められることは論をまたない。また、ウィシュマさんの死が日本の入国管理行政に一石を投じたのもまた事実であろう。
しかし、ウィシュマさんの死を奇貨として入国管理行政を糾弾し、「人権意識に優れた欧米諸国では日本と比べものにならないほど難民を受け入れている。日本もそうあるべきだ」といった“出羽守”的な議論には、慎重な意見もある。もとより、入国管理行政は突き詰めて考えれば、「誰を国民として扱い、また扱わないか」「外国人をどう扱うか」という国家観そのものの問いに行き着くとともに、「人権を擁護するために、何が求められるか」という人権論とも結びつく。
法社会学者で桐蔭横浜大学法学部教授の河合幹雄氏は、「日本の入国管理行政を論じるには、まずその歴史・社会情勢、そして表裏一体の関係にある諸外国の入国管理行政と歴史・社会情勢を理解しなければならない。それらを理解すれば、入国管理行政の背景にある国家観や人権観も見えてくる」と語る。
その発言の意味とは? 日本の入国管理行政はどのような歴史・社会情勢に立脚しているのか? それは世界的にイレギュラーなのか? 日本、そして世界の入国管理行政の背景にある国家観・人権観とは?
本連載では今回、前後編の2回にわたり、ウィシュマさんの死という結果を招いた日本の入国管理行政・社会情勢と現在に連なる歴史的経緯(前編)、難民の取り扱いに関する日本および欧米諸国の異同(後編)を取り上げ、国家と人権について紐解いていきたい。
国家と人権についての価値観は数あれども、必要なのは近視眼的な人権擁護論に留まらない、歴史的経緯や各国の姿勢を踏まえた実効性ある議論であろう。第二、第三のウィシュマさんを生まないためにも――。
【後編「日本は難民を拒否する冷たい国」なのか?…法社会学者が考えるウィシュマさん事件の意味」】はこちら

「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」
――名古屋出入国在留管理局による収容中に亡くなったウィシュマさんの2021年3月の死をきっかけに、当時、国会で審議中であった入管法改正案に関する議論が広く世論を巻き込んで行われることとなり、結果として当時の菅義偉首相率いる政府は、この入管法改正案を成立させることができませんでした。そもそも、ウィシュマさんの死と入管法改正の背景にはどういった事情があるのでしょうか?
河合幹雄 ウィシュマさんの死はショッキングな事案ですし、徹底した再発防止が求められるのはいうまでもないことです。しかし、ウィシュマさんの死と入管法改正をめぐる議論においてまず理解すべきは、およそあらゆる近代国家において、自国民と外国人の間には不平等が存在し、かつそれが容認されているということです。憲法学においては「外国人の人権享有主体性に関する問題」、つまり外国人に日本国憲法で保障されている基本的人権が認められるか否かの問題として議論されていますが、外国人の人権を国家がどこまで認めるかについては各国でばらつきがあります。
日本では1970年代、ベトナム戦争や日米安保条約に反対する政治活動に参加したことなどを理由に在留期間の更新が不許可となった米国籍のロナルド・アラン・マクリーン氏が国を相手取って争った事件がありました。これは「マクリーン事件」と名づけられ、外国人の人権享有主体性を語るうえで欠かせない事件です。マクリーン事件において、最高裁判所大法廷は1978年10月4日の判決で「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」としながらも、「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」とし、マクリーン氏の訴えを認めませんでした。
マクリーン事件のこの判決は、外国人にも政治活動の自由を認めています。しかし、その結果、法務大臣によって在留期間の更新不許可処分がなされたことについては、判断の基礎とした重要な事実に誤りがあるといった場合を除いて、法務大臣に広い裁量があるとされました。政治活動の自由はあるが、事実上の不利益が生じるのはやむなしということですね。
ただし、だからといって「外国人に対してなら何をしてもいい」という話にもなりません。自国民と外国人の間で不平等が存在する一方、最低限の人権は守らないといけません。まず、これらの前提を理解することが必要です。
話が複雑になってくるのは、ここに移民問題が関連してくるからです。自国民と外国人の間には不平等が存在し、かつそれが容認されているにもかかわらず、なお移民が発生するのは、国家間の経済格差があるからです。たとえばウィシュマさんの母国であるスリランカと日本でいうと、国際労働機関(ILO)のデータによれば、両国の賃金格差は10倍以上です。これほどの違いがあれば、日本国内では低水準の賃金であっても、本国で働くより断然稼げると考えるのは自然なことです。
そして、わざわざ自国を離れて外国に働きに来る人たちですから、彼ら彼女らの大半は能力が高く、バイタリティのある人たちです。同水準の賃金で働く自国労働者と比較すれば、言語の問題は別にして移民労働者のほうが優秀である可能性が高い。かくして、移民を受け入れる企業からしても、低水準の賃金で能力の高い労働者を確保でき、双方の利害は一致するわけです。さらにいうと、企業としては景気が良い期間には働いてもらい、景気が悪くなったら本国に帰ってもらえれば、理想的です。こうした移民労働者とそれを受け入れる企業の構図は、フランスやスイスといったヨーロッパ諸国でも変わりません。

「移民が増えると治安が悪化する」は本当か…問題が顕在化する“二世問題”と「ホームグローンテロリスト」
――受け入れる企業と移民労働者の間で利害は一致しているからこそ、自国民と外国人の不平等が公然と存在していても大きくは問題にならないということですね。ところで、移民が増えると治安が悪化する、というのは巷でよく見受けられる議論ですが、その点についてはいかがですか?
河合幹雄 そこにも論理の飛躍があります。まず、移民労働者自身は先ほども説明したように、優秀な労働者である場合がほとんどです。そもそも働いてお金を稼ぐことが目的であり、知り合いは少なく土地鑑もない。そんな環境で、わざわざ犯罪に手を染める理由がありません。普通に考えて、道を踏み外すのは就労先の企業が倒産してにっちもさっちも行かなくなったとき、あるいは悪徳企業にあたってしまい賃金を十分に支払ってもらえない場合、くらいのものです。
移民に関して問題が顕在化するのは、移民労働者の子どもが学校に通い始めたときです。いくら親である移民労働者の能力が高く、バイタリティがあるといっても、子どもに現地の言葉を教えるという点では、問題のある場合が多いです。たとえば、日本人夫婦がフランスに駐在しているときに子どもが産まれたとして、自分たちで子どもにフランス語を教えられるかというと、そう簡単にはいかないのが実情でしょう。
同様の問題が、移民労働者の子どもの言語教育には横たわっています。そうした移民労働者の子どもたちがたくさん学校に通っていると、当然自国民の子どもたちと比べて教育に手間がかかり、結果として学校全体の学力が低下することが多いです。かくして、地域住民と移民労働者の間で軋轢が生じてくるわけです。また、子どもたちも学校の勉強についていけなければ、不良グループの仲間入りをするといった非行に走りやすくなります。
主にヨーロッパでは、移民労働者の子どもが言語障壁や苦しい家庭環境のために現地社会に適応できず、不満を募らせていくといった事象がみられます。そうした子どもたちは、まだ見ぬ母国への憧憬と生まれ育った現地社会への怨嗟を屈折させ、自身の生まれ育った現地社会やヨーロッパ諸国を対象とする「ホームグローンテロリスト」となることもあり、大きな社会問題となっています。
まとめると、移民労働者の受け入れは短期的には企業のコスト減につながり、「儲かる」話です。しかし、長期的には子女の語学教育をはじめ、彼ら彼女らとその家族を社会に適応させるための社会的コストが発生します。少子高齢化が進む日本において、移民労働者の受け入れが必要であるという主張は一理ありますが、では誰がそれに伴って発生するコストを負担するのか? そもそも、どのように移民労働者を受け入れるのか? そうした議論がまったく煮詰まっていないというのが現状です。
留学生、日系ブラジル人、そして外国人技能実習制度…日本への“移民”と、入国管理行政の戦後史
――自国民と外国人の間の不平等に関する背景や移民労働者に関する問題などに関する議論が理解できました。ところで、日本においてどのように移民労働者を受け入れるのかについての議論はまったく煮詰まっていないとのことですが、一方で外国人技能実習制度をはじめ、日本でもさまざまな政策が実行されています。日本において、外国人の就労に関する入国管理行政は、どのように整理できるのでしょうか?
河合幹雄 日本で外国人留学生にアルバイトが解禁されたのは1983年、ちょうどディズニーランドが開園した年です。外国人留学生へのアルバイト解禁の背景にあるのが、中曽根康弘内閣の打ち出した「留学生10万人計画」です。この計画が発表された当時、日本に来ていた留学生は約1万人、うち約7500人が私費留学生、残りは国費留学生や外国政府からの派遣留学生でした。
そこからさらに9万人といっても、国費留学生や外国政府からの派遣留学生はそんなに増やせませんし、なにより予算がない。そこでターゲットは主に私費留学生となるわけですが、そうすると日本で生活していくだけのお金が必要になる。だからアルバイトを解禁します――というロジックだったわけですね。もっともそこには、単純労働を低賃金で引き受けてくれるありがたい労働者としての側面もあったとみることもできますが。
その後、留学を隠れみのにした就労目的の来日や、不法残留などが問題になりつつも、来日留学生の数は増加し、留学生10万人計画も2008年には留学生30万人計画へと形を変え、現在に至っています。
留学生のアルバイトはそうした形で始まり、変化してきたわけですが、移民労働者に対してはまた違った経緯があります。まず、世間一般のイメージ通り、伝統的に日本は移民労働者をなかなか受け入れようとしませんでした。一方で、特に工場での単純労働や農繁期の収穫などの季節労働における労働力不足の解決策として、移民労働者の必要性が日増しに高まってきていたのも事実です。
そこで政府が目をつけたのが、日系ブラジル人です。政府は1990年に日本人であるブラジル移民1世の子または孫とその配偶者に限った受け入れを開始しました。行政のやることですから、条件を満たす人は平等に取り扱わないといけません。しかし、単純に移民労働者のハードルを下げると大挙して人が押し寄せてしまい、困ったことになる。移民労働者は欲しいが、数万人レベルで細々と受け入れたい。しかも、できれば世論の反発を招かない形で――。
日系ブラジル人の移民労働者は、単純労働や季節労働に対する労働力不足のみならず、ルーツが日本人であることや、条件を満たす人がそこまで多くないこと、そしてブラジルが経済的に苦境に立たされていたことなど、彼ら彼女らを取り巻く状況が時代のニーズにマッチしていたことで始まったのです。
彼ら彼女らは群馬県太田市や栃木県小山市といった工場地帯を中心に移住し、そのまま定住した人も数多くいます。そうした地域では日系ブラジル人コミュニティが形成され、ブラジルの食材などを扱うスーパーなどが営業しているほか、標識にブラジルの公用語であるポルトガル語が併記されている場合もあります。
悪名高き「外国人技能実習制度」…“移民反対”の警察・法務省が受け入れを認めたきっかけ「顔認証技術」
河合幹雄 そして、入国管理行政において今もっともホットなのが、ご存じ「外国人技能実習制度」です。この制度は、日本企業の海外工場で働く現地採用の従業員に対して、社員教育として行っていた研修が源流です。1993年に法整備がなされて制度化されたのち、何度かの修正を経て今の形に至っています。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」、いわゆる技能実習法の第一章第三条では、基本理念として「技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない」「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされています。人手不足を安く解決するためのものではなく、あくまで開発途上国の人材育成への貢献が目的ということですね。
監理団体等の制度も整備されていますし、性善説に立てば、程度の差こそあれ、おそらく多くの企業において外国人技能実習制度は制度の趣旨にのっとって運営されており、技能実習生と彼ら彼女らの本国にとって有用な制度であると信じたいところです。
しかし、いくら技能実習生を受け入れる産業界がそのように主張しても、警察や法務省はそうした性善説に立ってくれません。警察や法務省の関心は外国人の不法就労や治安の悪化にありますから、基本的に労働者としての外国人受け入れには反対なのです。
ここでポイントになったのものは何か。実は、「顔認証技術」なのです。技術の発展によって、かなりの精度で個人を特定することができるようになり、悪事を働いた外国人を強制退去させてしまえば、たとえパスポート上では別人になりすまして再度日本にやってきても、二度と入国させない――などといったことが可能になりました。この顔認証技術があったからこそ、労働者としての外国人受け入れに消極的な警察や法務省も、制度導入を受け入れた。かくして、外国人技能実習制度は今の形となったのです。
**
ここまで、留学生のアルバイト解禁、日系ブラジル人の受け入れ、そして顔認証技術に後押しされる形で始まった外国人技能実習制度と、日本の入国管理行政の経緯について整理してきた。
ところで、入国管理行政において、難民についてはどのような制度になっているのだろうか? 国家と人権を語るうえで、労働者としての外国人もさることながら、難民としての外国人を語らないわけにはいかないだろう。また、難民問題は必然的に諸外国の制度や社会情勢とも関連づけて理解しなければ、その本質はつかめない。
本連載の後編では、主に欧米諸国の難民に関する取り扱いや社会情勢にも触れながら、難民に対する日本の入国管理行政、そしてウィシュマさんの死の原因について掘り下げていく。
(構成=青木 隼)