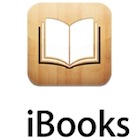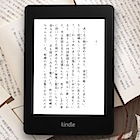楽天がぶち上げる「打倒アマゾン」に出版社は眉唾…kobo事業説明会に出版界から非難轟々
 相変わらずイケイケの三木谷社長(撮影/Guillaume Paumier「Wikipedia」より)
相変わらずイケイケの三木谷社長(撮影/Guillaume Paumier「Wikipedia」より)また、注文した翌日に商品が到着する「あす楽」の対象商品・地域の拡充のため、在庫拡充と倉庫の増設などを行う。また、販売面においては、アマゾンが弱いというスマートフォンによる注文のほか、レコメンド機能の強化などに取り組む。さらに商品を供給する出版社との連携も強化する。販売情報の閲覧や商品登録などができるベンダーサービスを2014年から導入するとともに、年間を通じて販売促進をサポートする「Sales Relation Program」(SRP)への加入も促進している。
出版社だけでなくマスコミ各社も集まったこの説明会で、三木谷浩史代表取締役社長兼会長は、3年後の16年にkoboの年商を500億円に到達させるとし、さらに日本の電子書籍市場が1兆円になると予測される20年には、そのシェアの50%をkoboで獲得したいと息巻いた。
この目標を達成するためにも、(1)今夏までにベストセラーの80%の電子書籍化、(2)新刊本は紙と電子の同日発売を標準化、(3)紙の書籍の50%の電子化――を出版社に要望。こうした取り組みを進めて、電子書籍の市場規模を10倍にしたいと考えている。さらに、市場規模の拡大に当たって、楽天基準で判断した「優良コンテンツ」約2万点を楽天の負担で電子化したいとも申し出た。
電子書籍の推進は楽天の使命――。そこまで言ってのけた三木谷氏の大風呂敷が上記の内容だ。しかも、電子書籍の推進に賛同する出版社として、NHK出版、学研、角川GP、幻冬舎、講談社、小学館の社長や事業担当者を登壇させ、マスコミにフォトセッションの時間まで与えて、出版業界との緊密さをアピールした。出版社の支援がなければ単なるホラに終わってしまうであろうこの目標、一方で、三木谷氏なぜここまで強気な発言をしたのか。
この強気発言の裏には、三木谷氏と講談社の野間省伸社長との親密な関係にあると、某出版社の営業幹部が話す。
「三木谷さんと野間さんは、楽天の事業説明会の後に行われた懇親会でも終始2人で話し続けていたほど親密な関係。どうも野間さんは、『講談社は楽天のためなら何でもする』というようなことを三木谷さんに言ったと聞いている。また、12年のkobo事業開始時に、東京国際ブックフェアのブースも両社は隣同士。その上、楽天ブースでは講談社の電子書籍を前面に打ち出していたし、同フェアの基調講演の際には三木谷さんが『打倒 アマゾン』Tシャツなるものを野間さんにプレゼントするなどの親密さを見せていた(苦笑)。電子書籍の普及に関して、温度差はあるが、『アマゾンへの対抗』という点で意気投合したのだろう」
さらに、ある取次会社の営業担当者はいう。
「12年に楽天が出版流通に乗り出すという記事が出た。あれは、日本出版インフラセンター(JPO)という業界団体が進める『フューチャー・ブックストア・フォーラム』の実証実験に、楽天が流通業者として参加するという話がベースになっている。その実験とは、顧客が書店に注文した書籍を迅速に配送する実験を、楽天ブックスを通じて行うというものだ。テーマとしてはアマゾンに負けない客注流通の構築で、ここでもアマゾンの対抗馬として楽天が持ち上げられた」
この話に加えて、「事業説明会の懇親会で驚いたのが、乾杯のあいさつがJPOの永井祥一専務理事だったこと。永井さんは元講談社で、長年出版流通の発展に貢献された方。業界の重鎮と言っても過言ではない。あくまで団体職員であり裏方であるにも関わらず、永井さんがあいさつをしたという事実を鑑みると、楽天がこれほどまでに出版業界の団体とも関係を構築しているということがわかる。現に、楽天ブックスの新刊の予約登録には、JPOの近刊情報センターに登録されているデータを優先的にアップするなど、JPOとの連携が密接になっているのが証拠だ」(別の出版社営業)という話も聞かれた。この事情説明会の配役を見ると、三木谷氏を持ち上げる出版界のキャストが見て取れるわけだ。
ネット書店もリアル書店も合わせ、アマゾンが日本ナンバーワン書店という現状において、出版社はこれ以上アマゾンの力が強まることを望んでいない。一方、楽天はアマゾンに溝を空けられた書籍の販売において、同社に追いつくために、出版界の既得権益者に取り入って、電子書籍や紙の書籍の取引をスムーズにしたいーーこうした両者の思惑もあり、楽天と出版業界との距離はじわじわと縮まっている。
このように一部の業界人から持ち上げられ、それを利用し業界の覇者として君臨しようとする楽天。だが果たして、電子書籍だけでなく紙の書籍も販売し、三木谷氏が「アマゾンに対抗できるのは楽天だけ」とうそぶく楽天に期待できるのだろうか? 実は、現場にいた出版業界陣はこれを眉唾ものとしており、説明会に対しても、何をいまさらと非難轟々だったようだ。同説明会に出席した面々の声を紹介しよう。
前出の出版社営業担当は「楽天ブックスの施策のほとんどは、アマゾンが今やっているもの。楽天ブックスのベンダーサービスはアマゾンではベンダーセントラル、SRPはアマゾンとの年間契約と同じもの。翌日配送の強化のために倉庫を増やすのも、アマゾンと同じ方針。これまで楽天ブックスがやってこなかったことなので、『やっとか』という思い」と話す。
また、前出の出版社の営業幹部は「アマゾンに比べて楽天ブックスは、出版社との協力体制が、現場レベルではまったくできていないのが現状。楽天の担当者は、すぐ替わったり、辞めたりする。その上、担当者が不在のまま、なんの音沙汰もない時期すらあった。アマゾンはネット書店が得意とする予約注文にかなり積極的であるのに対し、楽天ブックスの対応は、新刊の情報がきちんと流れているのかもよく分からないほど、お粗末。ベンダーサービスの導入で、アマゾンのように新刊予約もやりやすくなるというが、それも来年からの話。これではその間に、ますますアマゾンに差をつけられるだろう」
さらに畳み掛けるように、出版社のネット書店担当者は訴える。
「楽天は、SRPという販促サポートを年間を通じてやるので、キックバックを要求してきた。しかも金額を聞いたら、ありえないほどの高額だった。アマゾンとの年間契約はそれなりの売り上げがあるから支払っているが、うちとアマゾンとの取引額に対して10分の1ほどしかない楽天ブックスが、数百万円単位のキックバックを要求してきたので、驚いた。ほかの出版社にも話を聞いたが、同じように突っ返したようだ」
出版界において、アマゾン一強という現実は重い。出版社はこれまでの楽天ブックスの営業姿勢を見てきて、「打倒アマゾンなんて……」と思わざるを得ない状況だった。しかも、楽天ブックスの取り組みはアマゾンの真似ばかり。それで本当にアマゾンに追いつけるほどの売り上げを達成できるのだろうか? kobo事業も、出版社が楽天にだけしか電子書籍を配信しないことはありえないのだから、コンテンツが今の10倍になれば、アマゾンの取り扱いも10倍になる。それでアマゾンに追いつけるのだろうか? アマゾンが昨年に投入したキンドルHDに対抗するカラー版の端末も、いまだ発売されていない。ようやく4月25日にiOS版のアプリが出たというありさまだ。
少なくとも楽天ブックスもkoboも、アマゾンの現場担当者以上に緊密に出版社と連携しない限り、三木谷氏の「打倒アマゾン」という理想も、絵に描いた餅に終わってしまうことだろう。
(文=碇 泰三)