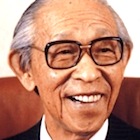なぜプロレスは八百長批判から解放されたのか?馬鹿みたいにやり続ければ常識になるの法則
 「Thinkstock」より
「Thinkstock」より私は、プロレス者(もの)である。幼い頃からプロレスが大好きだった。学生時代は、プロレス研究会に所属し、プロレス雑誌を愛読し、アルバイトで稼いだお金で会場に通いつつ、学生プロレスのリングにも上がっていた。毎日、東スポ(東京スポーツ)を買って読んでいた。今も毎週、『ワールドプロレスリング』(テレビ朝日系)を観ている。年に数回ではあるが、会場にも足を運ぶ。今年はもう少しプロレスの生観戦を習慣化しようと思っている。
自分語りはこれくらいにして、最近気づいたことがある。それは、プロレスに関する議論で「八百長」という言葉を聞かなくなったことである。これはなぜだろうか? そして、この問題はビジネスにしろ政治にしろ、反発を生むようなことを浸透させていくプロセスの参考になるのではないだろうか。
以前はよく、こんな疑問がよく聞かれたものだ。
「なぜ、選手をロープに振ったら戻ってくるのか?」
プロレスに関して抱く、最初の疑問はこれじゃないだろうか。ほかにも、
「なぜ5カウント以内の反則が認められるのか」
「時間無制限一本勝負や60分一本勝負でも、長くても30分くらいで試合が終わるのは、テレビの放送を意識しているのではないか」
「相手の協力がないとできない技があるのはどうなのか」
「なぜ、相手の技を逃げないで受けるのか?」
などなど、突っ込みどころはたくさんある。そもそも、スポーツ新聞以外が、試合の結果を伝えないということ自体も疑問点である。あくまで、普通に考えれば、だが。
<2>八百長疑惑との戦いプロレスと八百長の問題に関しては、過去にも何度か暴露本のようなものが発売されてきた。例えば、初代タイガーマスクだった佐山聡氏の『ケーフェイ』(ナユタ出版会)や、新日本プロレスの元レフェリーのミスター高橋氏が発表した『流血の魔術 最強の演技 すべてのプロレスはショーである』(講談社)などである。特に後者はK-1やPRIDEなどがブームになっていた2001年に発表されたものであり、当時の新日本プロレスの動員減などに影響を与えたのではないかとさえいわれている。
このような暴露本がなくても、プロレスというジャンル自体が常に八百長という疑惑と戦ってきたように思う。そのために、強さや痛みを証明しようとした。
例えば、今では知らない人も多いだろうが、アントニオ猪木はモハメド・アリ、ウィレム・ルスカ、ウイリー・ウイリアムスなど、他種目の強豪との異種格闘技戦を行うことにより、強さを証明しようとした。1980年代に盛り上がった、前田日明、高田延彦、藤原喜明、船木誠勝、鈴木みのるなどが在籍したUWFと、そこから分派した団体は、ロープに飛ばず、格闘技志向のルールで試合をすることにより、やはり強さを証明しようとした。
90年代の全日本プロレスは、三沢光晴、川田利明、田上明、小橋建太による四天王プロレスの時代だったが、垂直落下式の過激な技を連発することにより、痛みに関する納得感、説得力のある試合をしていた。大仁田厚はFMWを立ち上げ、ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチなど、過激なルールのデスマッチを行った。邪道プロレスと言われたが、これはこれで、痛みを証明するものだった。
やや余談だが、文藝春秋が毎年発売している『論点100』シリーズの第1号が出たのは92年だが、そこには「プロレスは今、面白いのか?」という論点が掲載されており、大仁田が寄稿している。ロープに振ったら戻ってくることについても、理解されるまでやるしかないなどの趣旨のコメントをしていた。
八百長という声を吹き飛ばした
このように、90年代くらいまでのプロレスは、暗に八百長疑惑と戦っていたように思う。その後のプロレスはどうなったか。結論から言うと、見事に八百長という声を吹き飛ばしたように思う。もう、そういう議論自体、どうでもよいものになってしまった。個人的には、プロレスがさらに進化すること、多様化することにより、それを成し遂げたのだと思う。
その一つは、プロレスリング・ノアのように、ますます過激なプロレスをすることにより、強さ、痛みを伝えていった流れである。三沢光晴が小橋建太に花道で放ったタイガースープレックスなどは10年以上たつにもかかわらず、いまだにファンの間で話題になる。ネット上では「ノアだけはガチ」という言葉も流行した。
過激なプロレスだけでなく、華麗なプロレスというものもある。空中殺法はこの10年でさらに進化した。トップロープから場外に飛ぶ技は、ますます華麗になった。
レスラーの肉体も鍛えぬかれたものになっていった(団体や、ファイトスタイルにもよるが)。新日本プロレスのエース、棚橋弘至選手の肉体などはすさまじいまでの鍛え方である。
逆に、ファンタジーと言ってもいいほどのエンターテインメント性の方向に走ることで、八百長論をどうでもいいものにしたという流れもある。一時興行が行われていたハッスルなどはその典型だろう。最近は映像を駆使した演出なども増えてきた。
冬の時代といわれたこともあったが、プロレスは、耐えた。気づけば、K-1もPRIDEもブームが去っていた。大規模な格闘技興行も、すっかり少なくなってしまった(もっとも、格闘技は競技人口が増え、小規模な大会が増えているのだが)。そして、プロレスブームがまたやってきたといえる。なんせ、新日本プロレスが人気だが、他の団体もがんばっている。プロレス女子(プ女子)なる言葉も生まれ、メディア露出も増え、ますます盛り上がりそうな予感だ。
ショーだと宣言する日
今後注目されるのは、団体自らが「これはショーだ」と宣言するのはいつだろうかということだ。「そんなこと、宣言するわけない」と誰もが思うだろう。ただ、時と場合によっては、そう宣言せざるを得ないこともあるのだ。
ずばり、上場である。上場企業は、どんなビジネスをしているのかをガラス張りで報告しなくてはならない。海外においては世界最大のプロレス団体といわれるWWEが上場しているが、その際に彼らは「レスラーという名のアクターによるショーを行っている」ということをカミングアウトした。今後上場するプロレス団体が現れるかどうかということに、私は注目している。ただ、カミングアウトしても、今さら怒られないだろう。
プロレスは八百長から解き放たれた。継続すること、そして環境の変化によるものだといえるだろう。この発想はビジネスにも活きると思う。現在は非常識だといわれていることでも、次のスタンダードになるかもしれない。もっとも、この話というのは、良くないことがなし崩し的に認められるプロセスともいえるのだが。
最後にお知らせ。私の最新作『下積みは、あなたを裏切らない!』(マガジンハウス)が3月26日に発売されるのだが、この本の中で、前出の棚橋選手と対談している。この対談を通じて、彼が体を張って新日本プロレスを引っ張っていったからこそ、プロレスは社会に認められたのだと思った。熱い本になっているので、ぜひ。
プロレスとは、肉体と魂による、ドラマである。
(文=常見陽平/評論家、コラムニスト、MC)