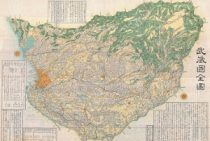ビックカメラ本社(「Wikipedia」より/Kamemaru2000)
ビックカメラ本社(「Wikipedia」より/Kamemaru2000)普段、何気なく目にしたり口にしたりしている、有名企業の名前。個人名がそうであるように、それぞれの企業名にも、もちろん由来や意味がある。
「法人」というように、企業は法律上「人」扱いされる側面があるため、各企業ともそれなりに意味や由来のある社名にしており、中には画数まで考えられている場合もあるほどだ。そんな社名の由来を調べてみると、意外な事実が浮かび上がってきた。
スペルミスから生まれた、IT界の革命児
家電量販店の大手として有名な「ビックカメラ」。看板ロゴなどを見ると「BIC CAMERA」となっており、決して「BIG」ではない。一見「スペルミスなのでは?」とも思えるが、その疑問に対して、同社は株主・投資家情報サイトで以下のように答えている。
「『Bic』はバリ島のスラング(俗語)です。『大きい(Big)』の意味を持つ一方、ただ大きいだけでなく中身を伴った大きさ、という意味もあります。『限りなく大きく、限りなく重く、限りなく広く、限りなく純粋に。ただの大きな石ではなく、小さくても光輝くダイヤモンドのような企業になりたい』という希望をこめて、『ビックカメラ』と命名しました」
ちなみに、本当にスペルミスから生まれた社名もある。「グーグル(Google)」だ。共同創業者で、現在は持ち株会社アルファベットのCEO(最高経営責任者)を務めるラリー・ペイジ氏が、「10の100乗を意味するgoogol(グーゴル)」を間違え、ドメイン名を「google.com」と登録したことが「Google」誕生の由来といわれている。
カシオ、ブリヂストン…創業者の苗字から誕生した伝統企業
よくあるのが、創業者が自分の名前を社名に用いるケースだ。しかし、これは誰でも思いつくし、ある意味でありふれている。そこで、物の名前の由来や日本史に詳しい放送作家・小説家で『【悲報】本能寺で何かあったらしい……光秀ブログ炎上中! 歴史Web2.0』(日本文芸社)著者の藤井青銅氏に話を聞いた。
「自分の名前をそのままつけるのではなく、一捻りして命名する。そんなところに、創業者のセンスが出るでしょう。それに、日本名でもカタカナ表記にするだけで、外資系企業っぽい雰囲気が生まれます。カタカナ表記の日本企業名にもタイプがあり、そのままの直球型と名前をいじる遊び型があります」(藤井氏)
遊び型の典型が「ブリヂストン」だろう。創業者の苗字である「石橋」を英語に直訳した「ストーンブリッジ」では語呂が良くなかったため、ひっくり返して「ブリッジストーン」にした、というのが由来である。
一方、電機メーカーの「カシオ計算機」は直球型だ。ロゴでおなじみの「CASIO」を見ると外資系企業のように思えるが、実は創業者の樫尾忠雄氏の苗字が由来である。
「『シオノギ製薬(塩野義製薬)』も創業者名に由来していますが、苗字+1文字というパターンです。創業者が塩野義三郎なので、『塩野+義』=『シオノギ』というわけです。学習机で有名な『イトーキ』も創業者・伊藤喜十郎の『伊藤+喜』から、創業時は『伊藤喜商店』でしたが、後にカタカナ表記になり『イトーキ』になりました」(同)
藤井氏によると、ほかにも「伊勢丹(現三越伊勢丹)」(創業者・小菅丹治が婿養子に入った米穀問屋「伊勢又」から)のような「老舗屋号のれん分け型」や、「松竹」(創業者・白井松次郎と大谷竹次郎の名前から)のように複数の創業者からの「一文字ずつ合体型」もあるようだ。
狩野英孝もびっくり? マセキ芸能社のルーツとは
また、芸能事務所の社名にも創業者の名前がついていることが多い。一見、特筆すべきものはなさそうだが、「メジャーな芸能事務所の中に、実は日本史に出てくる人物と非常に関係の深い会社があります。それが『マセキ芸能社』です」(同)
マセキといえば、ウッチャンナンチャン、出川哲朗、バカリズム、狩野英孝といった人気芸人が所属しているが、そもそも「“マセキ”ってなんのことだろう?」と思っている人も多いはずだ。聞き慣れないが、実は「マセキ」は苗字である。
「板垣退助が自由党を創立した当時、創立メンバーの自由党員に対して『政治講釈師になれ』と命じて、政治家兼芸人にしたのです。まるで、現代とは真逆ですが……(笑)。講釈師になった男は伊藤痴遊(いとうちゆう)といい、伊藤のマネジメントをしていたのが柵木政吉(ませきまさきち)という人物です。
彼は『講談演芸社』を設立し、その後『柵木演芸社』と改名、これが『マセキ芸能社』の始まりです。今は社員や所属タレントもこの由来を知らないと思いますが、会社設立に板垣退助が関係しているというのはすごいですよね」(同)
狩野がこの歴史を知っているかどうかは不明だが、社名の由来は面白い話のタネになることは間違いない。うんちくとして覚えておけば、取引先との商談や飲みの席で役に立つこともあるだろう。ただ、若手社員や女性部下に向かってドヤ顔で披露すると、敬遠されること必至である。メンバーに加え、タイミングと空気を読んだ上でサラッと披露する程度がいいだろう。
(文=アーク・コミュニケーションズ)