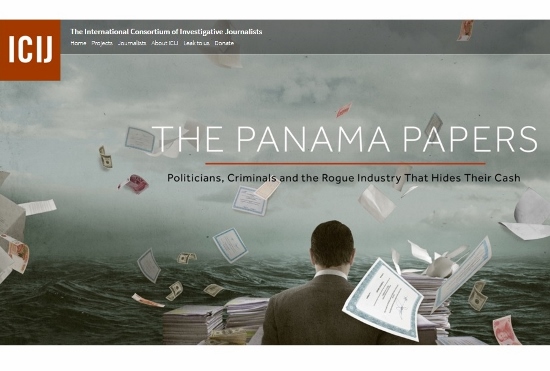 「ICIJ HP」より
「ICIJ HP」より「パナマ文書」の公開以降、タックスヘイブン(租税回避地)への非難や規制強化の機運は強まる一方だ。本連載前回記事で述べたように、タックス・ヘイヴン潰しは民間経済の活力を奪い、庶民や社会的弱者の生活水準を下げる。
それだけではない。法的な問題も大きい。タックス・ヘイヴン批判の理由として脱税以外によく持ち出されるのは、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金の隠し場所として悪用されるおそれがあるというものだ。しかし、これは針小棒大な非難といわざるを得ない。
スイスの独立系シンクタンク、バーゼル統治研究所は世界各国を対象に、資金洗浄やテロリストの資金調達に利用されるリスクを数値化し、ランキングしている。2015年版でみると、ワースト10カ国(イラン、アフガニスタン、タジキスタン、ギニアビサウ、マリ、カンボジア、モザンビーク、ウガンダ、スワジランド、ミャンマー)の中に、経済開発協力機構(OECD)が挙げるタックスヘイブンはひとつもない。
タックスヘイブンは企業や富裕層を顧客として引きつけようと互いにしのぎを削っている。犯罪への関与が明らかになれば、まっとうな顧客が寄りつかなくなるから、もともと法令順守には敏感なのだ。悪用されるケースがないとは言わないが、政府が本当に資金洗浄やテロ資金をなくしたいのであれば、タックスヘイブン潰しが効率的な方法とは思えない。
租税公平主義
タックス・ヘイヴン叩きは、さらに大きな問題をはらむ。それは法的な問題だ。
あらためて強調すると、租税回避(課税逃れ)は脱税と違い、違法な行為ではない。合法である。その点、庶民も行う普通の節税と変わらない。法的には、節税も租税回避も課税額を減らす行為だが、通常の法形式を使った場合は節税、通常とは異なる法形式を使った場合は租税回避とされる。そして租税回避の場合、課税の公平を損なうとの考えから、通常の法形式を使ったものとみなして課税される場合がある。これを「否認」という。
問題はその際の法的根拠だ。税当局は、所得税法や法人税法など税法に個別の規定がなくても、税負担は国民の間で公平でなければならないという原則(租税公平主義)に基づいて否認できるとする立場をとる。
これに対し税法学者の間では、税法のもうひとつの原則である「租税法律主義」を重視し、個別の規定によらない否認は認められないとする見解が通説となっている(増田英敏『リーガルマインド租税法』/成文堂)。租税法律主義とは、税金の賦課・徴収は議会の制定した法律によらなければならないという原則をいう。
たとえば法人税法の場合、第132条に同族会社を使った税逃れは否認し、課税するという規定がある。税法学の通説では、このような個別の規定がない限り、明らかな租税回避でも課税してはならないということになる。
今後タックス・ヘイヴンへの課税が強化される場合、それが法人税法や所得税法を改正し、個別の否認規定を追加する明確な形をとるのであれば、経済的な悪影響はともかく、法的な問題はない。しかし、現実にそのような正攻法の対応は考えにくい。
タックス・ヘイヴンでの取引は複雑かつ多様で、しかも次々と新しい手法が考案される。いちいち国会の手続きを踏んで関係する税法を改正するとなると、大変な手間と時間が予想される。
法律改正でなく、国税庁が出す通達で課税できれば、国会の手続きを踏む必要はない。しかし、これは「通達課税」と呼ばれ、租税法律主義に反する。本来ならあってはならない行為だが、徴税の現場では横行しているといわれる。政府がタックスヘイブン潰しの姿勢を強めれば、通達課税など税当局の恣意的な徴税が広がり、租税法律主義の形骸化が進むおそれが大きい。
租税法律主義にはそれだけの重みがある。税法上の原則というだけでなく、近代憲法の大原則でもあるからだ。日本国憲法では第84条に「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と明記されている。
リベラル派の矛盾
租税法律主義の起源は古く、約800年前に定められた英国の大憲章(マグナ・カルタ)にさかのぼる。戦費をまかなうため重税を課した王に貴族が団結して反抗し、課税には貴族の同意を得るよう認めさせた。
大憲章は同時に「立憲主義」の土台にもなった。立憲主義とは、権力を法で制限する考えである。租税法律主義は権力者が国民に勝手に課税することを制限するわけだから、立憲主義の具体的な表れのひとつといっていい。
立憲主義という言葉は、最近よく目にするだろう。改憲問題や安保法制に関連して、政府に批判的な野党やリベラル派メディア、言論人が「立憲主義を守れ」と主張することが増えているからだ。安保法制とタックス・ヘイヴンは一見縁遠い話のようだが、どちらも立憲主義に深くかかわるのだ。
さて、ここでひとつの矛盾に気づかないだろうか。政府や保守派メディアはともかく、いつもは「立憲主義を守れ」「憲法で権力を縛れ」と声高に主張する野党やリベラル派メディアまでが一緒になって、権力者である政府に課税強化を求めるのは、筋が通らない。
たとえば朝日新聞は憲法記念日の5月3日、「立憲主義を取り戻す時」と題する論説主幹執筆の記事で、次のように安倍政権を批判した。
「憲法の縛りを何とか解き放ちたい。この点で、政権の姿勢は一貫してきた」
この批判には同感だ。ところが一方、朝日は主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)を控えた同月14日、社説で「安倍首相はサミット議長として、議論を引っぱってほしい」とタックスヘイブン対策に発破をかけた。本当に立憲主義を大切に思うのなら、タックス・ヘイヴン問題に限って、権力者である首相を激励するのはおかしい。
このように言うと、リベラル派は「それは古い考え。現代の憲法にはそぐわない」と反論するかもしれない。だとすれば皮肉なことに、立憲主義の理解は安倍首相と五十歩百歩と言わざるを得ない。首相は2014年2月10日の衆院予算委員会で、憲法についてこう述べている。
「憲法とはまさに権力を縛るためだけのものであるという考え方については、それは古いものではないか」
立憲主義を信じるのなら、その原点ともいえる租税法律主義を軽視してよいはずがない。思想が力をもつには首尾一貫しなければならない。政府が多くの税を手にすれば、リベラル派の好む社会福祉の予算だけを増やすとは限らない。軍事費や国民の自由を抑圧する政策に回す恐れもある。もしリベラル派が安易なタックスヘイブン叩きを続ければ、いつかその底の浅さが露呈し、権力の暴走に歯止めをかけることができなくなるだろう。
(文=筈井利人/経済ジャーナリスト)




















