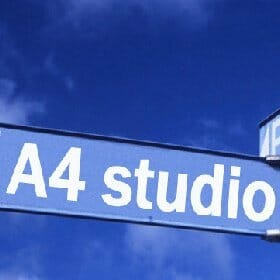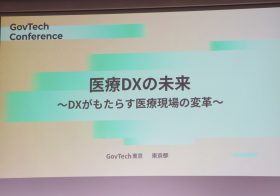高校「世界史」必修科目から除外、重大な弊害も…日本以外の重要な歴史を学ぶ機会失う
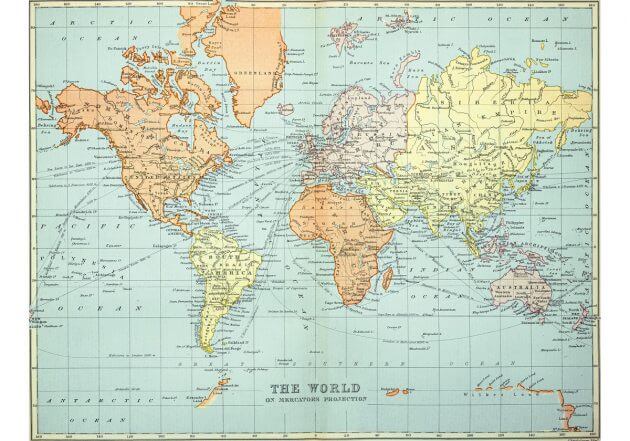
来年度から、日本全国の高校で「世界史」が必修科目ではなくなることをご存知だろうか。これまでは「世界史A」か「世界史B」を必修することになっていたが、2022年度からは世界史と日本史を統合して近現代史を中心に学習する「歴史総合」が新たな必修科目となり、世界史は「世界史探究」という選択科目になるのだ。
来年度からスタートする「歴史総合」だが、世界史教員を中心に必修で世界史を教える機会がなくなることに対して危機感を露わにする意見は多い。世界史が必修でなくなることには、どのような弊害があるのだろうか。
そこで、静岡大学の人文社会科学部社会学科の教授で、歴史教育の分野に詳しい岩井淳氏に話を聞いた。
設置のきっかけは06年の世界史未履修問題
「歴史総合」は高校の学習指導要領が改訂されて新たに設置された科目だが、なぜ設立されることになったのだろうか。
「新学習指導要領導入の動きは高校だけのものではなく、小中高一連の教育改革の仕上げにあたります。すでに20年度に小学校で改訂されて、大学入試では共通テストを導入、21年度には中学校で改訂され、22年度に高校の必修科目に『歴史総合』『地理総合』『公共』の3科目が新設されるというわけです。
今回の歴史教育改革は、06年秋に表出した、必修科目の世界史を教えていなかった未履修問題に端を発しています。そこで世界史必修の改革案として、日本学術会議が11年に世界史と日本史を統合した科目『歴史基礎』の新設を文部科学省に提言し、これが15年の『歴史総合』誕生につながりました」(岩井氏)
岩井氏によれば、「歴史総合」には大きく4つの特色があるのだという。
「歴史・地理・公民が横並びで必修となったこと、学生が能動的に学ぶアクティブラーニングが志向されていること、近代化・大衆化・グローバル化に着目した構成になっていること、世界史と日本史の統合が特色です。特に世界史と日本史の統合に関しては大きな意義があります。
海外では世界史と自国史を併せて教えることが主流になっている一方で、日本では世界史と日本史に分かれ、それぞれに専門家がいる分断状態だったことが、かねてから問題点として指摘されていました。『歴史総合』の登場によって日本を世界史のなかで位置づけ、世界史と日本史を相互に関連づけて学ぶ重要性が説かれるようになったことは、教育においても研究においても大きな前進といえるでしょう」(岩井氏)
「歴史総合」の学習指導要領が抱える大きな問題点
ある意味では歴史教育のグローバルスタンダードに立脚したアプローチがとられている「歴史総合」。しかしながら、世界史と日本史を統合したことによる弊害もあるようだ。
「『歴史総合』は近現代史を教えていた『世界史A』と『日本史A』の流れを汲む科目になります。しかし、『世界史A』における近代史は大航海時代にあたる16世紀以降を、『日本史A』は幕末にあたる19世紀後半以降を近代史としていたため、時代区分に矛盾が生じているのです。
日本史のほうが独自の時代区分になっているので、本来世界史の区分を基準とすべきなのですが、『歴史総合』では折衷的に18世紀後半からを近代としています。これによって、世界史という科目が持っていた長い時間認識が失われてしまうことが懸念されますね。
これまでの世界史では日本と直接関係しない地域や、国民国家が形成されていない地域の歴史的変遷を取り扱うことで、幅広い空間認識を育ててきました。ところが、『歴史総合』では国家史に重点を置き、国民国家の形成・統合を中心に論じているため、日本などの国民国家を形成できた国以外の地域について、あまり触れられなくなってしまいます。これは『歴史総合』の大きな問題点のひとつです」(岩井氏)
ほかにも「歴史総合」の学習指導要領が抱える問題点は存在すると岩井氏は続ける。
「学習指導要領の内容を見ていくと、『歴史総合』では産業革命に始まる工業化や、日本における大日本帝国憲法の制定といった国民国家の形成過程のプラス面が強調されています。工業化や国民国家形成の負の側面や、民主主義の成立に重要なヨーロッパの市民革命については詳しく論じられないので、ある種偏った歴史記述になってしまうわけです。
また、『歴史総合』が着目している近代化・大衆化・グローバル化の考え方は、もともとは歴史社会学的な概念に基づくものだったのですが、『歴史総合』のなかでは単なる時代区分概念になっています。これによって、歴史社会学的な概念として一貫していないことも研究者からは問題視されていますね」(岩井氏)
必修でなくなることで助長されていく世界史離れ
世界史と日本史を統合したこと自体の意義は大きい「歴史総合」。だが現在の学習指導要領では、それによって生まれた時代区分の矛盾や、国家史中心のアプローチなど数々の問題点をはらんでいる。さらに、世界史教育の観点でも懸念されることがあるという。
「これまでの大学受験において理系の受験生は『地理B』を、文系の受験生は『日本史B』を選択する傾向があり、世界史が必修であるにもかかわらず『世界史B』の受験者は減少していました。
『歴史総合』などの新設された3科目を学んだあとは『世界史探究』か、『日本史探究』の2科目から選択して学ぶことになります。ですが、世界史が必修でなくなったことで、『世界史B』のときよりも『世界史探究』を選ぶ学生は減少するでしょう。このままでは日本とかかわりの薄い国や地域について学ぶ機会が少なくなるので、世界の歴史について、もっと広く学ぶ必要はあると思います」(岩井氏)
また、「歴史総合」の登場で教育の現場でも混乱が起きているそうだ。
「一部の高校の世界史、日本史教員のなかには専門分野の棲み分けの意識が強く、『歴史総合』の担当を押しつけ合っているケースもあります。『地理総合』と『公共』を教える教員が人数的に少ないので、世界史必修に対応するために採用された世界史教員が、当面それらの担当になり、『歴史総合』は日本史教員が担当する可能性も十分あります。
科目新設に伴う現場の混乱は新しい必修科目の専門教員が育つことによって、ある程度は是正されていくでしょうが、やはり問題は国民国家形成を基準としている『歴史総合』の学習指導要領ですね。新学習指導要領は、その作成途上で日本史の必修化を主張した自民党政権の影響が強く、それが問題点として残されています。
しかし、歴史の教育・研究に携わる各学会や、世界で活躍するビジネスパーソンを育成したいと考える企業からの反発が強く、結局は『歴史総合』が必修科目となりました。ただ、残された問題の解決のために研究者や現場の教員が声を上げていくべきです。これから新たな教育課程を経験した世代が社会に出ることになるので、教育に直接携わらない方々も、この問題に注視して発言していくことが大切でしょう」(岩井氏)
現在の教育で起こっている出来事は、学校という閉じられた空間だけの問題ではない。遠くない未来で共に働くことになる若者に何を学んでほしいのか、どう向き合っていくのかという、今の日本社会を支えている私たちにかかわる問題でもあるのだ。