東大理科三類、優秀な若者をダメにする閉鎖性…現役学生が福島で学んだ現場の大切さ
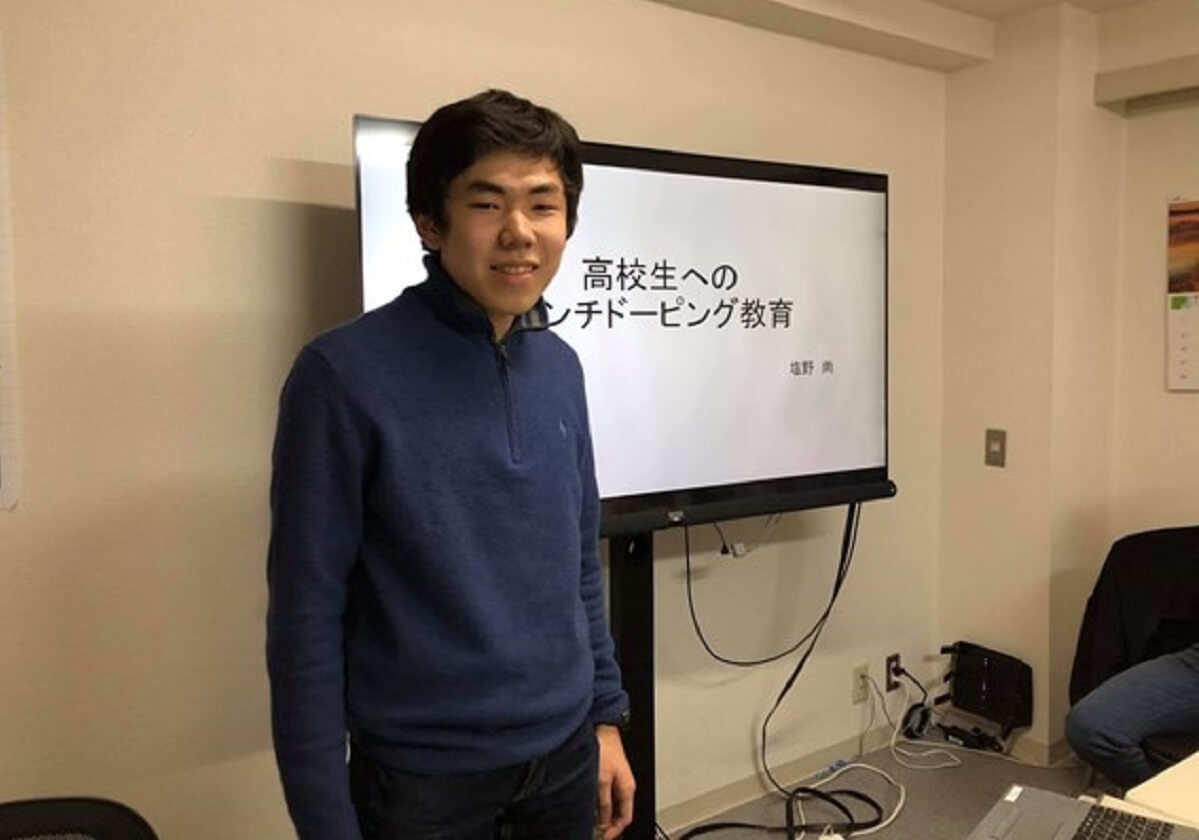
田中愛翔君と杉浦蒼大君という大学生がいる。今春、兵庫県の灘高校から東京大学理科三類に合格した。彼らの学び方はポストコロナの大学教育を考える上で参考になる。ご紹介したい。
私が彼らと知り合ったのは、彼らの東京大学理科三類の同級生である塩野尚君の紹介だ。塩野君は、愛知県の東海高校出身。東海中学3年生で自主研究の宿題がでたときに、『日本の医療格差は9倍~医師不足の真実~』(光文社新書)などの私の著作を読み、インタビューを申し込んできた。長い間、若者を指導しているが、こんな中学生は初めてだった。ものすごい行動力だ。
その後、高校2年生の冬にも、研究所にインターンにやってきた(写真1)。礼儀正しく、約束したことを着実に実行する有能な高校生に成長していた。
今春、塩野君は東京大学理科三類に合格した。私と東京大学医学部の同期で、東海高校OBの日紫喜光良医師が、「週刊誌を読んだら、塩野君が理三に合格していた」と教えてくれた。日紫喜医師には、塩野君が高校2年生のインターン時に紹介し、それから交流があったようだ。私は日紫喜医師と共に、塩野君の入学祝いの会を企画した。その時に、塩野君が呼んだのが田中君と杉浦君だった。この2人は灘高卒で、高校・大学とも筆者の34年後輩にあたる。
筆者が東京大学に入学したのは1987年だ。国鉄が解散、JRに事業を継承し、米アップル・コンピューターが、伝説の「マッキントッシュII」を発表した年だ。電子メールも携帯電話もなく、筆者が入寮した敬天寮という学生寮では、外部と連絡するには、寮の3階にあるピンクの公衆電話を利用するしかなかった。東京にきても、特にすることがなく、ほどなく運動会剣道部(ほかの大学の体育会に相当)に入部し、ゴールデンウィークがあけると講義にもほとんど出なくなった。そして、学生時代の多くを道場と部室で過ごした。
大学時代を通じて交流したのは剣道部の部員・OB、医学部の同級生、敬天寮関係者さらに家庭教師先のご家族だけだった。縁もゆかりもない人を訪問し、話を聞くなど、当時の私は想像だにしなかった。携帯電話やSNSが発達した昨今、若者は他者との「間合い」を詰め、関係を構築するのが上手くなった。その象徴が塩野君、田中君、杉浦君たちだ。その後、塩野君だけでなく、田中君と杉浦君も医療ガバナンス研究所に出入りするようになった。
日本のエリート大学の教育の問題点
私は、東京大学に限らず、日本のエリート大学の教育の在り方に危機感を抱いている。かつて灘高校の教頭を務めた倉石寛氏は、若者を駄目にする環境として、「昔、陸軍参謀本部、今、東京大学理科三類」という。倉石氏は、かつての東大紛争の闘士で、灘高校教諭として多くの卒業生を東京大学に送り込んだ人物だ。彼が問題視するのは、優秀な若者を閉鎖的な空間に置いてしまうことだ。社会のリアリティを知らないまま、観念論だけが先走る。
東京大学の場合、「日本をリードする」という自負がある。入学して数カ月もすれば、体制寄りであれ、反体制であれ、「国家」や「改革」という言葉を語り出す。そして、現場の泥臭い作業より、戦略を構築することを重視するようになる。
理科三類の学生の場合、個別の患者を診るよりも、「研究で世界に貢献したい」と言うようになる。再生医療や人工知能などの「流行語」を駆使して、自分の将来像を語りだす。病人や要介護者と接したことはないため、このようなテクノロジーが現場で、どのように実装されていくか想像することはできず、理念だけが空回りする。
このような現象は、今の学生に限った話ではない。私の学生時代も状況は変わらない。高校・大学の同期にはオウム真理教事件に関わった人物がいる。彼らは優秀で真面目だった。近代医学の限界を痛感し、チベット密教の系譜と喧伝されていたオウム真理教に帰依するようになった。オウム真理教のその後を知っている人から見れば、その教えは滑稽だろう。なぜ騙されたのかと疑問に思うだろうが、当時の東京大学医学部では、名前の挙がった人以外にも多くの学生がオウム真理教の施設を訪れていた。何を隠そう、私自身もその一人だ。信者となった同級生に誘われて、南青山の道場を訪問したことがある。
私が「犯罪者」にならなかったのは、彼らが私をリクルートしようとした時、「剣の達人は刀が触れずとも、相手を切ることができる」と言ったからだ。私が剣道部に所属していることを知り、それに合わせたのだろうが、東京大学の剣道部に入部し、関東の大学はもちろん、部内のレベルの高さに自信を失っていた私には、この発言はリアリティがない虚言に感じられた。私は医学生としては頭でっかちの「エリート」だったかもしれないが、剣道家としては自分の限界を知った「大人」だった。
だからこそ、私は南青山で留まり、上九一色村に行かなかった。そして、「犯罪」に手を貸すことはなかった。あの時、オウム真理教の幹部が剣道の話をしなかったら、どうなったかわからない。このあたり、まったくの偶然だ。私は剣道のおかげで、頭でっかちのエリートにならずに済んだ。
目の当たりにしたリーダーシップ
私は大学生と会うと、「自分の専門分野に閉じこもらず、自分が経験したことない領域や場所に飛び込むように」と指導している。現場にはリアルがあるからだ。コロナが流行している状況はチャンスだ。やる気さえあれば、現場を経験しやすくなった。それは講義の多くがZoomなどを用いたリモートで実施されるからだ。コロナ流行前は、講義を聞くためには、教室に行かなければならなかった。身体を物理的に拘束されたといっていい。リモート教育で、この制約はなくなった。
筆者が、このことを痛感したのは、杉浦君と田中君に福島県相馬市でのコロナワクチン集団接種の手伝いを紹介したときだ。私たちのグループは、東日本大震災以降、福島県の医療支援を続けている。現地で常勤医として働く医師・看護師もいる。今回もコロナワクチンの集団接種をお手伝いすることになっており、私も現地で接種を担当している。
私が学生たちに「相馬でお手伝いしないか」と誘ってみたところ、彼らは「是非に」と返事してきた。私が現地の担当者に連絡したところ、「受け入れ可能」と回答があった。ここで学生たちから一つだけ要望があった。彼らは「どうしても出席しないといけない講義の時間だけ、任務から外してほしい」と求めたのだ。学生たちは、集団接種会場の片隅で、スマホを用いてZoomで講義を聞くことを考えていたらしい。担当者は「まったく問題ありません」とのことだった。
5月20日、彼らは1週間の予定で相馬市に入った。東京駅から夜行バスで仙台に向かい、そこから常磐線を利用した。杉浦君にとって東北地方訪問は初めて、田中君は高校1年生の時に石巻と気仙沼を訪問したことがあるが、福島は初めてだった。
灘高校出身の2人にとって、相馬は「異郷」だった。1323年に相馬重胤が下総より移り住んで以来、明治時代まで約550年にわたり相馬家が治めたこの町には、いまでも城下町の伝統が息づく。江戸時代、阪神間の町作りを主導したのは造り酒屋だ。灘高を経営するのは、菊正宗と白鶴を経営する嘉納家だ。かつての相馬中村城の敷地内に相馬高校が存在する相馬市とはまったく違う。
ワクチンの集団接種会場で、彼らに与えられた仕事は接種希望者の案内や誘導、および施設の消毒だった。彼らは実務を通じて、相馬市を体感した。2人が口を揃えるのは、立谷市長の強いリーダーシップだ。5月24日、相馬市役所で開催された「相馬市新型コロナウイルス接種メディカルセンター」設立の会合に参加した2人は、「トップダウンで物事がどんどん決まっていく」(杉浦君)のを目の当たりにした。

翌朝、集団接種会場には立谷市長が登場し、「接種に訪れた住民と親しげに話し、日本国内でもっとも速いペースでワクチン接種を進めている立谷市長を市民が信頼している」(杉浦君)ことを実感した。一方、「普通の会社には少なからず存在するであろう『仕事をあまりやりたくない』という雰囲気を出している市役所職員がいなかった」(田中君)ことも驚きだった。「見事な一体感」を感じたそうだ。
彼らが育った神戸では、日常生活で市役所や市長を意識することはない。市長や市役所が市民生活の一部となっている相馬市は、彼らにとって新鮮な存在だった。この一体感は一朝一夕でできるものではない。彼らが、立谷市長や相馬市職員と話すと、「何度も東日本大震災の時の苦労について、笑いを交えて語ってくれた」(田中君)そうだ。
これこそ、相馬市の強みだ。かつては仙台藩との熾烈な抗争、近年は東日本大震災・原発事故、さらに水害や余震を経験し、コミュニティが成熟した。そして、その中心にいたのは相馬家と市役所だ。毎年7月に開催される相馬野馬追の総大将は、相馬家の当主あるいは「若殿」が務めるし、市役所は相馬中村城のかつての敷地の中に位置し、和風の建物は相馬中村城の雰囲気と見事に調和している。
これこそ、相馬市の強みなのだが、東京にいて、「マネジメント」や「戦略」などの空理空論を弄んでいるだけでは、実感することはできない。彼らは6月にも相馬市を訪問するという。接種は順調に進み、6月1日からは基礎疾患のない64才以下の市民に対する接種が始まる。高齢者とは違う相馬市の一面を垣間見ることできるだろう。コロナが流行し、大学教育は大きく変化しつつある。行動力のある学生にとっては飛躍の機会になるだろう。大いに期待したい。
追記
田中君と杉浦君が相馬市を訪問するにあたり、我々が運営するナビタスクリニックが請け負った都内での集団接種を手伝っている。その際にコロナワクチンの接種は済ませている。
(文=上昌広/特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長)







