『青天を衝け』渋沢栄一…エリートに嫁いだ3人の娘、廃嫡された長男、第一銀行を継いだ孫
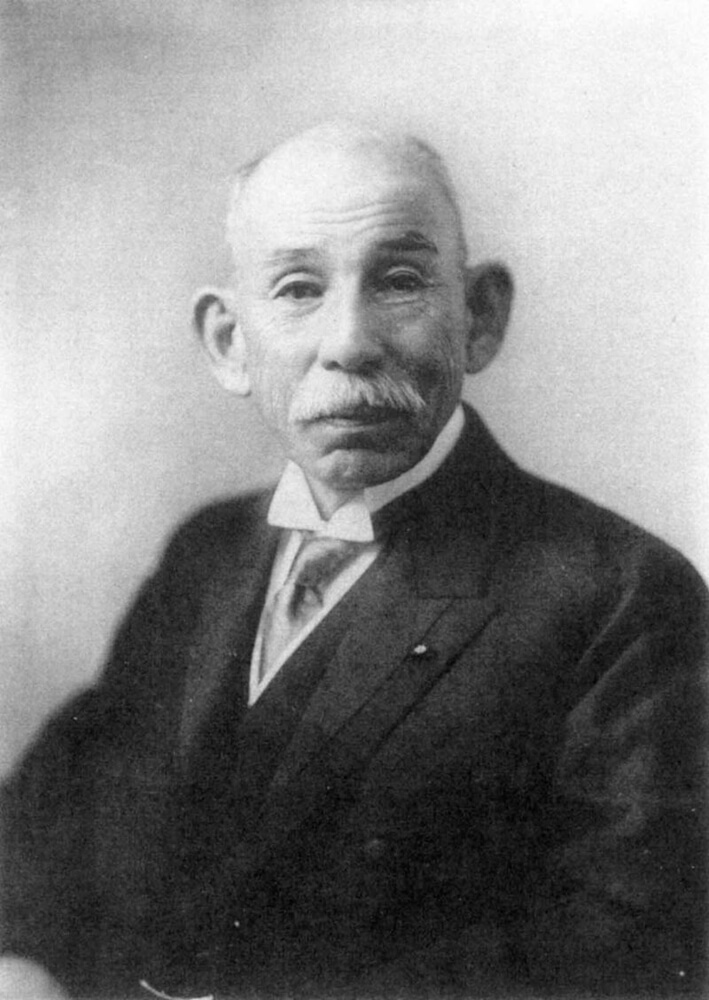
NHK大河ドラマ『青天を衝け』で、渋沢栄一(篤太夫/演:吉沢亮)は京都で活動を続けている。故郷・血洗島村にはまったく帰っていない。妻の千代(演:橋本愛)、長女のうた(歌、歌子とも書く)と再び生活するのは1868(明治元)年、実に6年ぶりのことである(『青天を衝け』では、栄一が江戸から京都へ戻る宿場で妻子との再会を果たすが事実ではないらしい)。
というわけで、次の子どものこと(琴、琴子)が生まれるのは、その2年後の1870(明治3)年。その翌年に3女のいと(糸、糸子)が生まれるが早世。その翌年に待望の嫡男・渋沢篤二(とくじ)と、立て続けに出産が続いた。篤二が生まれた時、千代は数えの30歳(満29歳)。当時では高齢出産に当たり、それ以降は出産を控えた(という名目で、栄一は側室を相手にした)らしい。
渋沢栄一の長女・歌の夫には、とびきり優秀な法学者・穂積陳重が
長女の歌は、1882年4月に旧宇和島藩士の東京大学教授兼法学部長・穂積陳重(ほづみ・のぶしげ)と結婚した。歌は満19歳、陳重は8歳年上の27歳だった。
なぜ旧宇和島藩士かというと、渋沢栄一は1869(明治2)年に明治新政府の大蔵省に出仕したのだが、当時のトップ・大蔵卿(きょう)が、旧宇和島藩主・伊達宗城(だて・むねなり)だったのだ。宗城は栄一の才覚を見込んで伊達家の経済顧問を委嘱。栄一が第一国立銀行を設立すると、宗城も同行に出資した。そこで、伊達家の代表として、旧宇和島藩士・西園寺公成(さいおんじ・きんしげ)を同行の取締役として派遣した(西園寺公成というと、のちの首相・西園寺公望の近親に思えるのだが、ほとんど血縁関係がない。西園寺家の支流が鎌倉時代頃に伊予に進出したものの末裔で、江戸時代は松田を名乗っており、幕末に西園寺に復姓したのだという)。
公成は伊達宗城の側近として仕え、明治維新後は伊達家の経済活動を支えた。この公成が穂積陳重との縁談を持ってきたのだ。
陳重は宇和島藩のなかでも比較的高い家柄に生まれ、極めて優秀だった。明治新政府が1870年に貢進生(こうしんせい)制度を導入。各藩から数人の若手藩士(数えの16~20歳)を大学南校(現・東京大学)に留学させる道を開いた。
陳重はちょうど数えの16歳(満15歳)だったため、第1期の貢進生に選ばれた。さらに陳重は1876(明治9)年には文部省海外留学生に選ばれ、ミドル・テンプル(英国の法曹院)、およびベルリン大学に留学。帰朝後、1881(明治14)年に東京大学法学部に勤務し、翌1882(明治15)年に東京大学教授兼法学部長に就任した。わずか26歳である。東京大学創業の頃であり、若年での抜擢も不思議ではないかもしれないが、それにしても若い!
栄一は、「当時自分には十九歳の長女とその妹がいたが、男の子(篤二)は一人でまだ十歳だったので、将来自分と長男の相談相手になるような婿を望んでいた。そこへ西園寺がこの話を持ってきてくれたので大変喜んだ」と述懐している。西園寺公成は、渋沢栄一が優秀な人材を女婿に迎えたいと聞き、旧宇和島藩士のホープ・陳重を紹介したのだろう。その後、宇和島人脈が第一銀行へと食い込むことになったのだから、公成の慧眼に狂いはなかった(なにしろ公成の子が第一銀行頭取となり、孫も重役になったのだから)。
その後、陳重は貴族院議員、帝国大学法科大学長、枢密院議長などを歴任。1915(大正4)年に男爵に列した。
なお、歌の長女・孝子が、てい(栄一の妹。演:藤野涼子)の子・渋沢元治と結婚している。戦前は近親結婚が多かったからだ。

渋沢栄一の次女・琴の夫には、大蔵省主計局のエリート官僚・阪谷芳郎が
次女の琴は1888(明治21)年2月に、備中の儒者・阪谷朗廬(さかたに・ろうろ/演:山崎一)の子で、大蔵省(現・財務省)主計局調査課長の阪谷芳郎(よしろう)と結婚した。琴は満18歳、芳郎は7歳年上の25歳だった。
阪谷朗廬は『青天を衝け』第18話(6月13日放送)に出てくる一橋家領の儒者で、同放送では、朗廬が主宰する私塾・興譲館(こうじょうかん)での宴席シーンがあった。おそらく多くの方が見落としておられると思うのだが、私塾での宴席なのに、朗廬の横には妻子とおぼしき人物が参加している。その子どもが芳郎だという設定なのだろう(『青天を衝け』では、「あっ! あの時の子どもか!」という伏線の回収が行われるのだろうか)。
そういうわけで栄一と阪谷家とは旧知の間柄ではあったが、栄一がその後も芳郎の成長をウォッチし続けていたわけではない。芳郎は年齢を偽って東京英語学校(のち東京大学予備門、旧制第一高等学校)に入学、東京大学文学部政治学理財学科(現・経済学部)に進んだ。東京大学では法理学を穂積陳重、日本財政論を渋沢栄一(講師)に学んだというが、ここでも両者が芳郎を特別視したという話はないようである(というのも、琴がまだ若かったからだろうか)。芳郎は1884(明治17年)年に卒業し、大蔵省に入省した。
1887(明治20)年11月、栄一は王子村(東京都北区)の別荘に東京大学理財学科卒の若者15人ばかりを招待した。これが琴の婿選びだったという。数日後、渋沢家から阪谷家に縁談の打診があり、その翌日、渋沢家を代表して穂積陳重が阪谷家を挨拶。その3カ月後には結婚という慌ただしさだった。
その後、芳郎は大蔵省主計局長、大蔵次官を経て、日露戦争(1904~1907年)の最中(1906[明治39]年)に大蔵大臣に就任して高橋是清(これきよ)とともに戦費調達に活躍。翌1907(明治40)年に、その功績によって男爵に列した。1912(明治45)年には、東京市長(現・東京都知事)に就任した(当時は任命式であり、選挙による選出ではない)。

渋沢栄一の四女・愛子の夫には、渋沢家の“中継ぎ”として優秀な銀行員・明石照男が
千代が1882(明治15)年7月に39歳の若さで死去してしまい、栄一は後妻として伊藤兼子を迎えた。兼子との間に5男1女をもうけた。そのひとり娘を愛子という。
栄一は歌・琴の結婚相手に、自分の事業とは関係なく、若手有望株の青年を選んだ。ところが愛子の縁談は、自身の事業継承を視野に入れたものになった。それには渋沢家の「御家の事情」が関係している。
栄一はいろいろな会社を興したが、本業は第一銀行であると考え、そのトップを渋沢家の跡取り息子に任せたいと考えていたらしい。ところが、栄一の事実上の長男・渋沢篤二は、どちらかといえば芸術家肌で、事業には向かない性格だった。しかも、父親同様に女性関係がハデで、1892(明治25)年に旧制高校を退校して謹慎処分され、結局1913(大正2)年に廃嫡されてしまう。
栄一にはほかに息子がいたのだが、江戸時代的な発想だと、家督継承は長男の子の男子(つまり孫)となる。渋沢家の跡取り息子は、篤二の長男・渋沢敬三に決定した。敬三はものすごく優秀だった。ただ、いかんせん若すぎる。父が廃嫡された時、敬三はまだ未成年だった。
そこで栄一は、優秀な銀行員を娘婿に迎えて、敬三までの中継ぎを任せようと考えた。そのお眼鏡にかなったのが、明石照男(あかし・てるお)である。
明石は岡山県和気郡英保村(現・岡山県備前市)に生まれ、旧制第一高等学校文科、東京帝国大学政治科を卒業し、三菱合資会社に就職。1909(明治42)年に愛子と結婚、結婚とともに第一銀行に転じた。愛子は満19歳、明石は9歳年上の28歳だった。
なぜ、三菱合資会社、つまり三菱財閥から引き抜いたかというと、当時は民間企業が学卒者を定期的に採用することなどまだまれで、東京大学から民間企業といえば、三菱財閥くらいしかなかったのだ。住友財閥が学卒者の定期採用を始めたのは1907(明治40)年。三井財閥は三菱に次いで進んでいたが、銀行なら慶応義塾、物産は東京高商(一橋大学)が主流だった。安田財閥に至っては、学卒者を縁故採用することはあっても育成するルート・ノウハウがなく、結局退職してしまう者が多かったという。奇異に思われるかもしれないが、「学卒者」を「大学院卒」に置き換えれば、現代企業でも通用する話である。学歴が高けりゃいいってものではないのだ。
明石照男は第一銀行で順調に出世を遂げ、1926(大正15)年に45歳で取締役兼本店支配人、2年後に常務兼業務部長。1932(昭和7)年に副頭取、1935(昭和10)年には54歳で第一銀行頭取に就任した。
そして明石は、甥に当たる渋沢敬三を1941年に45歳で副頭取に登用。これで渋沢家の悲願が成就し、すでに亡くなっていた栄一も草葉の陰で喜んでくれるだろう――というところで、敬三が副総裁として日本銀行に取られてしまう。敬三は1944(昭和19)年に48歳の若さで日本銀行総裁に就任。戦時中の難局を任されるということはとんでもなく優秀だったということなのだが、渋沢一族にとっては不幸な結果になってしまった(ちなみに敬三は終戦直後の1945[昭和20]年に大蔵大臣就任を要請され、日本銀行総裁を辞任している)。
(文=菊地浩之)







