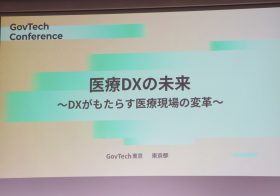マクドナルド、好調を支えるデリバリー&デジタル戦略の研究…進化続ける“店舗力”

日本フードサービス協会が8月25日に発表した「外食産業市場動向調査 7月度」によれば、7月は持ち帰り需要が強みのファストフード業界が外食全体を牽引した。全体売上は前年を少し上回った(102.1%)ものの、コロナ禍前の一昨年の86.3%だ。そして営業時間と酒類提供の制限が厳しいなかで、パブ・居酒屋業態の深刻な状況は続いている。
そうしたなか、8月12日、日本マクドナルドホールディングスは2021年12月期第2四半期決算説明会で、コロナ禍にあっても業績が好調に推移していることを発表した。売上高は1512億円と前年比8.6%プラス、営業利益は172億円と対前年比16.6%。
外食チェーンをけん引するファストフード業界のなかでコロナ以前から堅調な数字を残してきた同社。中期経営計画(18-20年度)の最終年度である20年に新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも、成長のための3本の柱である
(1)コアビジネス(メニュー、バリュー、ファミリー)
(2)成長を加速する(デリバリー、デジタル、未来型店舗体験)
(3)店舗展開(新規出店、リビルド)
をやり遂げたことで、好調を支えてきたことがわかる。
特にデリバリーとデジタル戦略は、時流を先読みした戦略であったともいえるだろう。自社デリバリーを軸としながらも、顧客の利便性向上につながるようにウーバーイーツと出前館をデリバリーツールに加えたことは大きい。自社デリバリーもバイクだけでなく自転車の運用も始まり、機動力を増した。自転車であれば免許も不要であり、道路事情や標識にとらわれず最短の経路で配達することが可能となる。自社の看板を背負っているからこそ、他社のように歩道を疾走する姿は見られない。
デリバリーを担当するスタッフの幅が広がったことも大きい。デジタル対応はコロナを意識してスタートしたわけではない。もともとは顧客の利便性や店舗体験向上に資するためのツールであった。
パークアンドゴーとドライブスルー
説明会資料のなかでは、20年までの計画をさらに進化させることと併せて、「パークアンドゴー」の拡大と「ドライブスルー」の活用が記されていた。新しい取り組みだけでなく、従前から持つ仕組みの再活用。首都圏では環八等々力店のような環状線沿いに立地するドライブスルー対応店舗で、並ぶ車列が延びすぎて通行の妨げになる光景をよく見かける。待機する車両を駐車場に収容できるのであれば、短い時間で手渡しできるパークアンドゴーが有効だ。一方、郊外エリアにおいて車列ができても近隣の迷惑にならなければ、ドライブスルーを強化したほうが、顧客の利便に加え店舗スタッフの効率的な運用につながる。
ファミリーレストランのテイクアウト実績が思うように伸張しない大きな理由は、駐車してわざわざ店内に支払いと受け取りのために赴かないといけないという「顧客のひと手間」ではないだろうか。パークアンドゴーは、この顧客のひと手間を排除することで、顧客の利便と売り上げに大きく貢献している。
店舗スタッフと顧客の手間をどこで線引きしてシェアするかという課題の解決が、ファミレスのテイクアウト実績を伸ばすことにつながるのではないか。当然、店舗の立地によりパークアンドゴーかドライブスルーのどちらが適しているのかは分かれる。
例えば、都心で駅前かつ住宅地に立地する店舗やビジネス街に立地する店舗であれば、駐車場もなく、デリバリー強化が顧客の求める利便性であろう。一方、駅前で駐車場がある店舗であれば、複数の選択肢が想定される。
地域の顧客に受け入れられる店舗づくり
かなり昔になるが筆者が居住していた千葉県船橋市には、マクドナルド南船橋店(16年に閉店)があった。同店はドライブスルーを備え、併設された遊具や赤い二階建てバス内では誕生日会などが開かれ、地域に住む親子連れたちの集いの場所として機能していた。
店舗がどのように地域顧客に利用されているか。顧客の動きやニーズは、店舗が一番把握している。それを戦略として後押しし実績に結び付けるためには、本社と店舗の目線が合致しているかがカギとなるだろう。地域の顧客に受け入れられる戦略を策定し、実行することは意外に難しい。特に全国的にチェーン展開している会社であればなおさらである。
選択肢として多くの提案が生まれるということは、それだけ柔軟な対応ができる素地があるということではないか。顧客が店舗から提案された選択肢をもとに、利用する店舗を決める。特段の強みを持たないチェーンや店舗は、わかりやすい「割引クーポン」や「特別価格」などで対応するしか手はなくなる。
好調なマクドナルドは、さらなる進化を模索している。京急糀谷駅にある店舗では、巨大なタッチパネルが2基設置されている(画像参照)。同店を訪問した際は1基がメンテナンスと記されていたが、パネルを操作する楽しみもあるようだ。若者が多く並んでいたため、残念ながら実機に触ることはかなわなかった。

また、東京有楽町国際ビル内店舗でモバイルオーダー推進のために付されたシール(画像参照)を発見した。

まったく新しいものだけにこだわらず、従来から持つツール(強み)にさらに磨きをかける姿勢のマクドナルド。ライバルは他社ではなく、自社の今なのであろうかと感じさせる。モバイルオーダーの仕組みも未導入の店舗もあるようだが、顧客の利便性に併せて早期の導入が望まれる。
(写真・文=重盛高雄/フードアナリスト)