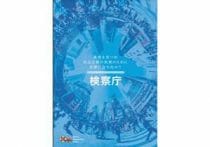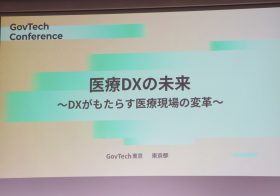【江川紹子が問う戦争の本質】ロシアのウクライナ侵攻は「正義のぶつかり合い」の結果か

ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が始まって、まもなく2カ月になろうとしている。最近は、ロシア軍が去った地域には、日本を含めた世界各国のメディアが入り、ウクライナの人々に対して行われた残虐極まりない蛮行を次々に伝えている。ニュースを見る度に、いったいどうしたら、武器を持たない市民に対してこれほど非道な行為ができるのだろうかと、暗澹たる気持ちに陥る。
ウクライナ侵攻は「ロシアによる重大な国際法違反」
今回の戦争に関しては、日本でもさまざまなメディアで専門家が発信してきたが、それでもまだ、「プーチンにはプーチンの正義がある」「ロシアの正義とウクライナの正義の対立」といった、「正義」でこの戦争を語ろうとする人たちがいる。つい最近も、東京大学の入学式での祝辞で、映画作家の河瀬直美氏が、次のように述べて話題になった。
〈「ロシア」という国を悪者にすることは簡単である。けれどもその国の正義がウクライナの正義とぶつかり合っているのだとしたら、それを止めるにはどうすればいいのか。なぜこのようなことが起こってしまっているのか。一方的な側からの意見に左右されてものの本質を見誤ってはいないだろうか?〉
対象からできるだけ距離を置き、世論に流されずに、客観的にモノを見ようとする態度には、敬意を表したい。ただ、残念に思うのは、こんなふうに「正義」を持ち出すから、逆に「本質を見誤って」しまうのではないか、ということだ。
そもそも、善悪や正義不義の判断には、人それぞれの倫理、宗教観、歴史観などさまざまな価値観が反映される。プーチン大統領や国営メディアを通じてのみ情報を仕入れている多くのロシア国民にとっては、軍事侵攻は「善」であろう。このような価値観の人たちに、その悪や不義を説いても、なかなか交わるところはない。挙げ句の果てには、力の強いものが勝ち、自らの「正義」を敗者に押しつけ、「正義は勝つ」ということになってしまう。
だからこそ、判断基準として国際法があるのではないか。強者が正義となり、大国が国益=正義=善に基づいて侵略や支配を繰り返した時代への反省から、国家間の合意や実績を積み重ねて、国際的な規範が整えられていった。
今回の件でいえば、他国に軍事侵攻したロシアの行為は、明らかにそうした国際法に違反する。たとえば国連憲章2条4項にはこう書かれている。
〈すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない〉
国連緊急特別総会において、「国連憲章第2条4項に違反するロシアによるウクライナに対する侵略を最も強い言葉で非難し」「(ロシア軍の)即時、完全かつ無条件の撤退を求める」とした決議は、賛成141カ国という圧倒的多数で可決された。グテーレス国連事務総長も、「ロシアの侵攻は国連憲章違反」と明言している。
行われているのは、「正義と正義のぶつかり合い」ではなく、「ロシアによる重大な国際法違反」である。これこそが、この戦争の本質だろう。善と悪の対決でもないから、ロシアを「悪者」にするために、ウクライナを「善」の体現者に持ち上げる必要もない。
アメリカが一方的に開始し、多数の市民が巻き添えになったイラク戦争
さらに、首都キーウ近郊のブチャなど、ロシア軍が一時占拠していた各地での住民虐殺やレイプなどが判明している。ウクライナ側が主張するだけでなく、各国メディアの取材でもさまざまな事実が明らかになっている。
こうした行為は、国際刑事裁判所(ICC)に関するローマ規程で定める「人道に対する罪」(7条)、「戦争犯罪」(8条)に当たる可能性が高い。法医学のチームや検察官が現地に入って遺体の検死をはじめとするさまざまな証拠収集を始めている、と報じられている。ICCのカーン主任検察官は、メディアの取材に「ウクライナは犯罪現場だ」「犯罪が行われたと信じるに足る合理的な根拠があるから、ここに来た」と述べた。
ロシアは、ローマ規程の締約国ではなく、捜査に協力するとも思えないので、実際に被疑者を逮捕したり犯人を処罰することへのハードルは高い。それでも、国際的な司法機関で捜査を行い、犯罪事実を明確にする意義は大きい。
独自の歴史観に基づく「善」や「正義」は、それを共有する人たちの間では受け入れられても、国際社会に対する説得力は持たない。学問の場においても同様だろう。
河瀬さんが最高学府の入学式で祝辞を述べるのであれば、むしろ「正義」で戦争を語る愚を語っていただきたかった。そのうえで、今回の戦争が起きるまでの経緯や背景を検証し、大国による国際秩序の破壊を防ぐにはどうしたらいいかを、考え、見極めるよう、学生たちを励ましてほしかった。
そうした検証を行うには、アフガニスタン戦争やイラク戦争など、過去の戦争とそれに対する国際社会の対応を見直すことも、避けて通れない。
たとえばイラク戦争は、イラクが大量破壊兵器を隠し持っているとアメリカが決めつけ、今回のロシアによるウクライナ侵略とは異なり、この時のアメリカにイラクの領土を奪う野心を見て取ることはできないが、明らかに体制転覆を狙っていた。
「明らかな国際法違反」との批判の声もあがった。国連安保理常任理事国ではロシアと中国だけでなく、フランスも開戦に反対した。しかし、アメリカは耳を貸さなかった。「テロとの戦い」のなか、当時のイラクの大統領サダム・フセインを成敗することが、当時のアメリカの「正義」にかなったのだろう。
アメリカは、いまだ国連の査察が終了する前に、国連安保理の決議もなしに英軍とともに攻撃を開始した。アナン事務総長(当時)は「強い遺憾の意」を示したものの、今回のように緊急特別総会を招集して非難決議をあげるようなこともなく、国連はアメリカの侵攻をほぼ黙認する形となった。日本は、当時の小泉純一郎首相がいち早く米国支持の立場を明らかにした。
今回のプーチン大統領と同じく、当時のブッシュ米大統領もまた、短期間で戦争が終結するという楽観的な見通しだったらしい。イラク人民は、米軍をフセインからの解放者として歓迎してくれると思い込んでいたようだ。ブッシュ氏は開戦から1カ月半もしないうちに、「大規模戦闘終結宣言」を行った。しかし、そこからが長かった。イラクの人々は、フセイン支配の終焉は歓迎したが、米軍による支配には反発。周辺から武装勢力も流入し、大勢の市民が巻き添えになった。
大国が自国の「正義」をふりかざし、国際規範を歪めることのないように
イラク戦争における犠牲者数にはさまざまな統計があるが、少なめの報告でも、米軍が撤退するまでに、イラクの民間人11万6000人の命が失われた。多国籍軍兵士も約4800人が死亡している。その過程では、むごたらしい拷問など国際人道法に違反していると思われる行為もあった。
そのため、今回のロシアのウクライナ侵略に関するアメリカの対応には、「偽善的だ」といった批判も出ている。
こうした事実も踏まえ、ロシアに限らず大国が自国の「正義」を振りかざし、国際規範を歪めることがないようにするにはどうしたらいいか。特効薬はないだろうが、専門家には少しでも状況を改善するには何が必要か、知恵を絞ってほしい。
ところが、今、活発にロシア批判の発信をしている専門家の一部には、そういう議論を毛嫌いする人たちがみられる。その発言からは「どうせ自分たちの行為について反省する(させられる)のは日米ばかり」という、いささか被害者意識めいた拒否感情や、ウクライナに肩入れする思いがあまって「戦時中の今、そんな議論をすれば、ロシアの情報戦、心理戦に使われてしまう」といった警戒心が伝わってくる。背景に、アメリカ流の「正義」がちらつくこともある。
人間として、今の状況を見れば、ウクライナに共感するのが人情だとは思う。とはいえ、同国もまた、情報戦の当事者である。
また、今回のロシアの軍事行動には、ウクライナのNATO加入に好意的だったアメリカの責任を問う声もある。私自身は、それがロシアの責任を薄めることにはならないと考えているが、今回のような悲劇を防ぐためには、どうすればよいかを考えるうえでは、あらゆる状況をすべて精査する必要はあるだろう。
専門家は、自身の考えと異なる主張を「どっちもどっち論」として揶揄したり排斥したりするのではなく、できるだけ冷静、客観的に現状を分析し、同時に今後の国際社会の秩序回復に向けての研究や議論を始めてほしいと願う。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)