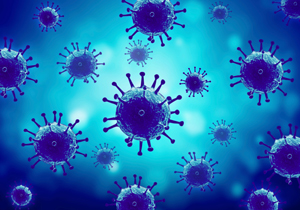 「Thinkstock」より
「Thinkstock」より「週刊東洋経済」(東洋経済新報社/8月30日号)は『保険のウソとホント』という特集を組んでいる。「消費増税がじわじわと家計を苦しめている。しかし消費を手控えるにも限度がある。衣・食・住のどれを取ってもそう簡単に減らせるものではない。それよりは保険料を見直すほうが簡単かもしれない。その術を徹底伝授する」という内容だ。
リスクが過剰に演出されている営業トークやパンフレットの注意点を紹介し、「自力で対応しかねる、大金が必要になる事態に限定して利用することに決めれば、おのずと必要な保険は見えてくる。現状、検討に値するのは、子どもが自立するまで世帯主の万が一に備える保険(定期死亡保険や収入保障保険)、それと病気やケガで仕事に就けないときの所得を補填する保険(就業不能保険)である」とする(特集記事「保険は相互扶助? FPを信じていい? 保険の通説を撃つ!」)。
●日本の保険料は米国の2~4倍
特集の中で興味深いのは『日本の保険は世界の贅沢品』という記事で「日本では『保険は入るもの』と考えられているが、欧米では『保険はできるだけ入らない』のが常識」だと紹介している。
国民皆保険制度のない低福祉国家の米国では、その補完として民間の医療保険が発達。その中心は「年金と医療保険だ。死亡保険に入るのは住宅ローンを組んだときくらいだ。それから富裕層が相続対策で利用する」という。また「英国では一時払いの貯蓄性保険が中心、フランスでは銀行での貯蓄性保険販売が主流だ。英仏とも高福祉国家なので、医療保険や死亡保険にはほとんど入らない。高福祉でありながらこれほど多くの(死亡)保険に入っている国は日本だけ」(同特集より)なのだ。
しかも、日米の生命保険料を、プラン内容が同じ定期死亡保険で比較してみると、日本の保険料は米国の2~4倍であることが判明したのだ。
「米国では喫煙状況や健康状態に応じて細かく保険料を分けるので、非喫煙で健康体の場合にはさらに日本の3分の1~5分の1近くまで安くなることもある。ここまで日米格差が大きいので、相続対策で高額保険が必要な日本の富裕層の中には安い保険を求めてわざわざ米国に出向き、現地の生命保険に入る人もいる」(同)
この日米格差は、日本の「保険料の元値」や「保険会社の手数料」が高いことなどが原因だという。
同記事では、保険に対する過剰な期待を捨て、欧米のように冷静に経済合理性で考えることが必要で、そのためには企業の経済合理性を学ぶべきだと説く。
「あくまでリスク対応の一手段として保険を合理的に活用している。企業が保険を使うのは(その大半が損害保険ではあるが)、対処方法がどうしても保険以外に見当たらない場合に限られる。必要最低限の保障を必要な期間だけ買っている。まさに、企業は『保険はできるだけ入らない』のである」(同)
このため企業は掛け捨てで、すべて保障期間が限定されている有期保険を選び、いろいろな保障が詰め込まれたパッケージ型の保険には入らないのだ。





















