会社からは「不要」の烙印…50代で独立できる人、できない人の違い
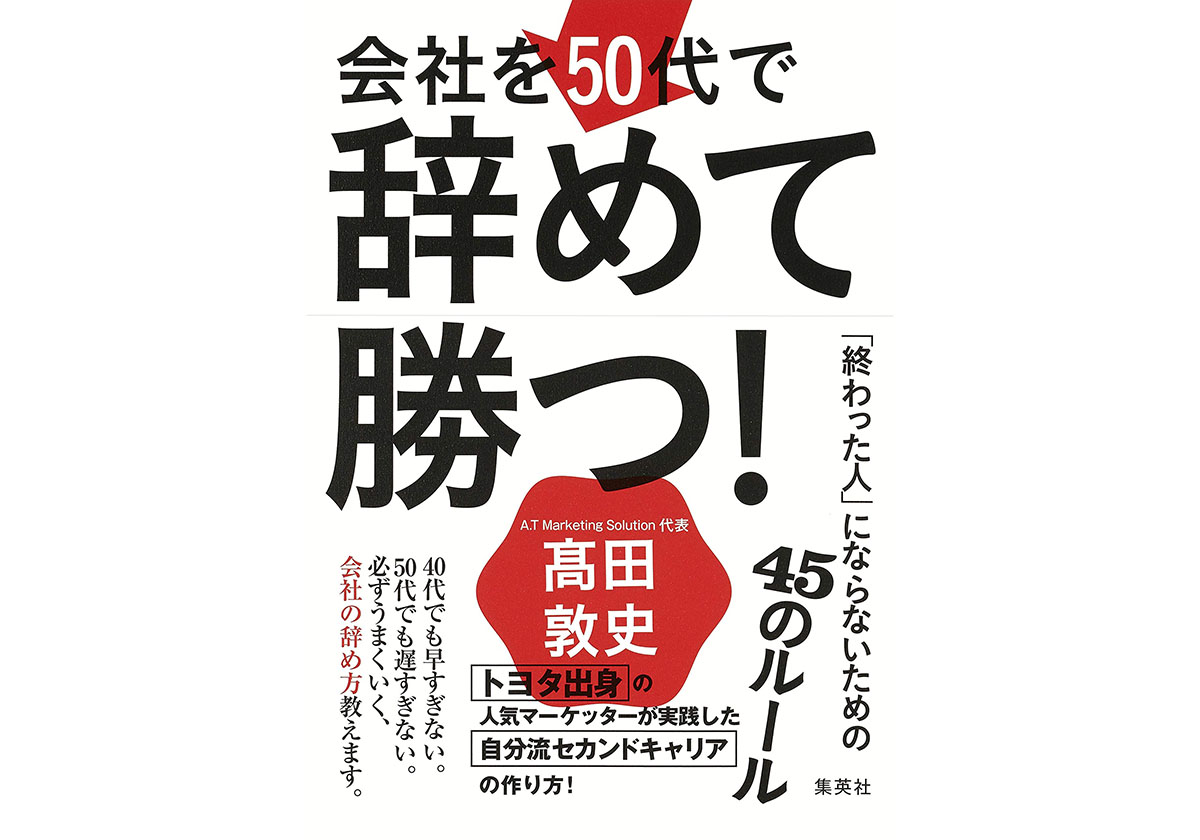
終身雇用制度が機能していたのは、もう昔の話。かつての企業は新卒入社した社員を定年まで面倒を見るのが当たり前だったが、今では誰もが知る一流企業が「早期退職制度」を使って退職者を募ることも珍しくない。
『会社を50代で辞めて勝つ! 「終わった人」にならないための45のルール』(集英社/高田敦史)によると、早期退職の対象として多いのが「50歳以上」。この年齢以降の人材は、会社から「伸びしろのない、終わった人」と見なされていると言っても過言ではない。実際に、勤めている会社で居心地の悪さを感じている人も多いのではないか。
本書は、この年代層のビジネスパーソンに、定年まで会社にしがみつくのではなく、独立して新たな人生を踏み出すためのアドバイスを送る。
独立できる50代と会社にしがみつく50代の決定的な差
50歳ならば、少なくとも30年前後は社会人として仕事を通して技術を磨き、知識を身につけ、人脈を築いてきたことになる。そのキャリアは、自分が思っているよりも貴重なものかもしれない。一方で、すべての人が独立して成功するわけではない。では、独立してやっていける50代と、そうでない50代の違いはどこにあるのだろうか。
本書によると、両者にはいくつかの違いがある。代表的なのが「専門性を持つエキスパートかどうか」。著者の高田敦史氏は、「何らかの専門分野がある人ほど、フリーランスとして生き抜ける可能性は高くなる」としているが、一方で専門分野があるからといって準備なく独立するのではなく、会社員時代から周囲の人にフリーランスとしての自分の可能性を相談したり、取引先など付き合いのある企業に独立後の仕事について打診したりしておくべきとしている。
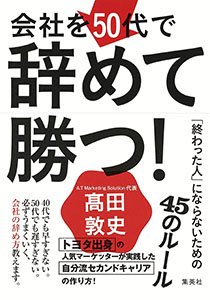
専門性のあるなし以外にも、独立して成功する人とそうでない人には、こんな違いがあるという。
・仕事はノウハウを盗む場と考えている
会社員時代から、独立した自分を想像して仕事ができているかどうかの差は大きい。お金を稼ぐために仕事をするという事実は変わらないが、独立したときのために会社のノウハウを盗んでいると考える人のほうが、実際に独立してからも成功しやすい。
・自腹を切ってでも人に会う
人脈は独立後にものを言う。自分にとって学びになる人、将来の仕事に結びつきそうな人とはお金を払ってでも会いにいく、という積極性が大切だ。
・年下の若手からも学ぶ
歳を取ってくると、目下の人間からものを言われたり何かを教えてもらったりすることに抵抗を感じるようになる人は多い。しかし、何かを学ぶのに年齢など関係ない。
・休みの日でも勉強する
「歳を取ってまで勉強したくない」という人がいる一方で、仕事の時間以外にもたゆまぬ努力ができる人もいる。どちらが会社に頼らず生きられるようになるかは明白だ。
◇ ◇ ◇
ほとんどの人は、50歳まで続いてきた会社員生活からフリーランスにキャリアチェンジすることなど想像もできないかもしれない。しかし、一歩踏み出せば、そこには自由で刺激的な毎日が待っている。
繰り返すが、すべての人が独立して成功できるわけではない。しかし、独立する生き方を一度でも思い描いたことがあるならば、現実的にそれが可能かどうか、真剣に検討してみてはどうだろう。本書はその手助けになってくれるはずだ。
(文=編集部)
※本記事はPR記事です。






















