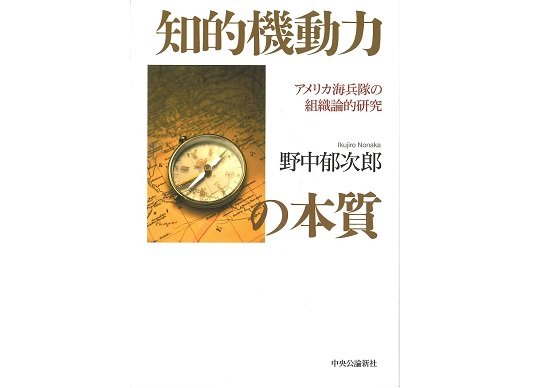一橋大学・野中郁次郎名誉教授が語る、日産・トヨタ・ホンダ…巨大組織のマネジメントの真髄
AIやIoT、ビッグデータ、クラウドなどの先進技術が、世界中にすさまじいスピードで普及している。デジタル化、情報化、ネットワーク化によってビジネスのスピードは増し、従来の経営手法、開発手法では、対応できなくなっている。
国内の電機産業や自動車産業が世界をリードし続けるには、組織の力が問われる。組織の力とはなんなのか。組織を動かすための本質は、どこにあるのか。
一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏と、トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、パナソニックなどの事例を起点に、巨大組織のマネジメントについて語った。
巨大組織のマネジメント
片山 日本経済の屋台骨を担う製造業、なかんずく自動車産業は今、世界的に激しい環境変化に見舞われています。世界の自動車市場の現状を見ると、いわゆる「CASE(コネクティッド・自動化・シェアリング・電動化)」の大波に加え、中国市場は年間4000万台という未曽有の規模に育ちつつあり、アフリカ、インドなど新興国市場も拡大が見込まれます。
トヨタは自動車産業においては独フォルクスワーゲンなどと世界一を争う、日本を代表する巨大メーカーですが、巨大ゆえにスピーディな方向転換は苦手です。急速な環境変化に対応できるのか。また、トヨタは中印アフリカなどの新興市場には、北米や東南アジアのような確固たる足場を持ちません。世界36万人の従業員を抱え、今後、年間販売1000万台を超えて成長を続けていけるのかという課題があります。
数年前から、トヨタの幹部が「マツダに比べると、トヨタはゆるい」といっているのを聞くようになり、トヨタは難しいところにきていると感じるんです。組織が大きくなるほど、社員は危機感を持ちにくくなったり、現場とマネジメントの距離が開いたりする。
さらに、もう一つの課題は、トヨタ社内における技術系の強さです。これも、オペレーション&マネジメントが難しい。例えば、初代プリウスの生みの親であるトヨタ会長の内山田竹志さんなどは、EV(電気自動車)に対していまだに懐疑的な発言をされたりします。
トヨタ社長の豊田章男さんは、早くからコネクティッドカーやEVに取り組もうとしてきました。テスラのイーロン・マスク氏と一緒に、2010年以降、EV「LAV4」の開発もやった。でも、成功したとはいえません。技術者がテスラの風土に合わず、テスラとの提携は、結局、解消。トヨタは、EVの商品化で他メーカーに後れをとったといわれています。
トヨタの技術者はプライドが高くて、必ずしもトップと同じ方向を向くとは限らない。これも、巨大組織の弊害の一つともいえます。そのあたりを、どうご覧になりますか。
野中 巨大組織をいかにマネジメントしていくかという話ですね。例えば、日産の“電気自動車”「e-POWER」はおもしろい例ですね。あれは、数寄者(すきもの)が時間外に手弁当で集まって、「電気自動車の本質はなんだ」とういうことで開発を始め、あっという間にプロトタイプをつくってしまった。インフォーマルの取り組みだったために、フォーマルの取り組みではあり得ないスピードで実現してしまった例です。
「e-POWER」は、エンジンを発電機として使い、発電した電気でモーターを回して走る技術です。このとき、従来のエンジン屋は「発電機屋」になる。これもまた、フォーマルな取り組みならばマインドセットは大変ですが、インフォーマルだったから、やっちゃえたわけです。いわゆる「アジャイルスクラム」ですよね。「部活動」を許容する自律分散的で自由な風土が日産に根づき、ヒット商品を生むベースとなっているんですね。
片山 「スクラム」とは、プロジェクトを段階的に進めるウォーターフォール型に対して、短い期間や単位、小さなチームに分け、各工程を並列に進める「アジャイル型」の開発方法ですよね。ラグビーのスクラムのように、選手が一丸となって同じゴールを目指しつつ、一人ひとりが自律的に動く様子からそう名付けたそうですね。
野中 うん。アジャイルスクラムの発祥は、日本です。もとは、日本の製造業の新製品開発について、1986年に『ハーバード・ビジネス・レビュー』に「新たな新製品開発競争」という論文を竹内弘高と一緒に書いたんですが、「スクラム」は、そのなかで名付けた手法です。
日本企業が元気だったころは、当たり前にそれをやっていたんだ。ただ、間接的に聞いた話ですが、トヨタは改めてアジャイルスクラムを取り入れようとしたときに、主査制度ががっちりと根づいていて、受け入れられなかったそうですね。
片山 トヨタの主査制度の場合は、主査、すなわちチーフエンジニアが、担当する車種に関して、あらゆる責任をもって開発を進めます。確かに、アジャイルスクラムとは相容れないでしょうね。
野中 ですからね、トヨタのような大企業の場合、例えば今導入しているカンパニー制の仕組みのほかに、自己完結的にアジャイルでプロジェクトを回せる仕掛けをもう一つもって、並立させることが必要なんじゃないでしょうか。章男さんのアイデアで、すぐプロトタイプをつくれる仕組みとかね。
組織の機動力をいかにもつか
野中 技術系については、内山田さんだって、ワイワイやるうちに偶然が偶然を呼んでハイブリッド自動車ができあがったわけでしょう。組織がシステマチックに動いたから成功したわけではない。その経歴があるんだから、アジャイルスクラムの要点は、わかると思うんだよね。
燃料電池車やEVも含めて、多種多様なプロジェクトをきちっとこなす伝統的なトヨタの部分と、もう少しライトフットに動いてプロトタイプをつくっては進める部分を、きちっと分けて、両立させる仕掛けをつくることじゃないでしょうかね。
片山 その意味では、トヨタはオープンイノベーションを加速しています。本体とは別にマツダ、デンソーと組んでEVの基盤技術開発会社「EV.C.Aスピリット」をつくったり、「トヨタ・ネクスト」というオープンイノベーションプログラムで、新たなモビリティサービスの案件を募集したりしています。
野中 オープンイノベーションなんて、そんなにうまくいくもんじゃないですよ。本当にうまくいくためには、相互にまっとうにコミットしなければなりません。オープンイノベーションは、コンビネーションがものすごく大変です。必ず葛藤が生じます。ですから、他社とのネットワークを広げつつ、自分たちの組織のなかで機動的に動けるメンバーが必要なんです。
ホンダジェットをつくった藤野道格さんみたいに、本社から離れるとうまくいくんですよ。ホンダの場合は組織の自由度があって、志があるヤツが出てきたときに、その人を許容できる。そういう仕掛けは持っていたほうがいいのかなと思いますね。
片山 ソニーでは、かつて大賀典雄さんが、久夛良木健さんにプレイステーションをやらせるとき、組織につぶされないように、ソニーミュージックからお金を出させて、本体の外でやらせましたよね。久夛良木さんはソニーを去ったけれど、事業はしっかりとソニーのなかに残りました。
野中 そんなことがありましたね。
片山 これらの例に比べると、トヨタの組織は全体的に非常に官僚的なシステムかなという気もします。
野中 それから、技術でいえば、マルチ・エンジニアがポイントですね。ホンダジェットの例では、開発の人員が少ないために、技術者がいろんな分野をマルチでカバーせざるを得なかった。
藤野さんは、翼と機体とエンジンとを別々に最高にするのではなく、3つを合わせたときに最高の効率を発揮させようとして、主翼上面のエンジン配置を実現しました。それはつまり、3つをマルチにカバーしていたからひらめいた。
三菱のMRJがダメなのは、サイロのなかで部分最適化を図っているので、全体最適ができない。トヨタの開発システムも、「主査制度」は段々ガチガチになってくる。どこかでサイロ化してしまうので、そのサイロをぶち破ってスムーズに進めるには、マルチ・エンジニアみたいな役割が、やはり必要になるのではないでしょうか。もともとトヨタ生産方式の「アンドン」は、生産工程の前後の関係性がマルチにわかるようにする仕組みですね。
片山 生産ラインの異常があったときに、作業者がヒモをひいてラインを止める「アンドン」ですよね。異常表示板で、必要な情報を前後の人たちと共有するための見える化の手段ですね。
野中 同じように、開発の連中も、もっとフレキシブルにできるはずだと思いますね。
片山 それができないというのは、余裕がないんでしょうかね。
野中「知的機動力」がないんですよね。
日本企業とアメリカ海兵隊の共通点
片山 「知的機動力」といえば、野中先生は昨年、『知的機動力の本質――アメリカ海兵隊の組織論的研究』(中央公論新社)を出版されました。このなかで、アメリカ海兵隊の備える「知的機動力」を詳細に分析されています。また、日本企業はアメリカ海兵隊と共通する点が多いともおっしゃっていますね。
「知的機動力」は難しいコンセプトなんですが、組織の一人ひとりが市場や技術などの環境変化や組織全体の動きを感じ取り、進む方向が正しいかを適時適切に判断して、戦略や戦術をダイナミックに変えながら行動していく力のことですね。
野中 私はこれまで、数えきれないほどの組織を研究してきましたが、アメリカ海兵隊ほど興味深い組織はほかにありません。凄まじい組織ですよ。軍事組織は、「勝つ」ことが至上命題です。文字通り兵士の命をかけて、勝つ組織を目指して絶えず自己革新しながら進化する。戦略や組織、技術にイノベーションを起こすことで存続し続けてきた組織です。
彼らはまずね、全員がライフルマンです。いつ、どんな立場にあってもライフルを手にし、人命や財産、あるいは仲間を守るために戦う覚悟を持っていなければならない。海兵隊員であるためには、パイロットであれ総司令官であれ、全員が毎年ライフル検定に合格しなければいけないんですね。
要するに、組織を動かすとき、その根底において、異なる職種を通底するスキルが重要になるんです。海兵隊の場合、身体的には、それは全員ライフルマンだということです。
それから、感情面でいえば、生き方のカルチャーですよね。海兵隊の場合のそれは、絶対に仲間の骨は拾うというカルチャーなんだね。戦傷あるいは戦死した海兵隊員を、戦場に残したり放置することは、決してあってはならないとする。死傷しても必ず収容されるという信頼、互いに仲間の骨を拾い合うという戦友愛が、海兵隊員の連帯意識の支柱なんです。
片山 異なる職種を通底するスキルですか。そういえば、直近、パナソニックを取材しているんですが、津賀一宏社長になって以降、パナソニックは車載事業に注力しています。
車載に注力すると明言した当時、車載事業はパナソニックとパナソニック電工、三洋電機の寄り合い所帯で、業績は赤字でした。しかし、いまや車載だけで売上高約2兆円、利益率は5%が視野に入っていて、今後さらなる成長が見込まれています。
当初、組織を立て直すにあたり、バラバラの社員を一つにまとめようと、車載を扱う社内カンパニーのAIS(オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社)は、チャンバラ大会をやった。
野中 チャンバラですか。
片山 そう。AIS社のトップが剣道三段だったこともあって、3年間にわたって毎年、パナソニックの講堂に社員を集めてスポーツチャンバラのイベントをしたんです。参加者は大喜びで盛り上がったそうですよ。マネジメントにはそういう要素も必要ですね。
野中 先ほどの「スクラム」をつくるのは、技術に加えて、感情面をも含む「共感」や「共振」なんですね。「俺とお前」「貴様と俺」の関係です。
片山 パナソニックは、三洋電機やパナソニック電工を統合しましたが、幸之助に連なる「松下グループ」のスピリットがあるのかもしれません。
「量」から「質」への転換
野中 パナソニックといえば、最近、オーディオが復活しましたね。
片山 音響機器ブランドの「テクニクス」ですね。
野中 ええ。「テクニクス」には、小川理子さんというジャズピアニストが携わっていますね。彼女はプロだから、音質を判断できる。「質」はアートの世界ですね。それを機器のスペックに落とすときには、数値に変換しないといけない。「量」はサイエンスです。「テクニクス」は、なぜこれがうまくいったかというと、マルチ・エンジニアやマルチの職種のチームが、その場で音楽を一緒に聞いていたからです。
例えば、ピアノとトランペットの音を鳴らして、スピーカーシステム上でちょっとトランペットを弱くしようといったとき、それを数値にどう変換すればいいかがわからないといけない。それは、何回も何回もチームでコンテクストを共有する。それをやっているうちに、わかってきたんですね。
津賀社長は、「これからの家電は量から質だ」といいましたが、質の判断能力は、アートの世界。それをサイエンスに変換しないとモノにならない。となると、マルチに対応できるチームでやらなきゃダメなんですよ。
片山 そして、一体感がないとうまくいかない。
野中 うん。ホンダのワイガヤや京セラのコンパ経営もそうですけど、必ず彼らは飲むんだよね。
片山 はい、飲みニケーションですよね。
野中 飲んで素の状態にならないと、「共感」なんか生まれないんだよ。
片山 昨今の一連の大企業の不正事件を見ていると、いずれも一体感のない組織ですよね。現場と管理者など、なんだかバラバラなんですよ。「通底するスキル」や「共感」がないんでしょうかね。
野中 まったくそう思いますね。場を共有するとか、日常性のなかに組み込むことが大切です。マルチ・エンジニアというのは、基本的にはプロジェクトリーダーだと思います。トヨタには、多くのリーダーや専門家がいますよね。いろんなものの見方を持った彼らが、同じものを見たとき、いろんな側面がわかってくる。ですから、徹底的にサイロを破壊することが重要ですね。
製造業だけじゃなくて、ソフトウェア開発も同じです。ソフトウェア開発におけるウォーターフォール型の開発では、例えばプログラミング段階で判明した仕様の不備を、仕様策定段階までさかのぼって修正せねばならず、時間もかかるし難しい。アジャイルスクラムなら、開発段階から顧客も入れ込んで、ミーティングやペアプログラミングの場で問題を共有し、すぐにフィードバックできる。
ペアプログラミングという手法もおもしろくて、いわばITの世界の徒弟制度なんですね。ベテランと新人が一緒に、一台のワークステーションを使って共同でソフトウェアの開発を進める手法です。
大事なのは、ペアは毎日必ず5分でも10分でも会って、とにかく何か喋ることです。「今日は何をやった」「問題はこれだ」とか。そのなかでコンセプトが出かかったら、ペアプログラミングで落としこむ。一人でやらずに、ワイワイやり合いながら進めるんです。いちばん生産性が上がるのはね、ペアでやっている時の「差し入れ」だといいますよ。
片山 ああ。
野中 チョコレートとか。寿司がいちばんいいとか聞いたな(笑)。楽しむんですよね。ただ、重要なのは、シロウトのブレインストーミングではなく、プロが集まって一体感につなぐということです。アジャイルスクラムは、プロがいいたいことをいい合わないとダメです。一人ひとり、見る側面が違うので、無心の状態になった時に、そこで初めてピーンとつながるんですよね。そういう場が、すごく重要だと思うんですけどね。
デジタルやAIは、本質ではない
片山 一体感という意味では、トヨタは組織の不正が起きにくい例ではないでしょうか。トヨタには現在、副社長と専務に、トヨタ工業学園卒の叩き上げの人材が入っている。その一人、副社長の河合満さんに、先だってお会いする機会があったんですが、日産やスバルで不正検査問題があった際、河合さんのもとに章男さんから「うちは大丈夫か?」とすぐにメールがきたそうです。河合さんは、「大丈夫です」と即答した。
トヨタの完成車工場は国内に6つありますが、50年も現場を見て回っているから、自信があったと。全部見ているからわかるんだ、といっていましたね。ちなみに、河合さんは鍛造出身なんですが、本社のなかには「鍛造の湯」っていうでっかいお風呂があるんだそうですよ。「俺は朝からその風呂に入って、みんなと話をしている」といっていましたよ。
野中 うん。やっぱりね、体を使わなければダメですね。AIとかIoTとかは、本質的ではない。すべての源泉は、アナログなんです。アナログを普遍化しているのがデジタルであって、最初にデジタルありきじゃないんですよ。
AIやIoTは大いに結構なんですが、あくまで人間の暗黙知をオーグメント、あるいは補完・拡張するツールであって、ああいうものが前面に出てきてしまうと違ってくる。人間が全身全霊で物事に向き合うという身体感覚がなければ、ダメなんですよ。
片山 河合さんも、やはり人間の五感のセンサーが大事なんだという話をされていました。例えば、温度センサーはあっても、頼り切ってはいけない。火の色を見て温度がわかれば、かりにセンサーが壊れているとき、目で見てセンサーの故障に気づけると。
よく、河合さんは習字の例を出されます。ロボットに字を書かせるとき、下手が教えたらロボットは下手な字しか書けない。プロの書いた字を教えないとダメだというんですね。
野中 そうですね。重要なのは意味とか価値づけです。それをつくるのは人間の五感であり、主観なんです。主観のセンスの鋭いヤツが、いちばん重要なんですよ。背後にあるものの意味づけ、価値づけができる人間が、プロジェクトリーダーとして重要になると思います。
AIは確率だから、意味を考えてくれるわけじゃない。コンセプトをつくる、カテゴリーを超えるということは、AIにできるはずがないんだよ。それができる人間とか、場を、組織に仕組みとして組み込むことはすごく重要だと思いますね。
片山 これからの時代は、AIを活用できない企業は、成長できないといわれます。一面では、それも正しいけれど、AIやロボットは教えたことしかできません。
野中 暗黙知と形式知は、相互補完で絶えず補完し合って互いに高めていく。だけど最初に暗黙知ありきです。われわれは、直接経験のなかから学び、意味を獲得していくわけで、数値自体にはなんの意味もないですからね。
片山 暗黙知でつくったものを形式知化して、また暗黙知で進化させていく。一度ロボットに組み込んだことは、勝手には進化しませんからね。そこでもう一回、人間が匠の技で進化させないといけない。
野中 まさにそうだと思います。だから、絶えず暗黙知と形式知は循環していないと具合が悪い。その意味でいうとね、破壊的イノベーションのコンセプトは無理がある。突然、破壊なんて起こるはずはないんです。本質は、持続のなかでの連続の非連続なんだ。
片山 連続の非連続ですか。非連続だけではダメなんですか。
野中 最初に非連続なんてあり得ないんだよ。歴史的ダイナミズムを無視して、突如イノベーションが起きるというのは、あり得ない。破壊的イノベーションのコンセプトには、歴史感覚がないという大きな問題があるんです。
片山 なるほど。連続しているからこそ、非連続となったときにイノベーションが起きるわけですね。AIだ、IoTだといいますけれど、むしろ今こそ原点を押さえるべきですね。
野中 そうそう。経験の質量を、日常性のなかで鍛えていかないといけません。
(文=片山修/経済ジャーナリスト、経営評論家)