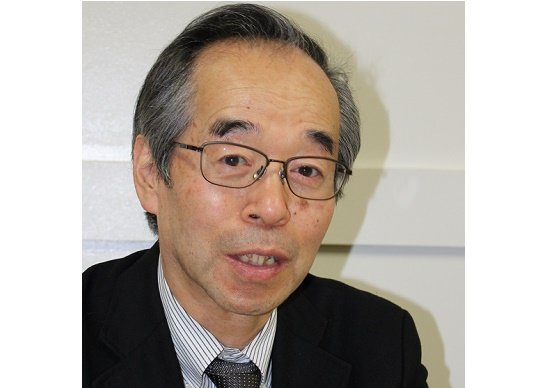 東京大学大学院工学研究科・鈴木真二教授
東京大学大学院工学研究科・鈴木真二教授2016年には災害復興や産業用として注目されたドローン。法整備なども進み実際に使われていくなかで、ドローンの有用性、そして課題がみえてきた。今月23日から「ジャパン・ドローン2017」を主催する社団法人日本UAS 産業振興協議会(JUIDA)理事長で東京大学大学院工学研究科の鈴木真二教授に話を聞いた。
――16年は産業用ドローンの利用元年といわれましたが、振り返ってどう思いますか。
鈴木真二教授(以下、鈴木) 15年に航空法が改正、施行されたので、16年はきちんとしたルールに則っていろいろな事業が始まりました。特に測量分野では国も推進しました。橋梁点検でもドローンの利用が検討されています。これを人手でやるのは大変で、まだ研究段階ですがドローンにハンマーをつけて確認するというのは、意義が大きいと思います。災害でもドローンが活躍しました。
――物流でドローンがどう活躍するかが注目されています。
鈴木 物流は大きな目標になっていますが、これからです。倉庫の荷物の荷揚げも、まだこれからです。今のドローンは、GPSを使って自分の位置を確認しています。ドローンにとって倉庫関連は大きな市場がありますが、室内ではGPSが使えないので、操縦自体をマニュアルでおこなわなければなりません。そのため、操作するためにはエキスパ―トが必要になります。
――物流では今、人手不足が深刻な問題となっていますが、それをカバーできるようなものになりますか。
鈴木 過疎地や山間部、離島など人口密度の低い地域、海上輸送が必要な地域ではニーズはかなりあると思います。熊本の天草など、人工が減って限界集落のような地域も出てきました。高齢者も増えてくるなかで、行方不明の老人を捜索するためにドローンを活用することもできます。
――農業などでも、さまざまな可能性があります。
鈴木 農業でも、農薬散布やイノシシやシカなどの獣を駆逐するのにも活用できると思います。農林水産省も検討会を立ち上げました。このほか、夜間の監視システムなどでも可能性を秘めています。ただ、まだ飛行時間の問題や落下のリスクをどう回避するかという問題は抱えています。保険制度の整備の課題もあります。最初は地方の自治体のサービスの一環として期待しています。長野の伊那市など積極的な自治体もありJUIDAも協力しています。
行政でも活用
――自治体が積極的に活用できるのは、どういう機能なのでしょうか。
鈴木 離島に薬を届けたり、雪に閉ざされた民家に非常物資や通信機器を届けるようなケースです。災害地は、陸路が破壊されるとそこに行くこと自体が難しいので、ドローンが活躍する場面がたくさんあると思います。
――JUIDAでは、どのような取り組みを行っているのですか。
鈴木 JUIDAの会員団体のなかで、地方自治体と防災の連携協定を結んで「何かあったら助けます」というところがあります。JUIDAはライセンスを取得するための教習所の認定事業をやっていて、全国で約50カ所ドローンスクールがあります。使い方を学びたいという人も増えており、そうした人たちが今後、災害があったときにいち早く、活動できると思います。
――産業用ドローンの課題は。
鈴木 信頼性や安全性です。新しい技術ですのでまだ統一的な基準ができていません。。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のほうで性能評価ワーキンググループをつくり、カタログに載せるスペックの基準を検討しています。
――制度を整えるためには、どのくらいの時間がかかりますか。
鈴木 そうですね。政府は18年までにさまざまなことが実現できるように準備を進めています。国土交通省は衝突防止について検討しています。経済産業省は研究開発の予算を確保したり、総務省はドローン用の電波の検討をしています。各省庁が連携してつながっていけば、5年ぐらいでなんとかなると思います。
――現在の周波数帯は。
鈴木 今は2.4ギガヘルツ帯です。Wi-Fiの周波数帯を使っているのですが、機器を安く調達するためです。ただ5ギガヘルツ帯のWi-Fiの周波数は日本では屋外では使えないので、これを昨年夏に緩和して、ドローン用に5ギガ帯でも外で使えるようにしました。
――Wi-Fiの周波数帯はユーザー数が多いのではないですか。
鈴木 電波が被らないように調整しながら、新しい電波を利用する必要があります。昨年JUTM(日本無人機運行管理コンソーシアム)という組織をつくったのですが、そこで出力の高い電波を使うときにはで調整を行います。
ドローン先進国、欧米での取り組み
――今後は航空管制システムをしっかりやっていくことが大きな課題になると思いますが、ドローン先進国の欧米はどのような対応を取っているのでしょうか。
鈴木 まだ実用化されてはいません。これからだと思います。これは段階的に進んでいくと思いますが、最初は誰がどこにいるのかを把握するところから始まり、その次には、同じ空域を同じ時間に高度を変えて飛行できるようにする。飛行機の管制システムのようなイメージです。
――ドローンの操縦者は、どの程度まで機器の仕組みを理解していればいいのでしょうか。
鈴木 米国ではすでに業務用に利用する人向けに、飛行機のパイロットが受けるようなペーパー試験が行われています。更新は2年ごとで、日本ではどのようなかたちで実施するのかが課題です。
――17年はどのような年になりますか。
鈴木 昨年は「利用元年」というような言い方をしたのですが、今年は「事業化元年」になると思います。その背景には制度が整ってきたことと、大手の事業者が参入を検討し始めていることがあります。全日空や日本航空が機体の点検などにドローンを活用しようとする動きもあります。大型のドローンで海上で物が運べるようになると、離島への物流などで活用が期待できます。
――町中でのドローン活用は、今後実現されるでしょうか。
鈴木 そうした期待もありますが、各国とも規制が厳しいので町中で物流面で活用されるのはまだ難しいと思います。
物流危機を救う?
――今後、ドローンは物流ではどのようなかたちで活用されるでしょうか。
鈴木 ドローンポートのようなものを、標準の離着陸システムをつくっていかなければならないと思います。
――長距離の物流についてはどうですか。
鈴木 大型のドローンでカーゴ便を無人で飛ばそうという構想はあります。大手空輸会社が真剣に考え、国連の専門機関でもルールづくりが検討され、2020年代には実験的に飛ばすということになると思います。砂漠の飛行場から離陸して海上の飛行場に着陸することなどが検討されています。こうした時代は意外に早くくるかもしれません。ただ、通信の問題や衝突回避の問題など技術的な課題はまだまだあります。
――ドローンを活用すると、未来の社会はどのように変わっていきますか。
鈴木 地方からドローンは使われるようになるのではないかと思います。災害や過疎地域での活用が大きなテーマになるでしょう。過疎地域で活用されながら、技術が成熟し、信頼性、安全性が確保できれば都市にも入っていくのではないでしょうか。
――ドローンはシンギュラリティ(技術的特異点:従来とはまったく異なる世界が生まれる契機)をもたらすでしょうか。
鈴木 室内で使われるようになると、社会に大きな変化をもたらすかもしれません。倉庫内の点検などでも活用できますし、落下しても大きな問題にはなりません。ドローンは空を飛んでいるようなイメージがありますが、そうした屋内や排水溝などでも大きな力を発揮できると思います。今、ロボットが排水溝内で作業していますが、速度が遅い。それを加速できると思います。さらに広角のステレオカメラを搭載して、室内で飛行位置を推定し、障害物も回避できる室内自動飛行ドローンシステムの研究を行っています。
(構成=松崎隆司/経済ジャーナリスト)




















