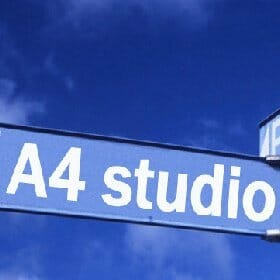「Thinkstock」より
「Thinkstock」より中国生まれの料理ながら、日本で独自の進化を遂げてきたラーメン。気取らず手早く食べられる“庶民の料理”として愛されているが、近年は本格志向のラーメン店も少なくない。
「ラーメン1杯に払える値段は?」といったアンケートでは、「800円前後」という回答が多いようで、現代のラーメンは高級料理とまでいかなくとも単なるファストフードの枠には収まらない、独特な位置づけにあるといえそうだ。
さて、ラーメンに限った話ではないが、どんなに手間やコストをかけた絶品メニューであっても、最終的には店の利益が出る仕組みになっていなければ、経営は成立しないだろう。原価率という観点から見て、ラーメン店のビジネスモデルはどのようなものなのか。
「らーめん無双」(東京都八王子市、2016年4月に閉店)元店主の西村政司氏と、ラーメン評論家の山路力也氏に話を聞いた。
味噌ラーメンは料金を高めに設定しやすい?
まずは、ラーメン好きが高じて14年にラーメン店を開店するに至ったという、西村氏の談。
「ラーメンの原価率は、麺やスープ、その他もろもろのトッピングなどを載せて、30~32.5%前後が適正だといわれています。私が営業していた店は、うまく原価率を下げられるよう、いろいろと厳選した食材を使っていました。多種多様なメニューを提供していたなかでも、特に低い原価率でつくっていたのは、清湯系スープのオーソドックスなラーメンです」(西村氏)
当時の具体的な原価率を振り返ってもらうと、各690円(税込み、以下同)の醤油ラーメンと塩ラーメンが28%。1杯売れれば、店に約500円の儲けが出る計算だ。そして、意外かもしれないが、790円の味噌ラーメンは、醤油と塩よりも低い24%でつくっていたという。
「味噌ラーメンの具材は、もやしとコーン、それにチャーシューが1枚でした。野菜は安く仕入れることができる上にラーメンのボリューム感を出すことができ、見栄えもよくなります。もやしは味噌と相性がいいですが、仕入れ値は100gで9円でしたし、コーンも50gで20円と、ものすごく安かったですね。店からすると、味噌ラーメンはほかのメニューに比べて料金を高めに設定しやすいと思います」(同)
西村氏いわく、同じ原価率のラーメンであっても、野菜をたくさん盛るのか、チャーシューをちんまり盛るのかなど、アピールの仕方が違えば客に与える印象も違ってくるとのこと。
一方、評論家の山路氏は、原価率についてこう補足する。
「丼そのものの形状や大きさを変えれば、ラーメンの見栄えもガラリと変わりますし、それによってスープの容量が少なくなるだけでも、1日トータルで考えれば原価率に差が生まれます」(山路氏)
原価率をコントロールするには、食器まで含めて「どんな見せ方をするか」が重要な要素となるようだ。
一番原価率が高いトッピングはチャーシュー?
元店主の西村氏によると、ラーメンの具材でもっとも原価率が高いのはチャーシューだという。
「豚肉はだいたい1kgで1000円しますし、それをチャーシューに仕上げる工程でも、ガスや醤油などの費用がかかります。肉の塊からチャーシューを何枚切り出すか、どれくらいの厚みにするかは店によって違うと思うのですが、私の店では原価率が50~60%を超える厚切りのチャーシューを、トッピングで安く提供していました。チャーシューは、お客様に喜んでもらうために利益を度外視していたんです」(西村氏)
ただ、次第に原価率と売り上げのバランスを保てなくなり、それが店をたたむ一因になってしまったという。
「開店当初から、自分が理想とするラーメンをつくっているつもりでした。ただ、一方では『店の個性を強く打ち出していかなければ、リピーターのお客様がついてきてくれないだろう』という焦りも感じていました。
そんななか、テレビ番組の企画で有名店に弟子入りして勉強させてもらう機会をいただき、濃厚でドロドロなスープの豚骨ラーメン(750円)の販売を始めるようになったのですが、この原価率は41.3%。スープだけで212円と、ほかのメニューに使っていたスープの3倍近いコストだったのです。
私が店を出していたのは、さっぱりめの『八王子ラーメン』が流行っていた地域なので、『豚骨なら“異色”で戦える』と踏んだのですが、結果的には無理でしたね。営業中ずっと忙しい、それこそ薄利多売の状態でやっていければ問題はなかったのでしょうが、あまり集客が見込めないなかで高い原価率を維持し、店を続けていくのは厳しかったということです」(同)
それ以外にも、繁華街の中心地に全33席の店を構えていたことによる高額な家賃や、スープのダシを取るために使った豚の骨(産業廃棄物)の処理費なども、経営を圧迫していたという。西村氏は、「もっと家賃が安く、1人でまわせるような狭い店であれば、この原価率のままでも逆に儲かっていたのでは」と心境を吐露した。
原価100円のまぜそばが人気になる顧客心理とは
利益を生むためには原価率を調整する必要があるものの、肝心の味が落ちてしまえば本末転倒になる。品質と利益の板挟みになるというのは、飲食店の永遠のテーマなのかもしれないが、一方で客は原価率についてどう考えているのか。評論家の山路氏は、その顧客心理をこう分析する。
「一般的に、飲食店の客は原価まで考えることはないと思います。ラーメン店では、ビールやコーラなどのドリンク類に関しては原価を意識してしまうかもしれませんが、『このトッピングの原価は冷静に考えるといくら』だなんて、いちいち計算しないでしょう。原価的に得だから食べるのではなく、“食べたいから食べる”というシンプルな心理なのではないでしょうか。
現在、増えてきている『まぜそば』(油そば)は、まさにその最たる例。まぜそばには原価のかかるスープが使われていないのに、ラーメンとほぼ同料金で提供されていますが、それでも人気を集めていますよね」(山路氏)
元店主の西村氏も、まぜそばの原価率についてはこう同意する。
「もちろん、味が悪ければお客様はつきませんが、確かにまぜそばの原価は安いです。まぜそばは、タレを丼に30~40ccほど入れて麺を茹で、具材を載せ、あとはお客様に混ぜて食べてもらうだけで十分に成り立ちます。タレが足りないお客様には、卓上のお酢やラー油をセルフで入れてもらえばいいのです。
私の店を例に原価を計算してみると、普通のラーメンなら、タレをスープで割るのでそこに約70円かかりますが、まぜそばの場合はタレしか使わないため30円前後。麺と具材まで含めても、原価は100~130円程度で済むのではないかと思います」(西村氏)
1000円超えのラーメンが主流になる日は来る?
最後に、西村氏は、ラーメンの価格帯が高騰している背景について、次のように推察する。
「今はラーメンに対する店側のこだわりが強くなってきており、『これくらいお金を取っても大丈夫だろう』というボーダーラインも上がってきています。トッピングなしの通常のラーメンが900円くらいするケースもざらでしょう。
そのラーメンも、実際には原価率15~20%あたりかもしれませんが、『900円で1食になるならいいだろう』と納得するお客様も多いのだと思います。たとえばファミレスで食事をしても、料金は同じかそれ以上の金額になることが多いですから」(同)
高価格帯のラーメンが受け入れられる土壌は整っているということか。しかし、評論家の山路氏は以下のような見解を示す。
「今のところ、1000円を超えるようなラーメンが主流になるのは、なかなか厳しいのではないかと思います。確かに、ラーメン自体はつくり手のこだわりが強くなり味のレベルも上がりつつありますが、サービスや接客はいまだB級の域を出ていない店がほとんどです。
もっとも、客がラーメンという食べ物をどう捉えているかで、その感覚も変わってくるはず。ラーメンは500円以下が当たり前の時代を過ごしてきた年配の方だと、700円でも『高い』と言うでしょうしね」(山路氏)
サービスや接客といった諸要素まで勘案すると、昨今のラーメンに割高なイメージを持ってしまう客も少なくないのかもしれない。結局、ラーメン店にとっては、原価率を徹底的に抑えるにしろ、品質を高めた分だけ高値にするにしろ、いかにして客を“食べたいから食べる”気持ちにさせるかが勝負なのだろう。
(文=森井隆二郎/A4studio)