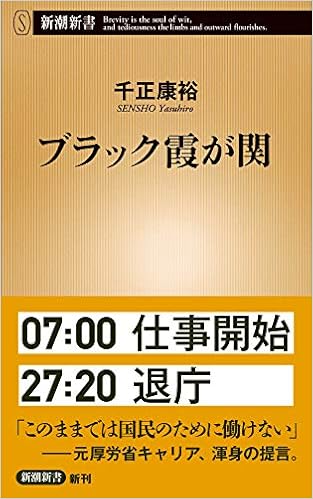キャリア官僚の志望者が激減…人手不足の“ブラック霞が関”を待つ沈没の危機と回避策とは

過労死ラインとされる月80時間を優に超える残業は当たり前、予測不能な国会対応などでテレワークは一向に進まない……。今、霞が関で働く官僚の多くは過重労働を強いられ、離職者の数は増加の一途をたどっているという。
そんな中、元キャリア官僚の視点から、霞が関で常態化している過酷な労働の実態や構造的な問題を炙り出した『ブラック霞が関』(新潮社)が話題を集めている。著者の千正康裕氏に、本書に込めた思いや官僚の働き方が変わっていくために必要なことについてうかがった。
霞が関の体質が変わらなかった理由
政治状況が変わり、内閣支持率が選挙結果にダイレクトに結びつくようになった。支持率を常に高く保つために、ある課題が出てきたときに、世の中の関心の高いうちに、世間の空気を読んで官邸主導で重要な政策決定がなされるようになった結果、霞が関の官僚は無理なスケジュールでの制度設計を強いられることが増えていった。
「政治状況が大きく変わって、迅速な対応が取られるようになったことは素晴らしいのですが、世の中の関心が高まっているうちに政策を打ち出すのであれば、それに追いつけるようなマンパワーが必要です」(千正氏)
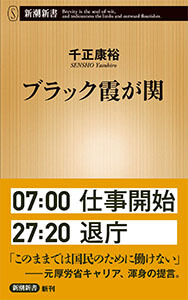
官僚の働き方を変えるためには、どのようなアプローチが求められるのだろうか。
「現在の霞が関が抱える問題を世間に広く認知してもらい、改革の必要性を理解してもらうことが大切です。2020年9月に河野太郎さんが国家公務員制度担当大臣に就任し、『霞が関のブラックな状況をホワイト化していく』と表明しましたよね。
ちょうど、その後、僕の『ブラック霞が関』も出版されたのですが、この問題に関する報道が増え、官僚の過酷な労働実態が少しずつ知られるようになり、実際にサービス残業をやめて残業代を適正に支給するよう指示が出されるなど、改善も見られています。国会も質問通告がいくらか早くなったり、政党の会議がペーパーレスになったり、ウェブ会議で官僚の説明を受けたり、できることから改善が始まっています。
もし、官僚の仕事に対して世間が『公務員だから“9時5時”で楽な仕事でしょう』という誤った古いイメージを持ったままであれば、権限のある政治家が変えようと働きかけても、世間からの支持は得られなかったはず。官僚の給料の原資は税金ですからね」(同)
千正氏は「霞が関に人材が集まらなくなり、組織の力が落ちていくと、政策の質が落ちたりミスが増えたりして国民に迷惑がかかる」という思いから、官僚の働き方を変えるための活動を始めた。
「政治家が悪いという人もいますが、彼らは個人の趣味で意思決定をしているわけではなく、常に世論を気にしています。(1)世間が『霞が関や永田町を変えていくべきだ』という声を上げること、(2)権限のある人が、その声を受けて変革のために動くこと。あらゆる政策の変更と同様に、官僚の働き方を変えるためには、この2つのステップが必要なのです」(同)
キャリア官僚の志望者は過去最大の減少率に
近年、深夜残業や長時間勤務といったネガティブなイメージが定着したこともあり、キャリア官僚を志望する人の数は減少傾向にある。2021年度の中央省庁幹部候補の総合職の申込者は前年度比14.5%減を記録し、減少率は過去最大となった。官僚の働き方を改革しない限り、霞が関の未来はない。
「『ブラック霞が関』というタイトルなので、霞が関の負の側面に興味を持ち、手に取ってくださる方も多いのですが、本書には『政策をつくって社会を良くする』という官僚の仕事の醍醐味についても記述しました。それは、キャリア官僚の仕事が社会にどういう価値をもたらしているかということを伝えないと、『遠いところにいるエリートたちは大変なんだね』というふうに、多くの方にとって自分とは関係のない話と受け止められてしまうと思ったからです。また、官僚に興味がある学生にも読んでほしい。官僚の仕事は国民の暮らしに不可欠なものであり、政策が形になれば、この上ない充実感を得ることができる。これは学生の人たちにも、声を大にして伝えたいですね」(同)
人手不足に喘ぐ霞が関を変えるためには、若い世代に向けて官僚の仕事のやりがいを伝えていくことも大切なのだ。
「もちろん、官僚が重要な仕事だからといって、働き方がブラックで良いというわけではありません。現在は過酷な労働を余儀なくされているけども、変わっていくんだという前向きな姿勢と、実際に変わっていく姿を正しく見せていかないと、霞が関は間違いなく沈没していきますよ。残業代が適切に支払われるようになってきたことは朗報ですが、次は残業そのものをどう減らしていくのかが課題ですね」(同)
官僚の働き方が変われば政策の質は必ず上がる
官僚になるためには、難関の国家公務員試験をパスする必要がある。いわば、中央省庁で働く職員たちは国を支える頭脳であるわけだが、現在霞が関で働く人々のほとんどは、重要な政策を担当している人ほど、日々の仕事に忙殺されて本を読む時間もろくに取れず、持っている能力を十分に発揮することができないでいる。
「本来なら官僚は、民間の人と会って話をしたり、政策に関わる現場を視察するなど、国民生活に寄与する良いアイデアを生み出すために時間を使うべきなのですが、現状はそれが困難です。外に目を向ける余裕がないことは、多くの国民が『これじゃない』と思うような、納得感の低い政策が生み出されたり、実務がうまくいかない制度設計をしてしまう要因の一つとなっています」(同)
千正氏によると、霞が関の働き方が変わり、自分の裁量で時間を使えるようになると、さまざまな面でポジティブな影響をもたらすという。
「基本的に霞が関で働く人材は、お金のためよりも社会の役に立ちたいと思っている人が多いので、時間の裁量を与えてあげれば放っておいても勉強するし、現場を見に行きます。霞が関という場所は、お客様である国民からすごく遠いんです。実際に現場に足を運んで“お客様”の声に耳を傾ける機会をつくらないと、自分の仕事が社会にどうつながっているかということが見えないのです。その機会を繰り返し持つことで、仕事のやりがいを感じることができますし、何より制度をつくるときに、それを必要とする人の存在をリアルにイメージできるようになる。
一つの法案を通すためには多くの人の承諾を得る必要があるのですが、予算が多い、現場のマンパワーが足りない、反対する人もいるなど『できない理由』にぶつかることがあります。それを乗り越えるには、かなりの知恵や労力が必要になるので、内容を一部変えるなど譲歩したくなるものですが、その政策を必要としている人のことがちゃんとイメージできていれば、妥協せずに100%の形で実現しようとがんばれる。霞が関の働き方が改善されると、政策の質は間違いなく上がるのです」(同)
国家の中枢で政策立案に携わる、霞が関の官僚たち。過労死ラインを超える長時間残業によって、優秀な人材が職を離れてしまうことで失われる国益は計り知れない。官僚の働き方を改革していくことは、我々の日々の生活に直結しているのだ。
『ブラック霞が関』 朝七時、仕事開始。二七時二〇分、退庁。ブラック労働は今や霞が関の標準だ。相次ぐ休職や退職、採用難が官僚たちをさらに追いつめる。国会対応のための不毛な残業、乱立する会議、煩雑な手続き、旧態依然の「紙文化」…この負のスパイラルを止めなければ、最終的に被害を受けるのは国家、国民だ。官僚が本当に能力を発揮できるようにするにはどうすればいいのか。元厚生労働省キャリアが具体策を提言する。