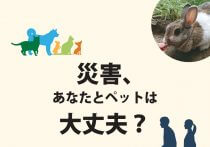7日の地震で品川区、一時滞在施設が開設されず…帰宅難民者へのアナウンスもされず

東日本大震災以来初となる“震度5強の揺れ”が首都圏を直撃した。7日深夜の首都直下を震源とする地震による負傷者は32人(8日朝時点、総務省消防庁の集計)にのぼり、新交通システム「日暮里・舎人ライナー」(東京都)も脱線、首都圏の鉄道各社は深夜まで運転を見合わせた。各社報道ではJR、京急品川駅などで右往左往する乗客の姿がたびたび切り取られ、あらためて「災害時の帰宅困難者の存在」が浮き彫りになった。
7日深夜、JR品川駅で立ち往生した川崎市在住の40代男性会社員は語る。
「震災の時のことがフラッシュバックしました。どこかで夜明かししようと考えたのですが、結局、一時滞在施設がどこなのかわからず、ただじっと電車が動くのを駅構内でうずくまって待っていました」
震災時に発生した帰宅困難者は約515万人。大規模災害時、首都圏に通勤・通学するすべての人がその被害者となり得る古くて新しい問題だ。果たして自治体やJR東日本はどのように対応したのだろうか。JR東日本広報部の担当者は次のように語る。
「一般的に大規模災害が発生した対応として、東京の30キロ圏内にある約200駅において一時滞在場所の提供や、そうしたスペースがない駅においてもトイレや公衆電話をできる限り、提供するといった対策を実施しています。一時滞在場所を提供する駅においても、要援助者を対象に飲料水や毛布、救急用品などの提供を行っております。
今回の地震に関してはそうした対応を行ったかどうかは各駅で確認してみないとわかりません。基本的に駅構内で安全を確保できる場所、運転再開まで支障なくお待ちいただける場所をできる範囲で提供するという考え方です」
民間事業者として自社の管轄内ででき得る限りの努力をしているが、駅が所在する自治体が用意する一時滞在施設などのアナウンスまでは手が回らないというのが実情のようだ。
品川区は駅に職員を派遣も、今回は一時滞在施設の開設を見送り
一方、品川駅を有する東京都品川区の防災課の担当者は次のように話す。
「今回の地震では、帰宅困難者向けの具体的なアナウンスはしておりません。昨晩は職員40人体制で対応にあたり、区内の主要駅、目黒、五反田、大崎、大井町各駅に職員を派遣し、帰宅困難者の状況などを把握していました。実際、それほど混乱している状態ではなく、未明に電車が動き出したタイミングでは、滞留されている方はほとんどいらっしゃらないという状況でした。区としては、一時滞在施設開設の準備だけはしていたのですが、実際には開設はしませんでした。
仮に帰宅困難者が大量に発生していた場合には、各駅に派遣した職員を中心に一時滞在施設などへの誘導を行う方針でした。後は、ホームページやSNS、情報発信をすることを検討しておりました」
今回の地震では(東京電力管内で250軒ほどが停電したが)大規模・広域停電もなく、インターネットなどの通信インフラも機能していたが、東日本大震災級の災害時にはネットへの接続障害も懸念される。前出の区の防災課担当者は語る。
「実際に現地に職員を派遣するというのは、そうした対策の意味もあります。また主要駅に関しては民間事業者とともに帰宅困難者対策協議会を立ち上げておりまして、協議会としての対策も行うよう進めています」
改めて確認したい「避難所」「一時滞在場所」の違い
自治体や事業者が混乱する帰宅困難者に対し、適切に「一時滞在施設」へ誘導を行わなければ、大きなトラブルを招く可能性がある。
例えば、帰宅困難者が「避難所」に向かってしまうトラブルが想定される。避難所は「開設自治体に住民票のある住民向けの収容先」であるため、域外から通勤している人や出張者、住所不定の人、ネットカフェ難民などは“基本的に対象外”(編集部注:自治体によって対応が異なる)だ。
大規模災害時には通信インフラに障害が出る可能性もあり、“いざという時”にネットで「一時滞在施設」を検索できない可能性もある。災害時には多くの人が精神的にパニックに陥っていることも多い。勤務先が所在する自治体の一時滞在施設がどこにあるのかなどは平常時に調べて手帳などに書き留めて、家族とも情報共有しておく必要があるだろう。
これまでも自治体設置の「避難所」と「一時滞在施設」が混同された結果、痛ましい事案が起こっている。当編集部では、災害時の帰宅困難者問題をこれまでたびたび触れているが、そうした事例のひとつとして2019年10月15日に掲載した記事『ホームレス受け入れ拒否で表面化…避難所、出張者・旅行者・ネカフェ難民は入れない?』を以下、再掲載する。
――以下、再掲載――

2019年12~13日、東日本を縦断した台風19号は日本列島に甚大な被害をもたらした。15日午後1時現在、全国47河川で堤防が決壊し、約8000棟が浸水。死者66人、行方不明15人、負傷212人の大惨事となっている。東京都内では世田谷区の東急線二子玉川駅付近で多摩川が堤防を越え、タワーマンションが浸水するなどの被害が発生。台風襲来当日には首都圏のJR私鉄各線が計画運休を実施し、多くの企業が営業を取りやめ、都市機能は休止した。
そんな中、ホームレスが台東区内の避難所に避難しようとしたところ、「住所不定」を理由に区職員に受け入れを拒否されたという報告がTwitter上で反響を呼んだ。ホームレスでなくとも、ネットカフェ難民など東京都内には住所不定の「住民」はたくさんいる。また住居地が県外で、東京に勤務先があったり、出張で遠方からきていたりする人や国内外からの旅行者も多い。
一般的に避難所は、当該自治体に住民票のある住民向けに開設されている。そのため、ホームレスでなくとも「部外者」は、せっかく逃げても「別の場所に移動してください」と言われる可能性があるのだ。では、もし自宅以外にいる時に、今回のような大災害に出くわした時、どこに避難すれば良いのか。
「住所がない」ので受け入れ拒否
13日付毎日新聞の朝刊は次のように報じた。
「台東区によると、台風19号の接近に伴って11日午後5時半以降、区内4カ所に避難所を開設。12日に区立忍岡小の避難所を訪れた2人に対し、『住所がない』という理由で受け入れを拒否した」(原文ママ、以下同)
しかも避難してきたホームレスは脳梗塞を患っていて、体調にも不安があった。結果として暴風が吹き始め、雨脚も強まっていたタイミングで外に放り出すことになった。
こうした対応に、東京都内でホームレスの自立支援などを行う認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長の大西連氏は、13日付のヤフーニュースの個人ページで「台東区のホームレスの人の避難所受け入れ拒否問題を考える」と題して記事を公開。次のように台東区の対応を批判した。
「今回は、実際に避難所におもむいた野宿の方がいて、その人たちを日常的に支援したり関わっていたりする人がいたので、明らかになりました。明らかになっていないだけで、こういった災害からの避難という文脈で、ほかの自治体で同様のことが起こっていない、とは言えません。
『住民じゃないと利用できない』などは言語道断ですし、どんな状況でも『いのち』に優劣はつけられません。避難にきた人を追い返して、その人が避難できずに被害をうけたらどうするのでしょうか。困難な状況にある人を支援しない公的機関などあっていいものなのでしょうか」
震災時の帰宅困難者515万人
東日本大震災時、東京都内の鉄道の運休や停電などの影響で発生した帰宅困難者は約515万人。交通渋滞などで完全に都市機能はマヒした。その教訓をもとに、都は2012年3月「東京都帰宅困難者対策条例」を制定。都内勤務の帰宅困難者のために、各事業所に対して従業員が待機するための食糧の備蓄や、一斉帰宅に伴う混乱を防ぐための「帰宅ルール」を定めることを求めた。
ここで定義されている帰宅困難者は「明確に帰る場所」があり、都内の事業者で雇用されている「従業員」であることを想定している。では、それにあたらない旅行者や出張中の人、そしてホームレスや住所・勤務先が不定のネットカフェ難民などはどうすればいいのか。
東京都総務局総合防災部防災管理課の担当者は次のように話す。
「東京都ではいわゆる行き場のない人が緊急避難できる『一時滞在場所』として都内各所の都立高や東京国際フォーラムなどの公共施設など計221カ所を準備しています。それらの場所は、都民であるか否かや住所の有無とかに限らず、誰でも避難可能です。広義の意味では、今回、利用を拒否されたホームレスやネットカフェなどで日雇い仕事をされている方々の利用も可能です」
ただ実施面では課題も残る。例えば駅や町中の防災無線などで的確な誘導がなされるとは限らず、基本的には自分でウェブページを調べて一時待機場所の開設を確認して行くことになる。震災や熊本地震、西日本豪雨など、これまでの大規模災害時にはネット回線や電話回線の輻輳が起こった。いざ、逃げようという時にスマホが使えないことは想定の範囲内として考えるべきだろう。スムーズに避難をするためには、あらかじめ「何かあった際にどこに逃げるか」を前もって知っておく必要がある。
「報道で、世田谷区では多摩川河川敷の路上生活者を避難所に誘導したという話もありました。ただ、避難所の運営は市区町村が原則として担いますが、実務面では自治会や住民自身による運営の側面が強いです。それぞれの避難所ごとに判断やルールが違うというのが実情だと思います」(前出の都担当者)
大槌町のトムとジェリー
東日本大震災の際、こんなことがあったのをご存知だろうか。
イルカ漁を細々と行っている岩手県大槌町には2011年3月11日、大津波が押し寄せた。津波は町役場を全壊させ町長や町幹部職員を含む住民計1286人が死亡した。そんな時、町には国際的な反捕鯨団体のシー・シェパードのメンバー6人が「イルカの保護のため」に訪れていたのだ。当時、現地を取材していた地元紙記者は次のように話す。
「シー・シェパードのメンバーはちょうど漁業者の行動を監視中だったそうです。さらに彼らを行動確認する警察の公安部の車両とともに大地震に遭遇しました。まるでアニメのトムとジェリーのように一緒に逃げたそうです。大津波が来るころには高台にいて、その後、漁船から漏れた重油などに引火し、町は大火災となりました。
彼らは被災住民の救助を手伝おうとしたものの果たせず、当日は車中泊し、警察に内陸の遠野市のホテルに行くよう言われましたが、徒歩で約40キロあったため現場で右往左往していたそうです。
そんな時に地元漁業関係者が『乗っけていってやるよ』と数少ない稼働可能な自動車とガソリンを提供。被災した別の商店主の運転でなんとか遠野市に逃れたとのことです。彼らは究極の帰宅困難者で、町の住民にしてみればよそ者中のよそ者です。でも、後でこの件に関わった住民に話を聞きましたが、『ああいうときはおだがい様。どこの誰かなんて関係ない』と話していました。結局、災害時はこういう助け合いができるかどうかなのだと思います」
当時のことを、このグループのリーダーのスコット・ウェスト氏は手記で、「この日、われわれに向けられた親切と寛容さを、書きつくすことはできない」「日本の人々は暖かくて親切だと、これまで以上に確信することになった」と振り返っている。
災害時にはいろいろなトラブルが発生する。中でも住民以外の「部外者」をどうするのかは大きな問題だ。ただでさえ、飲料水や食料の配分をどうするのかなどをめぐって、行政間、住民間、そして行政と住民間などさまざまな関係が険悪になる。ただ、どんな場所でも「犠牲者を出さない」ということが最も重要視されるべきなのは間違いない。
来年には東京五輪が開かれる。期間中は台風の季節にも重なり、今回のような風水害が起こる可能性は否定できない。東南海トラフ地震、首都直下型地震の発生も懸念されたままだ。防災インフラなどハード面の検証も当然だが、もしもの時、一人ひとりがどう動くのかをもう一度、確認したいものだ。
(文=編集部)