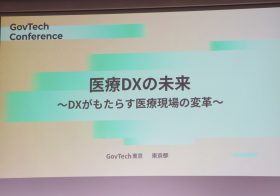塩野義コロナ飲み薬、3月に承認へ、病院・他企業も総力戦…第6波収束に極めて効果的
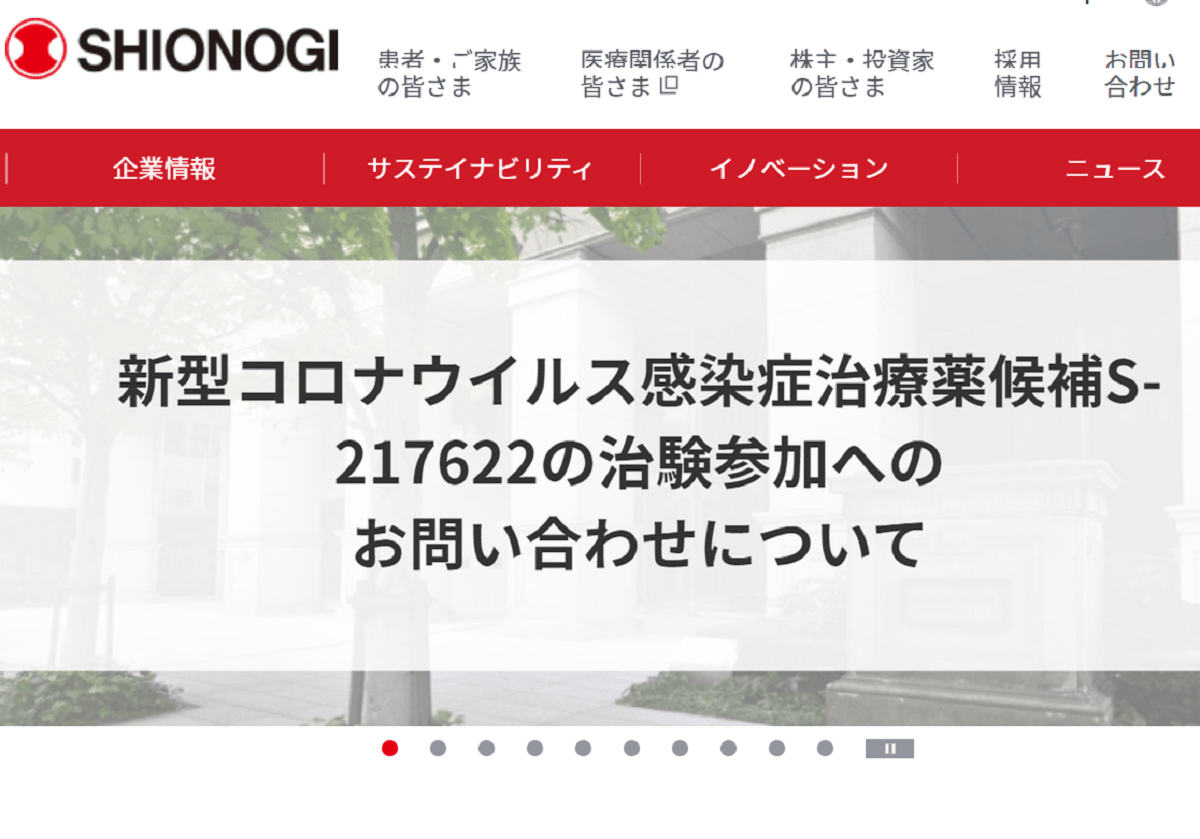
新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大の第6波で亡くなった人数は、今年に入ってから2月23日までに4000人を超え、デルタ株が広がった昨年夏の第5波を上回った。オミクロン株はデルタ株に比べて重症化するリスクは低いとされていたが、あまりにも感染者数が増加したことで死者数も急増している。
オミクロン株ではワクチンを打っていてもブレークスルー感染を起こしてしまうため、各地でクラスター感染が発生している。特徴的なのは、80代から90代の高齢の重症患者が多いことだ。高齢者の多くはコロナ肺炎ではなく、もともと罹っていた慢性疾患が悪化して重症化している。感染をきっかけに脱水や誤嚥性の肺炎などが起き、亡くなる方が多いという。寝たきりの状態の高齢者が感染して入院すると、食事や排泄などの介助、認知症などへの対応が必要となることから、医療逼迫を招いてしまっているのが現状だ。
世界に冠たる長寿大国である日本に必要なオミクロン対策は、寝たきり状態の高齢者などを重症化させないことが肝心であり、新型コロナの変異にも対応しやすいとされる飲み薬の処方が有効だ。
メルクとファイザーの飲み薬、処方進まず
感染拡大防止と社会活動の両立に向けた第6波からの出口戦略も議論されている。第1波の致死率は5.7%だったが、第6波で0.1%にまで低下した。0.1%という数字は季節性インフルエンザとほぼ同じだが、季節性インフルエンザにはタミフルなど手軽に飲める経口薬があるという安心感がある。
第6波対策としてブースター接種が進められているが、「切り札」として期待されていた飲み薬の活用が思うように進んでいない。その理由としては(1)飲み薬の入手が容易でないこと、(2)処方や効果が限られていることなどが挙げられる。
政府は米メルク社から160万人分の飲み薬の供給を受けることで合意しているが、入院・死亡の抑制効果が3割と低く、妊婦には処方できない。直近の投与実績は約7万人にとどまっている。米ファイザーの飲み薬についても200万人分の供給を受けることになっているが、納入済みの4万人分に加え、月内に追加で入荷するのは8万5000人分にすぎない。ファイザー製の重症化予防効果は9割と高いが、対象は大きく限られる。高血圧の薬など併用できない薬が約40種類あることから、実際の投与は約300人とわずかだ。両社には世界中から注文が殺到しており、予定通りの数量の飲み薬が確保できるという保証もない。
飲み薬は発症から5日以内に服用する必要があるが、自宅療養者への配送に協力する薬局は全国の約6万施設のうち3割程度にとどまっており、供給体制も十分とはいえない。
塩野義製薬、最終段階の治験
飲み薬については塩野義製薬も最終段階の治験を実施しているが、「海外製よりも期待ができる」との評価が高まってきている。海外製が重症化しやすい感染者を対象に薬を開発したのに対し、塩野義は「対象者の重症化リスクとは関係なく、症状がいかに改善されるか」という観点で薬の開発を行っている。12歳以上であれば重症化リスクのあるなしに関係なく処方できるとしている。
塩野義は2月7日、治験の初期データを公表した。対象人数が少ない(69人)が、投与群の症状は偽薬群に比べて早期に改善する傾向が確認された。その効果は60~80%と高い。ファイザー製の治験は2000人、メルク製が1400人と比べると規模ははるかに小さいが、データのほとんどが日本人であることは強みだ。塩野義は7月までに2000人規模の治験を行う予定だ。
国内の新型コロナの感染者が昨年末に激減したことで治験が思うように進んでいなかった塩野義だが、ここに来て治験が急ピッチで進んだ。オミクロン型の感染者が急増するなか、治験の進行を速めるため、塩野義だけでなく病院や支援企業も奔走したからだ。総力戦が功を奏し、500人規模の治験で有効な結果が改めて確認できたとして、塩野義は25日、厚生労働省に製造販売承認の申請を行った。通常、国内の薬の治験には3年以上かかるとされているが、塩野義の場合は、治験入りから申請までの期間は約7カ月、国内では類を見ないスピード開発となる。
こうした塩野義の動きに政府も前向きだ。岸田総理は衆議院予算委員会の場で「国産の経口治療薬の開発は大変重要だ。条件付き早期承認制度の適用を検討する」と述べた。この制度は最終段階の治験が完了する前の実用化を認める仕組みだが、本来は患者が極めて少なく大規模治験が難しい希少がんなどの治療薬を実用化させるためのものだ。多くの人が服用する薬を想定していないことから、塩野義の飲み薬にこの制度を適用することに慎重な専門家は少なくない。だが現在は非常時だ。この制度を活用して3月中に塩野義の飲み薬を早期承認して実用化すべきだ。
塩野義も早期承認を見込んですでに生産を開始しており、年度内に100万人分を供給できるとしている。そうなれば、診療所で高齢者などに幅広く処方することができ、重症化を大幅に減らせることができる。医療体制の負荷は格段に軽くなるだろう。
国産飲み薬を早期に実現することで高齢者などの重症化を抑制できれば、「第6波」を早期に乗り切ることができると筆者は確信している。
(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)