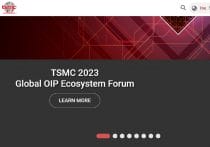TSMC、なぜ四半期の純利益1兆円?「下請けメーカーは低収益」の常識を覆す

世界最大の半導体受託製造会社(ファウンドリ)である台湾積体電路製造(TSMC)の好業績ぶりが凄まじい。2024年1〜3月期決算は前年同期比16.5%増の5926億台湾ドル(約2.6兆円)、純利益は同8.9%増の2254億台湾ドル(約1兆円)でともに同四半期としては過去最高を更新するなど、勢いが衰える気配はない。製造業ながら売上高営業利益率は40%を超える高水準を維持しているが、TSMCのように自社ブランド製品を手掛けず、他社メーカーから製造を受託する、いわゆる「下請けメーカー」は、利幅が少なく低利益率であるというのが一般的であった。なぜTSMCはこの常識を覆し、時価総額世界トップ10に入る巨大な高収益企業になれたのか。その経営の秘密について専門家の見解を交えて追ってみた。
TSMCは、米テキサス・インスツルメンツ(TI)の技術者として副社長にまで上り詰めた張忠謀(モリス・チャン)氏が1987年に台湾で創業。当時は珍しかった半導体のファウンドリというビジネスに目を付け、米国のアップルやAMD(アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)、インテル、クアルコムなどから大口の受注を獲得して飛躍的に成長。現在では生成AI向け半導体に強いエヌビディアなども大口顧客に持ち、4月の単月の売上高(速報値)は前年同月比59.6%増の2360億台湾ドル(約1.1兆円)にも上る。時価総額は7882億米ドルに達し、世界ランキングで10位となっている(5月15日現在)。
自社ブランドにこだわらない
国際技術ジャーナリストで「News & Chips」編集長の津田建二氏はいう。
「1980年代後半から90年代にかけ、アメリカのシリコンバレーを中心にファブレスゆえに投資を集めることに苦戦するスタートアップが多く誕生し、インテルなどに頼んでも大手は生産ラインで自社製品の製造を優先するので後回しにされてしまうという状況があった。そこに目をつけて半導体のファウンドリビジネスに特化したというのが、成功に至ったもっとも大きな要因だろう。
当時は日本でも米国でも半導体メーカーは自社ブランド製品の製造にこだわっており、ファウンドリを手掛けるという発想が生まれなかった。それに対して自社ブランドにこだわらなかったことが結果的に強みになったわけだが、多くの企業から同時に受注することで製造ラインを常にフル稼働させることができた。一方、日本の半導体メーカーは自社ブランド製品しか製造せず、生産ラインに余剰が生まれて赤字に陥った。台湾にはTSMC以外にも鴻海精密工業(ホンハイ)、コンペック、エイサー、UMCなどの世界的な製造受託企業が多いが、『儲かれば自社ブランドにはこだわらない』という台湾企業のマインドが企業を成功に導いている」
身の丈に合った堅実な経営も強さの要因だという。
「かつて日本の半導体メーカーが世界で高いシェアを持っていた頃、TSMCはあえてコストがかかる最先端の技術は追わずに、少し遅れた世代のプロセッサの製造に注力していた。だがその後、徐々に開発能力が高まったことで、いつの間にか日本勢を追い抜いてしまった。今では半導体製造の技術力は韓国サムスン電子より高いと評価されており、ファブレス企業側も『まずTSMCに依頼してみて、断られたらサムスンに依頼する』という動きになっている。また、昔から無理に銀行からの借り入れを増やすようなことはせず、無駄な支出も行わず、高い自己資本比率を維持しており、非常に経営がしっかりしている」(同)
開発段階から利益を優先
注目すべきはその高い利益率だ。一般的に自社ブランドを前面に打ち出さずに他社メーカーから製造を受託する企業は利益率が低く、あくまで製造業では“黒子役”のため売上的にも中小規模にとどまるとされてきた。なぜTSMCはこの常識を破ることに成功したのか。
「開発段階で技術者が考える『高い品質』を実現するためにはどうすればよいかを優先しがちな日本のメーカーとは異なり、TSMCは開発段階から『どのようにつくれば利益が出るか』を大前提に考えながら進めていく。米国企業もこの傾向が強く、TSMCは米国式の経営を取り入れているといえる。また、とにかく技術者をはじめ社員は猛烈に働き、残業もいとわないという社風があるが、その分、給料はすごく高く、日本企業の数倍くらいだろう」
自動車メーカー関係者はいう。
「日本の下請けメーカーは最終製品メーカーなど発注企業の言い値で受注してしまうケースも珍しくなく、結果的に採算を無視した価格で大量につくらされる羽目になる。現在、スマホや半導体の領域はTSMCなしでは成立しなくなっており、TSMCは発注元メーカーとの関係が対等か、もしくはTSMCのほうが上なので、発注元からの値引き圧力を回避できるのも大きな強みだろう」
(文=Business Journal編集部、協力=津田建二/国際技術ジャーナリスト)