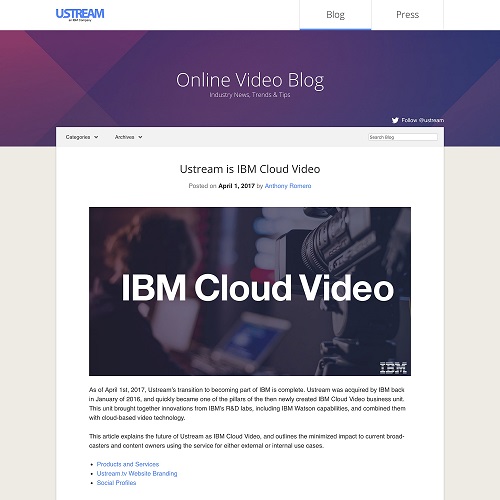 Ustreamが「IBM Cloud Video」へ統合されることをアナウンスするリリースページ。すでにこのページのデザインも変更されている。
Ustreamが「IBM Cloud Video」へ統合されることをアナウンスするリリースページ。すでにこのページのデザインも変更されている。ネットライブ配信の先駆けとなった「Ustream(ユーストリーム)」ブランドが消滅する。なぜUstreamは勝てなかったのか、ネットライブ配信の専門家・ノダタケオ氏に寄稿をお願いした(ITジャーナリスト・三上洋)。
5日、Twitterの「日本のトレンド」に「Ustream」というキーワードが約8時間にわたり登場し続けました。2016年1月に米国法人Ustreamが買収され、IBMの傘下へ移ったのちもブランド名として継続展開されていたライブ配信の代名詞Ustreamが、「IBM Cloud Video」へ統合されるというトピックに、インターネット上で大きな反応が示されたことからでした。
現在のサービスは「一般向け大規模配信」「クラウドでのBtoB配信」「CDNとしての利用」として継承されますが、Ustreamブランドは消滅。ウェブサイト「Ustream.tv」上の表記も順次変更されるとみられます。
Ustreamは07年に生まれたインターネット上の生放送(ライブ配信)のサービス。09年末にソフトバンクが出資を決め、10年にアジア圏の展開を目指す日本法人Ustream Asiaがスタートしました。
Ustreamが日本におけるライブ配信サービスの代表格となったきっかけは11年。東日本大震災の発災で、停電によりテレビ局やラジオ局が伝える津波の情報を得ることができない人たちへ向けて、いち早く「サイマル配信(放送と同じ内容のものがネット上でも配信)」をすることで、被災をした人たちの「貴重な情報源」となりました。
テレビやラジオの「メディア」とUstreamの「ライブ配信サービス」による、超法規的で画期的なこの連携は、過去にも、これからの未来においてももう起きることのない歴史的な出来事であったといっても過言ではないと思います。これをきっかけに、現在の「放送と通信の融合」の推進にもつながっていきます。
さらに、この歴史的な出来事は、これまでのテレビやラジオの電波ではなく、ネットを通じてリアルタイムに映像音声を伝送する「ライブ配信」という仕組みの認知度を大きく上げました。
「電波」と「ネット」のカタチの違いはあれど、テレビ局やラジオ局と同じように、一般の人でも自由に発信したい情報(コンテンツ)をありのままにリアルタイムで映像音声を送り伝えることができる「即時性」と、テレビやラジオにはないチャット機能による「コミュニケーション性」があるライブ配信に魅力を感じ、「配信者」というクリエーターが生まれていきます。
放送時間の枠や電波が届く範囲に限りがない、そんなUstreamというライブ配信サービスの情報を伝える新しいカタチに、大きく惹かれた人が増えていったのです。
Ustreamブランドが消えた原因・理由
しかし、「ライブ配信の革命児」「時代の寵児」とも呼ばれたUstreamは、15年12月に日本法人Ustream Asiaの解散を発表。そして16年1月には、米国法人UstreamもIBMに買収されました。
Ustreamは、企業やアーティストが提供する、同時接続10万規模の視聴者を集めるコンテンツであっても、膨大なトラフィックを適切に捌き、高画質・高音質で配信ができる強固なインフラをもつサービスでした。当時のライバル関係にあったニコニコ生放送(ニコ生)やツイキャスよりも圧倒的な優位性がありました。それは、現在においても変わりません。
そんな強固なインフラは、ビジネスサービス「IBM Cloud Video」を展開するIBMにとっても魅力的な資源であったはずです。しかし、IBMの傘下に入った「Ustream」と「IBM Cloud Video」というブランドが共存することは戦略的にも合わなかったのでしょう。おそらく、米国法人UstreamがIBMに買収をされた時点で、Ustreamのブランドは消える運命であったのかもしれません。
今後のライブ配信サービスが生き残り、ビジネスとして成功するためのカギ
Ustreamがライブ配信サービスの世界から消えた今、残ったライブ配信サービスが今後も生き残り、ビジネスとして成功するためのカギはなんでしょうか。端的にいうと「賑わい」をつくることだと考えます。
もちろん、ライブ配信サービスに限らず、ネット上で展開されるサービスも「賑わい」がないと成立しませんが、その「賑わい」の基準はサービスによってさまざまです。
たとえば、インターネットテレビ局「AbemaTV」や「Netflix」「Hulu」「dTV」「Amazonプライム・ビデオ」のような動画配信サービスでは、
・アプリDL数の多さ
・ユーザー登録者数の多さ
などでサービスの賑わいを表します。
一方、ライブ配信サービスの「賑わい」は
・リアルタイムに視聴してくれる「視聴者数」の多さ
・いままさにライブ配信されている「コンテンツ数」の多さ
・リアルタイムに展開されているコメント(コミュニケーション)の盛り上がり度
の3つです。つまり、一般の人でも手軽にリアルタイムで動画中継して情報(コンテンツ)を発信することができるライブ配信というサービスは、「いかにたくさんの人が配信をし、いかにたくさんの人が視聴し、そして、配信者と視聴者・視聴者同士のコミュニケーションが生まれるか」がカギとなります。「アプリDL数の多さ」「ユーザー登録者数の多さ」だけでは、ライブ配信サービスの「賑わい」の指標とするのは難しいのです。
ライブ配信サービスへ求める3要件
ライブ配信サービスの賑わいのつくりかたは、動画共有サービス「YouTube」と似ている部分があるかもしれません。
YouTubeは今や圧倒的に絶大な人気を誇る動画共有サービスです。YouTube上で独自に制作した動画を継続的に公開する人物や集団を指す名称として、「YouTuber」という言葉があります(Wikipediaより)。直近ではインターネットテレビ事業「YouTube TV」が米国で始まりますが、そもそも、動画共有サービス「YouTube」としての根幹はたくさんのコンテンツを用意し、たくさんの視聴者を呼び込むために、「クリエーターを育成し、コンテンツを生んでもらう」ことに注力しています。
つまり、多種多様なコンテンツがなければ、視聴者は来ない。だから、多彩なコンテンツを用意するために、クリエーター育成にYouTubeは力を入れています。
それは、ライブ配信サービスも同じ。ライブ配信サービスは、まず配信者を育成し、支援(応援)をしなければなりません。配信者というクリエーターがいなければ、ライブ配信サービスの賑わいは生まれません。
その配信者がライブ配信サービスへ求める要件は3つです。
・たくさんの人に視聴してもらえるサービスであること
・ライブ配信しやすい(利便性のある)サービスであること
・配信者(クリエーター)がマネタイズできること
16年からライブ配信というジャンルは黎明期から全盛期へ入りました。16年は15年に比べ、倍以上のライブ配信サービスが生まれました。
黎明期は「たくさんの人に視聴してもらえる」「ライブ配信しやすい(利便性のある)」ことがサービスへ求められてきましたが、全盛期に入り、リアルタイムに情報が発信できるという魅力は当たり前のものとなって、その魅力だけでクリエーターをサービスに引き止め続けることはできません。
YouTubeにおいても、クリエーターの制作モチベーションを維持するためのひとつの手段として、広告収入の一部をクリエーターへ還元する仕組みがあるように、ライブ配信サービスにおいても、特別な人だけが優遇されるカタチではなく、無理のない、公平なかたちで配信者へ還元されるマネタイズの仕組みも求められています。
ただ、サービスとサービスの競争が激化していることから、後発のライブ配信サービスは、これまでのライブ配信サービスで著名な人気のある配信者に対して、契約を結び、インセンティブを払うことによる配信者の取り合いが始まっています。
しかし、そのかたちは長い目で見ると、適切なものではないと思うのです。インセンティブを渡すためのいわゆる宣伝広告費がカットされる方向になれば、配信者は一気にそのサービスから離れてしまいます。配信者からみれば、上の3要件を満たすことができれば「サービスはどこでもいい」と実際に感じているクリエーターは多いのです。
(文=三上洋/ITジャーナリスト、ノダタケオ/ライブメディアクリエイター)
※後編へ続く





















