ポジティブ視点の考察で企業活動を応援、企業とともに歩む「共創型メディア」/Business Journal
クラウドファンディングの「社会的責任」と「本当の支援」とは?
自称ニートがネットで”生活費集め”はOKか!?(後編)
また、 『評価経済時代の個を考える』という6月18日の Ustreamで放送された企画で、東浩紀氏はstudygiftの失敗に触れ、「この人に才能があるから、お金を集めようというのだけが正義ではない。僕個人は能力のある人が好きだけど、社会全体を考えると、それは正義にはならない」と発言した。
そして、「奨学金はリスクをテイクした者に金を与えるものなのか」「自分の力で未来を切り開けない奴をフォローするというのがホントの奨学金じゃないですか」と疑問を投げかけた。そこで家入氏は、「考えなさ過ぎた。僕は病んでたのかもしれない。一番はしょっちゃいけない道徳をはしょっちゃった」と反省の弁を述べていた。
家入氏率いる「Liverty」では、「U2plus」との共同プロジェクト「うつっぽ」も「公開を急いだ結果として、“うつっぽ”は格好のスパムメールツールと化し、多くの方に大変ご迷惑をおかけしました」という理由で閉鎖に至っている【編註:「うつっぽ」は、うつなど、メンタル的な問題を抱える周囲の人間に匿名でメールを送り、診断を勧めるというもの】。
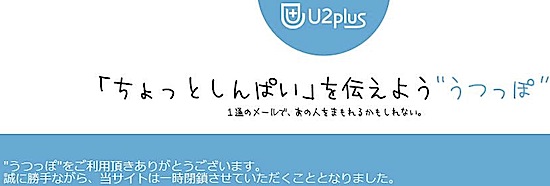 休止に追い込まれた「うつっぽ」。(サイト「うつっぽ」より)
休止に追い込まれた「うつっぽ」。(サイト「うつっぽ」より)そのような拙速な試みの代償は、すでにネット上に不信感となって表れている。
例えば、CAMPFIREで支援金を募っているプロジェクト「airpit」では、ユーザーから「CAMPFIREは、家入さんがつくったプラットフォームなので、studygiftのように寄付の行方やその後の対応がうやむやになるのではないか」という声が寄せられた。
悪用を見抜くのは運営者側の責任
しかし、クラウドファンディングに寄せられるプロジェクト内容の信憑性を確認し、社会的に容認できないものをフィルタリングするかどうかは、すでにハイパーインターネッツ1社に課せられた問題ではない。
RANKING
UPDATE:17:30






