当事者を茶化すマネは本当にやめたほうがいい 小6同級生殺害犯・ネバダたん人気の意味
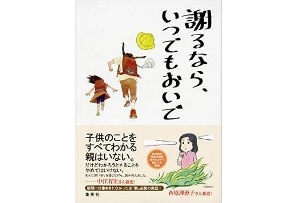 『謝るなら、いつでもおいで』(集英社/川名壮志著)
『謝るなら、いつでもおいで』(集英社/川名壮志著)
『謝るなら、いつでもおいで』(川名壮志/集英社)
最近こうして書評などをエラソーに書く機会が増えてくると何がいいかって、良書を色々と紹介してもらえるようになることだ。「何を書こうかなぁ……」なんて一つ泣き言を言えば、「○○が面白いよ」「○○だったらあなたに合うんじゃないかな」と言われる。
そんな中の一冊が『謝るなら、いつでもおいで』。2014年3月に発売された本だが、昨今少年犯罪に関心を持った人が「これは名著」と推薦してくれたのである。本書は04年6月に発生した「佐世保小6女児同級生殺害事件」を題材にしたノンフィクションである。お昼休みに女児が同級生の女児を「学習ルーム」と呼ばれる、6年生の教室から離れた部屋に連れて行き、カーテンを閉めて目隠しをした上で首をカッターナイフで切り、殺害した事件だ。
著者の川名氏は、被害者・御手洗怜美さんの父で、当時毎日新聞佐世保支局長だった御手洗恭二氏の部下である。事件発生当時は入社4年目。事件発生直後の御手洗氏の様子から、加害女児の態度、怜美さんと加害女児の関係、そして著者の葛藤が描かれる。
事件が一体なぜ発生したのかは、加害女児の心までは読み切れないため断定は避けているが、事実に基づき、多くの証言を引き出し、事件のあらましを解説する。これが「第一部」で、「第二部」は御手洗氏、女児の父、そして事件当時中学2年生だった怜美さんの兄による振り返りを元にし、遺族と家族の心情が綴られる。
事件直後から川名氏は突然の出来事に対し、大いに動揺するも、とにかく仕事をし続けなければ自分を保てないとばかりに、事件の取材をひたすら続ける。普段は支局長以下2名の記者と事務担当の女性1人というこぢんまりとした世帯に突如20人もの応援記者がやってきて、同僚に関する事件を高揚しながら追い続ける。ここまでの大事件であるがゆえに、御手洗氏への配慮はあるものの、これは「仕事」だと各人が認識した上での高揚だ。
「当事者意識」をめぐる逡巡
御手洗氏は事件の発生した夜に会見を行ったが、これが当時多くの人を仰天させた。通常遺族が当日に会見を開くことは考えられないからだ。だが、御手洗氏はこう述べた。
「話したくないと思ったが、自分も逆の立場だったらお願いするだろう。短い時間であっても取材に答えなければならないと思った」
つまり、記者というものは普段は事件が発生したら家族や遺族、友人らをそれこそ自宅まで押しかけて取材をする。同業者の気持ちがわかるからこそ、自分が常にやっていたことは因果応報、やられても仕方ない――。そういった文脈で御手洗氏は取材を受けたのだろう。その一方、本書では御手洗氏のこの会見が、怜美さんの遺体搬送からマスコミの目をそらす目的もあったことを明らかにする。
私が本書で最も重要だと感じたのが、「当事者意識」である。川名氏は、上司の娘であり、しかもよく一緒に食事をしていた怜美さんにかかわる記事を書くことへの罪悪感にさいなまれる。記事の一つひとつが御手洗氏を傷つけてしまうのでは――。こう逡巡もする。
御手洗氏にしても、自分が遺族という「当事者」になったからこそ新聞記者という職業の業の深さを感じ「遺族が取材にさらされるつらさは、逆に僕自身が求めてきた側だから、よくわかる。大変だということがね」と振り返る。
その一方、加害女児については、精神鑑定も含めたプロによる調査結果をもってしても「何を考えているのかよくわからない」というのが、川名氏の感想だ。当時彼女に当事者意識はあまりなかったとも取れる。
「当事者意識」は得られるのか
「当事者意識が大事」と述べたが、登場人物の「当事者意識」だけのことを言っているのではない。私は、外野による当事者意識といったものへの関心が本書を読むことにより高まった。当時、インターネット上では妙な高揚感があった。それは、ネットに流出したクラスの集合写真に写った女児の容姿をめぐってのものだった。
「史上最も可愛い殺人者」とまで言われるようになる女児は、小柄でダボッとしたズボンとブカブカのパーカーを着てピースサインをしている。パーカーの胸には「NEVADA」と書かれてある。アメリカのネバダ州にあるネバダ大学のことだと推察されるが、この写真が流出して以降、女児がネットの一部で大人気となったのだ。「NEVADAたん」「ネバダたん」といった愛称までつけられ、彼女をモチーフとしたイラストやコスプレも登場するほどだった。
外野からすると、当事者がどれだけ苦悩していようが、最も重要なのは「NEVADAたんはかわいい」ということである。遺族に感情移入をしろ、とは言わないものの、さすがにあの時のネットの盛り上がりを思い出すとともに、当事者が何を考え、どう動いていたかを本書で知ってしまうと、当時の「祭り」に乗ってしまった自分を恥じるしかない。
その一方で結局、「当事者意識」というものは、自分がその当事者にならない限りは得られないのかもしれない。東日本大震災(11年)関連の死者は約2万人で、阪神・淡路大震災(1995年)は約6000人。新潟県中越地震(04年)は68人。もちろん被害者の人数はまるで違うし原発事故がかかわったものの、この3つの地震を比較すると明らかに東日本大震災への注目度が高い。それこそプロ野球を見ても、「がんばろう!日本」のシールを各チームは今でも貼っている。阪神大震災時に「がんばろうKOBE」を謳ったのはオリックスのみだった。
メディアの扱いも東日本大震災が圧倒的に多く、「震災後」というと今や東日本大震災を指す言葉になっている。一つの理由は、情報発信の中核たる東京のメディアが、あの時は明らかに当事者になったからというのもあるだろう。当日、帰宅難民になり、数日間はスーパーやコンビニエンスストアからは食料が消え、放射能に怯えるあの恐怖。あれが当事者意識を呼び起こしたと考える。
東京在住の私は、阪神・淡路大震災の時は正直あまり被害への実感がなかった。一方、東日本大震災の直後、あまりにも陰鬱な東京に嫌気が差し、大阪に行ったら「そんなに揺れたん?」と言われた。彼らには、あまり実感がなかったようだ。ましてやスマトラ島沖地震やニュージーランド、四川の地震に対し、どれだけ当事者意識を持てるか。さらに言うと、現在も仮設住宅暮らしをしている人や原発事故のために避難生活している人のことを、「あの数日」だけ当事者になった東京の我々は慮ることができるのか。
身近な被害者がいない限り、それはなかなか難しいことだろう。
当事者と、どう付き合っていくのか
やや支離滅裂になってきたが、「当事者の気持ちを考えろ」と言いたいわけでもないし、「当事者と同じだけの苦悩を味わえ」と言いたいわけでもない。ただ、少なくとも当事者を茶化すようなマネはあまりしないほうがいいのでは、と「NEVADA祭り」を振り返り、思い知らされたのである。
そして、少年犯罪が発生した際、必ず厳罰化を求める声がネット(外野)からは出てくる。光市の母子殺害事件では当時18歳の少年が加害者だったが、遺族の男性が「死刑にならないで刑務所から出てくるのであれば私が殺す」といった趣旨の発言をした。これに対してはネット上で賛同の声が多数出た。
光市の件は明らかに当事者の発言である。だが、最高裁により死刑判決が出たところで男性は「この判決に勝者なんていない。犯罪が起こった時点で、みんな敗者だと思う」と述べた。これも時間を経た後の当事者の重い発言である。
本書の第二部には、当事者による少年法のあり方や加害女児への意見が記されている。
「少年法の厳罰化とか言われているけど、それはねぇ、僕にはわかんないんだよね。少なくとも、厳罰化が、これから起こりうる事件の抑止力になるかはわかんない」(御手洗氏)
「あの子を憎んでも仕方がない。何というか、こっちが疲れるだけですから。親父さんも軽々しく復讐とかは言わないですよね。(中略)結局、僕、あの子に同じ社会で生きていてほしいと思っていますから。僕がいるところできちんと生きろ、と」(怜美さんの兄)
慰めの言葉を述べた時に「お前なんかに私の気持ちがわかるか」と当事者から言われるのは心外ながらも、少なくともどんな距離感でどんな倫理観をもって当事者と付き合っていくか、当事者について言及するかを考えさせられる書である。
それにしても毎日新聞社は川名氏もそうだが、『捏造の科学者 STAP細胞事件』(文藝春秋)の須田桃子記者のような優れたノンフィクションの書き手による作品を、なぜみすみすライバル社から出版させるのか。毎日新聞出版という関連会社子会社があるというのに、実にもったいない話である。もちろん集英社や文藝春秋から出したほうが販売が強い、印税がもらえる、という著者の目論見もあるだろうが、記者個人が書籍を出すことへの社内からの妙なやっかみなどが理由で他社から出しているのであれば、実にもったいないことである。
各新聞社はノンフィクションの社内コンテスト(大賞賞金500万円)でもやり、自社の関連会社から出版させ、印税もすべて著者に渡すといったことをしてもいいんじゃないの? 当事者じゃないから勝手なこと言うけど。
(文=中川淳一郎/編集者)




















