「再婚禁止と夫婦別姓規定」最高裁判決に注目集まる 家イデオロギーに固執してきた永田町の「非常識」
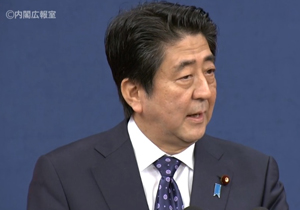 「首相官邸HP」より
「首相官邸HP」より民法の、女性に対してのみ定められた離婚後6カ月の再婚禁止規定と夫婦同姓を定めた規定について、それぞれ憲法に違反するかどうかが問われている2つの訴訟で、最高裁判所大法廷が当事者から意見を聞く弁論が行われた。
法改正への壁となった“「家」イデオロギー”への郷愁
いずれの規定も、明治時代に定められたものが、戦後もずっと維持されてきたもので、時代にそぐわないといわれて久しい。
確かに1世紀以上も前には、新たに生まれてくる子どもの父親を特定するために、女性の再婚禁止期間を設ける規定にも意味があっただろう。しかし、今では必要があればDNA鑑定を行えばよく、合理的理由はまったく失われている。
姓に関しては、法律上は夫の姓でも妻の姓でもよいことになっているが、慣習的に女性が姓を変えることが一般的とされており、結婚したカップルの96%が夫の姓を名乗っている。それによって自分のアイデンティティが損なわれると感じる女性もおり、働く女性が姓の変更で不利益を受けるなどの問題も指摘されている。世界に目を転じても、夫婦同姓を法律で義務づけている国は、もはや極めて少数派だ。
これら化石のような規定は、司法判断に任せておくのではなく、とうに政治が是正しておかなければならなかったはずだ。何度も機会はあったのに、今まで持ち越してしまったのは、日本の政治家、とりわけ自民党の国会議員の中に、明治民法が形づくった“「家」イデオロギー”に対する郷愁が根強いからだろう。
どちらの訴訟も、原告は、民法の規定が憲法違反であると同時に、国際的な条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)にも違反していると主張している。実は、今年は日本がこの条約を批准して、ちょうど30年目になる。
条約が、日本を含む130カ国の賛成で採択されたのは、1979年の国連総会。翌年、日本政府を代表して署名をしたのは、日本で初めての女性大使だった高橋展子デンマーク大使である。
批准が5年後の1985年になったのは、それまでの間に国内法の整備が必要だったからだ。中でも最も注目されたのは、男女雇用機会均等法の制定だった。
それまでの日本では、企業が男性のみを募集したり採用することが可能だった。女性はあくまで「職場の花」で、補助的な役割しか与えられず、結婚と同時に退職を迫ったり、女性は男性より若くして退職しなければならない若年定年制をとっている企業も多かった。女性は25歳を定年としていた会社まであったほどである。
差別的待遇に対して女性側から訴訟が起こされ、司法が「女性であることを理由とした不当な差別的取扱い」と認定した判決も相次いだ。しかし、それは被告となった個々の企業の問題とされ、すべての企業に是正を促す効果はなかった。
このため、均等法制定への女性達の期待は高まったが、一方、財界からの抵抗も強かった。結局、85年に制定された法律では、企業に対する罰則はなく、雇用機会の平等は「努力義務」にとどまった。











