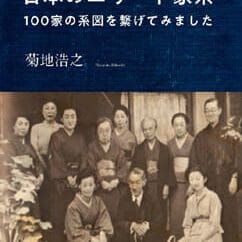三菱商事、三井物産を華麗に逆転す…戦前の覇者は、なぜ“財閥再編”に失敗したのか?

戦前の覇者・三井物産
明治初年、「社長」といえば、三井物産もしくは日本郵船の社長を指した――。
そういった伝説があるくらい、戦前の三井物産は圧倒的な存在感を放っていた。もとは、明治の元勲・井上馨が下野した1874年に興した貿易会社であったが、その後すぐに井上は政官界に復帰。1876年に三井によって買収され、三井物産会社となった。
三井物産の事実上の初代社長・益田孝は、もともとは幕臣で維新後に大蔵省に入り、井上の部下だったのだが、井上の下野に従って退官。三井物産の経営を任された。
益田はとにかくアタマがいい、というかアイデアマンで、何もないところからどんどんビジネスを創り上げていった。戦前日本の製造業で花形といえば紡績業だったが、益田はその将来性にいち早く着目し、原料の綿花や紡績機械の輸入、そして加工品の輸出を担い、1900年代には三井物産を、わが国貿易額の2割強を占めるほどの超優良企業へと成長させた。
その経営手法は、すぐれた人材を採用して、大胆に権限譲渡し、賞罰を徹底させるやり方だった。益田は商才あふれる人材を抜擢し、儲かるものには積極的に手を出して次々と子会社を設立していった。
・1918年に大正海上火災保険(現・三井住友海上火災保険)を設立。
・1920年に棉花部を分離して東洋棉花(トーメンを経て豊田通商に吸収合併)を設立。
・1925年に三機工業を設立。
・1926年に海外技術を輸入して東洋レーヨン(現・東レ)を設立。
・1937年に造船部を分離して玉造船所(三井造船、三井E&Sホールディングス)を設立。
・1942年に船舶部を分離して、三井船舶(現・商船三井)を設立。
三井物産は三井財閥の一部門というよりは、コンツェルンの親会社のようであった。
そんなこともあってか、第二次世界大戦後の財閥解体では、三菱商事とともに過酷な解散命令を受けてしまった。
物産・商事の解散命令
三井物産と三菱商事に対する解散命令は、ただ「解散しろ」というものではない。細かい、非常に細かい命令だった。その内容は以下の通りである。
・会社解散および清算の即時開始。
・許可なくして商取引や資産の譲渡を禁止。
・この覚書の日付以前10年の間に、役員・顧問・在内外支店支配人または部長であった者が集合して新たな会社をつくることを禁止。また、同一会社にこれらの人々の2人以上が雇用されることを禁止。
・これら役職員以外でも、100名以上が同一会社に雇用されることを禁止。
・今後いかなる会社も、三井物産、三菱商事の商号ならびに類似の商号を用いることを禁止。
・すべての帳簿および記録の維持。
この解散命令を受けても、三井物産社員は前向きだった。仲のよい社員が廊下ですれ違うと、声を掛け合って新たな会社設立を模索したという。かれらは何もないところからビジネスを生み出していった猛者(もさ)たちである。新たな会社・新たなビジネスを立ち上げることくらい、なんでもなかったのである。
三菱では作った物を売るために三菱商事が存在する、三井では三井物産が物を売るために子会社を作っていく
一方の三菱商事社員は悲嘆に暮れていたという。
三菱商事は1918年に三菱合資会社(三菱財閥の本社)の営業部を分離して設立された。もともとは売炭(ばいたん)部といって、鉱山部門(三菱鉱業。現・三菱マテリアル)の石炭を販売するための組織だった。
三井財閥にも鉱山部門(三井鉱山。現・日本コークス工業)があるが、これは政府所管の三池炭鉱を民間に払い下げる際に、三井物産が偽名を使って競り落としたものだ。かつて、所轄の大臣である伊藤博文が、同じ長州出身の井上馨が設立した三井物産に石炭販売を任せたことに端を発し、三井物産にとってドル箱的な存在だったため、どうしても競り落としたかったのだという。
こう書いていくと、三井と三菱では鉱山部門と販売部門が主従逆転していることがわかる。三菱では石炭を販売するために三菱商事を設立し、三井では三井物産が石炭を販売するために三井鉱山を買収した。
すべてが万事、そんな感じだった。三菱では作った物を売るために三菱商事があり、三井では三井物産が物を売るために子会社を作っていた。
そのため三菱商事では、解散によって三菱財閥・三菱グループと切り離されることを嫌った。解散命令を受けて、三井物産では人の好き嫌いで仲間を集め、「新会社」を創設していったが、三菱商事は将来の再統合を念頭に置いて、部課ごとに「新会社」を設置していった。まさに「人の三井」「組織の三菱」の違いである。
再統合で遅れた三井物産
1952年にサンフランシスコ講和条約が発効し、日本が占領から解かれると、強制的に解体された財閥が復活・再結集を遂げていく。三井物産・三菱商事の解散命令の制約も解け、三菱商事は早速再結集に動いた。百数十社に分かれた「新会社」が1953年には3社に統合され、これに三菱商事の商号を保全していた「新会社」を加えた4社が1954年に合併。新生・三菱商事が大合同を遂げた。
これに対し、三井物産では商号を保全していた「新会社」と、実力的には一番の「新会社」が合併条件の駆け引きで再統合が遅れに遅れ、5年後の1959年にやっと大合同を果たした。さすがは「人の三井」というべきか、合併後も人事抗争が続いたという。
両者の違いは、OBの関与にあった。三菱グループでは、戦前の財閥本社OBが大局的な見地から現役世代にアドバイスしていた。最後の4社合併で、現役世代は業績の悪い「新会社」を除く案を唱えたが、銀行OBの長老が4社合併を主張。その長老は三菱銀行に絶大な影響力を持っていたため、現役は受け容れるしかなかった(当時、銀行の支援なしには大合同が不可能だったからだ)。しかし、結果的にはそれが正解だった。
一方、三井ではOBが原則として現役不干渉だったので、目先の利益を追った現役世代の暗闘が続き、話がまとまらなかった。OB間の派閥が大合同の障壁になったという説もある。

戦後は「組織の三菱」の時代
戦前は三井物産の取り扱い高が三菱商事のほぼ倍の差を付けていたが、戦後は大合同の遅れもあって三菱商事が肉薄し、その後は三菱商事が逆転。現在、商社業界のトップカンパニーといえば三菱商事で、さらに伊藤忠商事の健闘ぶりも伝えられるが、昨今の三井物産にはそのなかに割って入っていくような勢いは見られないようである。
三菱商事は大合同を遂げると、すぐさま第三者割当増資を行って、三菱グループ各社に株式をもってもらい、三菱グループの窓口商社の地位を固めた。これが、三菱商事の「勝利の方程式」になった。
現在製造業のトップといえばトヨタ自動車だが、高度経済成長期にその地位にあったのは三菱重工業だ。三菱重工業が買う鉄は、一部の例外を除いて三菱商事を通さなければならない。当然、三菱重工業の威光を借りて、三菱商事は製鉄会社に対して優越的な地位を手にした。三井物産首脳は、いくら現場が営業努力しても、三菱重工業を背景にした三菱商事にはかなわないと愚痴をこぼさざるを得なかった。
海外からのタンカー受注で、三井物産は三井造船を猛烈に売り込んだが、三菱グループには石油会社(三菱石油。現・JXTGホールディングス)があるから三菱重工業に発注するといわれる始末。
三菱商事首脳は、三菱グループの強さが自社の強さに繋がっていることを強く認識し、最大限に活用した。いまや総合商社は企業間取引の媒介者ではないのだが、海外では「MITSUBISHI」ブランドが圧倒的な強さを誇っており、その恩恵はまだ続いているに違いない。
(文=菊地浩之)