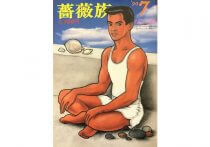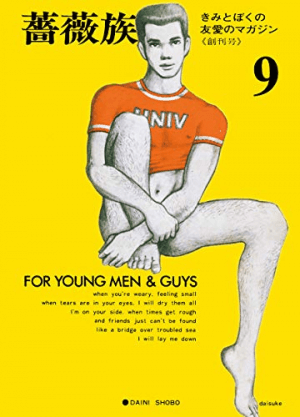
45年も経っているというのに、今でも忘れられないことがあった。
わが家が2階建てのボロ家から、やっと世田谷学園の同期生の設計士の友人が、3階建てのビルを設計してくれた。南側は家族の生活の場で、北側を事務所と仕事場に。3階は読者が集まれるように、16畳の大広間に。その時代はまだ今のような完備したゲイホテルがなかった。
僕はこの大広間を使って、高校生ばかりを集めたりしたことがあったが、その高校生をねらって若い子が好きな大人たちが、会の終わるころをねらって、表に何人もの人が待ち受けていた。心配してもそれから高校生たちがどうなったのかはわからない。結構、新宿2丁目に出入りしているような子もいたようなので、心配することもなかった。
何度か東大の教養学部に通う大学生が、ぼくを訪ねてきたことがあった。東大生で訪ねてきたのは彼だけだったので、忘れっぽいぼくでも覚えている。暗い神経質そうな青年だった。
初めて彼と逢ったとき、父のいない彼に長男として家族の期待が一心にかかっていることの重荷を彼は話してくれた。男好きであっても、まだ一度も男とのセックスの経験がないことと、仲間がいない寂しさを彼は語ってくれた。
気が弱そうで何となく暗い彼を感じていた。そんな彼を新宿2丁目のゲイバーに何度か連れて行ったのを覚えている。
それから1年以上も逢わなかったのだが、昭和50年の春ごろ、大学生ばかりの集会をわが家で催したときに、たくさんの大学生に交じって彼の元気な顔があった。そのときの印象では、前に逢ったときとは違って大人っぽくなったし、何か明るくなったように見受けたのだ。
高校生・大学生の集会をあのころ何度も催した。たくさんの若者が集まって、若い熱気で部屋の中がむんむんするばかりだった。
一人で悩んでいないで、みんなで語り合おう。確かにそのことでは成功だった。しかし、すでに酸いも甘いも噛みわけたベテランの読者も交っていて、結局は新宿2丁目のゲイバーの常連を増やすだけで終わってしまった。
そんな時にショックなことが起こり、ぼくは仰天させられた。
昭和50年10月25日(土)の「読売新聞」の社会面トップに「東大生不安の自殺・母の看病半年・葬式の翌日」と大見出しで載っていた。
「長い看病の甲斐なく母親に先立たれた東大法学部の4年生が、母の葬式を出した翌日、あとを追うように自殺しました。
祖母と妹という母子家庭の中の男1人。レポート用紙の日記には、看病疲れのほか卒業、就職を目前にした不安が書き残されていたが、葬儀の席で気を強く持とうと自ら誓ったのもつかの間、23歳の若い命を絶ってしまった。もっと強く生きることは出来なかったのか。」と書き出し、その詳細をつづっていた。
その小さく載った顔写真を見たとき、一瞬ぼくは背筋の寒くなるのを覚えた。
××君、忘れもしない彼だったのだ。彼が第二書房のすぐ近くの東大教養学部に通う学生であったころから、何度か訪ねてきたのは彼一人だったから、忘れっぽいぼくでもはっきりと覚えている。
彼のレポート用紙の最後のページに「卒業があぶない。就職も2社からあったが、どうもうまくいかない。自分は性格が弱くて困る。」と書いてあったそうだ。読売新聞の記事を書いた記者は、彼がゲイであることを知るわけがないから、本当の悩みを突っ込んで書けなかったのは仕方がないことだ。
就職のこと、母が死んだこと、そのショックもあった思う。しかし、彼の心のすみに男好きであったということが、どれほどの重みになって彼の全身にのしかかっていたかと思うと、僕の心は苦しいのだ。
ぼくを訪ねてくれたこと、大学生の集会にまで参加してくれた彼に、生きる力を与えることができなかったことを悔やむのだ。おそらく彼は期待してきていたと思う。
親にも、兄弟にも、先生にも言えない悩み、苦しみをみんな持っているのだから、そうした悩み苦しみをみんなで分かち、お互いに励まし合い生きていかなければ、だれも手を差し伸べてはくれないのだから……。
若い読者にとって性に目覚め、自分が男好きだと自覚したときそのことがどれだけの重荷になってのしかかってくるのか、僕自身の経験では理解できないところだが、人によって個人差はあるし、考え方も違うだろうが、ぼく個人としてはそんなときに少しでも悩まないで済む世の中に早くしたい、その実現に努力を重ねていくだけだが。
高校1年生の16歳の少年からこんな手紙をもらった。男好きだということに不安を感じているものの、よく冷静に自分を見つめているこの高校生に、亡くなった大学生より少し年代が若い少年の世代が持つ強さを感じるのだ。少年はこんなことを書いている。
「またもの寂しい秋がやってきた。ぼくは、ぼくたちの世界ってどことなく寂しく、未来が不安な、それゆえに刹那の愛を求めようとするところを『秋の愛』というイメージがぴったりのような気がしてならないのです。だから普通の男女の白痴的な情事は、甘美的な感のある春の字を使うのではないでしょうか。確かにぼくたちの世界には、将来が不安でならないーーー―それでも離れることのできない、哀れで無常感の匂う、そんな世界であるような気がしてならない。
僕は将来、女性と結婚するつもりだけど、この世界からは離れられない。もしも妻に知られたら、その時はこの世にはいないと思います。本当にぼくは自殺する覚悟でいます。」
自殺する、君はそういうけれど、君が大人になるころには、もう少し明るい世の中になるように努力はするけれど、『薔薇族』を読んでいる若者諸君!いつも言っているように世の中を良くも悪くもするのは君たちの力なのだ。与えられるのではなく、自分たちの力で切り開いていくべきではないだろうか。
××君に生きる力を与えてあげられなかった僕ら。なんとも無力さを感じるが、弱いものだって、2人、3人と集まれば強くなる。僕も弱虫で、すぐ涙が出るほうだったが、強くならないわけにはいかなかった。2人目の××くんが出ないように。お互いに励まし合って強く生きて行こう。
××君、安らかに眠ってください。
『薔薇族』の長い歴史の中には、こんな悲しい話もあったのだ。
(文=伊藤文學)