アイドル・栗原はるみ、扇動者・小林カツ代…“興奮させる”料理研究家と日本社会の潮流
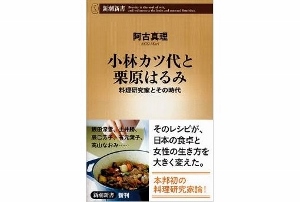 『小林カツ代と栗原はるみ 料理研究家とその時代』(新潮社/阿古真理著)
『小林カツ代と栗原はるみ 料理研究家とその時代』(新潮社/阿古真理著)
『小林カツ代と栗原はるみ 料理研究家とその時代』(新潮社/阿古真理著)
「なんだか妙に、盛りつけがモリッと立体的になったな……」
大学時代、久しぶりに顔を出した実家で母親の料理を見たとき、真っ先に感じたのがそれでした。さらに「なんだか妙に、余白感があるデカい皿に盛りつけるようになったな……」とも。そして、食べ終わった食器を下げにキッチンに行ったとき、同じ著者名を冠した料理本が数冊、視界に入ってきたのです。
「へぇ~、栗原はるみ。さては、この本の影響か!?」
栗原氏の出世作ともいうべき120万部超えの大ミリオンセラー『ごちそうさまが、ききたくて。』の刊行が1992年ですから、時期でいうとちょうどその頃です。栗原氏のおかげで以降の実家の食事は確実にランクアップを果たし、さらにここぞという場面では、やたらと余白のあるデカ皿や、ザラッとした質感の煮物鉢などが用いられて、栗原はるみ的(と母が解釈したと思われる)世界観まで食卓に醸されるようになったのでした。母は単に料理の参考にするだけでなく、栗原氏の提案するスタイルや世界観にも影響を受けている様子でした。
いきなり私事から入って無闇に行数を費やしてしまいましたが、今回紹介する本『小林カツ代と栗原はるみ』を読んで、ふとそんな過去の情景を思い出し、料理研究家という存在の役割や影響力の大きさについて、改めて感じ入ってしまった次第です。
小林カツ代と栗原はるみの登場
料理に関する書籍は世にあまた存在しますが、料理研究家にフォーカスし、詳細に論考を加えていく本は、非常にレアといえます。版元の紹介文は、こんな感じです。
「テレビや雑誌などでレシピを紹介し、家庭の食卓をリードしてきた料理研究家たち。彼女・彼らの歴史は、そのまま日本人の暮らしの現代史である。その革命的時短料理で『働く女性の味方』となった小林カツ代、多彩なレシピで『主婦のカリスマ』となった栗原はるみ、さらに土井勝、辰巳芳子、高山なおみ……。百花繚乱の料理研究家を分析すれば、家庭料理や女性の生き方の変遷が見えてくる。本邦初の料理研究家論」
明治期、主に洋食を家庭でもつくれるようにと、食材や調味料、料理法などを主婦に教えてくれる料理研究家が出現します。そして、その存在が表舞台で急速に注目されるようになったのが、戦後のことでした。テレビの料理番組や数々の雑誌に料理研究家が登場し、メディアで活躍する著名人として存在感を高めていきます。
高度経済成長期の料理研究家は、江上トミや飯田深雪、城戸崎愛など夫の海外赴任に同行して本場の欧米料理を身につけたような、いわゆるセレブ的な女性たちが中心でした。家庭料理と謳いながらも、レシピはなかなか本格的で手間ひまのかかるものが中心だったようです。当時の状況を、本書は次のように指摘します。
「毎食違う献立で一汁三菜そろえることが正しいとされ、主婦雑誌もテレビも、手をかけることがお母さんの愛情、とくり返し訴えた。(中略)便利な台所、豊かな食材、一日中家事に時間を費やせる主婦の誕生。条件が整って、家庭料理のハードルも急上昇した。だから、家電の普及が進んだ一九六〇年代、主婦の家事時間はほとんどへらない。(中略)ラクになった分だけ、主婦たちは新しい仕事をふやしたのである。その一つが、手のかかる料理である」
しかし、80年代を迎えると、潮流は変わってきます。女性の社会進出が加速し、共稼ぎやワーキングマザーが増加。そこで、手間や時間を短縮でき、アイディアとひと工夫でおいしく食べることができる家庭料理の伝道師として、小林カツ代が耳目を集める存在となります。
そして90年代に入ると、バブルの崩壊や価値観の細分化といった社会背景の中、専業であろうと兼業であろうと、主婦としての自分を肯定して、自分らしく暮らしを楽しむような気運も生じてきます。いわゆる“カリスマ主婦”の出現です。そうした流れのなか、料理を武器にしてスターダムにのし上がっていったのが、栗原はるみだったワケです。
アイドルとアジテーター
書中では、栗原のコメントと併せて、次のような考察が加えられています。
「『一番最初に私の料理をやって失敗しちゃったら、私のこと嫌いにならない?(中略)裏切らないようにしたいなっていうことだけですね。あなたのレシピは信頼できる。それで料理が好きになったと言われたら、最高の私へのプレゼントですね』
強い自意識とも取れる発言は、熱狂的なファンをたくさん持つタレントとしての自覚に通じる。あたかもそれは皆に愛されるアイドルのようで、愛されるための努力を栗原は惜しまない」
「彼女は、偶像の栗原はるみが実生活から乖離しないように、自分を主婦と位置づけている。私生活をネタにするスタンスは作家的とも言えるが、私が彼女をアーティストではなくアイドルと考えるのは、その親近感による」
なるほど、ちょっと身近で、自分にも真似できそうなことを教えてくれる、親しみやすいアイドル……それが栗原はるみという存在なのですね。
一方、小林カツ代については、その発言などを紹介しながら、このように論じられています。
「『とにかく仕事を持ち続けていきたいというのであれば、少しでも良い方向に、らくな方向に持っていく方法論が、もっと論じられてしかるべきです』(中略)『時間のないときの時間は実に効率良く使うものです。むろん完璧ではないけれど、短い時間と長い時間と、その時間内でやった仕事は同じという結果さえ生まれるものもあります』」
「家庭料理の常識に挑戦し続けた小林カツ代は、アジテーターと言える。常識をくつがえすような価値観を提示するアーティストでもあった。ファンは思ってもみない新しい世界を知って驚くのである」
栗原が主婦というプレゼンスを自覚的に活用しているのに対して、小林は主婦と括られるのを嫌い、プロの料理研究家というアングルを崩しませんでした。現在のライフハックにも通じる、方法論や時間に対するコスト意識といった小林の視点は非常にビジネスパーソン的でもあります。また小林は、フェミニズムや男女共同参画といった文脈にも連なるような発言を臆することなくクチにしています。対する栗原に、そうしたイデオロギーのにおいは皆無。実際に家でも使っているお気に入りの食器を用い、いつも家族につくって、喜ばれている料理を飾り気なくレクチャーする……といった調子で、とにかく自然体なのです。両者それぞれにこだわりや計算もあるのでしょうが、そうしたプレゼンスの違いから見え隠れする、世の女性の価値観やウケるモデルのトレンドは、とても興味深いと感じました。
本書には他にもさまざまな料理研究家が登場しますが、最大の読みどころはやはり、書名にも掲げられ、それぞれ一章ずつたっぷりと紙幅をとって詳細に語られていく、小林カツ代と栗原はるみについての論考でしょう。両者の発言やスタンスを丹念に洗い出しながら、ムーブメントを牽引する役割を担うことになった者の矜持、キャラクターの立て方、技術や味に関する信頼感の示し方といった側面について、対比的に浮かび上がらせてくれるのです。このあたりの論考に触れたとき、ビジネス誌などで扱われる著名な経営者の比較や、戦国武将の知略に関する考察を読んだときと同じような興奮をおぼえました。
イデオロギーの変遷も概観
さて、料理研究家をテーマにした論考の珍しさについては前述した通りなのですが、読み方ひとつで、本書はさまざまな知見を得ることができる一冊であることは間違いありません。一気通貫するテーマとして「家庭料理」を据えながら、「女性の社会的地位」「日本人の食生活」「専業主婦」「共働き」「家庭生活の役割分担」「男の料理」といったキーワードを斬り口にして、日本社会におけるイデオロギーの変遷を概観できる本として、関心を持って読み進めることができました。
本の冒頭で、書中に登場する料理研究家のマトリクス図(本格派←→創作派をタテ軸、ハレ←→ケをヨコ軸に、料理研究家を配置)が登場するのも面白いところですし、それぞれの料理研究家の個性や特徴を、ビーフシチューのレシピを例に検証する試みも、非常にユニークでわかりやすいものでした。
そうした、読者を飽きさせない工夫に加えて、膨大な資料にあたったことが行間から滲み出てくる誠実な筆致も好印象。良質な新書として、全力でオススメなのであります。
(文=漆原直行/編集者・記者)


















