 「Gettyimages」より
「Gettyimages」よりIQが高いからといって大人になってから成功するわけではない。そのようにいわれるようになって注目されているのが、非認知的能力である。
注目される非認知的能力
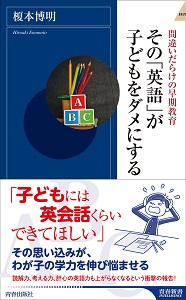 『その「英語」が子どもをダメにする』(榎本博明/青春新書INTELLIGENCE)
『その「英語」が子どもをダメにする』(榎本博明/青春新書INTELLIGENCE)非認知的能力とは、自分のやる気を奮い立たせる力、困難な状況でも忍耐強く粘り続ける力、欲求不満に耐える力、自分を信じる力、人の気持ちに共感し人間関係を良好に保つ力、自分の衝動をコントロールする力、必要なときには自分の感情表現を抑制する力などを指す。いわば、必要に応じて自分自身をうまくコントロールする力のことである。
幼い頃にこのような非認知的能力を高めることができた子は、大人になってから学歴が高い、収入が高い、持ち家比率が高い、健康度が高い、離婚率が低い、犯罪率が低い、生活保護受給率が低いなど、いわゆる人生で成功していることがわかってきた。
考えてみれば、当然のことだろう。やる気にならなければいけないと頭ではわかっても、どうもやる気になれない。困難な状況では、すぐにめげてしまう。欲求不満に耐えられず、つい攻撃的になってしまう。自分を信じることができない。人の気持ちがわからず、人間関係がうまくいかない。横暴な上司や取引先にキレるなど、つい衝動を爆発させてしまう。公的な場面で喜怒哀楽を表し過ぎる。
これでは、学校時代であれば学力向上は望めないし、友だちともうまくいかないだろう。仕事に就いてからも、業績は上がらず、人間関係でもつまづいてしまうだろう。
では、わが子の非認知的能力を高めるには、どのようなことを心がけたらよいのだろうか。
子どもと積極的にかかわる
忍耐強さ、自分を信じる力、衝動をコントロールする力、感情を抑制する力、人の気持ちに共感する力など、非認知的能力の特徴をみればわかるように、その基盤には情緒的安定があることがわかる。
そこで、何よりも大事なのが、親が子どもとじっくりかかわることだ。それによって、愛着の絆が形成されていく。乳幼児期のもっとも重要な課題は愛着の絆の形成ということになる。いつも身近で見守ってくれる親の存在を感じることで、子どもは落ち着いて物事に取り組むことができる。
たとえば、親との間に愛着の絆ができている1歳児は、その対象である親が傍らにいることで、安心して冒険ができる。公園で知らない子たちがいても、安心して遊ぶことができる。だが、愛着の絆ができていないと、親がいても冒険ができない。知らない場所や知らない子たちのなかでは気持ちが委縮し、親のそばから離れることができない。
愛着の絆の形成が順調にいけば、そのうち親が実際にいなくても、心の中に親がいる感じになり、ひとりでも安心して遊べるようになる。
遊びだけでなく、やがては本を読んだり勉強したりといった知的活動に集中できるようになるには、まずは安心を得ることが必要であり、そのためにも親が子どもとじっくりかかわることが大切となる。
共感性を育む
大人でも職場の人間関係が大きなストレスとなって仕事が手につかなくなったり、人間関係が原因で転職まで考えることもあるくらいである。ましてや子どもが幼稚園での活動や学校での勉強に集中するには、友だち関係が良好である必要がある。
そのために重要なのが共感性を身につけることだ。
親は子どもにとっての重要な言語的環境である。親が子どもや周囲の人にどんな言葉がけをするかによって、子どもが友だちとかかわるときの言葉づかいが大いに影響される。言葉づかいに限らない。親が相手の気持ちを思いやる言葉がけを日頃からしていると、子どもも友だちの気持ちを思いやる言葉がけができるようになる。
では、親として、どんな言葉がけをしたらよいのか。
たとえば、日頃の何気ないやりとりのなかで、相手の気持ちを想像させるように導く。
「○○ちゃん、とってもうれしかっただろうね」
「○○ちゃん、どんな気持ちだろうね」
「○○ちゃん、きっとがっかりしてるんじゃないかな」
「○○ちゃん、悲しかったんじゃないかな。もしあなたがそんなこと言われたらどんな気持ちになる?」
といった具合に。絵本や児童書を見ているときも、
「この子、ものすごく得意げだね」
「この子、なんで泣いてるのかな」
などと登場人物の気持ちをめぐって声がけしたり、
「このワンちゃん、淋しかったのかな」
「この小鳥さん、楽しそうにしてるね」
などと、人間でなくてもその気持ちを想像させることで共感性を高めることもできるだろう。
公園でアリが虫の死骸を運んでいるのを見かけたら、
「アリさん、一所懸命に食べ物を巣に運んでるね」
ぐっすり寝ている犬がいたら、
「ワンちゃん、気持ちよさそうにお昼寝してるね」
日陰に置かれている鉢植えの花を見かけたら、
「このお花、かわいそうだね、寒い寒い、お日様に当たりたいって思ってるよね」
などと、視点を向こう側に移し、その気持ちを想像させるような声がけをする。
自己コントロール力を身につけさせる
子どもは、親がよく口にする言葉をすぐに吸収し、自分のものにする習性をもっている。自分の口癖をわが子が口にするのは、誰もがしばしば経験しているはずだ。親が何かにつけて、
「もうダメだ」
「そんなの無理に決まってる」
「そんなこと、できっこない」
などと悲観的な言葉や諦めの言葉を口にしていると、子どもも悲観的ですぐに諦めるようになってしまう。反対に、親が日常的に、
「なんとかなる」
「やってみないとわからない」
「できるだけ、がんばってみよう」
などと楽観的で前向きの言葉を口にしていると、子どもも前向きにがんばれるようになる。親としては、前向きで粘り強さにつながる言葉を意識して口にすることが大切だ。
直接子どもに対するときも、
「やめようか」
「無理しなくていいよ」
などといった後ろ向きな言葉でなく、
「よし、がんばろう」
「諦めないでやってみようか」
などというように、前向きで粘り強さにつながる言葉がけを意識したい。
また、衝動や感情のコントロールといった面でも、親が怒りを爆発させたり、嘆き悲しんだりと、感情に溺れることのないように気をつけたい。親が自分の衝動や感情をコントロールできないでいると、子どもも思い通りにならないときに衝動的に怒りを爆発させたり、ちょっとしたことで嘆き悲しんだりするようになる。
こうした日常の何気ない親子のやりとりを通して、子どもは非認知的能力を身につけていくのである。
友だちとのかかわりを十分に経験させる
非認知的能力の発達のためには、友だちとのかかわりを十分経験させることが大切だ。親と違って、友だちは自分に合わせてくれない対等な関係だ。みんなが勝手な自己主張をするため、思い通りにならないことがしょっちゅうだ。そこで欲求不満への耐性が鍛えられる。
わがままな友だちに腹が立つこともあり、ケンカになることもある。友だちを泣かせたり、友だちに泣かされたりといったことも起こってくる。そうしたことを繰り返し経験することで、人の気持ちに対する感受性が磨かれ、人との距離のとり方や対立したときの解決の仕方を体得していく。
引きこもりという言葉が一般に広まり、引きこもりとまではいかなくても、友だちとうまくかかわれないという若者が増えている。そのような学生たちのカウンセリングをしたり、相談に乗ったりしてきたが、その根幹にあるのが、人との距離のとり方がわからないといった悩みだ。
人との距離のとり方がわからないため、友だちとうまくかかわれず、学校にいても落ち着ける居場所がなく、勉強にも集中できない。このままでは勉強に身が入らないばかりではなく、社会に出てもうまくやっていけないのではないかと不安だという。
たしかに、いくら知識を身につけ、思考力や発想力を磨いたところで、人とのかかわりがうまくいかないのでは、社会に出てもなかなか職場に適応できず、能力を活かす場を得るのは難しいだろう。
人との距離のとり方というのは、幼い頃からの友だちとのかかわりのなかで徐々に体得すべきことであり、大人になってから、こうすればいいと教えられ、頭で理解して何とかなるというものではない。その意味でも、子ども時代に友だちと遊ぶ機会を十分に与える必要がある。
友だちとの遊びは、自分の気持ちをコントロールしたり、相手の気持ちに共感したりといった人間関係力を高めるだけでなく、集中力を養うのにも効果がある。遊んでいるときの子どもたちは、ものすごい集中力で遊びに没頭している。何かに夢中になり没頭する経験が集中力を養う。
遊びを通して集中力を身につけることは、幼児期・児童期の最重要課題といってもよい。その時期に物事に没頭する経験を重ねることで、集中力が身につき、将来勉強に集中すべきときも、集中力を発揮できるようになる。
(文=榎本博明/MP人間科学研究所代表、心理学博士)





















