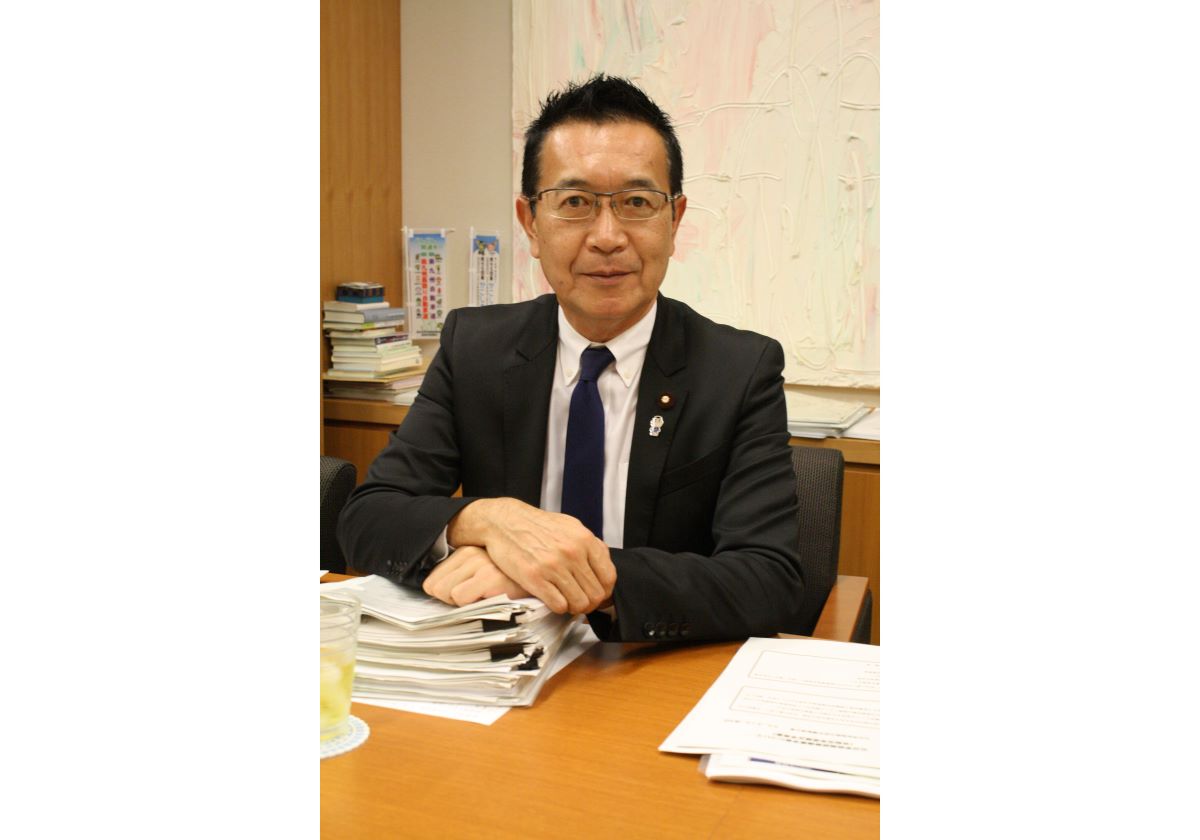
2020年度から大学入試センター試験に代わって導入される予定だった大学入学共通テストの国語と数学の記述式問題について、萩生田光一文部科学相は17日、実施を見送ると発表した。11月に実施延期が表明された英語の民間試験と合わせて、「大学入試改革の象徴」の2本柱が折れることになった。英語民間試験と国数の記述式問題の導入をめぐり、今年10月ごろから国会では与野党を超えて疑問点が噴出した。いったいこの政策の何が問題だったのか。
文部科学省に対する野党合同ヒアリングで、同省の不可解な政策決定プロセスに関する疑問点を指摘し続けてきた衆議院文部科学委員会理事の川内博史議員(立憲民主党、鹿児島1区)に話を聞いた。
「入試を変えれば教育が変わる」という倒錯した思想
――今回の延期・見送りをどのように受け止めていらっしゃいますか。
川内博史氏(以後、川内) 「入試を変えれば教育が変わる、子どもたちが伸びる」という倒錯した考え方のもとに、ごくごく一部の、しかし力を持っている人々が、「2020年度導入ありき」で、英語の民間試験活用と共通テストでの記述式問題の採用を政策決定してしまったことがわかりつつあります。文科省は、内部で制度設計ができないこと、大きな問題を抱えていることを感じながら、誰もそれにストップをかけることができず、事ここに至り、延期せざるをえなくなりました。
この問題の反省点は、政策形成のあり方、教育行政のあり方について、私たちにさまざまなことを教えてくれている案件です。一部の人たちの思い込みで、根拠に基づかない理想論だけで政策を進めてはダメだということに尽きます。
――大学入試共通テストへの英語民間試験と記述式問題の導入に関しては、下村博文元文科相、慶應義塾大学元塾長で、同大理工学部名誉教授の安西祐一郎中央教育審議会(中教審)会長、旧民主党参議院議員で文科副大臣や下村元大臣の補佐官を務めた鈴木寛氏(慶應義塾大学政策メディア研究科兼総合政策学部教授)の3人が強く導入を推進しました。導入が延期・見送りになった今もその必要性を主張しています。
川内 政策は科学的な根拠やエビデンスに基づいて立案されなければなりません。特に教育政策は20~30年の長いスパンで考えることが必要です。英語民間試験の件で言えば、英語4技能の試験を課す集団と、課さない集団を分けて検証が必要でしょう。その結果、4技能を課したほうが英語力が伸びているのなら、導入の根拠になり得ます。
日本人はほとんどのコミュニケーションが日本語で済んでしまいます。だから英語のスピーキングが弱いといわれれば、その通りです。しかし、「英語を伸ばすためには試験が必要だ」という根拠はどこにあったのでしょうか。英語を使えたほうが良いけれど、どうやったら英語が伸びるのかはきちんと理論に基づいてやっていただきたい。
イエスマンの高校長協会ですら疑問
――下村氏や鈴木氏らは、CEFR(セファール、言語能力を評価する国際指標)を挙げ、その基準をもとにした大学入試を行わなければ日本の英語や大学入学試験は「ガラパゴスになる」と主張しています。
川内 日本人の英語がガラパゴス化しているのではなく、彼らの政策の発想が「ガラパゴス化」しているのではないかと思いますね。
文科省が教育改革の柱としている「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の推進」の理念には賛同しています。アクティブラーニングはその通りだと思います。しかし、実践するにはどうすればいいのか。学校の教員を増やして、それぞれ自由な発想で授業をやってもらうよう任せるのが「主体的・対話的で深い学び」につながるのではないかと思います。
しかし今回の件でも明らかなように、実情は「アクティブラーニングをしなさい」と指示しつつ、国が厳しく管理する仕組みになっています。だから「主体的」にならず、わけがわからなくなってしまっている。その象徴が、今回の「高大接続改革」の議論だと思います。
「共通テストに英語民間試験を入れましょう」「記述式を入れましょう」「大学入試センターにはノウハウがないので、民間にお任せします」と。文科省としては、全体としての学力を測らないといけないので、全国一律のテストをしたい。しかし、全国一律のテストができるのは業者しかない。だから業者にお願いします。つまり、模擬試験と同じように考えてしまっている。入試は模擬試験と違います。地方在住者や家庭の経済状況など、日本全国にいる子供たちの環境に対する想像力が欠如しています。
英語民間試験活用に関する議論をしていた文科省の「検討準備会議」には当初、英語の専門家がいませんでした。あとで1名加入しましたが、日本英語検定協会のテストの開発者でした。結論からいえば、利害関係者です。
そして、本当の意味での議論が行われず、一部の人の意向を受けた文科省の官僚、事務局がとりまとめ文章に文言を無理やり入れていきました。まるで当初から結論があったのではないかという強引な進め方でした。
今回の文科省の大失態を象徴しているのが、全国高等学校長協会が、英語民間試験の活用と記述式問題の導入の双方に関して正式に疑問を呈していたことです。高校長協会は、文科省に対して滅多に反対しない組織です。その方たちが「ちょっとこれは無理だと思います」と一生懸命、反論していました。この政策がいかにダメかということの証左ではないでしょうか。
文科省に猛省を促したいです。どんなに力のある政治家が、強力に言ったとしても、「それはできません」とちゃんと言うことが大事です。出世したいのはわかるけれど、子どもたちや国民のためにならないと思う政策については、はっきりNOと言うべきだったのです。
かつて「ミスター文部省」と呼ばれ、旧文部省大臣官房審議官として「ゆとり教育」推進の最前線に立っていた寺脇研氏は、異例の降格人事で閑職に飛ばされても、文部省にとどまって自分の仕事を続けていました。ああいう生き方を今の公務員も見習えば、森友学園や加計学園の問題も起きていなかったでしょう。
いずれにしても下村氏、安西氏、鈴木氏の3氏には、自分が今回の政策決定の各局面でどのように行動したのかを語ってもらいたいと考えています。負け惜しみのように「このままでは日本の子どもたちが世界に取り残される」というように国民の不安を煽るのではなく、自分たちの何が問題だったのかを分析してもらいたいと思います。
安西氏の参考人招致が必要
――下村、安西、鈴木3氏の政策への関与を真っ向から指摘する声は大きくなりつつあります。具体的にどのような介入が行われたのでしょうか。
川内 記述式に関して言えば、中教審の高大接続改革特別部会の議論では当初、共通テストに「記述式」をいれるのは無理という議論の流れが主流でした。ところが、部会長の安西氏が「新しい高大接続メモ 2014年8月22日 部会長メモ」(通称:安西メモ)を提出したことで、潮目が変わりました。このメモに、安西氏は「記述式の設問を導入」を明記しています。「導入すべき」でも「導入を検討」でもなく「導入」です。この段階で記述式試験の導入が既定路線化していきました。
「安西メモ」は分厚いメモです。いろいろな入試についてのさまざまな専門用語が頻出します。安西氏は工学部の教授で、そもそも入試の専門家ではありません。ひとりでつくったとは思えません。そこで、私が文科省に「手伝ったのか」と聞いたら「文科省は手伝っていない」と回答がありました。文科省を通じ、安西先生に対して「誰に手伝ってもらったのか」を聞いたところ、安西氏は「記憶にない」と回答しました。
政策立案時に、ご自分が何をしたのか正直に言っていただきたいと思います。そのうえで議論をしたいです。安西氏には今後、国会に参考人として来ていただき、きっちりお話を聞かせていただこうと思っています。
安西氏はメモ提出後の14年11月、「一般財団法人進学基準研究機構(CEES)」の評議員になられました。同法人は通信教育大手のベネッセ東京本部の社内にあります。複数ある英語民間試験導入時に最も有力とされていた「GTEC」をベネッセとともに共催するのがこのCEESでした。
そして、鈴木寛氏はベネッセの創業者一族が運営する公益財団法人「福武財団」の理事を務めています。英語民間試験でも記述式試験でも、彼らは利害関係者だったのです。
なぜ利害関係があったことを隠すのか
――「プレイヤーとジャッジが一緒」という構図ですね。
川内 少なくとも安西氏と鈴木氏には、世の中の皆さんに対して、まず自分たちはベネッセの利害関係者であることを正直に明らかにすべきだと思います。
――あくまで延期と見送りなので今後、国会で審議が続いていくとは思いますが。
川内 入学試験制度に関わる多くの人たちを振り回した今回の大失敗が、どういう経緯でここまで引きずってきてしまったのか、責任の所在を国会で明らかにしなければなりません。安倍晋三首相は「教育が大事」だとか、「子どもたちにもっと良い学びをしてもらいたい」と謳っています。素晴らしいことです。それについては誰も否定しません。
ただそれを実現するために、特定の人々があらかじめ結論を決めていて、その結論をオーソライズするためだけに議論することが問題だと思うのです。与野党を超えて、それぞれファクトを出し合い、教育に関する論文などを踏まえて議論してほしいと思っています。萩生田大臣は、1年間かけて検討するとしていますが1年で結論が出る問題ではないと思います。時間をかけてじっくりと高大接続とはなんぞやということについて、まさに「主体的で対話的な深い議論」を実現してほしいと思います。
(構成=編集部)




















