世界一達成のスパコン「富嶽」、すでに人類的課題の解決に活用…AIとDXで社会を幸福に

前回(第6回)記事『 図らずもテレワーク普及で企業のデジタルトランスフォーメーションが一気に推進』では、NVIDIA社がたったの2100万円で5PFlopsと、あの「京」の半分の性能の超小型スーパーコンピューターを発売し、世界のAI開発を加速したことに触れました。AI開発基盤の独占という懸念を和らげてくれる良いニュースと筆者は評価しています。少し安堵するとともに日本勢が絡んでいない寂しさも感じました。
そこへ、「京」の後継である「富嶽」が9年ぶりに日本のスーパーコンピューターとして世界一、それも4種類の評価指標で同時に1位の、世界初の四冠王となりました。4種類目は新設のAI向けの性能指標HPL-AI。これはAIの計算処理などで求められる低精度の(bit数の少ない)演算の性能で、1.421 Exa Flops。1秒に142京回と、上記NVIDIAの新製品の300倍に迫る速度です。「富嶽」は、ソフトバンクが買収したアームのプロセッサを大量に使っていることから、部品レベルまで日本のものといっていいでしょう。
さらに、もう一冠は、いかに低消費電力で計算できるかを競うGreen500で、こちらも日本勢、プリファードネットワークスのMN-3が初の世界1位となりました。素晴らしい! 実は「富嶽」の富士通側のリーダーは筆者の高校の同級生で、理化学研究所側にも高校の後輩が関わっていて嬉しさもひとしおです。また、プリファードの西川徹社長は大学の学科の後輩ですし、東大の理工学研究科長を務めた平木敬先生(高校の先輩;拙著『人工知能が変える仕事の未来』の帯に推薦の言葉)が入社されていて、いつも力いっぱい応援したい気持ちです。
スーパーコンピューターで新型コロナウイルスと闘う
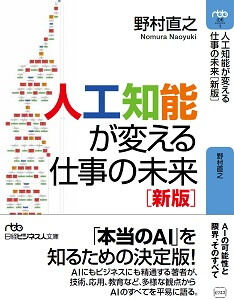
現場に残されたガムの噛みかすの唾液中のDNAをAIが解読して、その人の顔をかなり忠実に再現するようなことができるようになりました。遺伝子やその周辺の研究により、その個人専用に、適切な効能を発揮する薬を開発する、パーソナライズド・メディシンも急速に発達しようとしています。
新型コロナウイルスの感染の仕方、感染後の体内への拡がり方、そして、さまざまな症状を引き起こすあり方には、大きな個人差があります。その違いを遺伝子のレベルで解明するのもパーソナライズド・メディシンの役割であり、それには膨大な計算が必要です。「一刻も早く次世代スーパーコンピューターを持ってこい!」という声を東大医科学研究所などから聞きます。体内でコロナウイルスがどのように動き、「拡散」するかなどのシミュレーションにもスーパーコンピューターが必要となるでしょう。開発途上のワクチンを片端からヒトに打って危険にさらすわけにもいかないので、計算、シミュレーションで済むものは計算機に任せたいという事情もあります。
「富嶽」の優先活用テーマ
「富嶽」は、実はフルスケールで完成するより前倒しで実践に投入されました。学徒出陣みたいのようですが、非常に高い完成度、高性能で喫緊の人類的課題の解決に活用され始めています。理研の発表「新型コロナウイルス対策を目的としたスーパーコンピュータ『富岳』の優先的な試行的利用について」では、次の5つの課題を挙げています。
(1)新型コロナウイルスの性質を明らかにする課題
(2)新型コロナウイルスの治療薬となりえる物質を探索する課題
(3)新型コロナウイルス診断法や治療法を向上させうる課題
(4)新型コロナウイルスの感染拡大及びその社会経済的影響を明らかにする課題
(5)その他、新型コロナウイルスの対策に資することが想定される課題
新型コロナウイルスの対策につながるあらゆる研究テーマの提案を受け付けているとのことです。「我こそは!」という人はぜひこのページに記載の問い合わせ先にメールを送ってみてください。
すでに実施している研究はこのページで紹介されています。「医学的側面からの研究」として、「『富岳』による新型コロナウイルスの治療薬候補同定」他2つ、新型コロナウイルスの性質を明らかにする研究が走っています。医学的側面というのは、ヒトの1個体を相手にしますが、室内空間でのウイルスの拡散や、多人数の社会でどう感染が広がるかの研究も重要です。こちらは、「社会的側面からの研究」とされ、各1つの研究が、富嶽の膨大な計算パワーを駆使して進行中です。
すでに進行中のテーマには、あまりAI的なものはないようです。ただ、先述のように、ビッグデータからなんらかの法則性を見いだすような役割はAIが担います。ウイルスや治療薬候補の性質を解明する手段として、AI的な手法が使われることはあるでしょう。そのようなAIが機能するためにもスーパーコンピューターは欠かせません。
AIと、DX、オープンイノベーションの関係
時事ネタが長くなりました。人類の一大事への取り組みということでご容赦ください。今回の表題に絡めて、「AIと、DX、オープンイノベーションの関係」を簡単に整理して締めくくりたいと思います。
まだ人類が持たざる知識を発見し、それを使って真理の探究や課題を解決するのが「研究」の役割です。一方、産業界で使われる「イノベーション」という言葉は、革新的な技術開発や、斬新なビジネスモデルの考案と実践の両面を指します。研究は必ずしも役に立たなくてもいいのですが(新型コロナウイルス関連の課題は役立つものばかりですが)、ビジネスにおける技術開発は産業上のメリットを生まなくてはなりません。
だからといって、常に秘密裏に技術開発をすればいいというのではありません。アップルのような徹底した秘密主義の会社もありますが、世界中の知恵を結集し、データを出し合い、要素技術開発や実証評価を分担するような「オープンイノベーション」の重要性が昨今、叫ばれています。あのIBMですら、「うちの会社規模ではすべての要素技術を自社開発するわけにはいかない」と公然と唱えるくらいです。
AIの歴史をたどってみると、その時代その時代の最先端の「怪しげな」情報関連の研究をAIと呼んでいたフシがあります。数理最適化や情報検索の技術など、のちに当たり前になった技術は初期の頃はAIと呼ばれていたりしました。大半は論文発表され、その知識がオープンに共有されていました。今日のAIも、斬新な技術開発であり、最先端知識やビッグデータに支えられていることから、オープンイノベーションの形で重要な役割を果たします。論文がWeb上に迅速に投稿される上に、AIの実態そのものであるソースコードや学習済のモデルさえもオープンに共有され、イノベーションを支えています。
イノベーションが成功し、使われて、経済・社会に根付くには、それが使われるインフラが整備され、十分低コストで普及している必要があります。9年前の「京」でしか動かず、他のコンピュータとインターネットを介して連携できないプログラムでは、なかなか産業界で常時使われるようにはならないわけです。ネットを介して互いにいつでもデータを安全にやり取りし、加工し、ビジネスを100倍速(もっと大げさに「光速商取引(CALS=Commerce At Light Speed)」といわれたこともありました)にする。それに必要な企業内情報システム、組織体制の変革も含め、DX=デジタルトランスフォーメーションととらえる人が多いでしょう。
AIとDXによる幸福の増大を信じましょう
B2Cのビジネスでは、AI搭載のスマホアプリに象徴されるように、個人のサービス利用の利便性を飛躍的に高めるためにAIが直接使われることがあります。一方、B2Bのビジネスでは、企業間のデータ、情報のやりとり、承認のプロセスなどのデジタル化のために、デジタルでつながるAPI (Application Programming Interfaced)を互いに公開しあうことが重要になります。そして、従来どうしても人間の判断、介入が必要だったところをAIで置き換えることができて初めて、100倍速が実現します。FAXを人が読んだり電話で聞き取ったりする作業などは、前世紀の遺物ですね。何割もの間違い、ミスが積み重なって、集計結果が10倍も狂ったりすることが現実に起きています。
DXの結果、生産性が上がり、正確で個人に寄り添えるパーソナライズされたサービスが実現する。だから、冒頭、タイトルで「 AIとDXで社会を幸福に」と記しました。各論、たとえば金融業界のフィンテック(Fintech)など各業界の尖った技術X-techのことなど、7月2日発売の拙著『人工知能が変える仕事の未来 [新版]』をぜひご参照ください。文庫本なので税込み990円と、千円札でおつりが来ます(笑)。各産業ごとの詳細は、数年前の状況と予測にはなりますが、単行本のほうが役に立ちます。
必ずしも全部のX-tech、DXの尖った要素がAIというわけではありませんが、AIがきめ細かく人間の判断や作業を代替したり、業務フロー自体を一新したりすることで社会の平均的幸福があがっていく。このイメージはぜひ皆さまと共有してまいりたいと思います。
(文=野村直之/AI開発・研究者、メタデータ株式会社社長、東京大学大学院医学系研究科研究員)





















