「楽しい授業=良い授業」という勘違いの弊害と危険性…「笑顔の多さ」偏重の風潮

学校がつまらないというのは、子どもがよく口にするセリフだ。何がつまらないのかと尋ねると、授業がつまらないという。毎日朝から夕方まで行われている授業がつまらないのはかわいそうだから、何とかして楽しい授業にしないといけないということになる。そうした保護者をはじめとする世論に動かされ、楽しい授業づくりの動きが広がっている。だが、どうも楽しさの勘違いが横行しているように思われてならない。
「笑顔が絶えない授業」がよい授業なのか?
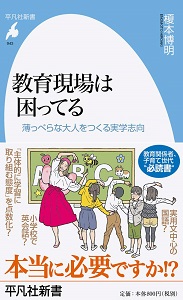
学校に対する批判として、しばしば耳にするのが、授業が楽しくないと子どもたちが言っている、もっと楽しい授業にならないのか、というものである。そこで、現場の教員たちは、子どもが楽しいと思える授業にすべく、いろいろ工夫を重ねている。
教員向けの雑誌をみても、楽しい授業づくりのためのヒントが散りばめられたり、楽しい授業づくりの試みの事例が紹介されたりしている。
だが、「このようにしたら、子どもたちの楽しそうな笑顔が増えた」「こんな工夫をしたら、子どもたちが楽しいと言うようになった」などといった事例紹介記事を見るにつけ、「何か違うのではないか」といった思いを抱かざるを得ない。
子どもたちが「授業が楽しくない」「授業がつまらない」と言うことへの対処として、子どもたちの楽しそうな笑顔を引き出すということでいいのだろうか。たしかに私自身の大学生や社会人向けの授業でも、熱心に授業にのめり込んでいる受講生たちは、適切な箇所で笑顔で反応してくれるので、場の雰囲気が盛り上がり、こちらも勇気づけられる。だが、笑顔になるのはほんの一瞬のことで、大半の時間は真剣な表情で、ときに頷きながら、じっと聴き入っている。
笑顔になる時間を増やすのなら、もっと雑談を増やし、漫談をふんだんに取り入れればよいわけだが、それで教育的に意味のある授業になるとも思えない。
そこで思い出すのは、ある大学に勤めていたときの出来事だ。私のゼミでは、各自が関心を持つ領域を聞き出し、その領域の代表的な研究論文や最新の研究論文を紹介し、その中から本人がとくに興味をもった研究論文を読んで、その概要を発表するという方針にしていた。論文も専門書も読んだことのない学生ばかりで、はじめは相当大変だったと思う。よく質問にやってきて、
「先生、私に教えるのって大変でしょ」
「すみません、私バカだから何度教えてもらってもわからなくなっちゃうんです」
などと言う学生たちもいたが、そう言いながらも必死になって課題に取り組んでいた。そのうち、他のゼミの学生たちがゆるくやっているのに、毎週図書館に籠もって論文や専門書を読んでいることに充実を感じるようで、そのうち自分からもっと他の文献も読みたいと言ってくる者も出てきた。
それに対して、ある影響力のある教員からの批判が出た。ゼミで研究指導をしているという噂を耳にしたが、本学のようなレベルの学生に研究指導なんて無意味だ、自分のゼミでは毎時間椅子取りゲームをさせている、友だちづくりを支援するのがゼミの役割だ、みんな笑顔で楽しそうに活動している、というのだった。
「授業が楽しい」ということの意味
それは楽しいだろう。授業中にゲームをしていればよいのなら。どんなに授業に興味のない学生でも、退屈せずに楽しい時間を過ごせるに違いない。
だが、学生たちを楽しませればいいのだろうか。それが教育的観点からして、よい授業ということになるのだろうか。もちろん、そのような批判や助言に耳を傾けるわけにはいかなかったし、友だちづくりの支援は、授業時間でなく、放課後や休日にお花見など季節の会やスポーツ大会などの催しをしょっちゅうやっていた。
いったい「楽しい授業」とはどういうものなのか。「授業が楽しい」とはどういうことなのか。私は考え込んでしまった。「遊びが楽しい」というのと、「授業が楽しい」「勉強が楽しい」というのとでは、まったく意味が違うはずである。ここでは、学びが遊びになるという意味の議論は棚上げしておくことにする。
「授業が楽しい」と思えるようにしようとの試みにおいて、遊びの要素を取り入れるということが盛んに行われている。それも、学びのなかにゲームの要素を取り入れるなど、ごく部分的に取り入れるのなら効果があるかもしれない。だが、本来は子どもの遊びとは違った次元の楽しさを味わえるように導いていくべきなのではないだろうか。
大学では授業評価が盛んに行われているが、そのなかで学生の成績ごとに集計するということも行われている。そこでわかるのは、成績の良い学生と成績の悪い学生では、授業の評価基準が違うということだ。
考えてみれば当たり前のことだ。その授業で行われている勉強の内容に強い関心のある学生とまったく関心のない学生では、授業に求めているものが違って当然だろう。
ここから言えるのは、小中学校や高校でも、「授業が楽しい」というときの基準は、子どもたちが勉強に、あるいは個々の科目に、どれだけ興味をもって取り組んでいるかによって、まったく異なるということである。
「授業が楽しい」ということを安易にとらえるのは危険である。そのあたりの勘違いが世間に広まっているように思われてならない。
英語の時間が楽しいという子どもたち
英語を小学校で教えることに関しては、NHKの英会話講座を長年担当している同時通訳の第一人者である鳥飼玖美子氏をはじめ、英語教育の専門家の多くが反対してきたにもかかわらず、2020年度から本格的に始まることとなった。
それに先行して、英会話を中心にした英語活動は、すでに小学校の高学年を対象に行われてきたが、その時間を楽しいという子どもたちが多いという。
たとえば、ベネッセが2015年に全国の小学5・6年生とその保護者を対象に実施した調査によれば、
「他の教科と比べて英語はおもしろい」という子が71.5%
「英語の授業をもっと増やしてほしい」という子が59.1%
「他の教科と比べて英語は簡単に感じる」という子が47.9%
などとなっている。
このようなデータをみても、学校での英語活動が楽しいという子どもが非常に多いことがわかる。そうした声を聞くと、英語の授業を小学校で行うのはよいことだと思うかもしれない。だが、そうしたデータを根拠に小学校での英語教育をどんどん推進すべきだとするのは問題だ。
なぜなら、これまで行われてきた英語活動というのは、簡単な英語を使ってゲームをしたり歌を歌ったりするわけで、いわば幼稚園でやってきたお遊戯を英語でやるようなもので、けっして他の教科のような勉強ではない。お遊戯のようなものである。
たとえ本格的な英会話をやるようになるとしても、英語が母国語である家庭に生まれたら、幼児でもできるレベルのことをやるにすぎない。英語圏に生まれれば、幼稚園児でも英語ペラペラである。日本の幼児が日本語がペラペラなのと同じだ。
ペラペラ流暢にしゃべるからといって、けっして頭がよい証拠になるわけではないし、会話をしていれば知的能力が高まるわけでもない。教員ならだれもがおしゃべりな子どもに手を焼く経験をしているはずである。おしゃべりな人間が知的であるわけではない。会話能力と知的能力が別物なのは、よく考えれば当たり前のことである。
知的能力を高めるには、おしゃべりかどうかよりも、考えている内容こそが問われるべきであり、学校教育はおしゃべりの仕方ではなく、考える内容を問題にすべきだろう。
英会話中心の授業は、他の教科のように勉強ではなく遊びのようなものであり、多少勉強の要素を取り入れるにしても、英語圏に生まれれば幼児期にやる程度のことをするわけで、他の教科のような知的鍛錬にも教養にもならない。せっかく学校に上がったのに、そのようなことのために他の教科の勉強時間を削ってよいものだろうか。
学校教育ばかりではない。子どもビジネスと呼ばれ、盛んに展開されている習い事の世界でも、子どもが楽しく活動している様子が売り物になっているが、それがどんな教育効果をもつかを十分考慮する必要があるだろう。
表層的な「楽しい」「おもしろい」にとらわれすぎる風潮
どうもこのところ「楽しいかどうか」ということにとらわれすぎる風潮が強まっているように思われてならない。新入社員を対処として日本生産性本部が毎年実施している「働くことの意識」についての調査結果をみても、「若いうちは自ら進んで苦労するぐらいの気持ちがなくてはいけないと思いますか。それとも何も好んで苦労することはないと思いますか」という質問に対して、これまで数十年にわたって「苦労すべきだ」と答える者のほうがはるかに多かったのだが、2013年から前者が急激かつ一貫して減り続け、後者は2012年からやはり急激かつ一貫して増え続けている。
その結果、2019年には、前者54.3%、後者43.2%となり、前者のほうが比率が高いものの、両者の差は過去最少の5.9ポイントとなった。
苦労するなかで人は成長する、苦しくても頑張り抜くことで力がつくはず。そのような発想はもう古い。苦労するような仕事はしたくない。そう思う若者が増えていることが、こうした調査結果から窺える。そのため、実際に働いてみて、楽しいと思っていた仕事でちょっと苦しい思いをしたりすると、「思っていたのと違う」「こんなはずじゃなかった」ということで転職を考える。そんな早期離職が少なくない。
子どもたちも、授業が楽しくないと集中力がもたず、すぐにおしゃべりを始める。教室をウロウロしたり、教室の外に出て行ったりする。小1プロブレムなどと呼ばれている現象も、そうした子どもたちが急増していることを指している。それでは困るので、なんとか楽しい授業にしようと工夫する。
でも、そのような動きをみていると、受け身の楽しさばかりを追求しているように感じざるを得ない。授業の楽しさとは異なる次元の楽しさを追い求めているように思われてならない。
何をするにしても、楽しいに越したことはない。つまらないことはしたくない。だれだってそうだろう。だが、子どもや若者が表層的な「楽しい/楽しくない」「おもしろい/つまらない」という軸にとらわれすぎる風潮があるとしたら、それはそのような文化を生み出している大人の責任と言わなければならない。
今の子どもや若者の多くは、今の文化の中で推奨されている子育てや教育を受けることで、表層的な「楽しい/楽しくない」「おもしろい/つまらない」という軸にこだわるようになったのである。そこのところを教育者だけでなく、世の大人たちもじっくり考えてみる必要があるのではないか。
(文=榎本博明/MP人間科学研究所代表、心理学博士)





















