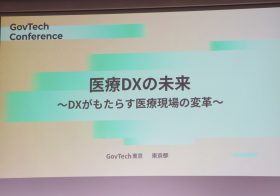ゆとり世代が投資に強い理由は…「米国株への親和性」「ゲーム感覚」「将来への不安」
少し前に話題になった“億り人”。暗号資産取引株式投資やFXなどで資産を1億円以上築いた投資家たちを指す言葉として浸透したが、1億円以上稼いだという実績はもちろん、その時に注目を集めたのは、“億り人”として紹介された多くが“ゆとり世代”だったことだろう。しかも、彼らのなかには、普通の会社員や投資ビギナーだったという人が少なくない。なぜ、彼らは“億り人”になれたのか、他の世代との違いはどこにあるのか――? ゆとり世代を代表する、元SMBC日興証券マンの投資家が考察する。

ゆとり世代が抱く将来への不安
ゆとり世代の私が思うに、投資において、我々とその他の世代との違いとして最も大きいのは、やはり、ITや最新テクノロジーに子供の頃から触れてきたかどうかだろう。早い人であれば小学生時代に携帯電話を持ち、中学校を卒業する頃にはクラスのほとんどが持っていた。小さい頃から携帯電話でのゲームや動画視聴が当たり前で、ネットと現実、2つの社会を同時に生きている。そんな我々ゆとり世代は「投資」への関心度が高い。
ゆとり世代は、自分自身の銀行口座を持つようになってから、低金利時代しか経験していない。たとえ100万円預けても、利息は1年で何十円、何百円というわずかなものだ。むしろ私も含め、最近の若者は大半がネットバンキングを利用しているから、利息そのものを意識することがないのだ。
銀行に預けていても資産が増えることはなく、老後の年金さえ期待できない――。その不安が、投資への欲望を掻き立たせる大きな要因のひとつだろう。 合わせて、昨今の株高に加え、つみたて(積立)NISA、IDECOなど投資のバリエーションが増えたことも、投資への関心を高めた。実際、2020年3月〜2021年4月の1年間で、30代以下のネット証券口座開設件数は約200万件と急拡大しており、これは40代以上の全年代の総数よりも多い数字だ。つまり、ゆとり世代が人一倍投資への関心が高いことの証左だろう。
お金とは面白い力を持つもので、実際に自己資金を投資に回してみると、なぜ世界で株価が上昇しているのか、なぜ円安円高が起きるのか、その要因は何なのかが気になり始める。すると、必然的に新聞を読み始め、ニュースを確認し、その結果として、経済の知識が身についていく。さらに、SNSの普及により、得られる情報量が増えたことも、若者の投資熱に拍車をかけたといえるだろう。
というのも、ニュースは“今、世界で起きていること/起こりそうなこと”は伝えてくれるが、個人的な見解は少ない。その一方、SNSはさまざまな立場、年代の人々が自由に自身の意見を投稿する。内容の質については玉石混交であるものの、ネットと現実の2つの社会を生きてきた私たちにとっては、すでにそれは当たり前の状態なのだ。
中高年世代とゆとり世代の大きな違いがここにもある。ネットという空間は、仮想空間ではあっても、私たちゆとり世代にとっては、もう1つの現実社会なのだ。2つの社会でさまざまな意見や考えに触れることで、私たちは投資意欲を育んできたのだ。さらに、暗号資産ブームが訪れ、ビットコインで多くの“億り人”が誕生したことも、 私たちに夢と刺激を与えた。
証券会社時代に感じた世代間ギャップ
ここで少し、私自身の体験を紹介したい。
私は、法政大学を卒業後、SMBC日興証券に入社し、2021年3月に退社するまで4 年間同社に勤めた。最初の配属地は北九州の小倉で、本社部門へ異動した半年間を除き、在籍期間のほとんどは2回りも3回りも上の世代に対して証券営業を行っていた。主な業務内容は富裕層の開拓、商品提案だが、会社からは“これを販売しろ”などという指示はほとんどなく、提案すべき商品は自ら考えなければならなかった。
当時から私には、“将来的には自分自身で株式投資をしていきたい”という思いがあったこともあって、業務後のほとんどの時間をテクニカル分析に充てていた。そこで、どこにどのように投資をすれば儲かるのかばかりを考えているうちに、日本株と米国株とではリターンに大きな違いがあることに気づいた。
以降、米国株の研究を続けた結果、日本株よりも着実に資産を増やせる可能性が高いと判断し、いざベテラン投資家であるお客様に、日本株から米国株への切り替えを提案をした。すると「米国企業はあまりよくわからない」「日本株じゃないと不安だ」という答えばかりが返ってきたのだ。いくら米国株の方が高リターンだとしても、何十年と日本株へ投資してきた人たちが、急に米国株へ移行するのは難しいものなのだ――この時に、私は、我々ゆとり世代との違いを強く感じたのだった。
この米国を中心とした海外企業への距離感、考え方は世代間で大きく異なっているが、とりわけゆとり世代と呼ばれる若手と、ベテラン投資家との違いは、伝統的な日本企業よりも、米国ハイテク企業の方が馴染みが深いということだ。
AppleやAmazon、NetflixにTwitter、最近ではUberなど、ネット関連の身近な企業を思い浮かべてみると、それは自然と米国企業ばかりである。
これは米国における人口の過半数が、1981年以降に生まれた“ミレニアル世代”で占められていることが大きな要因のひとつだろう。米国企業の多くは、ミレニアル世代を強く意識したサービスを展開し、その結果としてYouTubeやNetflixなどの革新的なイノベーションが次々と登場した。そして、それらは米国内だけでなく、“ミレニアル世代”とほぼ同世代であるゆとり世代の日本の若者をも巻き込み、成長してきたのだ。
そのため、ゆとり世代には、投資においても米国企業への抵抗がない。一昔前であれば、初めての株取引でトヨタ株を買ってみようという感覚が、今ではAmazon株を買ってみよう、なのである。
実際、我々ゆとり世代には、むしろ日本市場よりも、最初から米国市場を主戦場とする人が少なくなく、そこで多くの人が着実に資産を構築しているのだ。
ゆとり世代が魅力を感じる銘柄とは?

私は、この世代間での違いに気づいてから、まずは営業活動の際、年配世代のお客様から、米国株への抵抗感を取り除くことに努めた。
時間をかけて説明していくうちに、私よりもはるかに投資経験の長い方々も、徐々に私の提案を受け入れてくれるようになり、そして、一度米国株を保有してもらうと、お客様の収支は一気に改善していった。
おかげで証券マンとしての私も、お客様から感謝の言葉を貰うだけでなく、多くの表彰を受け、同期の中でもトップランカーとして走ることができた。
さらには退職後、半年間で5000ドルからスタートした株式資産を10倍にできた。これもひとえに、有名米国企業からマイナー企業に至るまで、すべてを米国株に投資してきたからだった。
我々ゆとり世代が米国株に抵抗がないのは、伝統的な日本企業よりも、むしろ米国ハイテク企業の方が馴染み深いから、と説明してきたが、投資においては、実はそれだけではない。
ゆとり世代の大きな特徴は、高配当や安定株、割安株よりも、高ボラティリティ(編注:価格の変動率が大きい)銘柄に魅力を感じる傾向が強いことだ。これは、ビットコインによる“億り人”の登場や、ネット証券の普及で投資家の絶対数が増えたことが大きいだろう。
我々世代は長期的な下落相場の経験がなく、また幸いにも、株式、ビットコインは大きく下落しても、高値を切り上げながら推移しているため、結果的に高ボラティリティ商品の恩恵を受けてきた。
そのため、過去の経験やアノマリー(編注:論理的根拠があるものではなく、説明がつかないものの、よく当たる相場の経験則や事象)から、米国テクノロジー企業やビットコインの上昇を信じてやまない傾向にあるのだ。
当然、こうした考え方はリスクも伴うが、生まれた時代が投資感覚を大きく変化させていることは揺るぎない事実だろう。
さらにゆとり世代の投資活動に特徴的なのが、投資をゲーム感覚で行なっていることだ。
昨今、投資をするにあたって、現金、株券などの現物を目にすることはなく、取引はすべてインターネット上で行われる。大きな損失や利益が出ても、表面的には、モニターの数字が変化するだけだ。だから実感が湧きにくい。そのため、暗号資産などのニューエコノミーなどはゆとり世代との親和性が高く、良くも悪くも、なんのためらいもなくハイリスク、ハイリターン株に投資できる理由だろう。
こうした投資志向・投資感覚は、ゆとり世代に多くの恩恵をもたらしたが、他方で、弱点もある。高ボラティリティの標準化や経験不足だ。長期的な下落相場を知らないということは、その対処方法もわからないということである。いつか到来するであろう下落相場を自ら経験し、時間をかけて様々な投資方法を知ることが今後の課題となるだろう。
だが、こうした弱点を自覚しつつ、ゆとり世代の投資感覚や投資手法を取り入れることは、とりわけ中高年世代には、大きなメリットをもたらす可能性を秘めている。
もちろん、ゆとり世代が軽視しがちな高配当株や割安株などは長期的には魅力的で、切り捨てる必要はないが、同時に、米国株を「馴染みがない」「日本株じゃないと不安だ」などと切り捨てるのは、あまりにももったいない。
こうしている間にも、ゆとり世代は、大きなリターンを求め、新たな米国テクノロジー企業を探しているのだ。
今後も当サイトで、具体的な投資手法や市場動向の見方、注目銘柄などを紹介していきたい。
(文=中沢隆太)