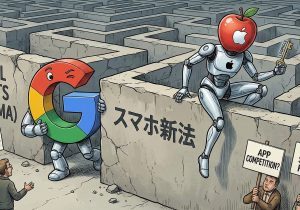コロナ時代でも「直接会って、話すこと」の重要性を忘れてはいけない理由

新種のコロナウイルス・オミクロン株の蔓延によって、人間関係がまたもや陰鬱とした閉鎖性に囚われ始めている。
私の妻は先日、体調不良で伏せる実父を安心させるために郷里の北海道に帰省した。しかし、同居する兄夫婦ははるばる訪ねてきた妹と直に会おうとせず、ドア越しに少々会話を交わしただけ。実家に寝泊まりすることも兄に許されず、結局は叔母宅に泊めてもらった。マスク着用はもちろんのこと、PCR検査で陰性が確認されているにもかかわらず、である。
私にしても「コロナが落ち着いたら」と取材相手に取材の延期を告げられるばかりで、取材が遅々として進まず、したがって書くこともままならない状態に置かれている。
「電話取材か、リモート取材にしたら?」と周囲に進められてはいるが、どうもその気になれないのが正直なところである。
週刊誌記者だった若い頃、上司の編集者や先輩記者にこう言われてきた。
「どんな短いコメントをもらうにせよ、なるべく相手に会うように」
そのアドバイスに従って、どんな短いコメントであろうが、東奔西走して直に取材した。確かに対面取材だと、相手の表面上の言葉だけでなく、表情の変化や含み持った言葉の意味を探ることができる。取材の後、飲みに誘ったところ、そこで取材中は出し渋っていた本音を吐露されたことも、たびたびあった。
対面取材で思わぬ情報を得て、それがスクープへと発展したことも何度かある。某プロ野球球団のある首脳陣などは、対面取材で私のことを気に入ってくれたのか、以来、何度か重要な情報を私に与えてくれた。
足を使う現地取材、対面取材は、私が週刊誌を離れ、フリーランスになってからも、私に思いも寄らない宝物を与えてくれた。
大場政夫に敗れた元チャンプの取材
思い出すのは、1988年、初めてタイに観光で赴いたときのこと。世界王者のまま愛車もろとも首都高速に散った大場政夫の最後の対戦者チャチャイ・チオノイ(大場が逆転KOでタイトル防衛)が、当地にいることを思い出したのは、帰国当日のことである。
私は急きょ通訳を雇うと、当地の新聞記者にチャチャイの居場所を聞いてもらった。バンコクから車で1時間以上もかかる僻地で悠々自適に暮らしていることがわかり、私はさっそく通訳を伴い、チャチャイのもとに向かった。
3度の世界タイトル奪取を成し遂げ、「タイの英雄」と称されていたチャチャイは、私たちを笑顔で迎え入れてくれた。しかし、帰国便の出発時間が迫っていたため、私はチャチャイに十分な話を聞けることなく、早々に空港に向かっている。
「チャチャイにもっと話を聞きたい」と私が再びタイを訪れたのは、その翌1989年のこと。そして、このとき思わぬ出会いがあった。
バンコクのラジャダムナン・スタジアムでタイの国技ムエタイを観戦中、2万人の大観衆の中に、どうも気になって仕方がない人物を見つけたのだ。スポーツ刈りだった頭髪は七・三に分けられ、精悍だった顔つきにも丸みが帯びている。当時の面影は失せていたが、私は迷いを振り払うと、彼に近づき、片言の英語でこう聞いた。
「もしかしたら、あなたはボクシングの元世界チャンピオンじゃないですか?」
「イエス」
「大場政夫を知ってますか?」
「イエス。もちろんだ」
彼の名は、ベルクベック・チャルバンチャイ。大場から世界フライ級タイトルを奪取された、当の本人だったのである。
大場の死のわずか23日前、大場と激闘を演じたチャチャイ。大場が世界の頂点への踏み台にしたベルクレック。この二人との思わぬ邂逅から、私は大場政夫についての本格的な取材を始め、のちに『大場政夫の生涯』(東京書籍刊)のタイトル(小学館文庫では『首都高に散った世界チャンプ』)で初出版にこぎつけている。
ここから私のノンフィクション作家としての歩みが始まったが、これも足を使った現地取材、対面取材があったからこその歩みに他ならない。
雑談から得た執筆のヒント
印象深いことはまだある。私は昨年夏、『「孤独」という生き方』(光文社新書)を上梓した。私の山暮らし体験を含めて、世間の喧噪から隔絶された山奥で「孤独」に憩う人々を取材したものだが、その過程で大分県北部に位置する耶馬渓という景勝地を訪ねている。
私が得たのは、明治時代に建てられた当地の古民家を二人の女性が賃貸したという情報だった。二人の女性が交互にその古民家を訪れ、それぞれの「孤独」を謳歌しているのだろう。そう勝手に判断して、わざわざ足を運んだが、話を聞いてみると、自然療法サロンを経営する女性が新鮮な野菜や果物を有機栽培で育て、それをサロンの会員に提供することを目的にして借りたのだという。もう一人の女性はその会員だったが、どう考えても「孤独」をメインテーマとする同書と内容がマッチしていない。
「私たちの話、参考にならないんじゃないですか?」
女性の一人も聞いてきた。
「そうです」とも言えず、私は一通りの話だけは聞くことにした。
取材後は3人で雑談に興じた。
その雑談で私は2016年11月、先妻との最愛の息子を病で亡くしたことを伝え、そのことが同書を書く導火線となっていることを強調した。
「息子さんのお話を聞いてるうちに……」と女性の一人が言い出したのは、ややあってからである。
「さっきから、私の目の前に野球のボールのようなものが見えるようになったんです。縫い目が見えるから硬式ボールかしら」
私は驚いた。息子は小学校2年から大学卒業まで野球に打ち込んできた。自宅の仏壇に飾る息子の遺影の前には、私たち父子の心をつないだ硬式の野球ボールも置かれている。
「それが大事、僕の宝物。息子さん、そうお父さんに伝えてほしいと言ってますよ。野球が大好きだった、と」<
女性はこう口にすると、さらに息子のメッセージを伝えてくれた。
「野球ではまっとうすることができなかったけど、アームレスリングでまっとうすることができた。やり切ったし、すごく楽しかった。そう言ってます。人生に悔いはないとも言ってますよ」
大学の硬式野球部時代を、右肩を痛めた息子が不完全燃焼で終えたことは私も知っている。そのことで息子が未消化感を抱き続けてきたのも、何となく気がついていた。その未消化感を何らかの手段で解消したかったのだろう。息子が本格的なアームレスリング競技に打ち込むようになったのは、よりによって末期のがんが発覚してからだった。
病んだ肉体を鼓舞するかのように激しいトレーニングに打ち込んだ息子は、日本選手権など強豪集う大会に十数回出場し、準優勝2回と3位入賞2回の成績を残した。
トレーニングは死の3日前まで続けられ、息子が2勝1敗と勝ち越したライバルは、息子の死後、日本選手権の軽量級で日本王者に上り詰めている。
「人生に悔いはない」「楽しかった」というメッセージが、すべてを物語っていた。優勝こそなかったが、息子は勝敗よりも、自分のこの世における存在意義を、アームレスリングを通して完結させたかったのだ――。
そう思って涙ぐむ私に、女性がまた声をかけてきた。
「光で顔ははっきり見えませんが、顔のようなものの背後に、緑が輝いているのが見えます。深い緑の光ですよ」
「緑」という言葉が、私の山暮らしを想起させた。私は息子の死後、世間の喧噪から逃れるため、まず誰もいない秘境の禅寺にしばらく籠もると、次に緑豊かな山中に自分の庵を構えた。その過程で、徐々に癒やされていった私の心……。
「もしかしたら、本当に息子が父親を山の奥に連れてきてくれたんですか? これは、何となくですが、ずっと感じてきたことです」
私の問いかけに、女性が静かにうなずいた。
「そうだよと、息子さん、笑って言ってますよ。ようやく納得してくれたの? って。息子さんはどうやら、お父さんやお母さんだけでなく、たくさんの人をサポートしているようですね。それが自分の使命だとも感じているようです」
私はしばらく声も出なかった。徒労に終わるかに見えた対面取材。それが、結果的に同書の核となる情報をもたらしてくれたのだ。
時間と経費をかけた足を使った対面取材が、こうした意味のある副産物を生み出すのは、珍しいことではない。お互いの情感の交流によって育まれた信頼関係が、そこに芽生えるからなのだろう。
コロナ禍に晒される今、それに対する警戒心もわからなくはない。しかし、警戒するあまり人間相互の心の絆まで遠ざけようとするのは、果たして私たちにとって得策なのか。
その先で待ち受けているのは、排他的で陳腐な孤立化した人間社会なのではないか、と私には思えてならない。
東京大学名誉教授で仏教学や日本思想史を専門とする末木文美士氏は、その著書『死者と霊性の哲学』(朝日新聞出版)の中で、<コロナは従来の価値観を大きく転換させることになった>として、次のように記している。
<生身の接触が控えられる中で、インターネットの普及によるバーチャルな人間関係が推進される。「他者」は身体性を失い、画面の中に現れる見せかけの存在に変わる。他者との「絆」は、アプリを消せば消えてしまうはかないものでしかない>
(文=織田淳太郎/ノンフィクション作家)