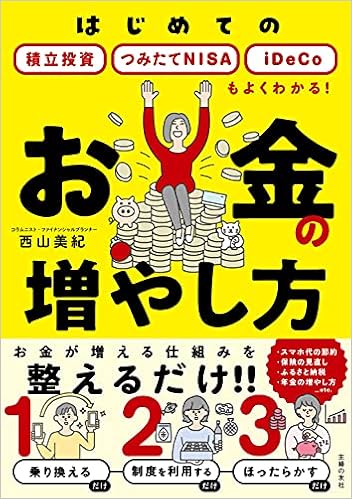資産運用はつみたてNISAから?物価高でやらないと損する7つの対抗策

食品を中心に、身の回りのモノの値上がりが止まりません。玉ねぎを手に取れば「3個ではなくて、1個の値段?」と驚き、お菓子を手に取れば「なんだか軽い……」とさみしい気持ちになる日々ではないでしょうか。
電気やガスも値上がりが続き、東京電力の2022年7月の電気料金は、平均的な家庭では前年7月の平均料金から1898円アップして8871円。東京ガスも同様に、前年7月の平均料金から1192円アップして5886円と発表されています。
モノやサービスの値段が上がっても、同じスピードで収入はなかなかアップしていかない昨今。そんななか、私たちがどんな対策を取れるのか、7つのポイントをお伝えします。
1■「スマホ代」を見直す
モノの値段が上がると「そもそも買い物を我慢したほうがいいの?」と感じてしまいますが、日々流動的に出ていくお金(流動費)ではなく、真っ先に見直したいのが「固定費」です。
固定費とは、毎月ほぼ一定額出ていくお金のことで、その一つに「スマホ代」が挙げられます。
スマホの料金プランやキャリアについて、何年も見直していない人も多いのではないでしょうか。家にいる時間が増え、Wi-Fiを使う時間が多ければ、契約データ容量を減らせるかもしれません。また、オプションのうち使わなくなったものをカットすれば、数百円セーブできます。
最近は、大手キャリアの格安プラン、別ブランドのほか、格安SIMなど、スマホ代が安くなる選択肢も増えています。ずっと大手キャリアのスマホのまま見直しをしていない人は、それらに変更するだけで月数千円セーブできる可能性大です。家電量販店にはさまざまな会社のスマホが並んでいるので、今週末にでもチェックしに行ってみてはいかがでしょうか。
2■「電気料金」を見直す
他の固定費として「電気料金」も挙げられます。最近、特に電気料金はどんどん高騰していますので、見直しの効果は高いでしょう。
まずは、契約アンペア数が大きすぎないかを確認しましょう。一人暮らしなら20~30A、家族住まいや電気を多く使う人なら40~60Aが目安です。ドライヤーや電気ケトル、乾燥機など、たくさんの電力を必要とするものを同時に使わないようにすれば、ブレーカーを落とすこともなく、低めのアンペア数でも問題ないかもしれません。契約アンペア数を一つ下げることで、月の基本料金が数百円安くなります。
また、電力自由化によって自分で電力会社を選べるようになりました。「エネチェンジ」などのサイトで現在の電気料金や電気の使い方などを入力すると、自分の使い方に合った安い電力会社を調べることができます。さらに、そのままネット上で電力会社の乗り換えもできますので、一度調べてみましょう。
3■「自炊」に励み、食品ロスを防ぐ
食材が高くなっているとはいえ、外食するよりは食材を買って家で料理をしたほうが安くなるのが一般的です。これまで外食やテイクアウトが多かった人は、家で料理をする機会を増やしてみましょう。
多めにつくって1食分ずつ冷凍しておければ、疲れて帰ってきて料理ができないときにも助かります。小麦を使った製品が値上がりしていますが、お米の値段は比較的落ち着いていますので、お米をメインに考えるのもよいでしょう。
また、食材を買いすぎて使い切れなかったり、冷蔵庫の奥に押し込んで気づかずに傷んでしまったりすると、食材もお金ももったいないもの。「買ったものは使い切る」という意識を持ち、使い切れなさそうなものは早めに冷凍保存をするか、多めに料理をつくってから保存するようにしましょう。
4■外食は「記憶に残るもの」に絞る
自炊をがんばるとはいっても、時々は外食を思いきり楽しみたいもの。外食は回数が増えすぎると、楽しさやおいしさに慣れてしまい、ありがたみを感じなくなってしまう側面があります。
そこで、外食をするときには、自分が「記憶に残りそうな食事やシーンに絞ること」がおすすめです。
家ではつくれないようなメニューを選んだり、何かのご褒美として、また誰かと一緒のときなどに絞ったりして、「あのときの外食は楽しかったな、おいしかったな」と振り返れるような、そんな楽しい外食の機会にしたいものです。回数を減らせば外食費を抑えられますし、楽しめる外食ならストレス解消にもなって、余計な支出を防ぐことにもつながるでしょう。
5■ふるさと納税を利用する
すでにふるさと納税をしている人も多いと思いますが、「今年こそ」と思いながら、まだチャレンジしていない人もいると思います。ふるさと納税は、地方自治体に寄付をすることで、一定額までの税金が軽くなり、実質2000円の自己負担で地方の特産品を受け取れるという仕組みです。
お米やお肉、魚介類、フルーツなどの食品を選べば、さまざまな地域のおいしさを楽しみながら、食費を浮かせることにもつながります。ふるさと納税の人気が集中するエリア以外からも選ぶことで、さまざまな地域活性化にも貢献できると思います。
6■収入アップの機会を常にうかがう
がんばって支出を減らすことには、やはり限界があります。入ってくるお金が増えるように、収入アップへの意識を高めていくことも非常に大切です。
たとえば、同じ職種でも他業種に転職することで、仕事の内容はそれほど変わらなくても給与が増えるケースも多々あります。最近は30~40代の転職も増えていますので、同世代の親しい人で転職経験者がいれば、話を聞いてみるのもよいでしょう。リモートで話ができるツールも増えてきたので、気軽に相談しやすいかもしれません。
情報を教えてもらい、何かお礼をしたいと思ったときには、直接会わなくてもアマゾンやスターバックスなどのデジタルチケットを活用する方法もあります。
また、会社によっては、資格取得で月数千円の手当が出るケースもあります。そのほか福利厚生が充実している場合もあるため、一度会社の制度を調べてみることをおすすめします。
7■資産運用にも着手する
超低金利の今、自分の資産を銀行に預けているだけでは、なかなか増えません。利息がつく以上に物価が上がっていく状況なので、他の資産運用を取り入れることも大切です。
特に円安が進む今、資産が日本円だけ(円の預貯金だけ)という人は要チェックです。海外の経済成長を取り込めるような資産運用も検討してみましょう。
といっても、今後どの国の経済が伸びていくのかは、確実にわかるものではありません。そのため、たとえば全世界の株式に投資するようなコストの低い投資信託を、月1000円や3000円などコツコツと積み立てていくのも一案です。
5年、10年と長く積み立てていくことで、途中で価格が下がったとしても、割安でたくさん買えることになり、価格が上がったときに資産を増やすことができるでしょう。つみたてNISAにある投資信託のラインナップならコストが安いものがそろっていますので、選びやすいと思います。
以上、物価上昇に対抗するための7つの方法をお伝えしました。「どんどん値上がりしている……」と感じる日々ですが、一つでも行動できれば不安な気持ちも和らぐはずです。できることから、ぜひ取り組んでみてください。