個人事業主・中小企業向け給与計算ソフト徹底比較2025──無料ツールの紹介も!

給与計算業務は、毎月の正確な処理と頻繁な法改正への対応が求められる、企業にとって非常に重要な業務です。本記事では、最新の給与計算ソフトを徹底比較し、無料プランから個人事業主、中小企業、中堅企業向けまで、事業規模ごとにおすすめのソフトをご紹介します。
目次
給与計算ソフトとは?他ツールと比較して見える機能と役割の違い
給与計算ソフトは、従業員の給与計算に関わる一連の煩雑な作業を自動化し、効率化するために開発された専門ツールです。毎月の勤怠データに基づく総支給額の計算から、社会保険料や税金の控除、さらには給与明細の発行に至るまで、正確かつ迅速な処理が可能になります。
給与計算ソフトの基本機能
給与計算ソフトには、以下のような機能が備わっています。これにより、人事・労務担当者の負担を大幅に軽減し、より戦略的な業務への集中を可能にします。
給与・賞与計算
勤怠情報や各種手当、控除項目に基づき、月々の給与や賞与を自動計算。
社会保険・労働保険計算
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などを最新の保険料率で自動計算。被保険者負担分と会社負担分を算出。
所得税・住民税計算
所得税の源泉徴収額や、各従業員の住民税額を計算・管理。
年末調整
扶養控除等申告書の情報に基づき、年間の所得税の過不足を精算する年末調整を計算。
給与明細発行
計算結果に基づき、Web明細や紙の明細書として出力。
Excelとの違い|ミス削減と法令自動アップデート
多くの企業で利用されているExcelでも給与計算は可能ですが、手作業による入力ミスや計算式の誤り、頻繁な法令改正への対応漏れといったリスクが常に伴います。
| 比較ポイント | Excelでの給与計算 | 給与計算ソフト |
|---|---|---|
| 計算・集計 | 手入力や複雑な関数設定が必要。 ヒューマンエラーが発生しやすい傾向がある。 |
勤怠データ等を取り込み、各種手当・控除を含め自動計算。 計算ミスを大幅に削減。 |
| 法令改正対応 | 税率や保険料率の変更の都度、手動で計算式やマスターデータを更新する必要がある。 対応漏れのリスクが高い。 |
法改正(税率、保険料率の変更など)に自動でアップデート対応 常に最新の法令に基づいた計算が可能。 |
| データ管理・共有 | ファイルの破損・紛失リスク 複数担当者での同時編集や共有、権限管理が難しい場合がある。 |
従業員情報や給与データを安全に一元管理。 アクセス権限設定により、セキュリティを確保しつつ情報共有。 |
| 明細発行・配布 | 給与明細の作成・印刷・封入・配布に手間とコストがかかる。 | Web給与明細機能により、ペーパーレス化を実現。 従業員はPCやスマートフォンからいつでも明細を確認可能。 |
給与計算ソフトの導入により、計算業務の正確性が向上し、迅速な法令対応が可能になります。
会計ソフトとの違い|仕訳自動連携で経理を簡素化
会計ソフトも経理業務において不可欠なツールですが、給与計算に特化した機能は限定的です。給与計算ソフトと会計ソフトを連携させることで、経理業務全体の効率化が期待できます。
| 比較ポイント | 会計ソフト | 給与計算ソフト |
|---|---|---|
| 給与計算の専門性 | 勤怠管理や複雑な手当計算、年末調整など、詳細な給与計算機能は持たない場合が多い。 | 給与計算に特化した機能を網羅。 |
| 法令対応の範囲 | 会計関連の法改正には対応。 給与計算に直接関わる法改正への迅速な対応は専門外となることがある。 |
労働関連法規(労働基準法、最低賃金法など)や社会保険制度の改正に迅速に対応。 税制改正にも対応し、常に最新の法令に基づいた給与計算が可能。 |
| 仕訳連携 | 給与計算結果を会計ソフトに手入力する必要がある。 二重入力の手間や転記ミスが発生しやすい。 |
計算された給与データを会計ソフト用の仕訳データとして自動生成し、出力。 手入力の手間を省き、経理業務の負担を軽減。 |
| 人事労務情報 | 従業員の詳細な人事情報の管理には適していない。 | 従業員マスタで人事労務情報を一元管理。 給与計算だけでなく、社会保険手続きや労務管理にも活用可能。 |
給与計算ソフトで計算された人件費や預り金などのデータを会計ソフトにスムーズに連携することで、月次決算の早期化や経理業務の精度向上に繋がります。
給与計算ソフト導入のメリット
給与計算ソフトを導入することは、単に計算作業を楽にするだけでなく、企業経営全体に多岐にわたるメリットをもたらします。ここでは主な4つのメリットをご紹介します。
1. 作業時間短縮と手計算ミス防止
勤怠データの取り込みから、各種保険料や税金の自動計算、給与明細の発行までを自動化。手作業による計算ミスや入力漏れを防ぎ、大幅な時間短縮。
2. 法令改正対応とコンプライアンス強化
頻繁に行われる健康保険料率や雇用保険料率の変更、所得税法改正などに自動でアップデート対応。常に最新の法令に基づいた正確な給与計算を行えるため、企業のコンプライアンスを強化。
3. 電子申請・脱ハンコでDX推進
社会保険や労働保険に関する各種手続きの電子申請(e-Gov連携など)に対応。行政手続きのオンライン化を促進し、ペーパーレス化・脱ハンコによるIT化を促進。
4. 社員セルフサービスで問い合わせ削減
従業員が自身のPCやスマートフォンから給与明細や源泉徴収票を閲覧・ダウンロードできる機能を提供。人事担当者への問い合わせ対応業務を削減し、従業員の利便性も向上。
給与計算ソフトの選び方|失敗しない7つのチェックポイント
自社に最適な給与計算ソフトを選定するためには、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。ここでは、導入後に後悔しないために7項目に分けてチェックポイントを解説します。
事業規模と将来の従業員数見込み
企業の成長フェーズや従業員数によって、最適なソフトの機能や処理能力は異なります。現状だけでなく、将来的な展望も考慮して選びましょう。
チェックポイント
- 現在の従業員数、および1~3年後の従業員数の見込みに対応できるか。
- 従業員数の増減に柔軟に対応できる料金プランやシステム体系か。
- アルバイト・パート、正社員、役員など多様な雇用形態に対応できるか。
導入形態(クラウド / インストール)
給与計算ソフトには、インターネット経由で利用する「クラウド型」と、PCにインストールして利用する「インストール型(デスクトップ型)」があります。それぞれの特性を理解し、自社の運用スタイルに合った形態を選びましょう。
チェックポイント
- クラウド型の場合、利便性や法改正時の自動アップデートが自社に適しているか。
- デスクトップ型の場合、オフラインでの利用や、買い切り型によるコスト管理のメリットが自社に適しているか。
- セキュリティポリシーやIT環境は、どちらの導入形態に適しているか。
料金体系とコストバランス
提供される機能と料金のバランスは、ソフト選定において非常に重要です。初期費用だけでなく、月額(または年額)のランニングコスト、オプション費用なども含めて総合的に比較検討しましょう。
チェックポイント
- 初期費用、月額(または年額)費用は予算の範囲内か。
- 従業員数に応じた従量課金がある場合、コストの見通しは明確か。
- 年末調整や社会保険手続きなどのオプション機能は別料金か、標準搭載か。
- 利用したい機能と料金のバランスは適切か。
電子申請・社会保険対応範囲
特定の社会保険手続きにおいて電子申請が原則義務化されており、ソフトがどの範囲まで対応しているかは重要な選定基準です。
チェックポイント
- 社会保険や労働保険の電子申請に対応しているか。
- マイナンバーの収集・保管・利用に関する機能は安全かつ適切か。
- 入退社手続きや各種変更届など、必要な行政手続きをカバーしているか。
勤怠・会計など他ツールとの連携
給与計算は、勤怠管理や会計処理といった他の業務とも密接に関連しています。既存システムとの連携の可否やスムーズさは、業務効率を大きく左右します。
チェックポイント
- 利用中の勤怠管理システムから勤怠データをスムーズに取り込めるか。
- 給与計算結果を会計ソフトと簡単に連携できるか。
- API連携などのシームレスな連携方法は提供されているか。
サポート・社労士連携の有無
導入時の設定や操作方法、法改正時の対応など、疑問点やトラブルが生じた際のサポート体制は重要です。また、専門家である社労士との連携機能も確認しましょう。
チェックポイント
- 電話、メール、チャットなど、利用しやすい問い合わせ方法があるか。
- サポートの対応時間やFAQ、マニュアルは充実しているか。
- 導入支援や初期設定サポートは提供されているか。
- 顧問社労士とデータ共有や連携ができる機能はあるか。
セキュリティ対策
給与情報やマイナンバーといった機密性の高い個人情報を取り扱うため、セキュリティ対策の万全さは最重要項目の一つです。
チェックポイント
- 通信の暗号化、データのバックアップ体制は整っているか。
- アクセス権限設定や操作ログの記録など、内部不正対策は講じられているか。
- 第三者認証(ISMS認証など)を取得しているか。
- 提供事業者の個人情報保護方針やセキュリティポリシーは信頼できるか。
無料プランがある給与計算ソフト
フリーウェイ給与計算
出典:公式サイト
「フリーウェイ給与計算」は、従業員5名まで永久無料で利用できるクラウド型給与計算ソフトです。6名以上の場合でも月額1,980円(税抜)の定額制で、中小企業や個人事業主のコスト負担軽減を目的としています。シンプルで分かりやすい操作性と、法令改正への自動対応が特徴です。
| 提供形態 | クラウド |
|---|---|
| 主な機能 | 給与計算、明細のメール配信、全銀協規定フォーマットでの振込データ出力、年末調整、社会保険関連帳票作成 |
| 主な連携サービス | フリーウェイシリーズ、NTTデータ「年調・法定調書の達人」 |
| 料金プラン | 無料版:0円 (5名まで) 有料版:1,980円/月~ (税抜、6名以上人数無制限) |
| 無料トライアル | 無料版として無期限利用可能 |
特徴
- 従業員5名まで完全無料
- 初心者にも優しいシンプルな画面設計と操作性
- クラウド型で法令改正(税率・保険料率変更など)に自動アップデート対応
ジョブカン給与計算

出典:公式サイト
ジョブカン給与計算は、給与計算業務の自動化と効率化を実現するクラウド型ソフトです。ジョブカンシリーズの勤怠管理システム等と連携し、従業員情報や勤怠データを自動で取り込める点が強みです。複雑な給与規定にも対応し、Web明細発行によるペーパーレス化も推進できます。
| 提供形態 | クラウド |
|---|---|
| 主な機能 | 給与計算、Web明細発行、年末調整、従業員管理、書類作成 |
| 主な連携サービス | ジョブカンシリーズ |
| 料金プラン | Freeプラン:0円(5名まで、機能制限あり) 有料プラン:400円/ユーザー/月~ (税抜) |
| 無料トライアル | 30日間 |
特徴
- ジョブカンシリーズ連携による給与計算業務の大幅な効率化
- 多様な雇用形態や複雑な給与規定・手当設定への柔軟な対応と自動計算
- Web給与明細・Web源泉徴収票機能によるペーパーレス化と利便性向上
個人事業主・スタートアップにおすすめの給与計算ソフト(~従業員50名程度)
マネーフォワード クラウド給与
 出典:公式サイト
出典:公式サイト
マネーフォワード クラウド給与は、従業員の勤怠情報などをもとに給与計算を自動で行うクラウド型のシステムです。割増賃金や各種手当、所得税といった複雑な計算を自動化し、業務効率化できます。また、法改正に伴う変更が自動でシステムに反映されるため、常に最新の法令・税制に対応した給与計算が可能となり、計算ミスの防止にもつながります。
| 提供形態 | クラウド型 |
|---|---|
| 主な機能 | 給与・賞与計算、各種保険料・所得税の自動計算、Web給与明細・賞与明細、年末調整書類作成、給与計算確定前の前月比較 |
| 主な連携サービス | マネーフォワード クラウドの各種サービス、他社サービス |
| 料金プラン | スモールビジネスプラン(3名以下):月額4,480円~(税抜、年額払いプラン) その他、従業員規模に応じたプランあり。詳細はお問い合わせ。 |
| 無料トライアル | 1ヶ月間 |
特徴
- 法令準拠の自動計算と法改正への自動アップデート対応
- Web給与明細によるペーパーレス化とコスト削減
- マネーフォワード クラウドの各種サービスとの連携による業務フロー全体の効率化
freee 人事労務
 出典:公式サイト
出典:公式サイト
freee 人事労務は、給与計算を含む人事労務業務を効率化するためのクラウド型システムです。勤怠データや従業員情報を一元管理することで、給与計算に必要な情報を自動で集計し、転記作業に伴うミスや工数の削減につながります。給与計算だけでなく、Web給与明細の発行・配布、年末調整、入退社手続き、マイナンバー管理といった幅広い労務業務に対応しています。
| 提供形態 | クラウド型 |
|---|---|
| 主な機能 | 給与・賞与計算の自動化、各種保険料・所得税・住民税の自動計算、Web給与明細・賞与明細の作成・配布、勤怠管理、マイナンバー収集・管理 |
| 主な連携サービス | freeeの各種サービス、他社サービスとのデータ連携 |
| 料金プラン | ミニマムプラン(法人向け):月額2,000円~(税抜、年払いプラン) その他、従業員規模や用途に合わせたプランあり。詳細はお問い合わせ。 |
| 無料トライアル | 30日間 |
特徴
- 給与計算を含む労務業務の一元管理と自動化による効率向上
- Web給与明細によるペーパーレス化とコスト削減
- 法令・税制改正への自動対応とエラーチェック機能による計算ミスの防止
やよいの給与 24+ クラウド
 出典:公式サイト
出典:公式サイト
「やよいの給与計算 24 +クラウド」は、主に従業員数20名程度の事業所向けに設計されており、給与計算、社会保険・労働保険関連の処理、年末調整といった給与業務に必要な主要機能を搭載しています。初心者でもスムーズに給与明細書の作成や年末調整作業を行えるよう、操作画面やナビゲーション機能が工夫されている点が特徴です。
| 提供形態 | デスクトップソフト (+クラウド機能) |
|---|---|
| 主な機能 | 給与計算、賞与計算、年末調整、マイナンバー管理 |
| 主な連携サービス | 税務申告ソフトとの連携に対応。その他については要お問い合わせ。 |
| 料金プラン | セルフプラン付き初年度優待価格:32,000円~(税抜) その他プランは要お問い合わせ。 |
| 無料トライアル | 30日間 |
特徴
- 給与計算業務の簡易化と入力ミス軽減をサポートする操作画面
- 初心者でも安心な「年末調整ナビ」によるスムーズな年末調整業務の実現
- 法令改正への対応と「あんしん保守サポート」(初年度無料)による充実したサポート体制
ジンジャー給与
 出典:公式サイト
出典:公式サイト
「ジンジャー給与」は、jinjer株式会社が提供するクラウド型人事労務システム「ジンジャー」の給与計算モジュールです。月次給与、賞与、退職金の計算、年末調整、Web給与明細の発行といった業務の自動化と効率化を目的としています。計算や処理を自動化することで、人為的なミスを最小限に抑えた給与管理を実現し、利用社数は18,000社を突破しています。
| 提供形態 | クラウド型 |
|---|---|
| 主な機能 | 給与計算、賞与計算、年末調整、各種帳票出力 |
| 主な連携サービス | ジンジャー製品群、外部連携サービス |
| 料金プラン | 初期費用+月額300円~/ユーザー(税抜) |
| 無料トライアル | 1ヶ月間 |
特徴
- 人事情報や勤怠情報に基づく計算式設定による給与計算の自動化と効率化
- Web給与明細発行によるペーパーレス化と従業員の利便性向上
- 他のジンジャーシリーズ製品とのデータ連携による人事労務業務全体の効率化
中小・中堅企業におすすめの給与計算ソフト(従業員50名〜)
SmartHR 労務管理
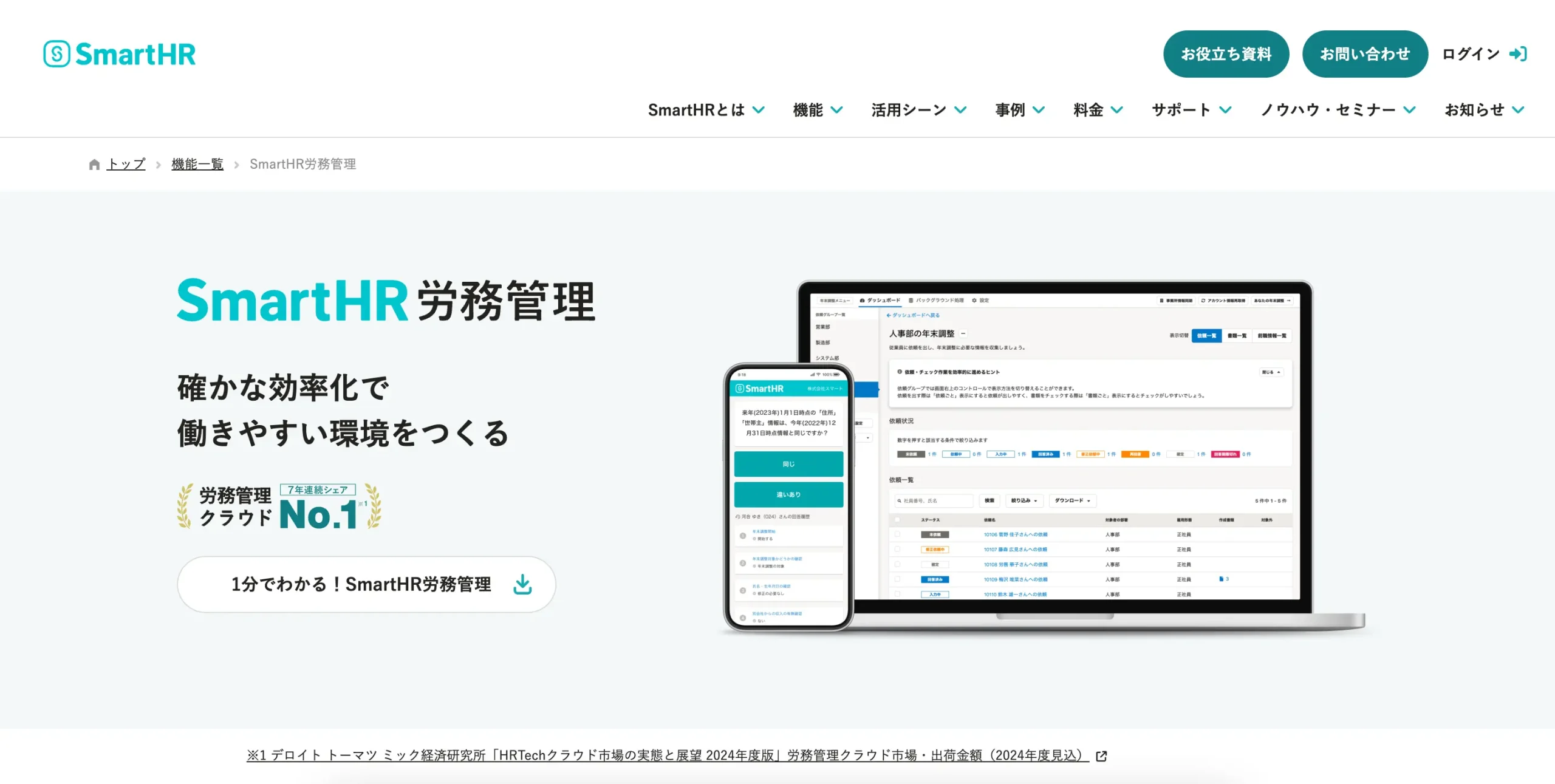 出典:公式サイト
出典:公式サイト
「SmartHR労務管理」は、人事・労務手続きの効率化とペーパーレス化を目的としたクラウド型人事労務ソフトです。給与計算機能も提供しており、従業員情報の一元管理や勤怠管理機能と連携することで、給与・賞与明細の作成・配付業務を効率化できます。特に、労務手続き全般のオンライン化とペーパーレス化に強みを持ち、従業員とのやり取りをシステム上で完結させられます。
| 提供形態 | クラウドサービス |
|---|---|
| 主な機能 | 給与明細作成・配付、賞与明細作成・配付、勤怠管理、年末調整 |
| 主な連携サービス | 他の給与計算ソフト、Slack、NAVITIME API連携 |
| 料金プラン | 複数プランあり。要お問い合わせ |
| 無料トライアル | 15日間 |
特徴
- 給与・賞与明細のペーパーレス作成・配付による業務効率化とセキュリティ向上
- 勤怠データの効率的な収集・管理と給与計算へのスムーズな連携
- 労務手続きと連携した従業員データの一元管理による正確性と作業時間短縮
給与奉行iクラウド
 出典:公式サイト
出典:公式サイト
「給与奉行iクラウド」は、給与計算から社会保険・年末調整に至る給与業務プロセス全体のデジタル化を支援するクラウドシステムです。従来の給与奉行の使いやすさを維持しつつ機能が充実しており、税率や法改正によるプログラム更新も自動で行われます。従業員情報の自動更新や手当計算、社会保険料、所得税の自動計算機能などを備え、給与明細の電子配付や各種電子申請にも対応し、業務のペーパーレス化と効率化ができます。
| 提供形態 | クラウド |
|---|---|
| 主な機能 | 給与処理、賞与処理、明細書配付・振込、年末調整 |
| 主な連携サービス | 奉行製品、カオナビ、ShiftMAXなど |
| 料金プラン | 月額5,500円~(税抜、年間契約) その他複数プランあり。要お問い合わせ。 |
| 無料トライアル | 30日間 |
特徴
- 企業独自の給与体系や複雑な手当計算に対応する精度の高い自動計算機能
- 従業員情報の自動更新、勤怠データの一括取込、計算結果の効率的な確認機能
- 給与明細の電子化、保険や年末調整の電子申請によるペーパーレス化推進
PCA 給与シリーズ
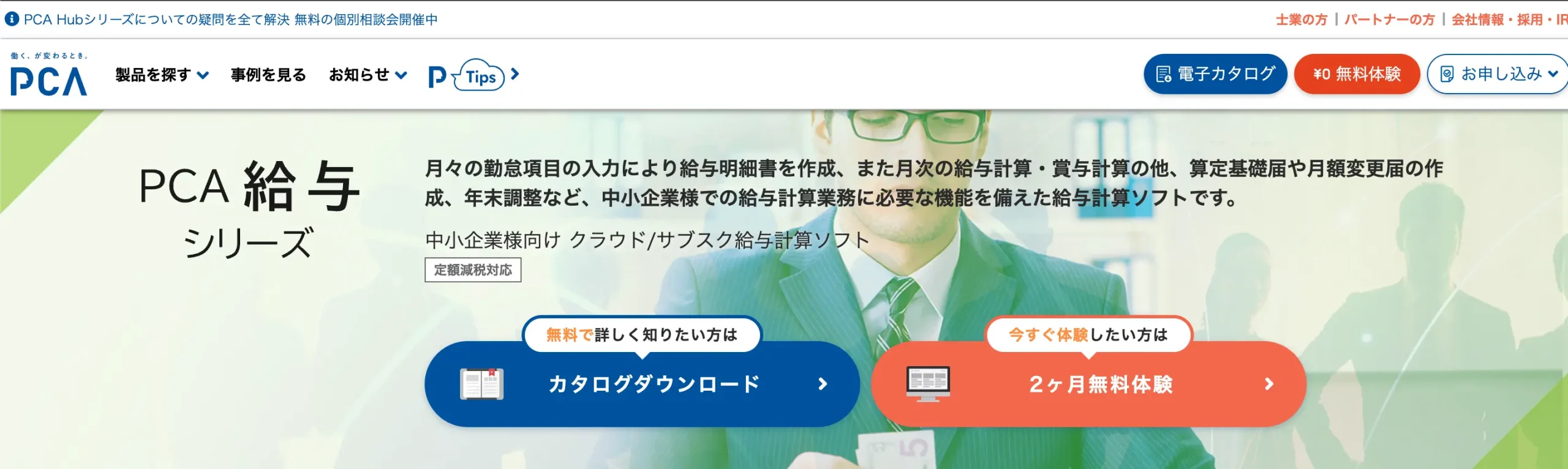 出典:公式サイト
出典:公式サイト
PCA 給与シリーズ(『PCAクラウド 給与』など)は、中小企業向けの給与計算ソフトです。月々の勤怠入力による給与明細作成、月次給与・賞与計算、算定基礎届・月額変更届作成、年末調整といった給与計算業務に必要な機能を備えています。プランによっては初期費用がかからず、定額減税にも対応しています。柔軟な給与体系設定や法定業務への対応、他システムとの連携が特徴です。
| 提供形態 | クラウド、サブスク(オンプレミス) |
|---|---|
| 主な機能 | 月次給与計算、賞与計算、給与明細書作成、年末調整、勤怠管理システム連携 |
| 主な連携サービス | PCAシリーズ、各種会計ソフト、e-Tax/eL-TAX |
| 料金プラン | PCAサブスク 給与 dx:月額6,160円~(税込) その他複数プランあり。要お問い合わせ。 |
| 無料トライアル | 2ヶ月間 |
特徴
- 柔軟な給与体系設定と計算機能
- 法定業務対応と電子申請・電子申告機能
- PCA人事管理シリーズや勤怠管理システムなどとの連携による業務効率化
ProActive C4 人事給与
 出典:公式サイト
出典:公式サイト
「ProActive C4」は、会計、人事給与、経費、勤怠管理などの基幹業務をカバーするクラウドERPシステムです。その人事給与モジュールは、月例給与や賞与の計算、社会保険・労働保険の手続き、年末調整といった給与関連業務全般に対応しています。多様な人事制度や雇用形態に応じた報酬計算が可能で、サブスクリプションモデルで提供され、初期費用を抑えつつ利用できます。
| 提供形態 | クラウドERP |
|---|---|
| 主な機能 | 月例給与計算、賞与計算、年末調整、電子申請対応、有給休暇管理 |
| 主な連携サービス | ProActive勤怠管理システム、既存勤怠管理システム、e-Gov、駅すぱあと |
| 料金プラン | 要お問い合わせ |
| 無料トライアル | 要お問い合わせ |
特徴
- 多様な給与体系への対応と法制度への迅速な追随
- 包括的な給与関連業務支援と昇給・賞与シミュレーション機能
- 年末調整の電子化、給与明細のWeb化などによるペーパーレス化
給与計算を取り巻く最新トレンド
電子申請の原則義務化(2025年1月)
2025年1月1日以降、労働者死傷病報告や就業規則変更届など労働安全衛生法系の届出は電子申請が義務化されました。紙提出は「やむを得ない場合」の例外扱いに縮小され、手続き対応の迅速化が企業側に求められます。
給与計算ソフトも e-Gov API 連携や入力支援サービスとの連動が標準装備か否かが実務コストを左右し、今後は年度更新・算定基礎届への拡大が予想されています。
マイナンバー管理&セキュリティ要件の高度化
2024年4月改正で個人情報保護法ガイドラインの対象が「個人データ」から「個人情報」全体へ拡大し、漏えい時の報告義務と本人通知が強化されました。
マイナンバーを扱う給与計算領域では、多要素認証、アクセスログ監査、暗号化ストレージが“事実上の必須要件”に。監査対応の負荷からオンプレ型を避け、ISMS取得済みクラウドへの移行を急ぐ企業が増えています。
クラウド化×コスト最適化の急伸
総務省調査では100名以上を雇用する民間企業の78%がクラウドサービスを利用し、そのうち約48%が給与・財務会計・人事領域に適用しています(「令和5年通信利用動向調査の結果」より)。中小企業向けでは月額3,000〜5,000円のサブスク型サービスの利用が広がり、法改正対応やWeb明細機能をベンダー任せにできる点が評価されています。
一方、弥生株式会社が従業員100名未満の中小企業を対象にした調査では、国内全体の給与ソフト導入率は4割強にとどまり、非導入層へのクラウド浸透余地も大きいことから、市場は今後2〜3年でクラウド比率6割超へ伸長すると見込まれます。
よくある質問
Q: 給与計算ソフトの導入には、どのくらいの費用がかかりますか?
A: 無料プランから、従業員数や機能に応じて月額数千円~数万円まで様々です。初期費用がかかる場合もあります。料金体系(月額、年額、従量課金など)を確認し、自社の予算と必要な機能のバランスを見ることが重要です。
Q: 無料の給与計算ソフトと有料のソフトの違いは何ですか?
A: 無料プランは多くの場合、利用できる従業員数や機能に制限があります(例:年末調整非対応、サポート限定など)。複雑な処理や手厚いサポート、高度な連携機能などを求める場合は有料プランが適しています。
Q: パソコン操作に不慣れでも、給与計算ソフトは使えますか?
A: 近年、多くのクラウド型ソフトは直感的なインターフェースで、専門知識がなくても操作しやすいように設計されています。無料トライアルやデモを利用して、実際の操作感を試してみることをお勧めします。
Q: クラウド型とインストール型、どちらを選ぶべきですか?
A: クラウド型は法改正への自動対応、場所を選ばないアクセス、初期費用の抑制がメリットです。インストール(デスクトップ)型はオフラインでも利用可能、買い切り型ならランニングコストを抑えられる場合があります。自社のネット環境や利用スタイルに合わせて選びましょう。
Q: 給与計算ソフトを導入すれば、社会保険労務士は不要になりますか?
A: ソフトは計算や手続きを効率化しますが、専門的な労務相談や複雑な個別ケースへの対応、就業規則の作成・変更などは社労士の専門領域です。ソフトによっては社労士との連携機能を持つものもあります。必要に応じて、ソフト導入と並行して社労士への相談も検討しましょう。
Q: Excelでの給与計算からソフトに移行したいのですが、データ移行は簡単ですか?
A: 多くのソフトでは、従業員情報などをCSVファイルで一括インポートできる機能があります。ただし、ソフトによって手順や対応フォーマットが異なるため、導入前に確認が必要です。サポート体制が整っているソフトを選ぶと安心です。
Q: 導入するタイミングはいつが良いですか?
A: 年度の切り替わり(1月や4月など)や、社会保険の算定基礎届の提出時期(7月)などに合わせて導入すると、キリが良い場合が多いです。ただし、準備期間も考慮し、余裕をもって導入を進めることが重要です。
Q: マイナンバーの管理は安全ですか?
A: 多くの給与計算ソフト(特にクラウド型)は、アクセス制御、暗号化、ログ監視など、法令に準拠した厳格なセキュリティ対策を講じています。導入前に、提供事業者のセキュリティポリシーや対策内容を確認しましょう。
Q: 勤怠管理ソフトや会計ソフトとの連携は必須ですか?
A: 必須ではありませんが、連携することで勤怠データの自動取り込みや仕訳データの自動作成が可能になり、大幅な業務効率化とミス削減につながります。現在利用しているソフトがある場合は、連携の可否や連携のスムーズさを確認することをお勧めします。
Q: 電子申請が原則義務化されましたが、ソフトを使えば対応できますか?
A: はい、多くの給与計算ソフトは社会保険や雇用保険に関する手続きの電子申請に対応しています。ソフト上で作成したデータを、e-Gov等のシステムと連携して申請できます。対応範囲(どの手続きに対応しているか)はソフトによって異なるため、確認が必要です。
まとめ
本記事では、給与計算ソフトの基本機能から選び方のポイント、具体的な製品比較、そして最新トレンドまで幅広く解説しました。無料プランを提供するソフトから、特定のニーズに応える高機能なソフトまで、選択肢は多岐にわたります。
本記事で紹介した情報を参考に、まずは自社の現状と課題を明確にし、必要な機能や予算を整理することから始めましょう。
多くのソフトでは無料トライアルが提供されていますので、気になるソフトを実際に試用し、操作感やサポート体制を確認することをおすすめします。バックオフィス業務の効率化に留まらず、従業員の満足度向上や、企業全体の生産性向上に向けて、最適な給与計算ソフトを導入しましょう。







