ガバメントクラウド移行で自治体の年間コストが5.7倍に…計画の重要性
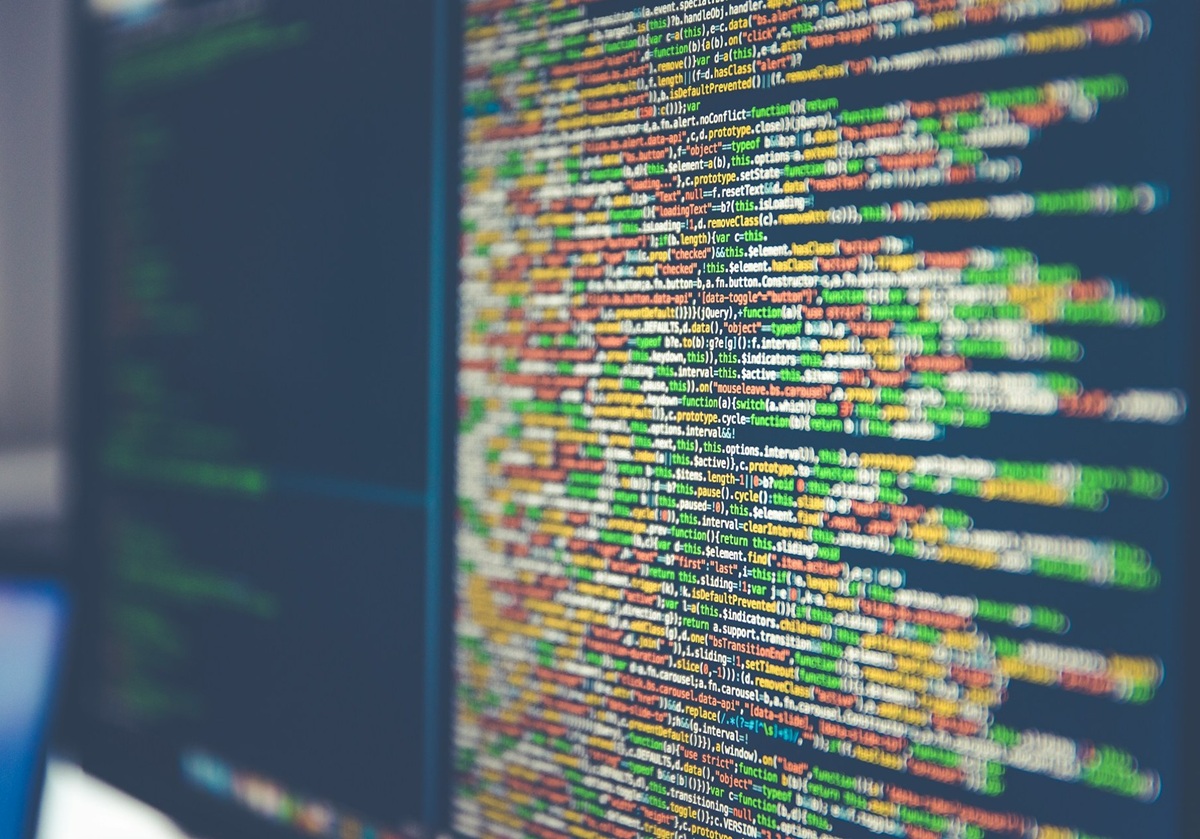
●この記事のポイント
・ガバメントクラウド移行、国は経費3割削減としていたが、実際には平均で2.3倍に
・標準化から移行まで本来は10年ほど必要なところ、猶予は5年ほどしかないのが要因
・民間企業でもクラウド移行では現行システムの整理・変更が不可欠
これまで個別でシステムの開発・運用を行ってきた全国の自治体は、今年度(2025年度)内をメドにシステムをデジタル庁が整備する「ガバメントクラウド」に移行させる必要がある。システムの共通化により行政のデジタル化を進めることが狙いであり、デジタル庁は自治体が負担するシステム運用経費が18年度比で3割削減されるとしていたが(目標値)、実際には平均で2.3倍、最大で5.7倍になっていることが問題視されている。システム開発会社役員は「民間企業でもコスト削減を目的にクラウドに移行したところ、トータルでみると運用コストが上がってしまうというケースはあり、国だけの問題ではない」と指摘する。なぜ、このような事態が起きているのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
国の定める標準仕様の増大により開発・保守費用が肥大化
21年に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、原則として自治体は25年度内に行政システムの標準化とガバメントクラウドへの移行を求められている。基幹業務システムの統一・標準化が目的であり、標準化対象事務は住民基本台帳、戸籍の附票、固定資産税、介護保険、国民年金など計20。デジタル庁はガバメントクラウド導入の目的について「人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています」と説明している。具体的には以下のとおり。
・標準化基準への適合などにより、ベンダロックインを回避し、アプリケーションレベルにおける複数の事業者による競争環境を確保する
・制度改正や突発的な行政需要への緊急的な対応等のために標準準拠システムを改修する必要がある場合には、地方公共団体が個別に対応する負担を軽減するとともに、当該改修の範囲を最小限にし、かつ、迅速に改修を行えるようにする
・地方公共団体がシステムを自ら整備・管理する負担を軽減する
・高い水準のセキュリティを担保する
・基幹業務システムからのデータの取り込みを円滑に行うことが可能となり、迅速な国民向けサービスの開始に寄与する
問題となっているのは、自治体のコスト負担の増大だ。デジタル庁は「標準準拠システムへの移行完了後に、2018年度比で少なくとも3割の削減を目指す」としていたが、中核市市長会は1月、デジタル庁と総務省に「地方公共団体情報システム標準化に関する緊急要望」を提出。そのなかで以下のように訴えている。
・中核市における移行前の運用経費の平均は3億3800万円である。これに対して、移行後の運用経費の平均は6億8400万円、平均倍率2.3倍に大幅に増嵩し、5割以上の自治体で2倍以上の増、最大で5.7倍にもなっている。
・平均で3億4600万円、最大で8億700万円も運用経費が増大するのは、中核市にとって大きな痛手であり、重い負担である。
・国の定める標準仕様の増大により開発・保守費用が肥大化したこと、またシステムの肥大化と相まって、当初期待されたガバメントクラウド利用の低減効果が得られなかったことも十分に想定される。
・調査結果からはガバメントクラウドの利用による運用経費の低減効果は確認できない。
突貫工事ゆえにさまざまな不都合
なぜ運用コストの増加が生じているのか。立命館大学情報理工学部教授の上原哲太郎氏はいう。
「自治体システムの標準化を進めるために、政府が高いセキュリティレベルのシステム基盤を構築して、そこに自治体のシステムを集約していき、運用コストも抑制するという方針は合理的といえます。
運用コスト増大の大きな要因としては、もともとの計画に無理があったことがあげられます。標準化から移行まで本来は最低でも10年ほど必要だろうとされてきましたが、法律が施行されてから移行までの猶予は5年と決められてしまいました。まず各自治体がオンプレミスで運用している現行システムを標準化してから、それを徐々にクラウドに移行していくというのが、あるべき形であり、大きくコストを低減できる進め方ですが、ワークフロー・仕様の整理・見直しを含めて現行システムの標準化をしっかりやろうとすれば、それだけで5年くらいかかります。それを移行まで含めてすべて5年でやろうとしているので、突貫工事ゆえにさまざまな不都合が生じて、それを抑え込むための費用が発生してコストが増大していると考えられます。
時間が限られるため、少なくない自治体がオンプレミスで運用しているシステムをストレートにそのままクラウドに移行しているとみられますが、それだとクラウドへの移行のメリットは出ず、コストダウンにつながりにくいです。
また、セキュリティレベルの引き上げも要因としては考えられます。これまで各自治体のシステムのセキュリティレベルはバラバラで、なかにはそれほど高くない自治体もあったかもしれませんが、クラウドへの移行に伴い全自治体が一律で非常に高いセキュリティレベルに合わせる必要があるので、その対策のためのコストは発生してきます。また、移行作業に伴い大きな手間と一時的なコストも必要となってきます」
では、将来的に自治体が負担する運用コストが徐々に下がっていくということは期待しにくいのか。
「とりあえずは期限が法律で決められた以上、移行を急がなくてはいけないということで一時的にはコストが増大するものの、移行前よりも運用コストが高いという状態が続くということは許されないでしょうから、今後はコスト抑制の方策について議論がなされ、中長期的には徐々に下がっていくという展開になるのではないでしょうか」
安易にクラウドへ移行しようとすると、逆にコストが増大
システム開発会社役員はいう。
「このケースは国に限った話ではない。民間企業でもクラウドへの移行で運用コストを下げるためには、現場の業務プロセスの見直しも含めて現行システムの整理・変更が不可欠となってくる。全社的な協力・取り組みが必要となり、そこに手を付けずに安易にクラウドへ移行しようとすると、逆にコストが増大したり運用が煩雑になってしまう」
デジタル庁は「ガバメントクラウド整備のためのクラウドサービス」として「Amazon Web Services(AWS)」「Google Cloud」「Microsoft Azure」「Oracle Cloud Infrastructure」「さくらのクラウド」を認定している。
(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=上原哲太郎/立命館大学情報理工学部教授)










