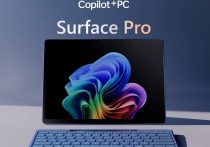年間で数万時間の業務効率化…Copilot活用で大きな成果を上げている企業の特徴をマイクロソフトに聞いた
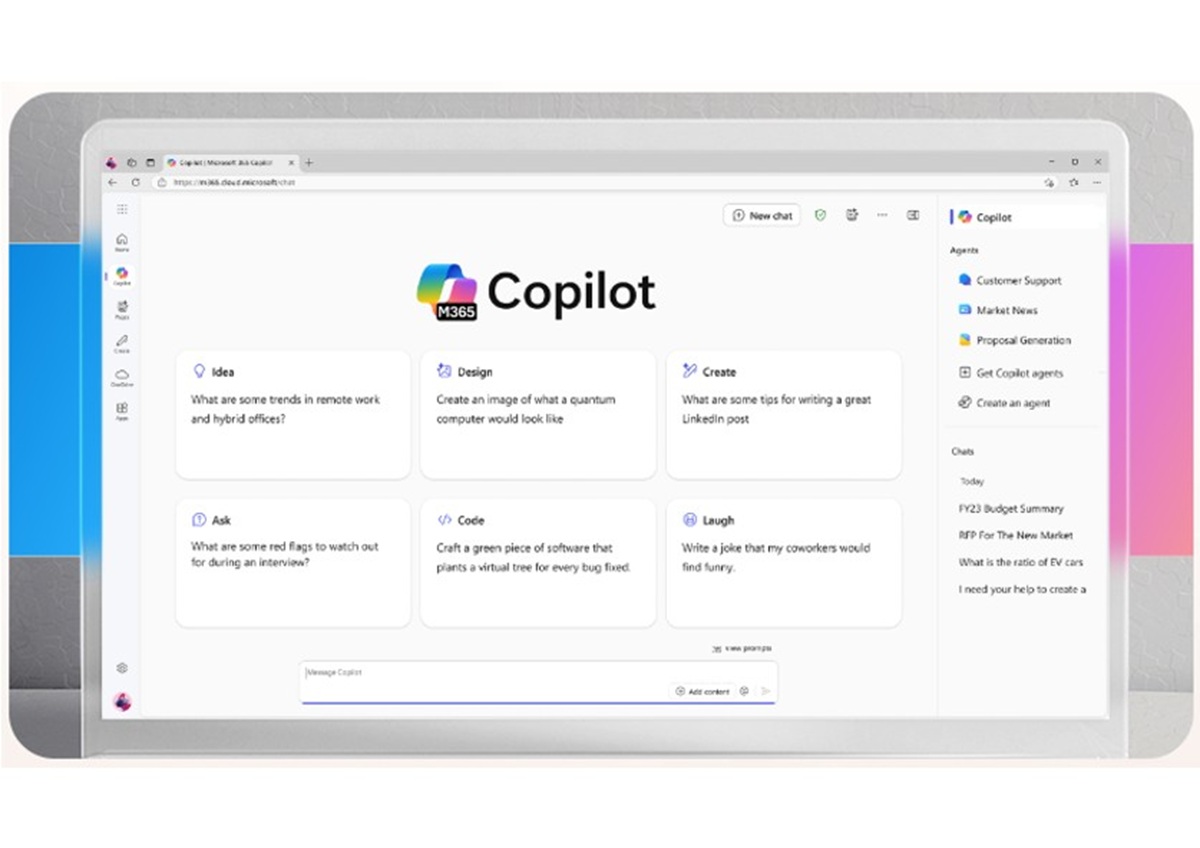
●この記事の特徴
・Microsoft 365 Copilotは代表的な日本企業の8割以上が導入し、幅広い領域で業務効率向上に活用
・業務効率によって生まれた余剰時間を新サービスの企画検討など創造的な業務への注力に活かす企業も
・JCBはCopilot導入後に1人あたり月平均約6時間の業務時間削減が確認された
2023年のリリースから約1年半が経過したマイクロソフトのAIアシスタント「Microsoft Copilot」。リリース後も続々と新機能が追加され、今年4月には、パソコンの画面データを記録し続け、AIで処理して画面に映っていたテキスト情報を検索できる機能、「リコール(Recall)」の提供が開始された。Copilotファミリーの中で一般法人向けのMicrosoft 365 Copilotは代表的な日本企業の8割以上が導入し、幅広い領域で業務効率向上に活用されており、一人あたりの業務時間が月平均約6時間削減されたり、会社全体で年間で数万時間の業務効率化が実現されたケースも出ている。業務効率によって生まれた余剰時間を新サービスの企画検討など創造的な業務への注力に活かす企業も出ているというが、Copilotの活用で大きな成果を生んでいる企業は、どのような方法・施策・工夫を行っているのか。また、Copilotの機能・能力を最大限活かす方法とは何か。マイクロソフトに取材した。
●目次
部門や職種を問わず発生する一般業務に対応
Copilotの契約プランは大きく分けて、無料版の「Microsoft Copilot」、一ユーザー当たり月額3200円のサブスクリプション「Microsoft Copilot Pro」、法人向けの同4497円(年払い)の「Microsoft 365 Copilot」がある。今回は法人向けのMicrosoft 365 Copilot(以下、Copilot)についてみていく。Teams、Word、Outlook、PowerPoint、Excelなどのアプリケーションを提供するMicrosoft 365 スイートとシームレスに統合され、職場の生産性と創造性を高めるツールであり、たとえばレポートに基づいてPowerPointスライドのプレゼンテーションを作成したり、Teamsで会議とチャット スレッドを要約したりする。現在、日本においてCopilotを導入している事業者はどれくらいあるのか。マイクロソフトは次のように説明する。
「日本は、Microsoft 365 Copilotの活用において世界を牽引する市場の一つであり、日経225(日経平均株価の算出に用いられる代表的な日本の企業)の85%以上の企業(2025年3月時点)が利用しています。 多くの企業様が業務効率化や生産性向上を目的に導入を進めており、他のどの新しいMicrosoft 365 スイートよりも、最も速いスピードで採用が進んでいます」
Copilotを導入した企業では、具体的にどのような業務効率の成果が生じているのか。
「Microsoft 365 Copilot を導入した企業の多くでは、まず日常的な業務における汎用タスクから活用を始め、業務効率の向上を実感されています。特に、Teams 会議の内容把握や議事録作成、Outlook でのメールの下書きや要約、Word や PowerPoint における資料作成・編集支援、Copilot Chat を活用した社内外情報の検索・収集などが、導入初期から広く利用されています。
これらの機能は、営業、マーケティング、人事、財務、法務など、部門や職種を問わず発生する一般業務に対応しており、結果として多くの企業で大規模展開のきっかけとなっています。また、Microsoft 365 アプリ内に組み込まれていることで、既存の業務環境の中で自然に Copilot を活用できる点も、定着を後押ししており、日常業務の質とスピードを同時に向上させる手段として、広く支持されています」(同)
日本製鉄、年間で数万時間の業務効率化が見込まれている
特に大きな成果が生じている事例としては、どのようなケースがあるのか。
「Copilotを導入した企業では、主に『会議の議事録作成』『メール要約』『ドキュメント作成支援』『社内情報検索』などの機能が日常業務で活用され、業務効率化に大きな成果を上げています。例えば、JCB様では、Copilot導入後の月間平均利用率が83%と高く、特に会議関連業務(議事録作成・要約・内容把握)での活用が進み、1人あたり月平均約6時間の業務時間削減が確認されました。
また、日本製鉄様では、Microsoft 365 Copilotを試験導入後、1カ月で会議メモの自動作成やメール要約、社内ファイルからの知見抽出などで業務効率が向上し、その成果として年間で数万時間の業務効率化が見込まれています。
これらの事例に共通するのは、Copilotが既存のMicrosoft 365アプリ(Word、Excel、PowerPoint、Teamsなど)に自然に統合されているため、従業員が日常業務の延長でAIを活用できる点です。特に、情報収集や文書作成の初期段階をAIが支援することで、心理的ハードルが下がり、業務のスピードと質が向上しています」(同)
気になるのは、大きな効果を上げることができている企業は、どのような方法・施策・工夫によって実現できているのかという点だ。
「Copilotの導入で大きな成果を上げている企業は、単なる業務時間の削減にとどまらず、AI活用による新たな価値創出に注力されています。例えば、JCB様では、Copilotの活用を『業務変革』の一環と位置づけ、段階的な導入と社内文化の醸成を両立させる施策を展開しています。具体的には、PoC(概念実証)段階で多様な職種・年齢層からユーザーを選定し、定量・定性のアンケートを実施。これにより、1人あたり月平均6時間の業務効率化に加え、ロールプレイやアイデア創出をはじめとする、企画・創造性の高い業務の補助としても活用し、社員の日常的な働き方に変化が生まれたそうです。また、Copilot活用を促進するために、社内にて『週次Tips配信』や『社内コミュニティサイト』の運営を通じて、ユーザーの自発的な活用を支援。特に、プロンプト共有機能の活用により、業務に即した使い方のナレッジが蓄積され、社内全体のAIリテラシー向上と活用の裾野拡大につながっています。
一方、日本製鉄様では、生成AIの活用を全社DX戦略に組み込み、Copilotを導入、会議メモの自動生成やメール要約、社内ファイルからの知見抽出などにより業務効率を大幅に向上させました。生成AIの活用を定着させる取り組みとして、Microsoft Teams を使って Copilot に関する情報発信や利用者同士の情報共有を行うコミュニティづくりなどを実施。これらの施策が、生成AIの定着と業務効率向上の鍵となったと伺っています。今後は、各職場にCopilot活用を先導する『チャンピオン』を任命し、成功事例の共有と社内浸透を促進。さらに、効果が見込まれる『モデル職場』には優先的に導入し、成果を可視化。全社的な活用を支えるために、リテラシー教育やトレーニングも実施し、現場の不安や疑問を解消する体制整備を予定しているそうです。
これらの企業に共通するのは、『AIを使う文化』を育てるための仕組みづくりと、成果を可視化して社内に共有する工夫です。AI活用が単なる業務効率化にとどまらず、創造的なアウトプットの促進や知の共有を通じて、組織全体の働き方と価値創出の質を高めているという点が、Copilot活用の真価といえるでしょう」(同)
企業の競争力強化やイノベーション創出に直結
では、 業務効率の向上によって、業務時間の削減やコスト削減につながる事例というのは、あるのか。
「Copilotの導入によって、多くの企業が業務時間やコストの『削減』だけでなく、新たな価値やイノベーションの『創出』に取り組まれています。前述のJCB様が注目しているのは、単なる時間短縮ではなく、その『空いた時間をどう活かすか』です。JCB様では、Copilotによって生まれた余剰時間を、提案資料の質向上や新サービスの企画検討など、より創造的な業務への注力に活かされています。
また、日本製鉄様では、Copilot導入によって年間数万時間の業務効率化が見込まれる一方で、AIを活用した新たな業務プロセスの創出にも注力しています。例えば、現在重要なテーマとして注力されているのが、法務、保全など業務特化型 AI エージェントの活用です。長い歴史の中で培ってきた社内の暗黙知を、生成 AI により発掘して活用することです。経験の浅い従業員も的確かつ迅速な判断が可能になるだろうと期待を寄せて頂いています。人材不足、ベテランの知見消失といった課題を克服し、競争力の向上が図れることに意義を感じていると伺っています。
このように、Copilotの導入は単なる『効率化ツール』ではなく、『創造性を引き出すパートナー』として機能しており、企業の競争力強化やイノベーション創出に直結する成果を生み出しています」(同)
「実はこういう機能を、こう使うと非常に便利」というような機能があれば知りたいところだ。
「Copilot の中でも、最近注目されているのが『AI エージェント(以下、エージェント)』の活用です。これは、特定の業務や部門に特化したAIアシスタントを構築できる機能で、従来の汎用的な生成AIの枠を超え、業務プロセスに深く組み込まれた支援が可能になります。弊社はお客様に提供するサービスをまずはマイクロソフトの社員が徹底的に使いこなし提案することを重視しており、エージェントの活用事例も続々と共有されています。
例えば、社内の問い合わせ対応では、情報検索や回答作成に時間がかかるという課題に対し、エージェントが質問の整理や応答を支援することで業務時間を削減するなど、大きな効果を上げています。また、営業と技術部門の連携においては、属人的だったナレッジをエージェントが可視化・共有することで、工数の削減と案件への対応力強化につながっています。
さらに、営業活動では、顧客情報の収集や提案準備といった時間のかかる業務をエージェントが支援することで、営業担当者の作業削減を実現し、生まれた時間で顧客との対話時間を増やし会話の質を上げるといった効果にもつながっています。また、会社や業界独自の専門用語をエージェントに知識として読み込ませておくことで、翻訳作業の精度を上げるといった実務に寄り添ったユースケースが登場しています。これらの事例は、Copilot Agent が業務フローの中に自然に組み込まれ、個人・チーム・組織全体の生産性向上に貢献していることを示しています。今後も、部門ごとの課題に応じた柔軟な活用が広がっていくと期待されています」(同)
Researcher とAnalyst
最後に、Copilotの機能拡張・追加の最新状況と計画について聞いた。
「Copilotの機能拡張に関しては、4月下旬にMicrosoft 365 Copilot Wave 2 Springという形で、Copilotへの新たな『エージェント』機能追加を発表しました。これらのAIエージェント機能は、ユーザーの業務をより適切かつ、幅広く支援するために設計された役割別のAIエージェントです。主なエージェントとしては、『Researcher(リサーチャー)』『Analyst(アナリスト)』『Interpreter(インタープリター)』などがあります。
Researcher とAnalystは、Copilotに搭載された推論型エージェントです。Researcherは、複雑な調査業務を自動化します。社内外の情報を横断的に収集・要約し、たとえば『競合分析』『業界トレンド調査』『クライアント向け準備』『プロジェクトの状況把握』などに活用可能です。Analystは、複雑なデータ分析を自動化します。OpenAIのモデルを活用し、Pythonコードを使ってデータを段階的に読み解き、仮説を立てながら検証・修正し、最適な結論を導きます。たとえば、複数のExcelからの需要予測、購買パターンの可視化、収益予測などに活用され、迅速かつ高精度な意思決定を支援します。
※ResearcherやAnalystは、2025年5月末より一般提供開始されています。
Interpreterは、Microsoft Teams会議における多言語コミュニケーションを支援するAIエージェントです。参加者は自分の母国語で話し、他の参加者はそれをリアルタイムで自分の言語で聞くことができます。同時通訳のような体験を提供し、話者の声を模倣する音声合成機能により、自然で一体感のある会話を実現する。グローバル会議や営業・サポート対応、経営層のメッセージ発信などに活用され、言語の壁を越えた会議環境を支えます。ユーザーの同意取得や管理者による制御、通知機能など、プライバシーとガバナンスにも配慮されています。日本語対応は現在パブリックレビュー中で、今後一般提供が予定されています。
マイクロソフトが働き方のトレンドを年次で発表している2025 Work Trend Index では、人とAIエージェントの適切な組み合わせを活用して業務を遂行する組織概念の登場が示唆されました。AI (エージェント)を、単なる業務の効率化や生産性の向上ツールとしてだけではなく、新たなイノベーション創出を目指すチームの1メンバーとして、どのように活用していくべきかというフェーズに移行しつつあります。その中で、Copilotは業務の支援ツールとしてのAIアシスタントから、知的生産性を高める頼もしい『同僚』として、そしてAI(エージェント)の新たなUIとして、さらに進化していくことが期待されます」(同)
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)