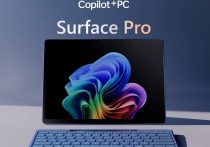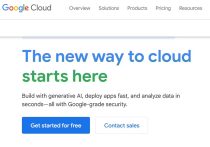マイクロソフトの新AIエージェントは熟練のデータサイエンティストのように働いてくれる

●この記事のポイント
・米マイクロソフトの新AIエージェント「Researcher」「Analyst」の提供が開始された
・役割特化型ゆえに必要な作業に対する的確さや回答の深度で優位性を発揮する
・他社AIに比べて企業利用のハードルが低く、導入後すぐに実業務に組み込みやすいという優位性
米マイクロソフトの新AIエージェント「Researcher」「Analyst」の提供が開始された。米OpenAIの「deep research」と「Microsoft 365 Copilot」の機能を組み合わせたResearcherは、調査業務に特化しており、「Salesforce」などと連係して外部データを取り込める。米OpenAIの「o3-mini」をベースに開発されたAnalystはデータ分析に特化している。“AIエージェントバブル”と呼ばれるほど次々と新たなAIエージェントがリリースされるなか、マイクロソフトの新AIエージェントはどのような特徴や強みを持つのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
●目次
- 企業データとのシームレスな統合、高度な推論能力と専門特化
- マーケティングリサーチ・市場分析、経営戦略・事業企画
- 留意すべきポイント
- より高度な自律性とプロアクティブな提案、専門領域の拡張とチームAIの登場
- 山本大平氏の経歴とAIについての実績
企業データとのシームレスな統合、高度な推論能力と専門特化
まず、他社のAIエージェントと比較して、どのような独自性や優位性があるのか。F6 Design 株式会社 代表取締役で戦略コンサルタント兼データサイエンティストの山本大平氏は次のように説明する。
「他社の類似 AI、例えば Google の Gemini、OpenAI の GPT 系モデル(ChatGPT)、Anthropic の Claude などと比べて、いくつか独自の強みがあると感じています。データサイエンティストの視点から主なポイントを挙げますね。
・企業データとのシームレスな統合
最大の特徴は、Microsoft 365環境に深く組み込まれており、ユーザーの社内データと外部のウェブ情報を統合して活用できる点だと思います。たとえばResearcherは社内のメールや会議メモ、ファイル、チャットなどから文脈を抽出しつつ、ウェブ上の公開情報や競合他社のデータも収集・選別して、分かりやすいレポートを自動生成してくれます。社内データだけでなくSalesforceやServiceNow、Confluenceといった外部サービスの情報源とも連携できるため、社内外の情報を横断した包括的な調査が可能になるんです。
従来のChatGPTなど単体の汎用AIでは、こうした企業内システムとの連携は標準では備わっておらず、追加のカスタマイズが必要でした。その点、ResearcherとAnalystはMicrosoft Graph経由で企業内のあらゆるデータソースにアクセスでき、業務に即したパーソナライズされたサポートを提供してくれる、ここは大きな強みと感じています。
・高度な推論能力と専門特化
これらのエージェントはOpenAIの先進モデルをベースにしつつ、それぞれ調査特化(Researcher)と分析特化(Analyst)という役割にチューニングされているようです。特にAnalystは、OpenAIの先進的な高性能モデルをベースに連鎖的な思考推論(Chain-of-Thought)により問題を段階的に解析していくのが特徴だと聞いています。
熟練のデータサイエンティストのように考え、必要に応じてPythonコードを自動で実行しながら複雑なデータクエリにも対応できるんですね。例えば散在する複数のスプレッドシートから売上データを集計し、新製品の需要予測や顧客購買パターンの可視化、収益予測までを数分で行ってくれるとのことです。これはまさに社内に自動データアナリストがいるようなもので、他社の汎用AIにはない強みと言えるんじゃないでしょうか。
確かにOpenAIのChatGPTも高度なデータ分析モード(Code Interpreter改め『Advanced Data Analysis』機能)でコード実行は可能になっていますが、AnalystはMicrosoft 365上で直接それを実現し、処理過程のコードをリアルタイムで可視化してユーザーが検証・学習できる点で優れていると思います。一方、Researcherも強力なモデルにMicrosoft独自のオーケストレーションを組み合わせており、ウェブ上の膨大な情報を取捨選択して出典付きのレポートをまとめる能力に長けています。GoogleのGeminiやOpenAIのGPT-4なども非常に高い汎用推論能力を持ちますが、Microsoftのエージェントは役割特化型ゆえに必要な作業に対する的確さや回答の深度で優位性を発揮する、ここは期待できるポイントだと感じています。
・エンタープライズ向けの安心感
Microsoftが提供するという点も大きな差別化要素ですよね。企業向け製品としてセキュリティやプライバシーへの配慮がなされており、各社のテナント内で完結して動作するため機密データも安心して扱えるそうです(Microsoft 365 Copilotの一部として提供)。また、利用にあたっての管理機能や監査機能も整備されているようで、企業規模での展開に適していると感じます。これに対し、GoogleのGeminiはマルチモーダル(テキスト・画像・音声・動画をネイティブに扱える)かつ最大100万トークン(今後200万に拡大予定)の長大なコンテキストウィンドウを持つ先進的なモデルで、ある意味では技術的に非常に強力ですが、現時点では主にGoogle Bardなどの形で提供されており、企業内システムとの直接統合という点ではMicrosoftに一日の長があるのではないでしょうか。
AnthropicのClaudeも最大10万トークンもの文脈保持が可能で、大量の文書を一度に解析する用途に優れています。しかしClaudeやChatGPTを企業で使う場合、機密情報を外部クラウドに出すリスク管理や、社内データとの接続には追加の工夫が必要です。その点、ResearcherとAnalystはMicrosoftのビジネスプラットフォーム上で動作する内製エージェントという位置付けで、他社AIに比べて企業利用のハードルが低く、導入後すぐに実業務に組み込みやすいという優位性があるように感じます」
マーケティングリサーチ・市場分析、経営戦略・事業企画
ResearcherとAnalystの具体的な活用方法や期待される効果として、どのようなものが考えられるのか。
「私自身、これらのAIエージェントが活躍できる分野は幅広いと感じていますが、特に可能性を強く感じる領域をいくつか挙げてみます。
・マーケティングリサーチ・市場分析
企業のマーケティング部門では、市場動向や競合分析、新規事業のアイデア出しなどリサーチ業務が多岐にわたりますよね。Researcherは社内の営業データや顧客フィードバックと、ウェブ上のニュースや統計データを掛け合わせて包括的な市場レポートを作成できるため、マーケティング担当者の強力なアシスタントになるのではないでしょうか。例えば新製品を企画する際に、競合他社の動向や顧客ニーズのトレンドを短時間で洗い出し、エビデンスに基づいた戦略立案までを支援してくれると期待できます。その結果、企画提案の精度向上や意思決定のスピードアップが見込まれると視ています。
・経営戦略・事業企画
経営企画やコンサルティングの現場でも、大量の情報収集と分析が欠かせません。Researcherは社内の経営データ(財務報告や会議議事録など)と外部の業界レポートを統合し、新規事業の立ち上げ計画や市場参入戦略のドラフトを作成することができます。私も戦略コンサルタントとして膨大なリサーチを行ってきましたが、その初期調査の部分をAIに任せられれば、人間はより創造的な課題設定や意思決定に注力できるようになっていきます。Analystも財務データのシミュレーションやKPIの傾向分析を自動化してくれるため、経営判断に必要なインサイトを迅速に得られるでしょう。こうした経営戦略分野でAIエージェントを使うことで、戦略立案のスピードと質が飛躍的に向上し、競争優位の獲得につながると期待しています。
・データ分析業務全般(需要予測・業績分析など)
データサイエンティストやアナリストの日常業務にも大きな恩恵があると思ってます。Analystは散在するデータを統合して高度な分析を行うのが得意で、例えば販売データから自動で需要予測モデルを作成したり、顧客の購買パターンを可視化したりしてくれます。熟練の分析担当者でなくとも、現場のスタッフが自然言語で『来期の売上見通しは?』『この商品カテゴリーの顧客傾向は?』と質問すれば、Analystがコードを書いて分析結果を提示してくれるわけですよね。こうなるとデータ分析の民主化が進み、各部署が自分たちでデータに基づく意思決定を行えるようになってきます。結果として、予測精度の向上やビジネス機会の早期発見、さらには業務効率化(手作業の集計作業の削減)といった効果が期待できると思います。
・研究開発・イノベーション創出
製造業やIT企業のR&D部門でも、AIエージェントの活用余地は大きいのではないでしょうか。新技術の動向調査や特許・論文のサーベイといったリサーチ業務にResearcherが役立ちます。例えば製薬企業であれば、最新の医学論文や臨床試験データをResearcherが短時間で読み込んで要点を整理し、新薬開発のヒントを抽出する、といった使い方があります(これは各社が独自のシステムを作ってとっくにやっていると思っていますが)。
言いたいことは、人間が何日もかけて行う調査をAIが代行することで、イノベーションのサイクルを加速できるということです。またAnalystは研究開発の過程で得られる実験データの解析にも有用です。複雑な実験結果データから傾向や相関関係を見つけ出し、次のアクションプランを提案してくれそうです。これらにより研究開発の効率化とブレークスルーの創出が期待できます。
以上のように、マーケティングや戦略立案から日々のデータ分析、さらに研究開発に至るまで、知的生産活動のあらゆる場面でResearcherやAnalystは大きな可能性を秘めていると感じています。共通する効果としては、『必要な情報や示唆を素早く引き出せること』『分析の属人性を下げて組織全体の知見を底上げできること』が挙げられます。これは企業の競争力強化に直結するため、これから様々な分野で活用が進むはずです」
留意すべきポイント
AIエージェントの導入・活用を進める上で、企業が考慮すべき課題や注意点としてはどのようなものがあるか。
「AIエージェントを企業で導入・活用するにあたり、いくつか留意すべきポイントがあります。特にMicrosoftのResearcher、Analystを検討する際、特に次の課題に注意が必要と考えています。
・データのセキュリティとプライバシー
まず自社データをAIに扱わせる以上、情報漏洩や機密保持の対策は最重要です。幸いResearcherやAnalystはMicrosoft 365内部で動作し、学習モデルの基盤はあってもユーザー個別のデータが外部に共有されない仕組みになっています(企業テナント内で完結)。とはいえ、社内での権限設定や機密情報の取り扱いルールを明確にし、人事データや未公開情報など扱うべきでないデータをAIが参照しないよう管理することが必要になってきます。また、生成されたレポートに社外秘の情報が含まれる場合の取り扱いにも注意し、必要に応じて自社ポリシーを整備することが求められるはずです。
・出力内容の正確性・妥当性の検証
AIエージェントの回答は便利な一方で、誤った情報(いわゆる幻覚/Hallucination)が混入するリスクもあります。特に外部のウェブ情報を収集するResearcherは、ソースが信頼できるか吟味する目利きが必要ですね。マイクロソフトのエージェントは出典を明記してくれるので、人間がその出典を確認し検証するプロセスを省略しないようにしなければいけません。Analystの分析結果についても、『コードが動いているから安心』と鵜呑みにせず、結果の妥当性を業務知識と照らし合わせてチェックすることが重要だと思います。例えば予測結果が現場の肌感覚とかけ離れていないか、異常な値が出ていないか、人間がレビューする仕組みを組み込むと良いでしょう。要するに、AIを過信せず人間とのダブルチェック体制で品質を担保する姿勢が求められます。ただそのうち、ダブルチェックすらも別のAIと掛け合わせればAIだけで自動化できると思っています。
・社員のスキルセット・受け入れ態勢
新しいAIツールを導入しても、現場の社員が使いこなせなければ宝の持ち腐れです。そこで、社員に対する教育やトレーニングが課題になってくるはずです。自然言語で指示できるとはいえ、効果的なプロンプト設計のコツや、得られた分析結果を解釈して活用するリテラシーを高める必要があるのではないでしょうか。また、AIエージェントが仕事の進め方に与える影響について社内で理解を促し、心理的な抵抗を減らすことも大切だと思います。たとえば『AIが自分の仕事を奪うのでは? 私、要らなくない?』という不安が作業者の根底にあると現場への定着が進みません。そのため、『AIはあくまでアシスタントであり、皆さんの生産性向上を助ける存在』という位置づけを明確に伝え、人とAIの協働に前向きな社内文化を醸成することが留意点になってきます。意外にもAIの専門家ほど、AIを脅威に感じている方々が現場に多くいることを把握すらできていませんから。
・システム導入コストとROI
MicrosoftのResearcherやAnalystを利用するには、前提としてMicrosoft 365 Copilotのライセンス契約が必要になるはずです。現在は一部ユーザー向けのFrontierプログラムで先行提供されていますが、一般提供時には追加のライセンス費用が発生するのではないでしょうか。投資対効果(ROI)を考え、どの部署・業務で使えば費用に見合う効果が得られるかを事前に試算しておかないといけません。パイロット導入で小さく検証し、効果が確認できてから全社展開するステップを踏むのがお勧めでしょうか。
また、Microsoft以外のサービス(例えば社内でGoogle Workspaceを併用している場合など)とのシステム統合も検討事項になってきそうですね。Microsoft製品で統一されていればスムーズですが、他ツールのデータを取り込むにはMicrosoft Graphコネクタ等の設定が必要になると思うので、IT部門による技術的準備も課題となってきます。
・Microsoft製品特有の留意点
MicrosoftのAIエージェントは強力ですが、その能力に過度に依存しすぎないことも重要だと思っています。Microsoft 365のアップデートに伴い機能やUIが変わる可能性がありますし、自社の業務プロセス自体もAIに合わせて改善する視点が求められます。導入企業側では『まず業務フローやデータ基盤を整備し、その上でAIの力を最大限引き出す』という段取りを意識すべきです。特に日本企業では、古い形式のデータ(紙やPDF)や属人的なナレッジが多く残っているケースもあります。そうした情報資産をMicrosoft 365上に整理・蓄積しておくことで、ResearcherやAnalystが十分に活躍できる土壌ができます。また、Microsoftが提唱するガバナンス指針やベストプラクティスにも目を通し、自社環境に適用することが望ましいでしょう。要するに、ツール導入だけに頼るのではなく、人・プロセス・技術の総合準備が成功のカギとなります。
より高度な自律性とプロアクティブな提案、専門領域の拡張とチームAIの登場
今後、AIエージェント技術はどのように進化していくと予想されるのか。また、マイクロソフトのResearcherとAnalystがその進化の中でどのような役割を果たすと期待されるか。
「AIエージェントは今後ますます進化し、企業の働き方を大きく変えていくでしょう。私の見立てでは、Researcher、Analystも含め、将来的に次のような方向で発展すると考えています。
・より高度な自律性とプロアクティブな提案
現状のAIエージェントはユーザーからの指示や質問に応答する形ですが、将来的にはスケジューリングされた定期レポート作成や、異常値検知時のアラート発信など、エージェント側から主体的に提案・実行する場面が増えていくかと。例えばResearcherが毎朝関連業界のニュースを要約して経営陣に報告したり、Analystがリアルタイムの売上データを監視して目標未達の兆候があればアドバイスを送ったり、といった具合ですね。人間の『気付き』を待たずともAIが先回りして支援することで、意思決定のスピードがさらに加速すると思っています。
・専門領域の拡張とチームAIの登場
現在のResearcherとAnalystは主として調査と分析という2つの役割ですが、今後は他の専門エージェントも登場するかもしれません。例えば『Designer』のようにクリエイティブ制作に特化したエージェントや、『Assistant(事務)』のように定型業務を自動化するエージェントなど、企業内の職種ごとにAIエージェントが配備されるイメージです。そうなれば各エージェントが連携してチームとして協働し、一つのプロジェクトを人間とAIの混成チームで進めることも格段に増えていくでしょう。ここでいう協働は、AIを誰かが補助的に使うといったレベルではなく、あくまでAIをチームメンバーとして、つまり人格レベルで協働することを指します。MicrosoftはすでにOffice製品群にCopilotを展開していますが、将来的には複数のAIが連動してユーザーを支援するマルチエージェント体制が進化していくでしょうね。
・人間との協働による新たな価値創出
AIエージェントが高度化するほど、『人間に何が求められるか』といった問いの答えもさらに変化していくと考えています。単純な情報収集や分析作業はAIが担う一方で、人間は創造性や倫理的判断、最終意思決定といった領域により集中できるようになります。例えば戦略立案プロセスでは、AIが緻密なデータ分析に基づくオプションを提示し、人間が企業のビジョンや価値観に沿って最終判断を下すという分担が当たり前化するんじゃないでしょうか。これは単に効率化というだけでなく、より高次の付加価値を生むことにつながります。
私は、将来的にAIエージェントは『知のパートナー』ではなく『知のストライカー』として人間の思考を拡張し、自律して課題を発見し課題を解決していくプロセスまで担う存在になると考えています。ResearcherやAnalystはその先駆け、あるいはほんのきっかけとして、企業内におけるAI活用の成功体験を積み重ね、人とAIの協働モデルを確立する役割を担っていくと視ています。つまり、マイクロソフトのResearcher、Analystは、単なる新機能に留まらず働き方の未来を象徴する存在だと言えます。他社の強力なAIモデルとも切磋琢磨(競争)しつつ、企業現場で価値を発揮する実践解を提供してくれることを期待していますが、これはあくまでビジネス上の話です。一方で、未来的にはAIが人を使う時代になってしまうとも感じていて、少なからず恐怖も感じていますが、それについて今は考えないようにしています。兎にも角にもResearcher、Analystのような機能は大変有用ですが、“AI様”にしてみたら、ちょっとしたこと、に過ぎないのかもしれません。
山本大平氏の経歴とAIについての実績

山本氏の経歴とAIについての実績について聞いた。
「まず自己紹介を兼ねて経歴や知っていることをお話しします。私は新卒でトヨタ自動車にエンジニアとして入社し、新型車の開発に長く携わりました。内装モジュールの担当で、レクサスやカローラ、iQなどの内装品質の向上に取り組む技術者でした。その中でトヨタでは特にデータ分析による原因特定能力を鍛え、全トヨタグループで開催されるデータサイエンスの大会で優勝した経験もあります。その後、縁あってTBSテレビに転職し、ドラマやバラエティ番組などのマーケティングや制作に携わりました。他局の編成パターン、番組制作の癖や傾向をデータ分析して「視聴率アップ」に貢献することが私の役目でした。具体的には『日曜劇場』や『SASUKE』では、プロモーションを最適化して番組のいわゆる『入り視聴率(放送開始直後10分の視聴率)』を上げるためにデータ分析や戦略を練ったり、「視聴の離脱を減らす」ために『日本レコード大賞』では歌手の歌う順番を最適化したり、といったことをしていました。あくまでデータマーケティングの側面から視聴率を上げることをプロデューサーから期待されていました。さらにその後、アクセンチュアで経営コンサルタントとしての経験を積み、2018年に独立して自社のF6 Design株式会社を創業しました。現在は社長業を行いながら自身も戦略コンサルタント兼データサイエンティストとして、各種企業課題の解決に取り組んでいます。
一方で、弊社F6 Designでは、統計分析やAIといったデータサイエンスの力をビジネスに応用し、マーケティングやブランディング、業務改革のコンサルティングを行っています。例えばAIのビジネスシーンへの導入支援は弊社の得意分野の一つで、最新の生成AI技術の活用法を企業に伝授し業務効率化や新規事業創出を支援しています。生成AIが登場するまでは、自社でAIの根幹となるモデルを作成し、各ベンダーと組んでオリジナルのAIを開発するといったことをしていましたが、生成AIの登場で風向きは変わったことを認識し、いま弊社では、ビッグテック企業のAIを使いこなす方向へとシフトしています。つまり、データサイエンティストもAIに置き換わる時代になったと言っています。たとえば生成AIの活用には『プロンプト(指示)』が必要でそのプロンプトの作り方を商売にしているコンサル会社もある様ですが、弊社では『その必要はない』と提言しています。
なぜなら、今回のテーマであるResearcherやAnalystのように、AI側が人間の方へ優しく歩み寄ってくれるスピード感が加速しているからです。つまり、人間が言葉足らずで適切な指示ができていなくても、そのうち指示側の人間の“指示癖”ですらAIは学習し、その上で分析や提案をしてくれると推察しています。その点がAIとの関わり方について弊社が他のAI導入コンサル会社と大きく違うスタンスになりますでしょうか。つまり、弊社の強みは『AIの根本(原理原則)』をモデル作成レベルで知っていることではないかと。弊社にはそのベースあるからこそ『この先、人間がAIとどの様に関わるようになっていくのか』を少しは先読みできているのではなかろうかと、勝手に思っている次第です。AIのモデル作成では、数多くの失敗もしてきましたので」(笑)」
(文=BUSINESS JOURNAL編集部)