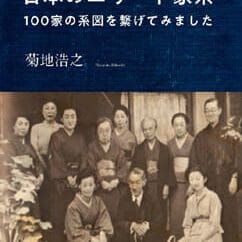「東芝が非上場」ではなぜダメなのか?「有名企業なら上場すべき」の価値観の歴史を考える

「非上場? トンでもない!」という価値観はどこから来ているのか?
東芝が投資ファンドの買収&株式非公開化提案で揺れている。経営陣の混乱や買収提案の中身についてはすでにいろいろと書かれているので、ここでは株式非公開化、すなわち株式の上場・非上場について考えてみよう。
報道では「せっかく上場に復帰したのに!」といった、非上場になることについて否定的な東芝役員・従業員の声が紹介されていた。現代日本では「上場企業=優良巨大企業」というイメージが強い。上場企業がみずから非上場になることはほぼないので、非上場になることは「上場廃止=不祥事」を意味している。
しかし、欧米では、上場企業が上場していることのデメリット、換言するなら非上場のメリットを考えて非上場に転換することは珍しいことではない。珍しいことではないから、外国の投資ファンドが勧めているのであって、別に東芝を貶めようとしているわけではない。
戦前の財閥系企業ではまったく珍しくなかった「非上場の巨大企業」
戦前の日本では、巨大企業が非上場というのは珍しくなかった。なぜなら、巨大企業を傘下に収める財閥にとって、傘下企業の株式を公開する(=株式市場に上場する)ことはメリットが薄かったからだ。
財閥家族が持株会社である財閥本社の株式の過半数を所有し、財閥本社が傘下企業の株式の過半数を所有して支配を貫徹するというロジックは学校で習ったことがあると思う。支配も重要なのだが、その傘下企業が生み出す利益の行方も重要である。利益は株式に対する配当として、財閥本社に吸い上げられ、それが財閥本社の利益、つまりは財閥本社の株式の配当として、財閥家族に還流していくのだ。
日本最大・三井財閥の三井家が日本でもっとも大金持ちだったのは、三井物産などが莫大な利益を上げていたからだ。三井家としては、三井物産の株式は全株持っていたほうがいい。
ところが、日本が第二次世界大戦に突入し、軍需産業(もしくはその関連企業)を巨大化させる過程で、財閥家族だけの資産でその資金をまかなうことができなくなっていった。財閥系企業も株式を公開し、資金を調達せざるを得ない状況に追い込まれたのである。
かくして、1940年、三井物産は株式を公開し、上場企業となった(そこには三井財閥の個別の事情があるのだが、それは割愛する)。実に三井物産創設(1876年)から64年もの月日が経っていた。戦争がなかったら、ずっと非上場のままだったかもしれない。
ただ、三井財閥軽企業でもサラリーマン経営者のなかには、日本を代表するような大企業は社会の公器であるという考えから、金融系の企業は上場が進んでいた。財閥のトップが開明的だった三菱財閥では、三菱商事、三菱重工業、そして財閥本社の三菱本社も株式上場を進めていた。
戦後の財閥解体で一気に進んだ、有名企業の株式上場…そしてそのことが“有名企業の証”に
日本が第二次世界大戦に敗れると、日本を占領したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、ひと握りの財閥家族が日本の巨大企業を支配し、戦争に進んだと解釈。財閥解体を実施した。財閥家族の持つ株式を放出し、財閥本社を解散。その所有株式も株式市場に放出した。この過程で、財閥系企業のほとんどが上場企業になってしまった。ここに至ってはじめて、「上場企業=優良巨大企業」という図式が生まれたのである。
そして、財閥解体を免れた巨大企業も、1950年代中盤以降の高度経済成長における資金需要の高まりから、株式を上場するようになった。そこで、オーナー一族は莫大なキャピタルゲイン(創業者利益)を手にすることになった。たとえば、非公開の50円株式を上場して、1000円の初値が付くとする。差額の950円はオーナーのポケットに入る。何百万、何千万単位の株式を上場すると、その利益は莫大なものになる。
20世紀の日本では長者番付というものが公開されていたのだが、そのトップに躍り出たのは、株式を上場したオーナー一族が多かった。たとえば、ブリヂストンの石橋家、大正製薬の上原家などである。こうした、キャピタルゲインによる資産家の誕生を目にして、株式上場に否定的だったオーナーたちも、株式上場のメリットに目を向けるようになった。
企業のトップが株式上場を目標に掲げ、従業員もまた上場会社勤務を夢見る。しかも、株式上場には厳しい審査項目があり、それをクリアすることが優良企業のお墨付きであるかのように考えられてくる。こうなると、もう上場するしかない――ってことだろうね。
大規模資金調達が不必要なためあえて上場しないサントリー、竹中工務店、講談社
では、日本を代表する企業はみな上場企業か、換言するなら、非上場企業に有名企業はないか――といえば、これがあるのである。
たとえば、サントリー、竹中工務店、講談社、日本生命保険などである。
このうち、日本生命保険相互会社はそもそも株式会社ではないので、株式を発行しておらず、従って上場もない。相互会社というのは、保険会社に認められた独特の会社形式で、保険契約者の拠出金(=保険料)をもとに会社を運営していく仕組みだ。戦前は第一生命保険と富国徴兵保険(現・フコク生命保険)しかなかったのだが、戦後、ほとんどの生命保険会社が相互会社形式を採用した。その背景には諸説あるのだが、どうやらGHQが推奨したらしい。
ただし1990年代以降、株式会社に転換する会社が増え、相互会社の元祖・第一生命保険も現在では株式会社になっている。相互会社は煩わしい株主対策がなく、買収の危険がないというメリットがあるのだが、機動的な資本調達ができず、経営危機に陥ったときに資本増強・資本提携ができないことがデメリットとして挙げられる。バブル崩壊後にバタバタと生命保険会社が破綻に追い込まれた一因にもなった。もっとも、それら生命保険会社が経営危機に陥った最大の原因としては、上場されていないから経営に対する外部からのチェック機能が働かず、放漫経営の挙句といったものが多かったのだが。
保険会社は別として、サントリーや竹中工務店、講談社が非上場のままでいられるのはなぜかというと、そこまで大規模な資金調達の必要がないからだろう。
酒類販売、建設、マスコミ・出版などの業種は、巨大資金を投入して工場を建設し、大量の資材を購入して――という業態ではなく、株式を上場して巨額の資金を動員しないと同業他社に負けてしまうという事態には陥らない。
それならば、上場して買収の危険にさらされ、経営権が安定しないことよりも、非上場のままのほうがよいという経営判断だということができる。事実、非上場企業の多くは、経営者が世襲(もしくは、サラリーマン経営者が社長を務めていても、オーナー一族が支配権を保持していると想定される)というケースが多い。
東芝の報道を見る限りでは、従業員も役員も「上場は善、非上場は悪」とばかりの感情的な論調が目立つが、何が会社にとっていちばんのメリットなのか冷静に考え直したほうがいいのではないか。株式の上場は資金調達の手段であって、目的ではないのである。

西武グループオーナー、堤義明は「西武鉄道が上場しなければならない理由がわからない」と釈明
かつて、そのことを冷静に考え、それを発言した御仁がおられた。西武グループの総帥・堤義明だ。
世間では、西武グループを西武鉄道を中心とする鉄道グループだとみているかもしれないが、オーナー・堤家から見ると、西武グループは(西武鉄道の親会社だった)国土計画を中心とするデベロッパー事業者だ。かつて、東京郊外を開発したときに買収したのが西武鉄道で、堤家にとって鉄道事業は特に思い入れのある事業ではない。
そして、堤家は西武グループを閉鎖的に所有・支配することを最重要事項に置いている。
ところが、何かの案件で多額の融資を受ける際に、その条件として西武鉄道を上場したらしい。思い入れがないとはいえ、事業の一部である。堤家は株式の名義を虚偽記載して80%以上の株式を保有したまま、西武鉄道を上場した。
当時はコンプライアンスなんかない時代だったから、それでも異論は出なかったのだろう。しかし、2004年に監査役がそれに気づいて「これはヤバい」と発表。これに対し、堤義明は記者会⾒で「私には西武鉄道が上場しなければならない理由がわからない」と釈明した。
堤家の論理からいうと、この釈明は誤っていない。でもそう思っているなら、問題が起こる前に非上場にしておくべきだった。当然、義明の会見を聞いた関係者は激怒。東京証券取引所は西武鉄道を上場廃止にした。みずから非上場に「する」のと「される」のとでは大違い。西武鉄道の株式の資産価値は暴落し、それによって親会社の国土計画の資産価値も毀損。銀行管理を受けることになり、西武グループは解体され、堤義明は経営者失格の烙印を押されて身を隠す羽目になった。
世間が「上場は善、非上場は悪」と感じているうちは、東芝の対応もやむを得ないといったところだろうか。
(文=菊地浩之)

●菊地浩之(きくち・ひろゆき)
1963年、北海道札幌市に生まれる。小学6年生の時に「系図マニア」となり、勉強そっちのけで系図に没頭。1982年に國學院大學経済学部に進学、歴史系サークルに入り浸る。1986年に同大同学部を卒業、ソフトウェア会社に入社。2005年、『企業集団の形成と解体』で國學院大學から経済学博士号を授与される。著者に、『日本の15大財閥 現代企業のルーツをひもとく』(平凡社新書、2009年)、『三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一勧 日本の六大企業集団』(角川選書、2017年)、『織田家臣団の系図』(角川新書、2019年)など多数。