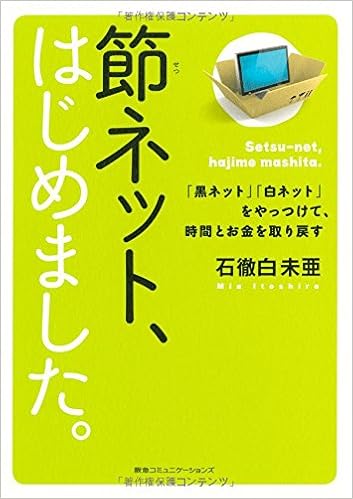ネット炎上犯は高学歴・高収入者が多かった!ネットを見て「自分は正しい」と思い込む人たち
 「Thinkstock」より
「Thinkstock」よりインターネット上でしばしば起きる“炎上”。それに加担する人というと、「年収が低く、コミュニケーション力は皆無で友達も恋人もおらず、人生の鬱憤をネットで晴らしている」という人物像をイメージしがちだ。
しかし、統計分析によって「子持ちで年収高めの男性が、炎上に加担する傾向がある」という意外な事実が、『ネット炎上の研究』(勁草書房/田中辰雄・山口真一著)のなかで明かされている。
炎上には、どのような社会的損失があるのか。また、どうすれば炎上を防ぐことができるのか。本書の共著者で国際大学グローバル・コミュニケーション・センター助教の山口真一氏に話を聞いた。
炎上しやすい話題は「安保」「原発」「中韓」
–有名人などのツイッターでの発言が炎上し、それが「まとめサイト」に掲載され、さらにマスメディアのニュースで報じられ……というふうに、今や炎上は日常茶飯事になっていますが、炎上にはどのような損失があるのでしょうか。
山口真一氏(以下、山口) まず、ミクロ的な問題として、炎上対象者の人生に大きな影響を与え、対象が企業の場合は株価が下がることもあります。もっと大きなマクロ的問題としては、みんなが誹謗中傷や批判を恐れることで、公の場で発言するのを控えてしまうということがあります。そして、荒れている環境下では極端な意見しか残らなくなってしまい、中庸な意見が蒸発してしまいます。
 『ネット炎上の研究』(勁草書房/田中辰雄・山口真一著)
『ネット炎上の研究』(勁草書房/田中辰雄・山口真一著)これは、ネットの持つ「自由な情報発信」という魅力を損なう原因になっています。実際、ツイッターのアクティブユーザーは減ってきており、特に若い世代はLINEに移っています。
LINEは、いじめの問題はありますが、基本的には閉じたコミュニティなので炎上はしません。オープンではないツールに人が移動し始めているのには、炎上に辟易しているという影響もあるのかもしれません。そもそも、「炎上には社会的な損失があるのではないか」というのが、本書の出発点です。
–特に、話題が「安保関連」「原発」「憲法9条」「靖国神社」「韓国」「中国」などになると、ネットには極端な意見しか見られませんよね。
山口 安全保障の話の場合、「集団的自衛権を支持しない人は非国民」とか、逆に「集団的自衛権を支持する人は、徴兵制を容認している」とか、極端な意見ばかりになってしまいますが、これはいい状態とは思えないですよね。
–この手の話題は、「刺激するとまずいから、触れちゃいけない」という暗黙の了解ができてしまっていますよね。
山口 中庸な意見が蒸発する一方で、過激な意見は同じ人が複数回書き込んでいるのです。だから、大勢いるように見えてしまう。わざと大勢いるように見せかける人もいるとは思いますが、自演というより、「自分の言いたいことを言いたいだけ言っている」という人が多いのではないでしょうか。
結局、「極端な意見の人」というのは、ものすごくエネルギーがあるんですよね。そのような人たちの動機が「正義感」であるというのが、また難しいところでもありますが。
炎上加担者は大勢いるように見えますが、実際に過去1年で炎上に参加した人は0.5%、「過去1年」という条件を外しても1.1%です。これは、本書で実施したアンケートの結果です。
炎上を引き起こしているのは、ごく少人数
–掲示板サイト「2ちゃんねる」のよく燃えているスレッドを見ていると、全体の20%くらいの人が炎上に参加しているように見えてしまいますが、実際は少ないんですね。
山口 大量のコメントが画面上に一斉に流れる「ニコニコ動画」の場合、見るからに荒れている時は大勢の人が炎上を引き起こしているような印象を受けますが、荒らしは少ないと川上量生氏(「ニコ動」を運営するドワンゴ会長)も指摘しています。荒れ放題のニコ動の画面も、数人のコメントを消すだけで、画面上が一気に平和になるという指摘もあります。
「ごく少数の人が暴れ回っている」という事実は衝撃的であると同時に「まぁ、そうだろう」とも思ってしまいますよね。
–「Web 2.0」という言い方も古いですが、コミュニケーションが双方向になるのは、とてもいいことのように言われていました。しかし、双方向は、ツイッターで一般人が数万のフォロワーを持つ有名人をリアルタイムでボコボコにすることもできる、ひどい仕組みでもありますよね。
山口 そうした場合、反論すると有名人のほうが叩かれてしまうんですよね。本書の共著者である田中辰雄先生は、「(ツイッターで)一般人が、オバマ大統領に対して誹謗中傷できるという状況は異常でしょ?」とおっしゃっています。
これに反論する人は「表現の自由」と言いますが、「表現の自由」と「誹謗中傷」や「ヘイトスピーチ」は別ですよね。ただ、誹謗中傷表現を禁止する時には線引きが難しい。それを利用して表現を規制しようとする権力者が現れるかもしれない。そういったリスクを考えると、規制も難しいですよね。
–本書内にも「炎上させる側に議論する気はない」とありますね。
山口 炎上を起こしている側は相手と議論する気はないし、自分たちが正しいと思っている。やはり、正義感なんですよね。それが一番の問題だと思います。
ネット検索で「自分の意見は正しい!」と思い込む人たち
–そもそも、炎上加担者はなぜ炎上に加担するのでしょうか。
山口 よく「炎上が起きるのは、ストレス社会のせいなのですか?」と聞かれるのですが、そういう定義づけをするのは危険だと思います。そうではなく、ソーシャルメディアによって、そういった人が表に出やすくなっただけなのではないでしょうか。
また、ネットでは検索するだけで自分と同じ意見の人を簡単に見つけることができます。それによって自分の意見が補強されて「自分は正しい!」という思いが強まっていく……。
人自体は昔と変わっていないのですが、ネットによって、考えが表に出やすくなったり強化されたりする仕組みができた、というふうに考えています。
–一方で「グルーポン」の“スカスカおせち事件”など、炎上によって広く認識されるようになった問題もあります。炎上には、「どこからが“クロ”」というような線引きはあるのでしょうか。
山口 基本的に、炎上はいいことではないと思います。何かしら騒動が起きた時、法の裁きと関係なく人々が思い思いに批判をするのは、集団で私刑をするのと同じであり、よくないことです。
一方、おせちの事件では、泣き寝入りになりかねなかった消費者が炎上によって救われてもいます。良い悪いで語るのは本当に難しいのですが、今の炎上の状況のなかに解決すべき課題はあると考えています。
–ネットの使い方に悩んでいる人に、アドバイスはありますか?
山口 炎上に加担しないという意味では、自分と同じ意見をネット上で見かけても、それが大多数の意見であると錯覚しないことが大切ですね。もし、自分が大多数の側であったとしても、それは、そうではない他人を誹謗中傷する理由にはなりません。
例えば、「2ちゃんねる」のまとめサイトを見ると、いろいろな書き込みが掲載されていることから多様な意見があるように見えますが、そこには管理人の意思が反映されています。にもかかわらず、「大手マスメディアと違い、まとめサイトは多様な意見のかたまりだ」と思って読んでいる人は多いのではないでしょうか。あたかも客観性のある意見のように見えてしまうのが危険なんです。
–ネット上の一部には、マスメディアに対する強い不信感がありますよね。
山口 それについても、ネットで「マスメディアはやっぱりダメだ」という記事を読むことで、さらにマスメディア不信を強めているのでは、と思いますね。自分と同じ意見を探して読むことで、その思いをさらに強くしてしまっているのです。
–ありがとうございました。
“祭り”とも称されるネット炎上だが、実際はごく少数の正義感をこじらせた人たちが火を放っているという現実があるようだ。次回は、「炎上加担者は子持ちで年収高めの男性が多い」という調査結果をはじめとしたネット炎上の実態について、さらに山口氏の話をお伝えする。
(構成=石徹白未亜/ライター)
『ネット炎上の研究』 炎上参加者はネット利用者の0.5%だった。炎上はなぜ生じたのだろうか。炎上を防ぐ方法はあるのだろうか。炎上は甘受するしかないのだろうか。実証分析から見えてくる真実。
『節ネット、はじめました。 「黒ネット」「白ネット」をやっつけて、時間とお金を取り戻す』 時間がない! お金がない! 余裕もない!――すべての元凶はネットかもしれません。