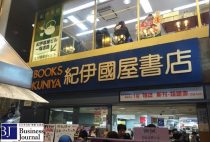サイト「グーグル」より
サイト「グーグル」より多国籍企業であるグーグルは、タックス・ヘイヴン(租税回避地)を駆使した“節税企業”としても知られる。「検索エンジン」や「グーグルアース」「ストリートビュー」「ユーチューブ」そして「グーグルブックス」といった同社のサービスは、すべて無料で使える。にもかかわらず、同社の持株会社アルファベットは、年間9兆円規模の売上を叩き出しているのだという。果たして同社は、そんな多額のカネをどのように稼いでいるのだろうか。
以下、拙著『グーグルに異議あり!』(集英社新書、2010年)から一部修正の上、引用する。
その答えは、グーグル社のホームページの中にあった。検索結果の画面やストリートビュー画面の周辺に出る「アドワーズ」と呼ばれる広告で、グーグルは多額の稼ぎを叩き出しているのである。
これは別名「キーワード広告」といい、検索する際に打ち込む言葉に関連する企業などの広告が、検索結果とともに表示されるのだ。
検索業者のための著作権法改正
そのアドワーズを利用している日本国内の広告主にお願いして見せてもらったのが、グーグルからの「請求書」である。
請求元は「グーグル・アイルランド」。所在地は本社のある米国・シリコンバレー(カリフォルニア州)ではない。アイルランド共和国の首都・ダブリンになっている。そしてダブリンといえば、世界的に有名なタックスヘイブン(租税回避地)としても知られる。
つまり、日本のユーザー向けサイトに載る日本人向け広告で得た収益は、日本の国税当局の前を素通りし、アイルランドのグーグルへと送金されているのだ。
その証拠に、請求書の下段にはこう明記されている。
「弊社の広告サービスは日本国外を拠点とするため、消費税の課税対象とはなりません」
(筆者注:16年10月以降は「クロスボーダー消費税」の課税対象になった。ただし、納税義務があるのはグーグル社ではなく、日本国内の広告主である。)
アイルランドへの送金は大半の場合、高い手数料を取られる銀行経由ではなく、クレジットカード決済のかたちで行なわれる。事情を知る関係筋は語る。
「グーグルに支払う広告費に、日本の消費税はかかりません。一方、ヤフーのキーワード広告『オーバーチュア』の場合は、日本法人による事業なので消費税がかかります。
アドワーズの広告費については、日本の消費税法上『国外取引』とされ、課税の対象とはならないんです。だから広告主は消費税分を上乗せして支払っておらず、グーグルは消費税を日本に納めていません。契約自体もグーグル米国本社ではなく、グーグル・アイルランドと日本の広告主との間で取り交わされているんですね。
ちなみに、タックスヘイブンであるダブリンの法人税率は12.5%です。2002年末まではなんと10%でした(筆者注:一部企業については05年末まで10%の法人税率が延長)。日本の法人税率は約30%(同:法人住民税と法人事業税を加えた実効税率では約40%)ですので、ダブリンがいかに安いかわかると思います」
ということは、法人税もかなり浮かせているかもしれない。
国税庁に聞いた。
「一般論として、外国法人であって、日本国内での源泉所得(日本国内で生じた所得)が発生しなければ、日本で法人税の納税義務は生じません」
――グーグルのように国外で所得が発生した形にしていれば、法人税を納めなくてもいいわけですね。まるで税逃れの抜け道みたいに見えます。
「我々は法律に沿った執行しかできないので……。今後、必要であれば、主税(財務省主税局)のほうでやっていくことだと思います」
グーグルにとって日本は「美しい国」というより「美味しい国」であるようだ。
グーグル社の意向を忖度する文化庁
引用は以上である。同書は10年4月に刊行された本だが、7年後の今もなお、こうした「税逃れ」の仕組みに大差はない。
となると、どうしても不思議でならないのは、日本で法人税を納めようとしない会社のために、なぜ文化庁がわざわざ著作権法を改正してまで「著者に無断で行なう書籍全文デジタルスキャン」を許し、インターネットでの「書籍全文検索サービス」という民間事業のお先棒担ぎをするのか――ということだ。
グーグル社の意向を過剰なまでに忖度する文化庁に対し、同社から何か見返りでもあるのか。ここで同社に貸しをつくり、あわよくば新規の“天下り先”を確保しようと考えているのだとしたら、それはあからさまな売国的行為であり、日本国民への裏切り行為でもあり、国家公務員の所業として決して許されるものではない。
ものの順序から言えば、日本で納税しないグーグル社をはじめとした海外のネット検索業者に対し、きちんと課税する仕組みを整えてから、著作権法の改正作業に着手するのが道理であろう。しかし、そうはなっていないからこそ、このたびの著作権法改正はさまざまな疑念を呼ぶことになるのだ。
文部科学事務次官までが関与していた一連の違法な「文部科学省挙げての大学への天下りあっせん」事件が発覚したばかりの昨今、文科省への信頼はないに等しい。著作権法の改正後、文科省あるいはその下部組織である文化庁からネット検索業者へと天下りする官僚が現れないかどうか、今後数年間は注視が必要である。
「ごくごく軽微な不利益」では済まない危険
前回記事の最後で触れたとおり、文化庁との「著作権法改正案勉強会」は3月22日、衆議院第2議員会館内の会議室で行なわれた。同庁からの出席者は、著作権課の秋山卓也課長補佐である。
秋山補佐はこの日、今回の著作権法改正案についてこう説明した。
「インターネット情報を検索して、膨大な情報のなかから我々が新しい情報に触れる機会を与えているという、社会的な意義があるサービスなので、権利者(著作権者)に及び得るごくごく軽微な不利益については少し我慢をしていただいて、権利を制限しましょうという発想です」
文化庁は、著者に無断で書籍の全文をデジタルスキャンしてテキストデータ化し、インターネットで無料検索できるようにするサービス、つまりグーグルブックスには「社会的意義が認められる」と考えていた。
現行の著作権法で同様のサービスが許されているのは、国立国会図書館だけである。ただし、ユーザーが自宅等でインターネット検索することはできず、いちいち国会図書館に出向いて検索を行なう必要がある。それを民間業者にも許し、さらにはインターネット検索もできるようにしようというのが、今回の著作権法改正案だ。
「アメリカでは認められているのに、(日本では)著作権が足かせになってできないのであれば、解消しましょうということです」(秋山補佐)
しかし、国会図書館がやるのと民間業者がやるのとでは、大きな違いがある。国会図書館の「書籍テキストデータ」は純然たる公共物であるのに対し、民間業者のそれは「社会的意義」というあやふやな概念が根拠の私物である。それに加え、国会図書館のデータは図書館内でしか扱えないのに対し、民間業者が管理する「私物」のデータベースはインターネットに接続して利用するのが前提だ。
秋山補佐は、著作権者に及ぶのは「ごくごく軽微な不利益」であるとする。だが、そう言い切れるものではない。
もし、まるごとデジタルスキャンされた書籍のデータがインターネットに漏洩した場合、被害を受けた著作権者は誰に対して損害賠償を請求することになるのか。文化庁の唱える「社会的意義」とは、その権利まで制限するものなのか。民間業者のデータベースがサイバー攻撃を受け、書籍テキストデータが大量流出する事件が発生すれば、漏れ出した本の著作権者らは「ごくごく軽微」どころではないダメージを被る。いったんインターネットに漏れ出してしまえば、取り返しがつかない。
インターネットに接続する限り、サイバー攻撃やデータの大規模漏洩と無縁で済ますことは不可能である。攻撃を受けたりデータ漏洩事件が起きたりするのは「当たり前のこと」として、たとえ起きても大問題には至らないような制度設計にしておくほかない。それができないのなら、インターネットに接続しようなどとは思わないことだ。
書籍データを扱う民間業者が倒産してしまうケースもあるだろう。データベースの管理が疎かになれば、データ流出の危険も同時に高まる。また、企業で使っていたパソコンが廃棄される過程で、ハードディスク内のデータが消去されずに中古市場へと流れ、情報が流出する事件の話を耳にするが、そうしたことへの対策も欠かせないだろう。
著作権法改正で外交問題勃発も
「アメリカでは認められている」から日本でもいいだろうとする理屈にしても、無知の産物であるばかりか、危険でさえある。著作権の世界において大勢を占める考え方は、実を言うとアメリカ的な考え方ではなく、ドイツやフランスなど欧州的な考え方のほうにある。アメリカ流の著作権は圧倒的少数派なのだ。
8年前の2009年、「グーグルブック検索和解」事件の和解案を審査していたニューヨーク南部地区連邦地裁にはドイツやフランス、イギリスなどの著作権者からのオブジェクション(異議申し立て)が文字どおり殺到した。ドイツやフランスに至っては、国家として異議を申し立てていたほどである。そしてグーグルは、これらの異議申し立てに屈伏し、和解案の審査で敗北を喫していた。
著作権法の改正により、こうした裁判が今度は日本の裁判所を舞台に繰り広げられる恐れがある。しかもその裁判では、グーグルなどの民間業者ばかりか、日本政府も一緒に訴えられる可能性が高い。
民間業者は新・著作権法の保護のもと、日本国内にある書籍を片っ端から無断全文スキャンすることだろう。そんな本の中には、フランス語や英語で書かれた書籍もきっと含まれることだろう。そして同法の改正案には、それを禁じる規定は見当たらない。
グーグル社をはじめとした、たった数社の民間業者のビジネスのため、アメリカ以外の世界を相手に矢面に立つ――。その覚悟が、今の文化庁にあるとはとても思えない。
新・著作権法の下では、国会図書館の「検索サービス」では考える必要のなかった対策まで用意しておかなければならない。「グーグルブック検索和解」事件の時と同様、著作権者が相当な苦労や面倒を強いられることになるのは間違いなさそうだ。
(文=明石昇二郎/ルポライター)