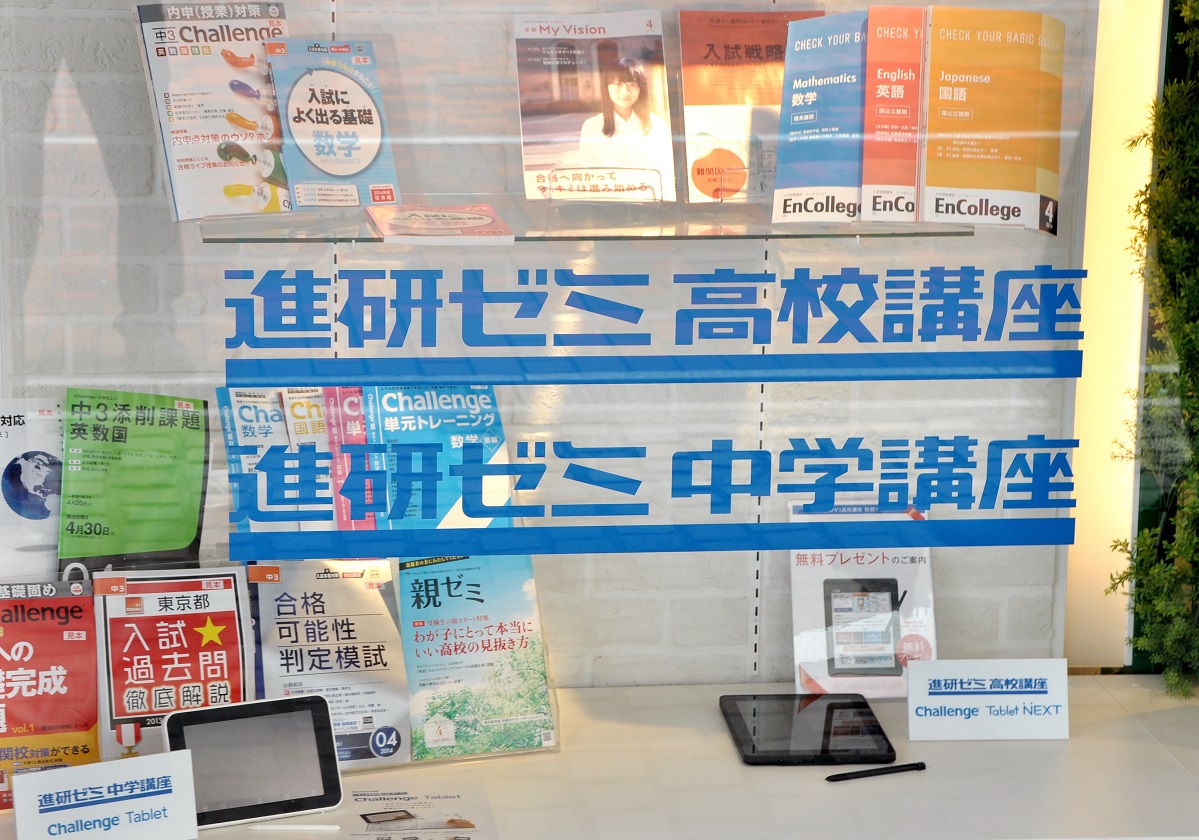
「身の丈に合わせてがんばって」――。
萩生田光一文部科学相の失言が引き金になり、来年度から始まる予定だった大学入学共通テストへの英語民間試験導入が延期になった。文科省の突然の方針転換を受けて、2020年度に実施する一般選抜で、独自に民間試験の活用を決めていた国立大で取りやめが相次いだ。全国82校のうち78校がほぼ全学部で採用する予定だったが、東京大や京都大など62校が取りやめた。公立大も多くが活用しない方針に転じた。
従来のセンター入試に代わる大学入試の英語民間試験は、下村博文氏が文科相時代の14年12月に方向性が打ち出され、3年後の17年7月に導入することが正式に決まった。大学入試センター試験は20年1月に廃止され、21年1月から新テスト「大学入学共通テスト」に移行する。国語と数学に記述式の試験も取り入れることになっていたが、12月17日、萩生田文科相は無期限の見送りを発表した。「受験生の不安を払拭し、安心して受験できる体制を現地点で整えることは困難だと判断した」と述べた。欠陥を認め、撤回した。
大学入試改革をめぐる迷走で、「進研ゼミ」の通信教育で知られるベネッセホールディングス(HD)が槍玉に挙がった。ベネッセと政治家、文科省の癒着疑惑が噴出した。英語民間試験の最有力候補はベネッセコーポレーション(本社・岡山市)が提供する「GTEC」。ベネッセHD傘下の中核事業会社だ。大学入試改革のもう1つの目玉である大学共通テストの記述式(国語・数学)の採点業務も、ベネッセグループの学力評価研究機構(東京・新宿区)が61億6000万円で落札した。
国・数の記述問題の実施も、見直しの方向だ。国・数の記述問題の実施も、期限を切った延期ではなく、「まっさらな状態から対応したい」(萩生田文科相)とした。「入試改革の2本柱」がともに失われたことになる。
「身の丈に合わせて」発言は、収入による教育格差を是認するものと受け止められ、萩生田文科相の謝罪・発言の取り消しへと発展した。親に金があれば塾にも通えるし家庭教師をつけて勉強することもできるから、生徒は成績が上がる。一方、貧困世帯の子供は教育の質が底割れする。底が抜ける状態になる。「教育の機会均等」を建て前としている文科省と大臣の発言が矛盾することになったわけだ。だが、萩生田文科相の発言は、教育の現状をきちんと捉えたものであり、萩生田氏の“本音”と思われるだけに問題の根は深い。文部行政が根本から問われる発言だった。
個人情報流出事件が転機
2014年の個人情報流出事件が、ベネッセHDの経営の転機となった。中高生向け通信添削講座「進研ゼミ」を柱に成長を続けてきたが、タブレット端末を利用した新しいシステムの導入が遅れ、進研ゼミの会員が減少した。
創業家の福武總一郎最高顧問はビジネスモデルを転換するため、日本マクドナルドHDで辣腕を振るった「プロ経営者」、原田泳幸氏を招いた。原田氏は14年6月、ベネッセHDの会長兼社長に就いた。その直後、子会社のベネッセコーポレーションの通信講座「進研ゼミ」の個人情報の漏洩事件が発覚。流出した個人情報は2895万人に達した。
会員情報の漏洩はベネッセHDの業績を痛打。会員数は激減、原田氏が進めようとしたタブレット学習への転換も不発に終わった。その結果、2期連続の最終赤字となり原田氏は16年6月、在任期間わずか2年で引責辞任した。
大学入試改革は絶好のビジネスチャンス
福武氏は原田氏の後任に、再び「プロ経営者」の安達保氏を招く。三菱商事出身で米投資ファンド、カーライルグループの日本法人会長を務め、「再建請負人」として知られる。16年10月、ベネッセHDの社長に就いた。
安達氏は大学入試改革がベネッセHDを成長軌道に戻す絶好のチャンスと捉えた。大学入試改革体制に組織をシフト。17年5月、採点業務を行う学力評価研究機構を設立。機構は19年8月、国語と数学の記述式の採点業務を受注した。文科省は他の教科にも記述式を導入することを検討している。
大学入試改革の最大の目玉である英語の民間試験の活用に備えて、英語の技能検定「GTEC」に全力投球してきた。18年3月、大学入試センターは共通テストで使われる8種類の民間試験にGTECを認定した。GTECの19年3月期の受験者数は126万人。前年より23万人増えた。英語民間検定試験が導入されれば、さらなる増加が見込まれている。
波及効果は大きいとみられていた。政府のお墨付きを得たベネッセHDの教育支援システムを小・中・高が採用することになるからだ。ベネッセHDとソフトバンクグループの合弁会社が手がける情報通信技術を活用した学校支援プラットフォーム「Classi」を採用する高校は2500校。前年より400校増えた。高校の導入率は50%になった。小中学校向けの支援サービス「EDUCOM」は19年1月、ベネッセHDが買収したものだが、採用校は7500校ある。
中期経営計画で19年3月期に4394億円だったグループ売上高を21年3月期に5000億円に引き上げる目標を掲げる。「教育・入試改革は最大の事業機会」と位置付け、「大学入学共通テストの民間検定の一つに『GTEC』が採用されたのは大きな転機」としていた。「進研摸試」に代表される受験産業の雄だったベネッセHDは、いまや“大学入試改革請負人”と呼ぶべき存在に大変身している。
しかし、政治家・文科官僚とベネッセの癒着が表面化し、ベネッセに逆風が吹きつける。受験ビジネスと大学入試の両方に手を突っ込むのは、行司と相撲取りの一人二役を演じるようなもの。「ベネッセが大学入試を請け負うのであれば、高校の教育現場からは手を引くべきだ」との声が強まる。大学入試改革という鉱脈を探り当てた安達社長は、この難問を上手にさばくことができるのだろうか。
(文=編集部)

















