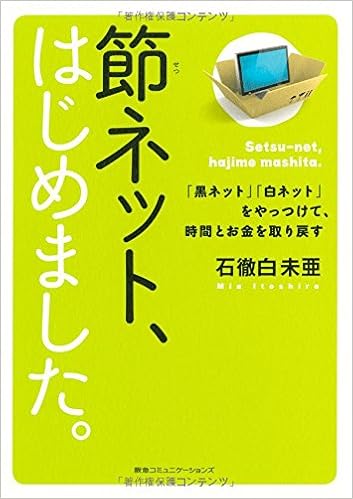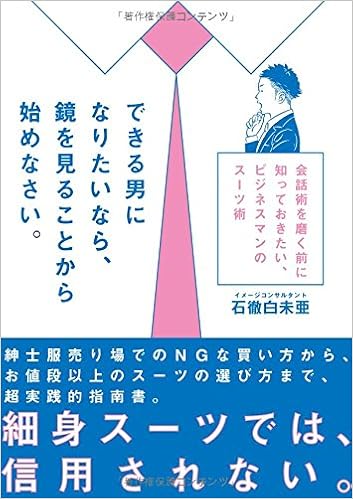ゲーム依存の問題を考えるとき、「悪役」になりやすいのがゲーム開発者だろう。果たして、ゲーム開発者は子どもを依存に陥れる「悪いゲーム」をつくる悪の科学者なのか?
前編でお伝えした「ゲーミングの未来を考える会」による研究会で、国内ゲーム開発会社でゲーム開発を行う、いわゆる「中の人」である吉田辰巳氏が「ゲーム開発者の意識変化とゲーム依存との関係」について講演を行った。後編では、ゲーム開発者の思いをレポートしたい(※記事内の吉田氏の発言は個人の見解であり、吉田氏所属企業の見解ではない)。
ゲーム開発者にとっての“成功”はどう変わったか
「ゲーム開発者は、あたかも良からぬことを企む科学者が依存性の高い悪いゲームをつくって、子どもたちからお金を巻き上げようとしている」というイメージを持たれているように聞こえるが、1人の「悪者」を決めてしまうのは問題の本質につながらず、ゲームが善か悪か、単純な結論を出すつもりはなく、正しい認識、知識で多角的な議論ができれば、と吉田氏は話す。
まず、ゲーム開発者にとって「成功したゲーム」のイメージは時代とともにどう変わっていったのか。通信対戦ができない家庭用ゲーム機などを中心とした20世紀の「オフライン時代」と、現在のスマホを中心とした「オンライン時代」を比較したい。
オフライン時代の頃は「発売日に行列」「ゲーム雑誌レビューで高評価」「家族みんなで盛り上がる」などがゲームの評価軸だった。なお、当時人気を誇ったゲーム雑誌のひとつ「電撃PlayStation」(KADOKAWA)は今年の3月で定期刊行を停止した。
オンライン時代になると、「正式サービス当日に大人数のログイン」「レビューサイトで高評価を獲得」「ボイスチャットなどを使った通信プレイで盛り上がる」などに変化するも、オフラインの頃と媒体が変わっただけで、評価軸そのものは変わっていないことがわかる。
ただ、オフラインとオンラインの大きな違いは「リリース後の先」の長さだ。
「オンラインゲームは半年、1年。好調であれば5~10年続くタイトルもあります。オンラインゲームはインパクトを与えて終わり、ではありません。グラフィックの美しさの印象は、もって最初の1週間、1カ月です」と吉田氏。
パッケージとして最初から最後が決まっているオフラインゲームと違い、オンラインゲームは「終わり」がない状態でリリースされるケースがほとんどだろう。そして、オンラインゲーム開発者はユーザーに1カ月後には別の感情を抱いてもらう必要が出てくる。そのため、飽きないように次はこれ、これ……というシナリオを描いているという。
たとえば、「ゲーム上で友達ができる」というのは、毎日ついログインする「習慣化」のきっかけのひとつになると言えるだろう。毎日遊んでほしい=依存的になる、ことについては「その関係性を否定できない部分ではある」と吉田氏は話す。
「不便さをなくす」ことで進化してきたゲーム
吉田氏自身、かつては「ゲームの作品性」、つまりおもしろいゲームさえつくれば遊んでもらえると思っていたという。しかし、ゲームセンターのゲームと連動し、さまざまな便利機能を提供するモバイル連動サービスの運営にかかわる中で、ゲームのおもしろさや作品性とはなんら関係のないサービスでありながら、ユーザーの感情を大きく動かすことができることを学んだという。
「ゲームのおもしろさ」とは関係のない「情報に触れる機会が増えること」がユーザーの評価につながったことが、吉田氏に「人を楽しませることは何か」を考えさせるきっかけになった。
「人を楽しませる」ことの1つの要素として、「不便さを減らすことがとても重要」と吉田氏は話す。たとえば「ゲームセンターなど特定の場所に行かないとゲームができない」というのは、娯楽の魅力をかき消す力があるという。アーケードゲームといった店舗で楽しむゲームから、家庭のコンピューターゲーム機へ、さらに個人のスマホへ、という移り変わりは必然なのだ。
ほかにも、不便さを減らす取り組みとして「ルールを覚えるのが面倒→従来のゲームをアップデートしよう」「おもしろいかどうかわからないゲームにいきなりまとまった額を支払うことに抵抗がある→基本無料で」という流れができている。
さらに、オンラインゲームはオフラインゲームと違い、ユーザーのプレイスタイル、離脱状況まで運営側がリアルタイムで把握でき、ユーザーの離脱といった「不便」発生点にすみやかに修正が加えられる。よって、今のオンラインゲームは「ユーザーの望む姿、より不便のない姿」に日々形を変えているのだ。吉田氏は「最近のオンラインゲームは、ユーザーの要望を正確かつ高速で取り入れることができるようになったため、いつまでも滞在したいと思える居心地のいい世界として進化してきた」と話す。
一方で、「大勢のユーザーの不便を解消する」方向にゲームが進んでいることについては、「一日中ゲームができる環境にあるプレイヤーが、ほかのプレイヤーより優位に立てること」を不満に思う気持ち、つまり一日中はゲームができない大勢のユーザーのニーズも多く出ている、と説明する。
金額や時間をかけたユーザーだけが優位に立てるゲームは、大勢のそうではないユーザーにとって「もうがんばれない」「やる気がなくなる」という「不便」な気持ちになるはずだ。よって、「プレイヤーが“得”をできる時間に一日の中で制限を設ける(一日中ゲームができるプレイヤーとそうでないプレイヤーの条件を平等にする)」といった形のオンラインゲームが一般的になってきている、と吉田氏は話す。
配信ゲームでも巨額のコストがかかる運営事情
リリースしても新規ユーザーがさっぱりつかず、配信即サービス終了となるゲームも多いという。また、物理的なソフトでの提供から配信という形態になったため、今のほうが低コストでつくれるように思えるが、サーバー管理費などで運営には毎月数百万~数千万円の費用がかかってしまうそうだ。
そして、一度ついたユーザーもあっという間に離れるため、「ゲーム依存とは対照的に、すぐにやめてしまう方が大多数です。それでもゲームを続けてくださるお客様を大切にするために、オンラインゲームの開発・運営者は日々努力をしているのです」と吉田氏。
冒頭で吉田氏は「ゲーム開発者は、あたかも良からぬことを企む科学者が依存性の高い悪いゲームをつくって、子どもたちからお金を巻き上げようとしている」イメージがあると話したが、おもしろいかどうかわからないものにいきなりまとまった額を支払うことに抵抗があるという社会の動向を受けて、基本無料で遊ぶことができるゲームを開発するなどのように、実像は「現代のゲームは世相を映す鏡であり、ゲーム開発はユーザーが望むものを提供するサービス業だと思っています」と話した。
* * *
「ゲームに時間をかけられ、他ユーザーより好成績を収めるユーザー」に対する不満が他ユーザーから出てきて、それを解消するために有利な時間を絞る(≒ゲームを使わせ過ぎない)という、吉田氏が示した可能性は非常に興味深い。「ゲームを使いすぎないで」という声は、外野からの「ゲームをやりすぎていて心配だ」という形だけでなく、同じユーザー内からの「ズルい」という形で出ることも十分考えられるのだ。
私自身、大学時代にやっていたことはほぼゲーム、というくらいゲームにはまっていた(当時はオフラインゲーム)。しかし、今はほぼしない。なぜか考えてみたときに、私は結局ゲームの話やキャラクターが好きなのであり、話やキャラクターが好きなら、漫画やアニメを見たほうが「ストーリーやキャラクターにすぐ入り込める(同じ作業の繰り返しであるレベル上げなどがいらなくて楽)」と気づいたからだ。
もともとアクションゲームが苦手でロールプレイングゲーム派だったし、ロールプレイングも攻略本を片手に最短距離でさっさと進めていた。ロールプレイングゲームが本当に好きな人なら、攻略本を見ずに、まずは自分であれこれダンジョンを探索するのだと思う。また、人付き合いが苦手なので、通信対戦や協業して敵を倒す、などにはさっぱり興味がなかった。
いまだに、しみじみとおもしろかった、凝っていて楽しかった、と思えるゲームタイトルもある。また、仕事で会った人と雑談で子どもの頃にしたゲームの話をすると、共通点が見つかり、ぐっと空気が和らぐことを何度も経験した。ゲームは多くの人のかけがえのない思い出であり、成人してからもコミュニケーションのきっかけにもなったりする。いい面もあるのだ。
一方で、自分でも少しゲームにはまりすぎているかもしれない、と危機感を抱く人にとっては、私の「漫画とアニメでいいのでは」というような「代替」もあると言いたい。代替のポイントは人それぞれだ。
そのため、いったい自分はゲームのどこが好きなのか? キャラか、ストーリーか、音楽か、声優か、敵を倒せた爽快感か、アイテムやキャラクターをそろえたりレベルを上げたりしたときの達成感なのか、ゲーム内で人と知り合ったり、実況動画を見て同好の士とつながったりして、気持ちを共有したいのか? はたまた、ゲームをやることが好きというより、直面したくないことから逃避するためにゲームをしているのか? こういったことを、一人ひとりが「自分で」考えることしかないのだろうと思う。
『節ネット、はじめました。 「黒ネット」「白ネット」をやっつけて、時間とお金を取り戻す』 時間がない! お金がない! 余裕もない!――すべての元凶はネットかもしれません。
『できる男になりたいなら、鏡を見ることから始めなさい。 会話術を磨く前に知っておきたい、ビジネスマンのスーツ術』 「使えそうにないな」という烙印をおされるのも、「なんだかできそうな奴だ」と好印象を与えられるのも、すべてはスーツ次第!